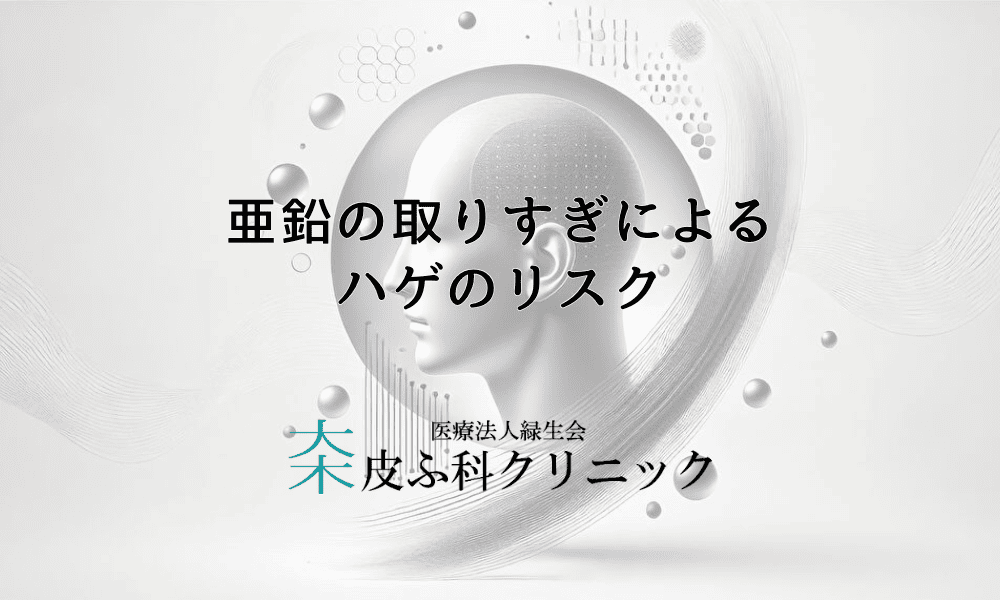亜鉛は私たちの体にとって重要なミネラルの一つであり、髪の毛の成長にも関与しています。しかし、健康に良いとされる亜鉛も摂取量が多すぎると逆効果となり、はげるリスクを高める可能性が指摘されています。
インターネット上でも「亜鉛 取りすぎ はげる」と検索する方が多いようで、関心の高さがうかがえます。
この記事では、亜鉛の過剰摂取がなぜ薄毛につながるのか、その理由と適切な摂取量、そして注意点について詳しく解説します。
亜鉛は髪の健康に必要?その理由とは
亜鉛は体内で多様な役割を担う必須ミネラルであり、髪の毛の健康維持にも深く関わっています。亜鉛が髪にどのように作用するのか、その主な働きを見ていきましょう。
髪の主成分ケラチンの合成を助ける
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。亜鉛は、このケラチンの合成過程で重要な役割を果たします。
食事から摂取したタンパク質をアミノ酸に分解し、それを再合成してケラチンを作り出す際に、亜鉛が酵素の働きを助ける補酵素として機能します。
亜鉛が不足するとケラチンの合成がスムーズに行われなくなり、髪の毛が細くなったりもろくなったりする可能性があります。
細胞分裂と成長を促進する
髪の毛は毛根にある毛母細胞が分裂し、増殖することで成長します。亜鉛はこの細胞分裂の過程に必要です。
DNAやRNAといった遺伝情報を担う核酸の合成やタンパク質の合成を調整する働きがあり、活発な細胞分裂を支えています。
毛母細胞の分裂が滞ると、髪の成長が遅くなったり休止期に入る毛が増えたりして、薄毛につながることが考えられます。
ヘアサイクルを正常に保つ
髪の毛には、「成長期」「退行期」「休止期」という一定の周期(ヘアサイクル)があります。亜鉛は、このヘアサイクルを正常に維持するためにも関与しています。
特に、髪が太く長く成長する「成長期」を維持するために、亜鉛の働きが大切です。
亜鉛が不足したり逆に過剰になったりするとヘアサイクルが乱れ、成長期が短縮されたり休止期が長引いたりして、抜け毛の増加や薄毛を招くときがあります。
抗酸化作用で頭皮環境を守る
亜鉛は、体内の活性酸素を除去する抗酸化酵素の構成成分でもあります。
活性酸素はストレスや紫外線、不規則な生活習慣などによって過剰に発生し、頭皮の細胞にダメージを与えて老化を促進します。
これにより頭皮環境が悪化し、健康な髪の毛が生えにくい状態になる場合があります。亜鉛が持つ抗酸化作用は、頭皮を活性酸素のダメージから守り、健やかな髪を育む土台を整えるのに役立ちます。
髪の健康維持における亜鉛の主な役割
| 働き | 具体的な内容 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| ケラチン合成の補助 | タンパク質からケラチンを作る酵素を助ける | 髪の強度や太さの維持 |
| 細胞分裂・成長の促進 | 毛母細胞の分裂や増殖をサポート | 髪の成長促進、ヘアサイクルの維持 |
| 抗酸化作用 | 活性酸素から頭皮細胞を守る | 頭皮環境の維持、健やかな髪の育成 |
亜鉛の過剰摂取がはげる原因になる?その仕組みを解説
適量であれば髪の健康に役立つ亜鉛ですが、なぜ亜鉛の取りすぎがはげる原因になると言われるのでしょうか。
その主な理由として、他のミネラルの吸収阻害や、ホルモンバランスへの影響などが考えられます。
銅の吸収阻害による影響
亜鉛と銅は体内で吸収される際に同じ経路(トランスポーター)を利用するため、互いに競合する関係にあります。亜鉛を過剰に摂取すると、腸管での銅の吸収が妨げられてしまいます。
銅は髪の色素であるメラニンを生成する酵素(チロシナーゼ)の働きに必要であり、髪の毛の結合を強くする役割も担っています。
銅が不足すると髪の色が薄くなったり、髪質がもろくなったりする可能性があります。
さらに、銅は鉄の代謝にも関わっており、銅不足が貧血の一因となる場合もあります。貧血は毛根への酸素供給を低下させ、髪の成長を妨げる要因となりえます。
亜鉛過剰摂取による銅吸収阻害の影響
| 影響を受ける要素 | 銅の役割 | 銅不足による髪への影響(可能性) |
|---|---|---|
| メラニン生成 | チロシナーゼの活性化 | 白髪の増加、髪の色の変化 |
| 髪の結合 | ケラチン線維の架橋形成に関与 | 髪の強度の低下、切れ毛、枝毛 |
| 鉄代謝 | 鉄の吸収や運搬を助ける | 貧血による毛根への酸素供給不足、成長阻害 |
鉄の吸収阻害による影響
亜鉛は、銅だけでなく鉄の吸収も阻害することが知られています。特に、植物性食品に含まれる非ヘム鉄の吸収に対する影響が大きいとされます。
鉄は血液中のヘモグロビンの成分として、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。
鉄が不足して鉄欠乏性貧血になると、頭皮や毛根への酸素供給が不十分になり、毛母細胞の働きが低下して髪の毛が十分に成長できなくなります。
その結果、抜け毛が増えたり髪が細くなったりして、薄毛が進行しやすいです。
男性ホルモンへの影響の可能性
亜鉛は、男性ホルモンであるテストステロンの代謝に関わる酵素(5α-リダクターゼ)の働きを抑制するという報告があります。
5α-リダクターゼは、テストステロンをAGA(男性型脱毛症)の主な原因物質とされるDHT(ジヒドロテストステロン)に変換する酵素です。
理論上は、亜鉛がこの酵素を抑制すればDHTの生成が減少し、薄毛予防につながる可能性も考えられます。
しかし、亜鉛を過剰に摂取した場合にこのホルモンバランスにどのような影響が出るのかは、まだ完全には解明されていません。
過剰な亜鉛が逆にホルモンバランスを乱し、薄毛を助長する可能性も否定できません。この点については、さらなる研究が必要です。
亜鉛過剰によるその他の身体症状
亜鉛を過剰に摂取すると薄毛だけでなく、吐き気や嘔吐、腹痛や下痢といった消化器系の症状が現れるケースがあります。
また、長期的な過剰摂取は免疫機能の低下やHDL(善玉)コレステロールの減少、神経障害などを引き起こす可能性も指摘されています。
これらの体調不良は、間接的に髪の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
亜鉛の過剰摂取で起こりうる身体症状
| 症状の種類 | 具体的な症状 |
|---|---|
| 消化器症状 | 吐き気、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢 |
| その他の症状 | 頭痛、めまい、倦怠感、免疫機能低下 |
| 長期的な影響 | 銅・鉄欠乏、HDLコレステロール減少 |
どれくらいが取りすぎ?亜鉛の適切な摂取量と上限
亜鉛の過剰摂取によるリスクを避けるためには、適切な摂取量を守ることが大切です。
厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」では、亜鉛の推奨量と過剰摂取による健康被害を防ぐための耐容上限量が設定されています。
日本人の食事摂取基準(推奨量と耐容上限量)
食事摂取基準によると、成人男性(18~74歳)の亜鉛の推奨量は1日あたり11mg、成人女性(18歳以上)は8mgとされています。
一方、健康障害のリスクがないとされる習慣的な摂取量の上限である耐容上限量は、成人男性(18~74歳)で1日40~45mg、成人女性(18歳以上)で35mgです。
この耐容上限量を超えて摂取し続けると、前述したような過剰摂取によるリスクが高まります。
成人の亜鉛の食事摂取基準(mg/日)
| 年齢区分 | 性別 | 推奨量 (RDA) | 耐容上限量 (UL) |
|---|---|---|---|
| 18~74歳 | 男性 | 11 | 40~45 |
| 75歳以上 | 男性 | 10 | 40 |
| 18歳以上 | 女性 | 8 | 35 |
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より一部抜粋・簡略化
年齢・性別による推奨量の違い
亜鉛の必要量は年齢や性別によって異なります。成長期の子どもや男性は、女性よりも多くの亜鉛を必要とします。
高齢になると食事量の減少や吸収率の低下により、推奨量がやや低めに設定されていますが、不足しないよう注意が必要です。
妊娠中・授乳中の女性の摂取量
妊娠中や授乳中の女性は、胎児や乳児の発育のために通常よりも多くの亜鉛が必要です。妊娠中は通常推奨量に加えて2mg、授乳中は4mgの付加量が推奨されています。
ただし、耐容上限量は通常の成人女性と同じ35mgですので、サプリメントなどを利用する場合は過剰摂取にならないよう注意が必要です。
日常の食事から摂取できる亜鉛量
亜鉛は肉類や魚介類、穀類や豆類など様々な食品に含まれています。特に牡蠣(かき)は亜鉛を非常に多く含む食品として知られています。
バランスの取れた食事を心がけていれば、通常の食事だけで耐容上限量を超えることは稀です。
しかし、特定の食品を極端に多く食べたりサプリメントを利用したりするときは、過剰摂取のリスクが生じます。
亜鉛を多く含む食品例(可食部100gあたり)
| 食品名 | 亜鉛含有量 (mg) |
|---|---|
| かき(生) | 14.0 |
| 豚レバー(生) | 6.9 |
| 牛肩ロース(赤身、生) | 5.1 |
| パルメザンチーズ | 7.3 |
| ごま(いり) | 5.9 |
| カシューナッツ(いり) | 5.4 |
出典:「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より
亜鉛を過剰摂取しやすい状況とは?サプリメント利用の注意点
通常の食事では過剰摂取のリスクは低い亜鉛ですが、どのような場合に摂りすぎてしまうのでしょうか。特に注意したいのが、サプリメントの利用です。
複数のサプリメントの併用
健康維持や美容目的で、複数のサプリメントを同時に利用している方もいるでしょう。
マルチビタミン・ミネラルサプリメントや育毛・美肌を目的としたサプリメントなど、亜鉛が含まれているものがあります。
それぞれの含有量を把握せずに併用すると、知らず知らずのうちに亜鉛の総摂取量が過剰になってしまう可能性があります。
自己判断による高用量摂取
「髪に良い」「免疫力アップ」などの情報を鵜呑みにし、推奨量を超えて高用量の亜鉛サプリメントを自己判断で摂取してしまうケースがあります。
特に海外製のサプリメントには、1粒あたりの亜鉛含有量が日本の耐容上限量に近い、あるいは超えるものも存在します。安易な高用量摂取は、過剰摂取のリスクを高めるため非常に危険です。
亜鉛強化食品の食べ過ぎ
近年、亜鉛を添加した栄養強化食品(シリアル、飲料、栄養補助食品など)が増えています。これらの食品を日常的にかつ大量に摂取すると、食事からの亜鉛と合わせて過剰摂取につながる可能性があります。
食品表示を確認し、摂取量に注意することが大切です。
サプリメント選びのポイント
亜鉛サプリメントを利用する場合は、信頼できるメーカーの製品を選び、成分表示をよく確認します。
1日あたりの摂取目安量とそれに含まれる亜鉛の含有量を把握し、食事からの摂取量も考慮して耐容上限量を超えないように調整します。
他のサプリメントとの併用にも注意が必要です。不明な点や心配なことがある場合は、医師や薬剤師、管理栄養士に相談すると良いでしょう。
亜鉛サプリメント利用時の注意点
| 注意点 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 含有量の確認 | 1日の摂取目安量あたりの亜鉛量を把握する |
| 耐容上限量の遵守 | 食事からの摂取も考慮し、上限を超えないようにする |
| 複数サプリメントの併用注意 | 各サプリメントの亜鉛含有量を合計して確認する |
| 自己判断での高用量摂取を避ける | 推奨量を守り、不明な点は専門家に相談する |
| 信頼できる製品の選択 | メーカー情報や品質管理体制を確認する(可能な範囲で) |
亜鉛の取りすぎによる薄毛が疑われる場合の対処法
亜鉛の摂取量が多く、かつ薄毛の症状が見られる場合、どのように対処すればよいのでしょうか。焦らず、以下のステップで対応を考えましょう。
まずは亜鉛の摂取量を見直す
サプリメントや亜鉛強化食品を利用しているときは、まずその摂取を一時中断するか、量を減らしてみましょう。
中止してから数週間から数ヶ月様子を見ても薄毛の状態に変化が見られない場合は、亜鉛の過剰摂取が直接の原因ではない可能性も考えられます。
食事内容を見直し、亜鉛を多く含む食品の摂取頻度などを調整するのも有効です。
医師や専門家への相談
自己判断で原因を特定するのは困難です。薄毛の悩みは、皮膚科医やAGA治療を専門とするクリニックに相談することが重要です。
医師が問診や視診、必要に応じて血液検査などを行い、薄毛の原因を診断します。亜鉛の過剰摂取が疑われる場合は、血中の亜鉛濃度や銅濃度を測定する場合もあります。
また、管理栄養士に相談し、食事内容やサプリメントの利用についてアドバイスを受けるのも有効です。
相談できる専門家
- 皮膚科医
- AGA専門クリニック医師
- 管理栄養士
食事バランスの改善
亜鉛の摂取量だけでなく、全体的な食事バランスの見直しも大切です。
タンパク質やビタミン(特にビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE)、ミネラル(鉄、銅など)はいずれも髪の健康に必要です。
特定の栄養素に偏らず、多様な食品をバランス良く摂取するよう心がけましょう。特に、亜鉛と相互作用のある銅や鉄の摂取にも注意が必要です。
他の薄毛原因の可能性も考慮する
薄毛の原因は亜鉛の過剰摂取だけではありません。AGA(男性型脱毛症)やFAGA(女性型脱毛症)、円形脱毛症や加齢、ストレスや生活習慣の乱れ、他の病気や薬剤の影響など、様々な要因が考えられます。
亜鉛の摂取量を見直しても改善しない場合は、他の原因を疑い、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。
薄毛の主な原因(亜鉛過剰摂取以外)
| 原因カテゴリ | 具体的な原因 |
|---|---|
| ホルモン性 | AGA(男性型脱毛症)、FAGA(女性型脱毛症)、産後脱毛症 |
| 自己免疫疾患 | 円形脱毛症 |
| 生活習慣・環境 | ストレス、睡眠不足、栄養不足、喫煙、頭皮環境の悪化 |
| その他 | 加齢、薬剤の副作用、甲状腺疾患などの病気 |
亜鉛とAGA(男性型脱毛症)治療の関係性
薄毛の中でも特に男性に多いのがAGA(男性型脱毛症)です。亜鉛の過剰摂取とAGAには直接的な因果関係はありませんが、亜鉛がAGA治療にどのように関わるのか気になる方もいるでしょう。
AGAの主な原因と亜鉛の関係
AGAの主な原因は、男性ホルモンのテストステロンが5α-リダクターゼという酵素によってDHT(ジヒドロテストステロン)に変換され、このDHTが毛乳頭細胞にある受容体と結合してヘアサイクルが乱れ、髪の成長期が短縮されることにあります。
亜鉛には5α-リダクターゼの働きを抑制する可能性が示唆されていますが、亜鉛の摂取によってAGAが改善するという明確な科学的根拠はまだ確立されていません。
亜鉛不足が薄毛の一因になる可能性はありますが、AGAの根本的な原因は遺伝や男性ホルモンの影響が大きいです。
亜鉛はAGA治療の補助になるのか?
一部の研究では、AGA治療薬の効果を高める目的や副作用を軽減する目的で亜鉛を補助的に使用することが検討されていますが、その有効性についてはまだ議論の余地があります。
亜鉛はあくまで髪の成長に必要な栄養素の一つであり、AGAの進行を直接抑制する治療薬とは異なります。
AGA治療においては、まず医学的に効果が認められている治療法(フィナステリド、デュタステリド、ミノキシジルなど)を優先するのが基本です。
AGA治療薬と亜鉛サプリメントの併用
AGA治療薬を使用中に、自己判断での亜鉛サプリメントの併用は推奨されません。予期せぬ相互作用や過剰摂取による健康被害のリスクも考えられます。
もし亜鉛サプリメントの利用を考えている場合は、必ずAGA治療を担当している医師に相談して指示を仰ぐようにしてください。医師が患者さんの状態や治療内容に合わせて、適切なアドバイスを行います。
クリニックでのAGA治療の選択肢
AGAの治療は、専門のクリニックで受けることが最も効果的です。クリニックでは、医師による正確な診断に基づき、個々の症状や進行度に合わせた治療計画を立てます。
主な治療法には、内服薬(フィナステリド、デュタステリド)や外用薬(ミノキシジル)、注入療法(メソセラピー)や自毛植毛などがあります。
亜鉛の過剰摂取による薄毛の懸念がある場合もまずは専門医に相談し、適切な診断を受けることが解決への第一歩です。
AGA治療の主な選択肢(クリニック)
| 治療法の種類 | 概要 |
|---|---|
| 内服薬 | 5α-リダクターゼ阻害薬(フィナステリド、デュタステリド)でDHT産生を抑制 |
| 外用薬 | ミノキシジルで毛母細胞を活性化し、血行を促進 |
| 注入療法 | 成長因子や栄養素などを頭皮に直接注入 |
| 自毛植毛 | 後頭部などから自身の毛髪を薄毛部分に移植 |
よくある質問
ここでは、亜鉛の摂取と薄毛に関するよくある質問にお答えします。
- Q亜鉛の取りすぎをやめたら髪は元に戻りますか?
- A
亜鉛の過剰摂取が直接の原因で薄毛が起きていた場合、摂取量を適正に戻すと銅や鉄の吸収阻害などが改善され、髪の状態が回復する可能性があります。
ただし髪の毛にはヘアサイクルがあるため、改善を実感するまでには数ヶ月以上の時間がかかるのが一般的です。
また、薄毛の原因が亜鉛の過剰摂取だけではないとき(例:AGAが併発しているなど)は、亜鉛の摂取をやめるだけでは十分な改善が見られないケースもあります。
まずは専門医に相談し、原因を特定しましょう。
- Qプロテインにも亜鉛は含まれていますか?
- A
プロテインの種類や製品によります。ホエイプロテインやカゼインプロテインなどの動物性プロテインには、原料となる牛乳由来の亜鉛が含まれている場合があります。
また、栄養強化のために亜鉛を添加している製品もあります。ソイプロテイン(大豆由来)にも亜鉛は含まれますが、吸収率は動物性食品に比べて低いとされています。
プロテインを摂取している場合は製品の栄養成分表示を確認し、亜鉛の含有量を把握しておくとよいでしょう。特に亜鉛サプリメントと併用する際は、合計の摂取量に注意が必要です。
- Q亜鉛不足でもはげると聞きましたが、どちらが本当ですか?
- A
亜鉛は不足しても過剰摂取しても、どちらも薄毛の原因となる可能性があります。
亜鉛は髪の主成分であるケラチンの合成や毛母細胞の分裂に必要であり、不足すると髪の成長が妨げられます。
一方で、この記事で解説したように、過剰に摂取すると銅や鉄の吸収を阻害し、結果的に髪の健康に悪影響を及ぼす場合があります。
そのため「亜鉛は適量を摂取することが重要」というのが正しい理解です。
- Q食事だけで亜鉛を過剰摂取することはありますか?
- A
一般的な食生活を送っている限り、通常の食事だけで亜鉛の耐容上限量(成人男性40~45mg/日、成人女性35mg/日)を超えることは非常に稀です。
亜鉛が豊富な牡蠣でも1日に何十個も食べるような極端な偏食をしない限り、過剰摂取に至る可能性は低いと考えられます。
過剰摂取のリスクが高まるのは、主にサプリメントの不適切な利用や亜鉛強化食品の過剰な摂取による場合が多いです。バランスの取れた食事を心がけるのが基本です。
参考文献
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
KIL, Min Seong; KIM, Chul Woo; KIM, Sang Seok. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. Annals of Dermatology, 2013, 25.4: 405.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
AZIZ, Abeer M. Abdel; HAMED, Sameera Sh; GABALLAH, Mohammad A. Possible relationship between chronic telogen effluvium and changes in lead, cadmium, zinc, and iron total blood levels in females: a case-control study. International journal of trichology, 2015, 7.3: 100-106.
FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.
GOLDBERG, Lynne J.; LENZY, Yolanda. Nutrition and hair. Clinics in dermatology, 2010, 28.4: 412-419.