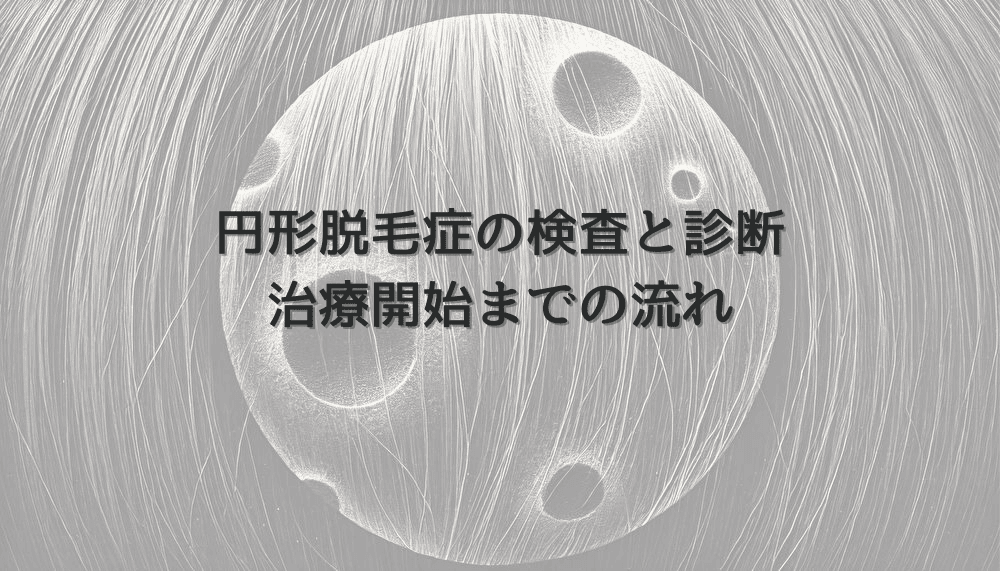ある日突然、髪にコイン大の脱毛斑を見つけたら、それは円形脱毛症かもしれません。特に女性にとって髪は大切なもの。強い不安を感じる方も多いでしょう。
円形脱毛症は、年齢や性別に関わらず誰にでも起こりうる自己免疫疾患の一つと考えられています。
ここでは、女性が円形脱毛症かもしれないと感じたとき、どのような検査を経て診断され、治療が始まるのか、その一連の流れを詳しく解説します。
円形脱毛症とは何か?基本的な知識
円形脱毛症は、頭部や体毛に円形または楕円形の脱毛斑が突然現れる病気で、多くの場合は頭髪に症状が出ますが、眉毛、まつ毛、ひげ、体毛など、毛が生えている場所ならどこにでも発症する可能性があります。
自己免疫疾患としての側面
現在の医学では、円形脱毛症は自己免疫疾患の一種です。
通常、免疫系は体外から侵入する細菌やウイルスなどを攻撃して体を守る働きをしますが、自己免疫疾患では、免疫系が誤って自分自身の正常な細胞や組織を攻撃してしまいます。
円形脱毛症の場合、免疫細胞であるTリンパ球が毛根を異物と認識し、攻撃することで毛が抜け落ちると考えられています。
なぜこのような異常が起こるのか、詳細な原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的な要因やストレスなどが関与している可能性が指摘されています。
円形脱毛症の種類と症状の現れ方
円形脱毛症は、脱毛斑の数や範囲によっていくつかのタイプに分類され、最も一般的なのは、頭部に1つまたは複数の円形脱毛斑ができる「単発型」や「多発型」です。
脱毛斑はコイン程度の大きさから始まり、徐々に拡大することもあり、また、脱毛斑が結合して大きな不規則な形になることもあります。
症状が進行すると、頭部全体の髪が抜けてしまう「全頭型」や、頭髪だけでなく眉毛、まつ毛、体毛など全身の毛が抜ける「汎発型(ばんぱつがた)」に至る場合もあります。
さらに、後頭部から側頭部の生え際に沿って帯状に脱毛する「蛇行型」という特殊なタイプもあり、どのタイプであっても、早期に専門医の診察を受けることが重要です。
脱毛斑の主なタイプ
| タイプ名 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単発型 | 頭部に円形脱毛斑が1つできる | 最も軽症で、自然治癒することも多い |
| 多発型 | 頭部に円形脱毛斑が複数できる | 脱毛斑が融合して拡大する場合がある |
| 全頭型 | 頭部全体の毛髪が抜け落ちる | 治療が長期化しやすい傾向がある |
| 汎発型 | 頭髪、眉毛、まつ毛、体毛など全身の毛が抜ける | 最も重症なタイプとされる |
| 蛇行型 | 後頭部から側頭部の生え際に沿って脱毛する | 治療に反応しにくい場合がある |
女性特有の悩みと円形脱毛症
女性の場合、円形脱毛症による外見の変化は、男性以上に深刻な心理的負担となることがあります。
髪型で隠すことが難しい場合や、広範囲に脱毛が及ぶ場合、社会生活や対人関係において大きなストレスを感じることが少なくありません。
また、妊娠や出産、更年期など、女性ホルモンの変動が発症や症状の悪化に関与する可能性も指摘されていますが、明確な因果関係はまだ分かっていません。
女性特有のライフイベントと円形脱毛症の関係性については、今後の研究が待たれるところで、いずれにしても、一人で悩まず、専門医に相談し、サポートを受けることが大切です。
円形脱毛症の検査はどこで受ける?医療機関の選び方
円形脱毛症の症状に気づいたら、まずは専門的な知識を持つ医師の診察を受けることが重要ですが、どの診療科を受診すればよいのか迷う方もいるでしょう。
皮膚科が第一選択肢
円形脱毛症の診断と治療は、主に皮膚科が担当し、毛髪や頭皮の状態を専門的に診察し、円形脱毛症かどうかを判断します。
また、他の脱毛症(例えば、女性型脱毛症や休止期脱毛症など)との鑑別診断も行い、多くの皮膚科クリニックや総合病院の皮膚科で対応可能です。
まずは、お近くの皮膚科を受診することを検討しましょう。
毛髪専門外来や女性専門クリニック
近年では、脱毛症や薄毛治療を専門とする「毛髪専門外来」や、女性特有の髪の悩みに特化した「女性専門クリニック」も増えています。
医療機関では、より詳細な検査や多様な治療選択肢を提供している場合があります。
特に、円形脱毛症だけでなく、他の要因による薄毛も併発している場合や、より専門的なアドバイスを求める場合には、こうした専門機関への相談も有効な選択肢です。
ただし、自由診療を中心に行っている場合もあるため、事前に診療内容や費用について確認してください。
医療機関の種類と特徴
| 医療機関の種類 | 主な特徴 | 受診の目安 |
|---|---|---|
| 一般皮膚科 | 円形脱毛症の基本的な診断・治療を行う | まずは相談したい場合、アクセスしやすい |
| 総合病院皮膚科 | 必要に応じて他科との連携が可能、入院治療も対応 | 重症の場合、合併症がある場合 |
| 毛髪専門外来/女性専門クリニック | 脱毛症に関する専門的な検査・治療を提供 | より専門的な意見を聞きたい、他の脱毛症も気になる場合 |
円形脱毛症の検査内容 詳細解説
医療機関を受診すると、円形脱毛症の診断や重症度の判定、他の病気の可能性を除外するために、いくつかの検査を行います。
問診 現在の症状と既往歴の確認
まず最初に行われるのが問診です。医師は、患者さんから症状について詳しく話を聞きます。
いつから脱毛が始まったのか、脱毛斑の数や大きさの変化、かゆみや痛みなどの自覚症状の有無、過去に円形脱毛症になったことがあるか、家族に円形脱毛症の人がいるか、などです。
また、アトピー性皮膚炎や甲状腺疾患などの自己免疫疾患の既往歴や合併症がないかなども確認します。
ストレスや生活習慣の変化など、発症のきっかけになったと考えられる出来事についても尋ねることがあります。
問診でよく聞かれる項目
| 項目 | 確認する内容の例 |
|---|---|
| 発症時期・経過 | いつ頃から脱毛に気づいたか、脱毛範囲は広がっているか |
| 自覚症状 | かゆみ、痛み、頭皮の違和感などはないか |
| 既往歴 | 過去の円形脱毛症の経験、アトピー素因、甲状腺疾患など |
| 家族歴 | 血縁者に円形脱毛症の人はいるか |
| 生活状況 | 最近、大きなストレスや環境の変化はなかったか |
視診と触診 頭皮と毛髪の状態を観察
問診に続いて、医師が直接頭皮や毛髪の状態を観察する視診と触診を行います。
脱毛斑の形、大きさ、数、分布範囲を確認します。脱毛斑の境界がはっきりしているか、皮膚の色に変化(赤み、萎縮など)はないか、毛穴の状態などを詳しく見ます。
また、脱毛斑の周りの毛髪を軽く引っ張ってみる「牽引試験(プルテスト)」を行うこともあり、活動性の高い脱毛(簡単に毛が抜ける状態)があるかどうかを判断する検査です。
円形脱毛症に特徴的な所見として、「感嘆符毛(かんたんふもう)」と呼ばれる、毛根側が細くなっている短い毛が見られることがあり、毛髪の成長が障害されていることを示唆します。
ダーモスコピー検査 毛穴や毛髪の詳細な観察
ダーモスコピーは、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を使って、頭皮や毛髪の状態をより詳細に観察する検査です。
肉眼では見えにくい毛穴の状態、毛髪の太さや形状の変化、頭皮の血管のパターンなどを確認でき、円形脱毛症の診断補助や、活動性の評価、他の脱毛症との鑑別に役立ちます。
円形脱毛症の活動期には、黒点(毛穴に残った断毛)や感嘆符毛、短い軟毛などが観察されることがあり、検査自体に痛みはなく、短時間で終わります。
ダーモスコピーで観察される主な所見
| 所見 | 状態 |
|---|---|
| 感嘆符毛 | 毛根側が細く、先端が太い毛髪 |
| 黒点 (Black dots) | 毛穴に残った黒い断毛 |
| 黄色点 (Yellow dots) | 皮脂や角質が詰まった毛穴 |
| 短い軟毛 (Short vellus hairs) | 細く短い、色素の薄い毛髪 |
血液検査 合併症の有無を確認
円形脱毛症は、甲状腺疾患(橋本病、バセドウ病など)や膠原病(全身性エリテマトーデスなど)、尋常性白斑といった他の自己免疫疾患を合併することがあります。
そのため、必要に応じて血液検査を行い、これらの合併症の有無を確認します。
調べるのは、甲状腺ホルモン(TSH, FT3, FT4)や自己抗体(抗サイログロブリン抗体、抗TPO抗体、抗核抗体など)の値です。
また、全身状態を把握するために、一般的な血液検査(血球計算、肝機能、腎機能など)や、鉄欠乏性貧血の有無(血清フェリチン値など)を確認することもあります。
円形脱毛症の診断基準と重症度判定
各種検査の結果を総合的に評価し、医師は円形脱毛症の診断を行い、診断が確定したら、次に治療方針を決定するために、脱毛の範囲や進行度合いから重症度を判定します。
診断の確定 他の脱毛症との鑑別
円形脱毛症の診断は、主に特徴的な円形または楕円形の脱毛斑の存在と、問診、視診、ダーモスコピー検査などの結果に基づいて行われますが、脱毛を起こす病気は他にも様々あります。
例えば、女性型脱毛症(FAGA/FPHL)、休止期脱毛症、抜毛症(トリコチロマニア)、脂漏性脱毛症、梅毒性脱毛症、膠原病に伴う脱毛などです。
さまざまな疾患と円形脱毛症を正確に区別すること(鑑別診断)が重要です。
鑑別が必要な主な脱毛症
| 脱毛症の種類 | 主な特徴 | 円形脱毛症との違い(例) |
|---|---|---|
| 女性型脱毛症(FAGA/FPHL) | 頭頂部を中心に髪が全体的に薄くなる | 明確な脱毛斑は通常見られない |
| 休止期脱毛症 | 頭部全体の毛髪がびまん性に抜ける | ストレスや出産後などに起こりやすい、脱毛斑は形成しない |
| 抜毛症 | 自分で毛髪を引き抜いてしまう | 不規則な形の脱毛、断毛が多い |
| 脂漏性脱毛症 | 頭皮の炎症やフケを伴う脱毛 | 頭皮の赤み、湿疹、かゆみが強い |
重症度の評価(Salty分類など)
円形脱毛症の重症度は、脱毛範囲の広さによって評価します。国際的に広く用いられている評価基準の一つに「Salty(ソルティ)分類」があります。
頭部全体の面積に対する脱毛面積の割合(%)に基づいて重症度を分類するものです。
脱毛面積が25%未満をS1(軽症)、25%~49%をS2(中等症)、50%~74%をS3(中等症~重症)、75%~99%をS4(重症)、全頭脱毛をS5(最重症)と分類し、治療法の選択や治療効果の判定に用いられます。
Salty分類による重症度
| 分類 | 脱毛面積の割合 | 重症度 |
|---|---|---|
| S1 | 25%未満 | 軽症 |
| S2 | 25% – 49% | 中等症 |
| S3 | 50% – 74% | 中等症~重症 |
| S4 | 75% – 99% | 重症 |
| S5 | 100% (全頭脱毛) | 最重症 |
※汎発型(全身の毛が抜ける)の場合は、Salty分類とは別に評価します。
治療方針決定への影響
診断された円形脱毛症のタイプ(単発型、多発型、全頭型など)と、Salty分類などによる重症度の評価結果は、治療方針を決定する上で非常に重要です。
軽症(S1)の場合は、ステロイド外用薬や経過観察が選択されることが多いですが、中等症以上(S2~S5)や、急速に進行している場合、あるいは蛇行型などの難治性のタイプでは、より積極的な治療を検討します。
診断後の流れ 治療開始に向けて
円形脱毛症と診断され、重症度が判定された後に、治療が始まります。
医師からの説明と治療法の選択
医師は、診断結果、重症度、考えられる原因、今後の見通し、そして推奨される治療法について詳しく説明します。
円形脱毛症の治療法は、塗り薬、局所注射、局所免疫療法、内服薬、紫外線療法などです。
それぞれの治療法の効果、副作用、費用、治療期間の目安などについて、医師から十分な説明を受けましょう。
治療計画の立案と同意
選択した治療法に基づき、具体的な治療計画を立て、治療の頻度、おおよその治療期間、治療効果の評価時期などを決定します。治療によっては、定期的な検査(血液検査など)が必要になる場合もあります。
医師は、治療計画の詳細と、期待される効果、起こりうる副作用について改めて説明し、患者さんの同意を得てから治療を開始します。
治療中のセルフケア
- 指示された薬剤の用法・用量を守る
- 頭皮を清潔に保つ(ただし、洗いすぎない)
- バランスの取れた食事と十分な睡眠を心がける
- ストレスを溜めすぎない工夫をする
治療期間と予後について
円形脱毛症の治療は、どのくらいの期間がかかるのか、治療によって髪は元通りになるのでしょうか。ここでは、治療期間の目安と予後(病状の見通し)について解説します。
治療期間の目安
円形脱毛症の治療期間は、脱毛の範囲(重症度)、発症からの期間、選択する治療法、個人の体質や反応によって大きく異なります。
一般的に、軽症の単発型や多発型の場合、数ヶ月から1年程度で改善が見られることが多いですが、全頭型や汎発型、蛇行型などの重症例では、治療が長期にわたる傾向があります。
数年単位での治療が必要になることも少なくありません。治療を開始してすぐに効果が現れるわけではなく、毛髪が生え始めるまでには時間がかかります。
焦らず、根気強く治療を続けることが大切です。
予後(治癒の見込み)
円形脱毛症の予後は、タイプや重症度によって異なり、単発型の約80%は1年以内に自然治癒するとも言われていて、多発型でも、多くの場合、治療によって改善が期待できます。
しかし、全頭型や汎発型、蛇行型、アトピー素因を持つ場合、発症年齢が低い場合、爪に異常(点状陥凹など)が見られる場合などは、治りにくく、再発しやすいです。
完全に元の状態に戻る方もいれば、治療を続けてもなかなか改善しない方、一度治っても再発を繰り返す方もいます。
予後に影響を与える可能性のある因子
| 因子 | 予後への影響(傾向) |
|---|---|
| 脱毛範囲が広い(全頭型、汎発型) | 治りにくい、再発しやすい |
| 蛇行型 | 治りにくい |
| 発症年齢が低い(小児期発症) | 治りにくい、再発しやすい |
| アトピー素因(アトピー性皮膚炎など) | 治りにくい、再発しやすい |
| 爪の異常(点状陥凹など) | 治りにくい |
| 発症からの期間が長い | 治りにくい |
再発の可能性と長期的な管理
円形脱毛症は、一度治癒しても再発する可能性がある病気です。再発率は正確には分かっていないものの、約半数以上の患者さんが再発を経験するという報告もあります。
再発を防ぐための確実な方法は現在のところありませんが、ストレス管理や規則正しい生活を心がけることが、再発リスクを低減する上で役立つ可能性があります。
もし再発してしまった場合でも、早期に治療を開始すれば、前回よりも早く改善することもあります。
治療が終了した後も、定期的に頭皮の状態をチェックしたり、何か変化があればすぐに医療機関を受診したりするなど、長期的な視点での管理が大切です。
日常生活での注意点
円形脱毛症の治療中や治癒後も、日常生活でいくつか注意したい点があり、まず、頭皮への刺激を避けることが重要です。
パーマやヘアカラーは、頭皮に負担をかける可能性があるため、症状が落ち着くまでは控えるか、医師に相談してから行いましょう。
シャンプーは、低刺激性のものを選び、爪を立てずに優しく洗うことを心がけてください。また、紫外線は頭皮にダメージを与える可能性があるため、外出時には帽子や日傘などで頭皮を保護すると良いでしょう。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動は、体の免疫バランスを整え、健やかな毛髪の成長をサポートします。
よくある質問(Q&A)
円形脱毛症に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Qストレスが原因だと聞きましたが、本当ですか?
- A
ストレスは円形脱毛症の発症や悪化の誘因の一つと考えられていますが、ストレスだけが直接的な原因ではありません。
遺伝的な要因や自己免疫疾患など、様々な要因が複合的に関与していると考えられています。
ストレスを溜めないように心がけることは大切ですが、過度にストレスを原因と思い込まないことも重要です。
- Q治療すれば必ず髪は生えてきますか?
- A
残念ながら、現在の医学では、すべての患者さんで必ず発毛するとは断言できず、治療効果には個人差が大きく、脱毛のタイプや重症度、発症からの期間などによって異なります。
軽症の場合は治癒しやすい傾向がありますが、重症例では治療が長期化したり、十分な効果が得られなかったりすることもあります。
- Q治療にはどのくらいの費用がかかりますか?
- A
円形脱毛症の治療費は、選択する治療法や医療機関によって異なります。
基本的な診察、検査、ステロイド外用薬、抗アレルギー薬の内服、液体窒素療法などは、多くの場合、健康保険が適用されます。
一方、局所免疫療法(SADBE、DPCP)、一部の内服薬(JAK阻害薬など)、紫外線療法(施設による)、毛髪専門外来での特殊な検査や治療などは、保険適用外(自由診療)です。
参考文献
Werner B, Mulinari-Brenner F. Clinical and histological challenge in the differential diagnosis of diffuse alopecia: female androgenetic alopecia, telogen effluvium and alopecia areata-part I. Anais brasileiros de dermatologia. 2012;87:742-7.
Starace M, Orlando G, Alessandrini A, Piraccini BM. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology. 2020 Feb;21:69-84.
Rakowska A, Slowinska M, Kowalska-Oledzka E, Olszewska M, Rudnicka L. Dermoscopy in female androgenic alopecia: method standardization and diagnostic criteria. International journal of trichology. 2009 Jan 1;1(2):123-30.
Sterkens A, Lambert J, Bervoets A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. Clinical and experimental medicine. 2021 May;21:215-30.
Papadopoulos AJ, Schwartz RA, Janniger CK. Alopecia areata: pathogenesis, diagnosis, and therapy. American Journal of Clinical Dermatology. 2000 Mar;1:101-5.
Finner AM. Alopecia areata: clinical presentation, diagnosis, and unusual cases. Dermatologic therapy. 2011 May;24(3):348-54.
Zhou C, Li X, Wang C, Zhang J. Alopecia areata: an update on etiopathogenesis, diagnosis, and management. Clinical reviews in allergy & immunology. 2021 Dec;61(3):403-23.