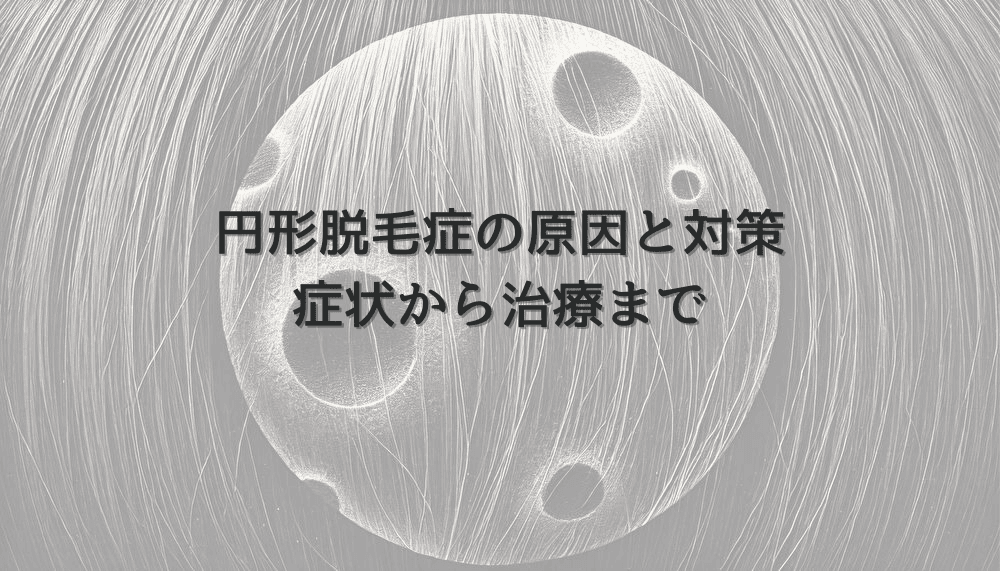この記事では、多くの女性が悩む円形脱毛症について、その基本的な情報から症状、考えられる原因、診断方法、そして治療法に至るまでを詳しく解説します。
突然現れる脱毛斑に不安を感じることもあるかもしれませんが、正しい知識を持つことが、適切な対応への第一歩です。
円形脱毛症とは何か
円形脱毛症は、頭部やその他の体毛のある部分に、境界がはっきりとした円形または楕円形の脱毛斑が突然現れる疾患です。
円形脱毛症の基本的な定義
円形脱毛症は、一般的に「10円ハゲ」とも呼ばれることがありますが、これは単発型の軽症例を指す俗称です。医学的には、毛髪が円形または不整形に抜け落ちる後天性の脱毛症と定義されます。
多くの場合、頭皮に症状が現れますが、眉毛、まつ毛、ひげ、あるいは全身の体毛に及ぶことがあります。
脱毛斑の大きさや数は個人差が大きく、一つだけの場合もあれば、多発する場合、さらには頭部全体の毛髪が失われる「全頭型」や、全身の毛髪が失われる「汎発型」といった重篤なケースもあります。
脱毛斑の特徴と現れ方
円形脱毛症の最も顕著な特徴は、境界が明瞭な脱毛斑で、脱毛斑の皮膚表面は、炎症や瘢痕を伴わず、滑らかであることが一般的です。
ただし、活動期には脱毛斑の辺縁部で毛髪が切れやすくなっていたり、「感嘆符毛(!マークのような形の毛)」と呼ばれる特徴的な毛が見られたりすることがあり、毛根部で炎症が起きているサインになります。
脱毛斑は、頭部のどの部分にも発生する可能性がありますが、好発部位は後頭部や側頭部です。
脱毛の進行速度や範囲は予測が難しく、数週間から数ヶ月で自然に治癒することもあれば、徐々に拡大したり、新しい脱毛斑が出現したりすることもあります。
円形脱毛症の主な種類
円形脱毛症は、脱毛斑の数や範囲によっていくつかのタイプに分類され、それぞれのタイプで、治療法や予後が異なります。
円形脱毛症の分類
| 種類 | 特徴 | 一般的な経過 |
|---|---|---|
| 単発型 | 頭部に1箇所の円形脱毛斑が生じる。 | 自然治癒することも多いが、再発や拡大の可能性もある。 |
| 多発型 | 頭部に複数の円形脱毛斑が生じる。 | 単発型より治癒に時間がかかることがあり、融合して大きな脱毛斑になることも。 |
| 蛇行型 | 後頭部から側頭部の生え際に沿って、帯状に脱毛する。 | 治療に抵抗性を示すことがあり、回復が難しい場合がある。 |
| 全頭型 | 頭部全体の毛髪がほぼ全て抜け落ちる。 | 重症型であり、治療が長期にわたることが多い。 |
| 汎発型 | 頭髪だけでなく、眉毛、まつ毛、体毛など全身の毛が抜け落ちる。 | 最も重症なタイプで、治療が困難な場合がある。 |
女性の円形脱毛症の主な症状
女性が円形脱毛症を発症した場合、その症状の現れ方にはいくつかの特徴があります。最も一般的なのは頭髪の脱毛ですが、それ以外にも注意すべきサインがあります。
頭髪の円形脱毛
円形脱毛症の最も代表的な症状は、頭髪が円形または楕円形に抜け落ちることで、脱毛斑の大きさは、直径数ミリ程度の小さなものから、手のひらサイズ以上の大きなものまで様々です。
通常、脱毛斑の皮膚は正常で、赤みや湿疹、かさぶたなどは見られませんが、活動期には脱毛斑の境界がやや赤みを帯びたり、軽いかゆみや違和感を伴ったりすることがあります。
脱毛は急速に進行することがあり、数日のうちにはっきりとわかる脱毛斑が出現することもあります。
脱毛斑は1つだけの場合(単発型)もあれば、複数同時に出現したり、次々と新しいものができたりする場合(多発型)もあります。
爪の異常
円形脱毛症の患者さんの中には、爪に異常が現れることがあります。
これは、毛髪と爪が同じケラチンというタンパク質からできているため、自己免疫反応が爪母細胞(爪を作る細胞)にも影響を与えることがあるためです。
代表的な爪の症状としては、爪の表面に点状の小さなへこみ(点状陥凹)が多数現れたり、爪がもろくなったり、横方向に溝ができたり(ボー線条)、爪が薄くなったり厚くなったり、光沢が失われたりすることが挙げられます。
爪の変化は、円形脱毛症の活動性や重症度と関連している場合があると言われています。
爪に見られる変化の例
| 爪の異常 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 点状陥凹 | 爪の表面に針で刺したような小さなへこみが多数できる。 | 最もよく見られる爪の変化の一つ。 |
| 爪甲横溝(ボー線条) | 爪の横方向に溝ができる。 | 全身疾患や高熱の後にも見られることがある。 |
| 爪甲の粗造・混濁 | 爪の表面がザラザラしたり、白っぽく濁ったりする。 | 爪の光沢が失われる。 |
脱毛範囲の拡大と進行
円形脱毛症の症状は、必ずしも一定ではなく、初期には小さな脱毛斑が一つだけだったものが、時間とともに徐々に大きくなったり、数が増えたりすることがあります。
複数の脱毛斑が融合して、より広範囲な脱毛になることもあります。症状の進行パターンは個人差が大きく、予測することは難しいのが現状です。
急速に悪化する場合もあれば、数ヶ月から数年かけてゆっくりと進行する場合もあり、また、一度治癒したように見えても、再発を繰り返すことも少なくありません。
特に、初発年齢が低い場合、アトピー素因がある場合、脱毛範囲が広い場合、蛇行型の場合などは、症状が慢性化したり、広範囲に進行したりするリスクが高いです。
その他の随伴症状
円形脱毛症の主な症状は脱毛ですが、それ以外にもいくつかの随伴症状が現れることがあります。
例えば、脱毛斑の周囲の毛を軽く引っ張ると容易に抜けてしまう「抜けやすい毛」が見られることがあり、毛包の炎症が活発であるサインです。
また、脱毛斑の皮膚にかゆみやピリピリとした軽い痛み、違和感を感じる人もいて、炎症反応や神経の刺激に関連している可能性があります。
女性の円形脱毛症の考えられる原因
女性の円形脱毛症の原因は、まだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が複雑に関与していると考えられていますが、現在の医学では、自己免疫疾患説が最も有力とされています。
自己免疫疾患説
現在、円形脱毛症の最も有力な原因と考えられているのが自己免疫疾患説で、私たちの体には、外部から侵入してきた細菌やウイルスなどの異物を攻撃して体を守る「免疫」という仕組みが備わっています。
しかし、何らかの理由でこの免疫系に異常が生じると、自分自身の正常な細胞や組織を攻撃してしまうことがあり、これが自己免疫疾患です。
円形脱毛症の場合、免疫細胞であるTリンパ球が毛根の細胞を異物と誤認し、攻撃することで毛包周囲に炎症が起こり、毛髪の成長が阻害され、脱毛が生じると考えられています。
なぜ自己免疫反応が起こるのか、詳細な引き金はまだ不明ですが、遺伝的な素因を持つ人が何らかの環境因子にさらされることで発症するのではないか、という説があります。
円形脱毛症の患者さんでは、甲状腺疾患(橋本病やバセドウ病など)や尋常性白斑、膠原病といった他の自己免疫疾患を合併する割合が、一般の人よりも高いです。
関連が指摘される自己免疫疾患の例
| 疾患名 | 主な症状 | 円形脱毛症との関連 |
|---|---|---|
| 甲状腺疾患(橋本病など) | 甲状腺機能低下(だるさ、むくみ等)または亢進(動悸、体重減少等) | 円形脱毛症患者における合併率が高い。 |
| 尋常性白斑 | 皮膚の色素が部分的に失われ、白い斑点ができる。 | 自己免疫的な機序が共通している可能性。 |
| 関節リウマチ | 関節の炎症、痛み、こわばり。 | 免疫系の異常が関与する点で共通性がある。 |
遺伝的要因
円形脱毛症の発症には、遺伝的な要因も関与していると考えられています。
家族内(親子や兄弟姉妹)で円形脱毛症を発症した人がいる場合、そうでない人に比べて発症リスクがやや高くなるという報告があります。
ただし、円形脱毛症は単一の遺伝子で決まるものではなく、複数の遺伝子が複雑に関与する多因子遺伝疾患です。
また、遺伝的な素因を持っていたとしても、必ずしも発症するわけではなく、何らかの環境因子(ストレス、感染症、薬剤など)が引き金となって発症に至ると考えられています。
精神的ストレス
精神的なストレスが円形脱毛症の発症や悪化の引き金になることがある、というのは古くから指摘されてきました。
強い精神的ショックや、長期間にわたるストレス、疲労などが、免疫系やホルモンバランス、自律神経系に影響を与え、円形脱毛症の発症に関与する可能性が考えられています。
しかし、ストレスと円形脱毛症の直接的な因果関係は、科学的にはまだ明確に証明されていません。ストレスがなくても発症する人もいれば、強いストレス下にあっても発症しない人もいます。
ストレスが関与する可能性のある要因
- 過労や睡眠不足
- 大きな精神的ショック
- 環境の変化(転居、転職など)
- 人間関係の悩み
アトピー素因
アトピー素因を持つ人は、円形脱毛症を発症しやすい傾向があることが知られています。
アトピー素因とは、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎などを起こしやすい体質のことを指します。
アレルギー疾患は、免疫系のバランスが崩れやすい状態と関連しており、円形脱毛症の自己免疫反応とも何らかの共通点があるのではないかと考えられています。
実際に、円形脱毛症の患者さんの約40%にアトピー素因が見られるという報告や、アトピー性皮膚炎を合併している患者さんでは円形脱毛症が重症化しやすいという報告もあります。
円形脱毛症の診断方法
円形脱毛症の診断は、主に皮膚科医による視診と問診に基づいて行われ、特徴的な円形の脱毛斑を確認することで、多くの場合診断がつきます。
問診
診断の第一歩は、詳細な問診で、以下のような質問をします。
いつから脱毛が始まったか、最初に気づいたきっかけ、脱毛斑の数や大きさの変化、かゆみや痛みなどの自覚症状の有無、過去の円形脱毛症の既往歴、家族歴、アトピー素因の有無、自己免疫疾患の既往や合併症、最近の健康状態、大きなストレスの有無、生活習慣の変化、服用中の薬剤
女性の場合は、妊娠・出産歴や月経周期に関する情報も参考になります。
視診とダーモスコピー検査
問診に続いて、医師は脱毛部の状態を詳細に観察し、脱毛斑の形状、大きさ、数、分布、脱毛斑の皮膚の状態(色調、炎症の有無、フケの有無など)、残存している毛髪の状態などを注意深く確認します。
この際、ダーモスコピー(皮膚拡大鏡)という特殊な拡大鏡を用いた検査が行われることが一般的です。
ダーモスコピー検査では、脱毛斑の辺縁部にある毛髪の状態(切れ毛、感嘆符毛、萎縮毛など)や、毛穴の状態(黄点、黒点など)、血管のパターンなどを詳細に観察できます。
円形脱毛症の活動性の評価や、他の脱毛症(例えば、トリコチロマニア(抜毛症)や頭部白癬(みずむし)など)との鑑別診断に役立ちます。
血液検査
円形脱毛症の診断自体は主に視診で行われますが、他の自己免疫疾患の合併が疑われる場合や、全身状態を把握するために血液検査が行われることがあります。
特に、甲状腺疾患(橋本病、バセドウ病など)や膠原病といった自己免疫疾患は、円形脱毛症と合併しやすく、関連する自己抗体や、甲状腺ホルモンの値を調べることがあります。
また、貧血や栄養状態の確認、炎症反応の程度を見るために、一般的な血液検査も行われることがあります。
診断に用いられる主な検査
| 検査項目 | 目的 | 備考 |
|---|---|---|
| 問診 | 発症時期、既往歴、家族歴、生活習慣などを聴取 | 診断の基本となる情報収集 |
| 視診・ダーモスコピー | 脱毛斑の状態、毛髪の状態、毛穴の状態を詳細に観察 | 活動性の評価、他の脱毛症との鑑別 |
| 血液検査 | 自己免疫疾患の合併、貧血、栄養状態、炎症反応などを評価 | 必要に応じて実施 |
女性の円形脱毛症の治療法
女性の円形脱毛症の治療は、脱毛の範囲、重症度、活動性、患者さんの年齢、健康状態、希望などを総合的に考慮して決定されます。
残念ながら、現時点では「これをすれば必ず治る」という特効薬はありませんが、症状の進行を抑え、発毛を促すための様々な治療法が試みられています。
ステロイド外用療法
軽症から中等症の円形脱毛症に対して、まず選択されることが多い治療法がステロイド外用療法です。
ステロイドには、免疫反応を抑制し、炎症を鎮める作用があり、脱毛斑にステロイドの塗り薬やローションを塗布することで、毛包周囲の炎症を抑え、発毛を促す効果が期待されます。
使用するステロイドの強さや塗布回数は、症状の程度や部位によって医師が調整します。効果が現れるまでには数週間から数ヶ月かかることが一般的です。
副作用としては、長期間使用した場合に皮膚が薄くなったり、毛細血管が拡張したり、ニキビのような発疹(ステロイドざ瘡)が出たりすることがあります。
ステロイド局所注射療法
脱毛斑が限局している場合や、ステロイド外用薬の効果が不十分な場合に、ステロイド局所注射療法が行われることがあり、脱毛斑の皮膚に直接ステロイド薬を注射する方法です。
外用薬よりも薬剤が直接毛包周囲に届くため、より高い効果が期待でき、通常、数週間から1ヶ月程度の間隔で、数回繰り返して注射を行います。
副作用としては、注射部位の皮膚が一時的に陥凹したり、色素沈着が起きたりすることがありますが、多くは時間とともに軽快しますが、広範囲の脱毛には適していません。
局所免疫療法(SADBE、DPCP)
広範囲に及ぶ重症の円形脱毛症に対して有効性が期待される治療法として、局所免疫療法があります。
これは、SADBE(スクアレン酸ジブチルエステル)やDPCP(ジフェニルシクロプロペノン)といった特殊な化学物質を脱毛斑に塗布し、人工的にかぶれ(接触皮膚炎)を起こさせることで、発毛を促す治療法です。
かぶれを起こすことで、毛包を攻撃している免疫細胞の働きを変化させたり、別の方向に向けたりする効果があると考えられています。
治療は、まず低濃度の試薬で感作(アレルギー反応を起こしやすい状態にすること)を行い、その後、週に1~2回程度、徐々に濃度を上げながら脱毛部に塗布していきます。
軽いかゆみや赤みが出る程度の反応が適切とされ、強すぎる反応が出た場合は濃度や塗布間隔を調整し、効果判定には数ヶ月以上かかることが多く、根気強い治療が必要です。
副作用としては、強いかゆみ、湿疹、リンパ節の腫れ、色素沈着などが起こることがあります。この治療は、実施できる医療機関が限られていて、また、妊娠中や授乳中の女性には通常行いません。
主な治療法の概要と比較
| 治療法 | 対象 | 主な作用・効果 |
|---|---|---|
| ステロイド外用療法 | 軽症~中等症、限局した脱毛斑 | 抗炎症作用、免疫抑制作用により発毛を促す |
| ステロイド局所注射療法 | 限局した脱毛斑、外用薬で効果不十分な場合 | より直接的に薬剤を届け、発毛を促す |
| 局所免疫療法 | 広範囲、重症例 | 人工的にかぶれを起こし免疫反応を変化させ発毛を促す |
その他の治療法(内服薬、紫外線療法など)
上記の治療法の他にも、いくつかの治療法が円形脱毛症に対して試みられていて、内服薬としては、抗アレルギー薬やセファランチンなどが補助的に用いられることがあります。
セファランチンは、血流改善作用や免疫調整作用などが期待されますが、効果については個人差が大きいです。
重症例に対しては、ステロイドの内服療法が行われることもありますが、全身的な副作用のリスクがあるため、適応は慎重に判断されます。
また、紫外線療法(PUVA療法やナローバンドUVB療法など)も、一部の円形脱毛症に有効な場合があります。
最近では、JAK阻害薬という新しいタイプの薬剤が、難治性の円形脱毛症に対する治療薬として注目されています。
円形脱毛症との向き合い方とセルフケア
円形脱毛症は、外見に変化をもたらすため、特に女性にとっては精神的な負担が大きい疾患です。
治療と並行して、日常生活でできるセルフケアや、精神的なサポートを得ることも、症状とうまく付き合っていく上で非常に大切になります。
精神的なサポートとストレス管理
円形脱毛症による外見の変化は、自己肯定感の低下や抑うつ気分、社会的孤立感などを起こすことがあります。
精神的な負担を軽減するためには、信頼できる人に自分の気持ちを話すことが助けになります。家族や友人、パートナーなど、身近な人に理解を求め、サポートを得ることが大切です。
また、同じ悩みを持つ人たちとの交流も、孤独感を和らげ、勇気づけられることがあります。
ストレスは円形脱毛症の悪化要因の一つとも考えられているため、日常生活の中でストレスを上手に管理することも重要です。
精神的サポートの種類
- 家族や友人からの支援
- 患者会やサポートグループへの参加
- カウンセリングの利用
頭皮ケアとヘアケアのポイント
円形脱毛症の治療中や回復期には、頭皮環境を健やかに保つことが大切ですが、過度なケアや刺激は逆効果になることもあるため、注意が必要です。
シャンプーは、低刺激性のものを選び、爪を立てずに指の腹で優しく洗い、洗い残しがないように、しっかりとすすぎ、ドライヤーは、頭皮から離して、熱風が直接長時間当たらないように注意しながら乾かします。
頭皮マッサージは、血行促進効果が期待できますが、強くこすりすぎると毛根に負担をかける可能性があるため、優しく行いましょう。
ヘアカラーやパーマは、頭皮や毛髪に刺激を与える可能性があるため、症状が活発な時期や、頭皮が敏感になっているときは避けてください。
頭皮ケアのポイント
- 低刺激性のシャンプーを使用する
- 優しく洗い、しっかりすすぐ
- ドライヤーの熱風を直接当てすぎない
食生活と生活習慣の見直し
健康な毛髪の成長には、バランスの取れた食事が基本です。
特定の食品が円形脱毛症を治すという科学的根拠はありませんが、髪の主成分であるタンパク質や、毛髪の成長に必要なビタミン、ミネラル(特に亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEなど)を日々の食事から十分に摂取することを心がけましょう。
極端なダイエットは、栄養不足を引き起こし、毛髪の健康にも悪影響を与える可能性があります。また、質の良い睡眠を十分にとることも大切です。
喫煙は、血管を収縮させて血行を悪化させるため、毛根への栄養供給を妨げる可能性があるので、禁煙を心がけることも、毛髪の健康にとってプラスになります。
適度な運動は、血行を促進し、ストレス解消にもつながるため、日常生活に取り入れることをお勧めします。
日常生活での注意点
| 項目 | ポイント | 理由 |
|---|---|---|
| 食事 | バランスの取れた栄養摂取(タンパク質、ビタミン、ミネラル) | 毛髪の成長に必要な栄養を供給する |
| 睡眠 | 質の良い睡眠を十分に確保する | 成長ホルモンの分泌を促し、細胞の修復を助ける |
| 喫煙 | 禁煙を心がける | 血行悪化を防ぎ、毛根への栄養供給を維持する |
円形脱毛症の進行と予後
円形脱毛症の進行や予後(今後の見通し)は、個人差が非常に大きく、一概には言えません。脱毛の範囲、発症年齢、アトピー素因の有無、合併する自己免疫疾患の有無などが影響すると考えられています。
自然治癒の可能性
円形脱毛症は、特に症状が軽い場合(単発型で脱毛斑が小さいなど)、特別な治療をしなくても自然に治癒することがあり、約80%の患者さんで、1年以内に何らかの発毛が見られるという報告もあります。
ただし、これはあくまで統計的なデータであり、全ての人に当てはまるわけではありません。自然治癒する場合でも、発毛が始まるまでには数ヶ月かかることが一般的です。
再発のリスクと予防
円形脱毛症は、一度治癒しても再発することがある疾患で、再発率は比較的高く、約半数の患者さんが5年以内に再発を経験するというデータもあります。
再発の頻度や時期、重症度は予測が難しく、数ヶ月後に再発することもあれば、数年あるいは数十年経ってから再発することもあります。
重症化するケースとその要因
円形脱毛症の中には、症状が広範囲に及んだり、長期間にわたって改善しなかったりする「重症型」や「難治性」のケースがあります。
まず、発症年齢が低い(特に思春期前)場合で、また、脱毛範囲が広い場合、例えば頭部全体の50%以上に脱毛が見られる場合や、全頭型(頭全体の毛が抜ける)、汎発型(全身の毛が抜ける)は重症と判断されます。
蛇行型(後頭部から側頭部の生え際に沿って帯状に脱毛する)も、治療に抵抗性を示しやすいタイプです。
アトピー素因(アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎など)を合併している場合や、爪の異常が著しい場合、他の自己免疫疾患(甲状腺疾患など)を合併している場合も、重症化のリスクが高くなります。
脱毛斑の範囲と回復期間の目安
| 脱毛範囲 | 一般的な重症度 | 回復期間の目安 |
|---|---|---|
| 頭部の25%未満 | 軽症 | 数ヶ月~1年程度で自然治癒も期待できる |
| 頭部の25~50% | 中等症 | 治療により数ヶ月~1年以上かかることが多い |
| 頭部の50%以上、全頭型、汎発型 | 重症 | 治療が長期にわたり、回復が困難な場合もある |
※上記はあくまで一般的な目安であり、個人差が大きいです。
医療機関を受診するタイミング
- 初めて円形の脱毛斑に気づいたとき
- 脱毛斑が徐々に大きくなっている、または数が増えているとき
- 数ヶ月経っても発毛の兆しが見られないとき
- 強いかゆみや痛みなど、他の症状を伴うとき
よくある質問
ここでは、女性の円形脱毛症に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ただし、個々の症状や状況によって対応は異なります。
- Q円形脱毛症は他の人にうつりますか
- A
いいえ、円形脱毛症は感染症ではないため、他の人にうつることはありません。円形脱毛症は、主に自己免疫反応によって引き起こされると考えられており、細菌やウイルスが原因ではありません。
- Q治療をすれば必ず髪は生えてきますか
- A
円形脱毛症の治療効果には個人差があり、必ずしも全てのケースで完全に髪が生えそろうとは限りません。多くの場合、治療を行うことで発毛が見られ、改善が期待できます。
特に、脱毛範囲が狭く、発症から間もない軽症のケースでは、比較的良好な経過をたどることが多いです。
ただし、脱毛範囲が広範囲に及ぶ重症例や、長期間治療に反応しない難治例もあります。
- Q妊娠中や授乳中でも治療はできますか
- A
妊娠中や授乳中の女性が円形脱毛症を発症した場合、治療法の選択には注意が必要で、使用できる薬剤や治療法が限られることがあります。
ステロイド外用薬は、医師の指示のもとで適切に使用すれば、比較的安全と考えられていますが、内服薬や一部の局所免疫療法などは、胎児や乳児への影響を考慮して、通常は行われません。
- Q円形脱毛症と診断されたら、まず何をすべきですか
- A
円形脱毛症と診断されたら、現在の症状の程度、考えられる原因、治療方針、予後などについて、十分に理解しましょう。不安や疑問があれば、遠慮なく医師に質問してください。
日常生活では、バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレスを溜めない工夫などを心がけ、頭皮への過度な刺激は避けましょう。
参考文献
Sterkens A, Lambert J, Bervoets A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. Clinical and experimental medicine. 2021 May;21:215-30.
Thiedke CC. Alopecia in women. American family physician. 2003 Mar 1;67(5):1007-14.
Starace M, Orlando G, Alessandrini A, Piraccini BM. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology. 2020 Feb;21:69-84.
Levy LL, Emer JJ. Female pattern alopecia: current perspectives. International journal of women’s health. 2013 Aug 29:541-56.
Garg S, Messenger AG. Alopecia areata: evidence-based treatments. InSeminars in cutaneous medicine and surgery 2009 Mar 31 (Vol. 28, No. 1, pp. 15-18). No longer published by Elsevier.
Darwin E, Hirt PA, Fertig R, Doliner B, Delcanto G, Jimenez JJ. Alopecia areata: review of epidemiology, clinical features, pathogenesis, and new treatment options. International journal of trichology. 2018 Mar 1;10(2):51-60.
Trüeb RM, Dias MF. Alopecia areata: a comprehensive review of pathogenesis and management. Clinical reviews in allergy & immunology. 2018 Feb;54:68-87.