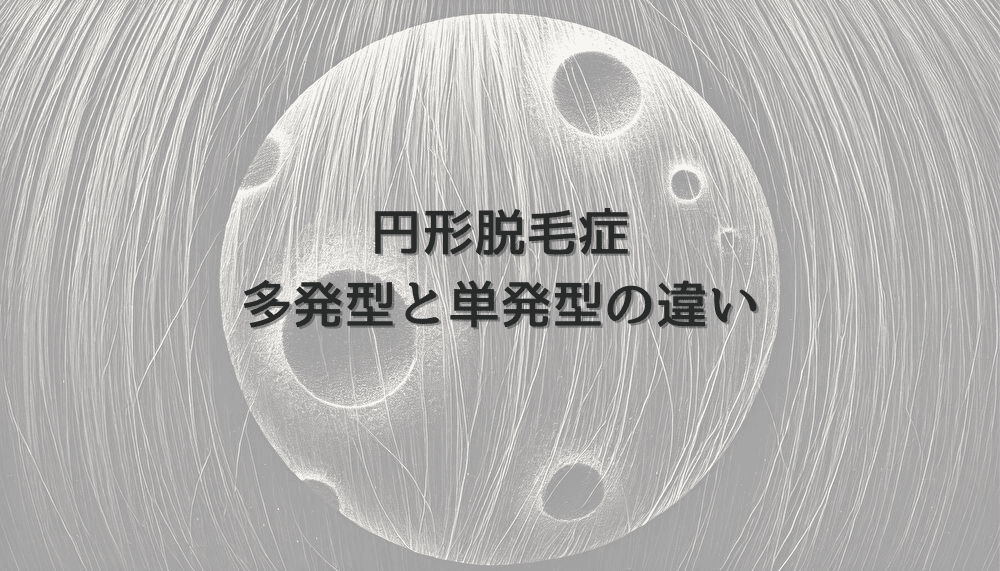この記事では、多くの女性が悩みを抱える円形脱毛症について、特に「単発型」と「多発型」の違いに焦点を当て、それぞれの特徴、原因、そして治療法について詳しく解説します。
円形脱毛症は、ある日突然、髪が円形や楕円形に抜けてしまう症状が出てきて、現れ方によって、単発型や多発型といった分類があります。
この記事を通じて、円形脱毛症に関する正しい知識を深め、ご自身の状態を理解する一助となれば幸いです。
円形脱毛症の基礎知識
円形脱毛症は、頭髪だけでなく、眉毛、まつ毛、体毛など、毛が生えている部分ならどこにでも発症する可能性のある脱毛症です。
円形脱毛症とは何か
円形脱毛症は、一般的に、コインのような円形または楕円形の脱毛斑が突然現れる疾患です。
脱毛斑の大きさや数は様々で、一つだけの場合もあれば、複数現れる場合、さらには頭全体の毛が抜けたり、全身の毛が抜けたりすることもあります。
かゆみや痛みを伴うことは少ないですが、発症前に軽いかゆみや違和感を覚える人もいて、多くの場合、毛根が残っているため、症状が改善すれば再び毛が生えてくる可能性があります。
しかし、症状の範囲や進行度合いによっては、治療が長期にわたることもあります。
単発型と多発型の基本的な違い
円形脱毛症は、脱毛斑の数や範囲によっていくつかのタイプに分類され、その中でも代表的なものが「単発型」と「多発型」です。
単発型は、脱毛斑が1ヶ所だけに限局して現れるタイプです。
多くの場合、自然に治癒することも期待できますが、中には脱毛斑が拡大したり、別の場所に新たな脱毛斑が出現して多発型へ移行したりすることもあります。
一方、多発型は、脱毛斑が2ヶ所以上に現れるタイプで、脱毛斑が融合して大きな脱毛巣を形成することもあり、単発型に比べて治療が難しく、長期間を要する傾向があります。
単発型と多発型の比較概要
| 項目 | 単発型 | 多発型 |
|---|---|---|
| 脱毛斑の数 | 1ヶ所 | 2ヶ所以上 |
| 自然治癒の可能性 | 比較的高い | 単発型より低い傾向 |
| 治療期間の目安 | 数ヶ月~1年程度 | 1年以上かかることも多い |
円形脱毛症 単発型の特徴と向き合い方
円形脱毛症の中でも、脱毛斑が1ヶ所だけにとどまる「単発型」は、比較的軽症例として扱われることが多いタイプですが、軽症だからといって油断はできません。
単発型の症状と進行の仕方
単発型の円形脱毛症は、ある日突然、頭部にコイン大程度の円形または楕円形の脱毛斑ができるのが典型的な症状です。
自覚症状はほとんどない場合が多いですが、発症初期に軽いかゆみや赤み、むくみなどを伴うこともあり、脱毛斑の境界は比較的はっきりしており、周囲の毛は正常に見えます。
多くの場合は数ヶ月で自然に新しい毛が生え始め、回復に向かいますが、中には脱毛斑が徐々に大きくなったり、数が増えて多発型に移行したりするケースもあります。
また、一度治っても再発する可能性も否定できないため、単発型であっても、経過を注意深く観察することが大切です。
単発型の診断と一般的な治療の流れ
単発型の円形脱毛症の診断は、主に視診によって行われ、医師は脱毛斑の形状、大きさ、数、頭皮の状態などを確認します。
ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いて毛根の状態や脱毛部の特徴を詳しく観察し、他の脱毛症との鑑別が必要な場合や、原因を探るために血液検査を行うこともあります。
治療は、脱毛範囲が狭く、症状が軽度な場合は、自然治癒を期待して経過観察とすることもありますが、脱毛斑の拡大傾向が見られる場合や、患者さんの精神的な負担が大きい場合には、積極的に治療を行います。
一般的な治療法は、ステロイド外用薬の塗布や、場合によってはステロイドの局所注射などです。
単発型円形脱毛症の初期対応
- 脱毛斑の発見
- 皮膚科専門医の受診
- 正確な診断
- 治療方針の決定
単発型の治療期間と予後
単発型の円形脱毛症の治療期間は、個人差が大きいですが、一般的には数ヶ月から1年程度で改善が見られることが多いです。
早い方では、治療開始後2~3ヶ月で産毛が生え始め、徐々に太くしっかりとした毛に成長していきます。しかし、すぐに効果が現れないからといって諦めず、根気強く治療を続けることが大切です。
予後はおおむね良好で、多くの方が回復しますが、前述の通り再発のリスクは常にあります。
円形脱毛症 多発型の特徴と向き合い方
脱毛斑が複数箇所に現れる「多発型」の円形脱毛症は、単発型に比べて症状が広範囲に及ぶことが多く、治療にも時間を要する傾向があります。
多発型の症状と進行の仕方
多発型の円形脱毛症では、頭部の複数箇所に脱毛斑が生じ、脱毛斑はそれぞれ独立していることもあれば、互いに融合して大きな不規則な形の脱毛巣を形成することもあります。
症状の進行は比較的早い場合があり、短期間のうちに脱毛範囲が急速に拡大することもあります。
中には、頭部全体の毛髪が失われる「全頭型」や、眉毛、まつ毛、体毛など全身の毛が抜ける「汎発型」へと進行するケースも見られます。
多発型の場合、脱毛の範囲が広いため、外見上の変化も大きく、患者さんの心理的なストレスは非常に深刻です。
多発型の診断と治療の選択肢
多発型の診断も、基本的には単発型と同様に視診やダーモスコピー検査によって行われ、脱毛の範囲や進行度、合併症の有無などを評価し、治療方針を決定します。
多発型の場合、治療はより積極的かつ長期的に行われることが一般的です。
治療の選択肢としては、ステロイド外用薬やステロイド局所注射に加え、局所免疫療法(SADBEやDPCPなどを用いたかぶれさせる治療法)、ステロイド内服療法、紫外線療法などが検討されます。
多発型円形脱毛症の主な治療法
| 治療法 | 概要 | 主な対象 |
|---|---|---|
| ステロイド外用 | 炎症を抑える塗り薬 | 軽症~中等症 |
| ステロイド局所注射 | 脱毛部に直接注射 | 範囲が限局した中等症 |
| 局所免疫療法 | 人工的にかぶれを起こし発毛を促す | 広範囲な場合、他の治療で効果不十分な場合 |
単発型と多発型を見分けるポイントと原因の探求
円形脱毛症と診断された場合、それが単発型なのか多発型なのかを把握することは、その後の治療方針や心構えにも影響します。
脱毛斑の数と範囲による見分け方
最も基本的な見分け方は、脱毛斑の数で、文字通り、単発型は脱毛斑が1ヶ所、多発型は2ヶ所以上ある状態です。
初期には単発型であっても、時間経過とともに新たな脱毛斑が出現し、多発型へ移行することもあります。
そのため、初診時の状態だけで判断せず、経過を観察することが重要で、また、脱毛斑の大きさや形状、融合の有無なども、重症度を判断する上で考慮されます。
考えられる円形脱毛症の主な原因
円形脱毛症の正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、現在最も有力視されているのは「自己免疫疾患」説です。
何らかの理由で免疫系に異常が生じ、自身の毛包組織を異物と誤認して攻撃してしまうことで、毛髪の成長が阻害され、脱毛が起こると考えられています。
円形脱毛症の主な原因と考えられるもの
- 自己免疫反応の異常
- 遺伝的素因
- 精神的ストレス
遺伝的素因については、家族内に円形脱毛症の人がいる場合、発症リスクがやや高まりますが、遺伝的素因があるからといって必ず発症するわけではなく、他の要因との組み合わせが重要です。
精神的ストレスも、発症の引き金や症状を悪化させる要因の一つとして指摘されています。過度なストレスは免疫系のバランスを崩し、自己免疫反応を誘発する可能性があるためです。
ただし、ストレスが直接的な原因であるとは断定できず、あくまで誘因の一つとして捉えられています。
アトピー素因との関連性
円形脱毛症の患者さんの中には、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎といったアトピー素因を持つ人が比較的多いです。
アトピー素因を持つ人は、免疫系が過敏に反応しやすい体質であるため、円形脱毛症の発症にも何らかの関連があるのではないかと考えられています。
実際に、アトピー素因を持つ円形脱毛症の患者さんは、症状が広範囲に及んだり、難治性であったりする傾向があるという報告もあります。
アトピー素因と円形脱毛症の関連で考慮される点
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 免疫系の過敏性 | アトピー素因を持つ人は免疫が過敏に反応しやすい傾向がある |
| 重症化リスク | アトピー素因があると円形脱毛症が重症化しやすい可能性が指摘される |
| 治療への影響 | 治療法の選択や効果に影響を与えることがある |
円形脱毛症の検査と診断プロセス
円形脱毛症の疑いがある場合、医療機関ではどのような検査が行われ、どのように診断が下されるのでしょうか。正確な診断は、適切な治療への第一歩です。
医療機関で行う主な検査内容
円形脱毛症の診断は、まず問診と視診から始まり、医師は患者さんから症状の経過や既往歴、家族歴などを詳しく聞き取ります。
その後、脱毛部の状態を直接観察し、円形脱毛症に特徴的な所見があるかどうかを確認します。
多くの場合、これらの情報で診断がつきますが、より詳細な情報や、他の脱毛症との鑑別がいる場合には、追加の検査が必要です。
問診の重要性と伝えるべき情報
問診は、診断において非常に重要な役割を果たし、医師は以下のような情報を得ることで、診断の手がかりや治療方針の決定に役立てます。
問診で医師に伝えてほしい主な情報
- いつから脱毛が始まったか
- 脱毛の範囲や進行の様子
- かゆみや痛みなどの自覚症状の有無
- 過去の円形脱毛症の経験
- アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の有無
- 甲状腺疾患などの自己免疫疾患の既往や家族歴
- 最近の大きなストレスや生活環境の変化
- 現在服用中の薬やサプリメント
ダーモスコピー検査とは
ダーモスコピー検査は、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を用いて、皮膚の表面や毛穴の状態を詳細に観察する検査です。
円形脱毛症の場合、脱毛部の毛穴の状態、残存している毛髪の形状(感嘆符毛など)、炎症の程度などを確認できます。
ダーモスコピーで観察される円形脱毛症の所見
| 所見 | 説明 |
|---|---|
| 感嘆符毛(!) | 毛根側が細く、毛先側が太くなっている切れ毛 |
| 黄色点(Yellow dots) | 毛穴に皮脂や角質が詰まって黄色く見える点 |
| 黒点(Black dots) | 毛穴に残った切れ毛の断端が黒い点として見える |
血液検査や皮膚生検を行うケース
円形脱毛症の診断は主に視診で行われますが、他の疾患との鑑別や、合併症の有無を確認するために血液検査を行うことがあります。
甲状腺疾患や膠原病といった自己免疫疾患は円形脱毛症と合併しやすいため、これらの疾患を除外したり、早期に発見したりする目的での検査です。
また、鉄欠乏性貧血なども脱毛の原因となることがあるため、必要に応じてチェックします。
皮膚生検は、局所麻酔をして脱毛部から小さな皮膚組織を採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。
通常、円形脱毛症の診断で必須ではありませんが、診断が困難な場合や、他のまれな脱毛症との鑑別が必要な場合に検討されます。
女性のための円形脱毛症治療法
円形脱毛症の治療法は、症状の範囲や進行度、患者さんの年齢や健康状態、ライフスタイルなどを総合的に考慮して選択されます。
外用薬による治療
脱毛範囲が比較的狭い場合や、軽症の円形脱毛症に対しては、まずステロイド外用薬(塗り薬)による治療が試みられることが一般的です。
ステロイドには免疫反応を抑制し、炎症を鎮める作用があり、毛包への攻撃を抑えることで発毛を促す効果が期待されます。
ステロイド外用薬には様々な強さのランクがあり、症状や部位に応じて選択され、医師の指示通りに、適切な量を適切な期間使用することが大切です。
その他、血行を促進する作用のある外用薬(塩化カルプロニウムなど)が併用されることもあります。
ステロイド外用薬の一般的な強さの分類
| ランク | 強さ | 主な使用場面 |
|---|---|---|
| 最強 (Strongest) | 非常に強い | 難治性の皮膚疾患(円形脱毛症では慎重に使用) |
| 非常に強力 (Very Strong) | かなり強い | 効果が求められる場合 |
| 強力 (Strong) | 強い | 一般的な強さ |
| 中程度 (Medium) | 比較的おだやか | 顔面や広範囲など |
| 弱い (Weak) | おだやか | 皮膚の薄い部位、乳幼児など |
局所注射療法
ステロイド局所注射療法は、脱毛斑に直接ステロイド薬を注射する治療法です。外用薬よりも薬剤が直接的かつ高濃度に作用するため、より高い効果が期待できます。
主に、脱毛範囲が限局しているものの、外用薬だけでは効果が不十分な場合や、比較的進行が早い場合に選択されます。
通常、数週間から1ヶ月に1回程度の頻度で治療を行いますが、注射時には痛みを伴うことや、注射部位が一時的に陥凹するなどの副作用が現れる可能性があります。
局所免疫療法
局所免疫療法は、SADBE(スクアレン酸ジブチルエステル)やDPCP(ジフェニルシクロプロペノン)といった特殊な化学物質を脱毛部に塗布し、人工的に軽いかぶれ(接触皮膚炎)を起こさせることで、毛包への免疫反応を変化させ、発毛を促す治療法です。
広範囲に及ぶ多発型や全頭型、汎発型の円形脱毛症に対して有効性が示されています。
治療は、まず感作(アレルギー反応を起こせる状態にする)を行い、その後、低濃度の試薬から徐々に濃度を上げていき、適切な強さのかぶれを維持するように調整します。
治療期間は長期にわたることが多く、根気が必要です。かゆみや赤み、腫れといったかぶれの症状が強く出ることがあるため、医師による慎重な管理が大切です。
その他の治療法
上記の治療法で効果が不十分な場合や、急速に進行する重症例に対しては、ステロイド内服療法が検討されます。
ステロイド内服薬は全身に作用するため、高い効果が期待できる一方で、長期間の使用や高用量の使用は、免疫力低下、糖尿病、骨粗鬆症、満月様顔貌などの全身性の副作用のリスクが伴います。
適応は慎重に判断され、通常は短期間の使用にとどめ、徐々に減量していくことが重要です。また、抗アレルギー薬やセファランチンなどの内服薬が補助的に用いられることもあります。
紫外線療法は、特定の波長の紫外線を脱毛部に照射することで、免疫反応を調節し発毛を促す治療法です。
エキシマランプやナローバンドUVBなどが用いられ、広範囲の脱毛にも対応可能で、比較的副作用が少ないとされていますが、効果には個人差があり、週に数回の通院が必要となる場合があります。
近年ではJAK阻害薬という新しいタイプの薬剤が、重症の円形脱毛症に対する治療薬として注目されていますが、まだ新しい治療法であり、長期的な安全性や有効性についてはさらなるデータの蓄積が待たれます。
日常生活でのセルフケアと心構え
円形脱毛症の治療と並行して、日常生活でのセルフケアや心構えも、症状の改善や再発予防にとって重要です。
頭皮と髪に優しい生活習慣
頭皮環境を健やかに保つことは、毛髪の成長にとって基本で、洗髪は、低刺激性のシャンプーを選び、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。
すすぎ残しがないように丁寧に洗い流すことも大切で、ドライヤーは、頭皮や髪に熱が集中しすぎないように、少し離して使用し、完全に乾かしすぎない程度に留めるのがポイントです。
また、パーマやヘアカラーは、頭皮や毛髪に負担をかける可能性があるため、症状が落ち着くまでは控えるか、医師に相談してから行うようにしましょう。
ブラッシングも、強く引っ張ったり、頭皮を傷つけたりしないように、優しく行うことを心がけてください。
バランスの取れた食事の重要性
健康な毛髪を育むためには、バランスの取れた食事が欠かせません。
毛髪の主成分であるタンパク質(肉、魚、大豆製品、卵など)はもちろんのこと、毛髪の成長をサポートするビタミンやミネラルも積極的に摂取しましょう。
特に、亜鉛(牡蠣、レバー、ナッツ類など)は毛髪の合成に、ビタミンB群(緑黄色野菜、魚介類、肉類など)は頭皮の新陳代謝に関与しています。
また、抗酸化作用のあるビタミンC(果物、野菜など)やビタミンE(ナッツ類、植物油など)も、頭皮の健康維持に役立ちます。
髪の健康に役立つ栄養素と主な食材
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 毛髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | 毛髪の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | レバー、魚介類、緑黄色野菜 |
ストレスとの上手な付き合い方
精神的なストレスは、円形脱毛症の発症や悪化の誘因の一つと考えられています。
現代社会においてストレスを完全になくすことは難しいですが、ストレスを溜め込みすぎないように、自分なりの解消法を見つけて実践することが重要です。
よくある質問
円形脱毛症に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
ただし、個々の症状や状況によって異なる場合があるため、あくまで一般的な情報として参考にし、詳しいことは必ず医師にご相談ください。
- Q円形脱毛症は治りますか
- A
多くの場合、円形脱毛症は適切な治療を行うことで治癒が期待できる疾患です。特に単発型の場合は、自然に治ることも少なくありません。
しかし、多発型や全頭型、汎発型といった重症のタイプでは、治療が長期にわたったり、難治性であったりすることもあります。また、一度治っても再発する可能性もあります。
大切なのは、早期に専門医の診断を受け、根気強く治療を続けることです。
- Q治療にはどれくらいの期間がかかりますか
- A
単発型で軽症の場合は、数ヶ月から1年程度で改善が見られることが多いですが、多発型や重症例では、1年以上、時には数年にわたる治療が必要となることもあります。
治療効果が現れるまでには時間がかかることを理解し、焦らずに医師の指示に従って治療を継続することが大切です。
- Q治療の副作用はありますか
- A
円形脱毛症の治療法には、それぞれ期待できる効果と共に、副作用が現れる可能性もあります。
ステロイド外用薬では、長期使用により皮膚が薄くなったり、毛細血管が拡張したりすることがありステロイド局所注射では、注射部位の痛みや陥凹、内出血などが起こりえます。局所免疫療法では、かぶれによるかゆみ、赤み、腫れなどが主な副作用で、ステロイド内服薬では、免疫力低下、糖尿病、骨粗鬆症などの全身性の副作用に注意が必要です。
- Q家族に円形脱毛症の人がいると遺伝しますか
- A
円形脱毛症の発症には、遺伝的な要因が関与していると考えられています。
家族内(特に一親等以内)に円形脱毛症の人がいる場合、そうでない人と比較して発症リスクがやや高まるという報告があります。
しかし、遺伝的素因を持つ人が必ずしも円形脱毛症を発症するわけではありません。
多くの場合、遺伝的素因に加えて、自己免疫の異常、精神的ストレス、アトピー素因といった他の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
参考文献
De Andrade FA, Giavedoni P, Keller J, Sainz-de-la-Maza MT, Ferrando J. Ocular findings in patients with alopecia areata: role of ultra-wide-field retinal imaging. Immunologic research. 2014 Dec;60:356-60.
Uchiyama M. Primary cicatricial alopecia: recent advances in evaluation and diagnosis based on trichoscopic and histopathological observation, including overlapping and specific features. The Journal of Dermatology. 2022 Jan;49(1):37-54.
Sterkens A, Lambert J, Bervoets A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. Clinical and experimental medicine. 2021 May;21:215-30.
Ohlmeier MC, Traupe H, Luger TA, Böhm M. Topical immunotherapy with diphenylcyclopropenone of patients with alopecia areata–a large retrospective study on 142 patients with a self‐controlled design. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2012 Apr;26(4):503-7.
Goksin S. Retrospective evaluation of clinical profile and comorbidities in patients with alopecia areata. Northern Clinics of Istanbul. 2022;9(5):451.
Echevarria FM, Roldan CS, Anderson A, Shastry JL. Multifocal alopecia of the scalp, axillae, and body. JAAD Case Reports. 2024 May 16;49:98.
Pratt CH, King LE, Messenger AG, Christiano AM, Sundberg JP. Alopecia areata. Nature reviews Disease primers. 2017 Mar 16;3(1):1-7.