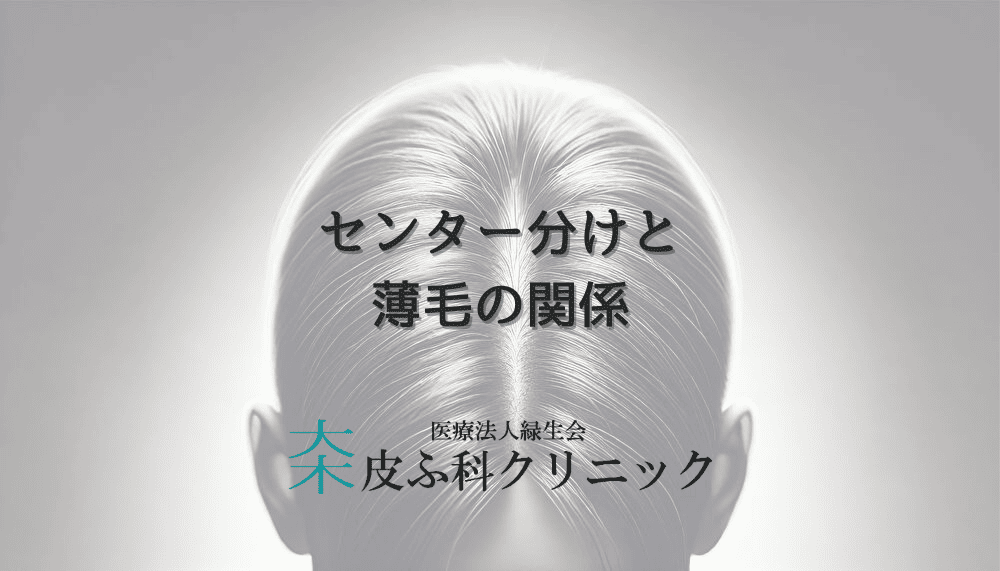いつも同じセンター分けにしていると分け目が目立ってくるのではないか、センター分けが薄毛の直接的な原因になるのではないか、と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、長期間同じ分け目を続けると頭皮への負担となり、薄毛の一因となる可能性があります。
しかし、女性の薄毛の原因はそれだけではありません。この記事ではセンター分けと薄毛の関係を解説し、女性の薄毛の様々な原因やご自身でできるセルフチェック方法、分け目を目立たなくするためのヘアケアや髪型の工夫についてご紹介します。
センター分けで分け目が薄くなる?その真相とは
長年センター分けを続けていると分け目部分の髪が薄くなったように感じることがあります。ここではセンター分けと薄毛の関係について詳しく見ていきます。
長期間同じ分け目を続けるリスク
毎日同じ箇所で髪を分けていると、その部分の頭皮や毛根に継続的な力が加わります。髪の重さによる引っ張る力や、ブラッシング時の摩擦などが特定のラインに集中するためです。
この負担が長期間続くと毛根が弱り、髪が細くなったり抜けやすくなったりする可能性があります。特に髪が長い方や量が多い方は、分け目にかかる負担も大きくなる傾向があります。
定期的に分け目を変えて、このリスクを分散させる工夫が大切です。
牽引性脱毛症の可能性
常に髪を強く引っ張るような髪型を続けることで起こる脱毛症を「牽引性脱毛症」といいます。
ポニーテールやきついお団子ヘアなどが原因としてよく知られていますが、長期間同じ分け目を続けると分け目部分の毛根に持続的な牽引力を与え、牽引性脱毛症を引き起こす可能性があります。
牽引性脱毛症のリスクを高める要因
| 要因 | 詳細 |
|---|---|
| 長期間同じ分け目 | 特定の毛根への継続的な負担 |
| 髪を強く引っ張る髪型 | ポニーテール、お団子、編み込みなど |
| ヘアアクセサリーの重さ | 重い髪飾りやエクステンションの使用 |
分け目部分の髪が細くなったり、地肌が透けて見えやすくなったりした場合は注意が必要です。
頭皮への紫外線ダメージの影響
分け目は頭皮が露出しやすく、直接紫外線を浴びやすい部分です。紫外線は肌だけでなく頭皮にもダメージを与え、乾燥や炎症を引き起こします。
頭皮環境が悪化すると健康な髪の成長が妨げられ、抜け毛や薄毛につながる場合があります。センター分けは特に頭頂部の中心線が常に露出するため、紫外線対策を怠るとダメージが蓄積しやすいといえます。
帽子や日傘、頭皮用の日焼け止めスプレーなどを活用して、分け目部分の頭皮を紫外線から守ることが重要です。
センター分け=薄毛ではない点も説明
ここまでセンター分けが薄毛につながる可能性について説明しましたが、センター分けをしている全ての人が薄毛になるわけではありません。
髪質や頭皮の状態、ヘアケアの方法、生活習慣など様々な要因が関わってきます。
センター分け自体が“悪”なのではなく、長期間同じ状態を続けることによる負担の蓄積や、紫外線対策の不足などが問題となるのです。過度に心配せず、適切なケアを心がけると良いです。
女性の薄毛を引き起こす主な原因
センター分け以外にも女性の薄毛を引き起こす原因は様々です。ご自身の薄毛の原因を知ることが適切な対策への第一歩となります。
女性型脱毛症(FAGA)やびまん性脱毛症
女性の薄毛で最も多いとされるのが女性型脱毛症(FAGA: Female Androgenetic Alopecia)です。
男性型脱毛症(AGA)とは異なり、生え際が後退するのではなく、頭頂部を中心に髪が全体的に薄くなる(びまん性)のが特徴です。
髪のハリやコシがなくなり、分け目が広くなったように感じる傾向があり、加齢やホルモンバランスの変化が主な原因と考えられています。
びまん性脱毛症も同様に髪全体が薄くなる症状で、特定の原因がはっきりしない場合もあります。
加齢とホルモンバランスの変化
年齢を重ねるとともに、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が減少します。エストロゲンは髪の成長を促進してハリやツヤを保つ働きがあるため、その減少は髪の成長サイクルの乱れにつながります。
特に更年期を迎えるとホルモンバランスが大きく変化し、薄毛や抜け毛が目立ちやすくなるケースがあります。
また、妊娠・出産後の一時的なホルモン変化によって抜け毛が増える方もいます(分娩後脱毛症)。
女性ホルモンと髪の関係
| ホルモン | 髪への影響 |
|---|---|
| エストロゲン | 髪の成長促進、ハリ・ツヤ維持、成長期の維持 |
| プロゲステロン | 髪の成長期を維持する働きをサポート |
| アンドロゲン | 過剰になると髪の成長を抑制する可能性(FAGA関連) |
生活習慣(食生活、睡眠、ストレス)の影響
健やかな髪を育むためには、バランスの取れた食生活、質の高い睡眠、そしてストレスを溜めない生活が重要です。
髪の主成分であるタンパク質や、髪の成長をサポートする亜鉛、鉄、ビタミンB群などを意識して摂取しましょう。
髪の成長ホルモンは睡眠中に分泌されます。そのため、十分な睡眠時間を確保し、質の高い睡眠を心がけると良いでしょう。
さらに、過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を引き起こして頭皮環境を悪化させて抜け毛の原因となるケースがあります。
誤ったヘアケア
毎日行うヘアケアも、方法を間違えると頭皮や髪にダメージを与え、薄毛の原因となりやすいです。
洗浄力の強すぎるシャンプー、ゴシゴシ洗う、熱すぎるお湯でのすすぎ、ドライヤーの熱風を当てすぎるなどの行動が頭皮の乾燥や炎症を招きます。
また、パーマやカラーリングの頻度が高すぎると、薬剤が頭皮や髪に負担をかける場合もあります。自分の髪質や頭皮の状態に合った優しいケアを心がけましょう。
見直したいヘアケア習慣
| NGな習慣 | 改善策 |
|---|---|
| 洗浄力の強すぎるシャンプー | アミノ酸系などマイルドな洗浄成分を選ぶ |
| ゴシゴシ洗い | 指の腹で優しくマッサージするように洗う |
| 熱すぎるお湯でのすすぎ | ぬるま湯(38度前後)を使用する |
| ドライヤーの熱風を近づけすぎる | 20cm以上離し、同じ場所に当て続けない |
| 自然乾燥 | 雑菌繁殖や頭皮の冷えを防ぐため早めに乾かす |
もしかして薄毛?分け目のセルフチェック
分け目が以前より目立つ気がすると感じたら、ご自身の頭皮や髪の状態を客観的にチェックしてみましょう。早期に変化に気づくことが、適切な対策につながります。
分け目の幅の変化を確認する
鏡を使って、分け目の幅が以前と比べて広がっていないか確認します。特に頭頂部の分け目は自分では見えにくいため、手鏡を使ったりスマートフォンのカメラで撮影したりしてチェックすると良いでしょう。
分け目部分の地肌が透けて見える範囲が広くなっている場合は、薄毛が進行している可能性があります。
頭皮の色や硬さをチェック
健康な頭皮は青白い色をしていますが、血行が悪くなると黄色っぽくくすんだり、炎症があると赤みを帯びたりします。
指の腹で頭皮全体を優しく触ってみて、色や硬さを確認しましょう。頭皮が硬く、指で動かしたときに動きにくい場合は、血行不良のサインかもしれません。
頭皮の状態チェックポイント
| 状態 | 健康な状態 | 注意が必要な状態 |
|---|---|---|
| 色 | 青白い | 赤み、黄色っぽさ、茶色っぽさ |
| 硬さ | 弾力がある | 硬い、ぶよぶよしている |
| その他 | 適度な潤い | 乾燥、フケ、かゆみ、べたつき |
抜け毛の本数や毛質の変化
1日の抜け毛の本数は、通常50本から100本程度と言われています。排水溝や枕についた抜け毛の量が明らかに増えたと感じるときは注意が必要です。
また、抜けた毛の中に細くて短い毛や、以前よりコシがなくなった毛が増えていないかも確認しましょう。毛周期が乱れ、髪が十分に成長する前に抜けてしまっている可能性があります。
以前の写真と比較する
過去に撮った写真、特に髪型が分かりやすい写真と現在の状態を比較してみるのも有効です。
分け目の幅や髪全体のボリューム感の変化を確認できます。定期的に同じ角度から写真を撮っておくと、変化に気づきやすくなります。
センター分けによる薄毛を防ぐ・改善するセルフケア
分け目の薄毛が気になり始めたら、まずは毎日のセルフケアを見直してみましょう。頭皮環境を整え、髪への負担を減らすことが大切です。
定期的に分け目を変える重要性
同じ分け目を続けて起こる頭皮への負担や紫外線ダメージを避けるために、定期的に分け目の位置を変えることをおすすめします。
毎日変えるのが理想ですが、難しければ数日ごとや1週間ごとでも構いません。
センター分けだけでなく、右寄り、左寄り、あるいはジグザグに分けるなど、分け目の位置をランダムに変えて特定の部分への負担集中を防ぎます。
分け目を変える頻度の目安
| 頻度 | 効果 |
|---|---|
| 毎日 | 最も負担分散効果が高い |
| 2~3日ごと | 比較的負担を分散できる |
| 1週間ごと | 最低限この頻度では変えたい |
正しいシャンプーと頭皮ケア
頭皮環境を健やかに保つためには、正しいシャンプー方法が基本です。
まず、シャンプー前にブラッシングで髪の絡まりをほどき、ホコリなどを落とします。次にぬるま湯で頭皮と髪を十分に予洗いし、汚れの大部分を洗い流します。
シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮を優しくマッサージするように洗いましょう。すすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流します。
シャンプー後は、頭皮用の保湿ローションや美容液などでケアするのも良いでしょう。
頭皮マッサージの方法と注意点
頭皮マッサージは血行を促進し、頭皮を柔らかく保つのに役立ちます。
指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージします。強くこすったり、爪を立てたりしないように注意してください。気持ち良いと感じる程度の力加減で行いましょう。
シャンプー中や、お風呂上がりで血行が良くなっている時に行うのが効果的です。
簡単な頭皮マッサージ
- 指の腹を生え際に当て、頭頂部に向かって円を描くように揉みほぐす。
- 側頭部(耳の上あたり)に指の腹を当て、同様に頭頂部へ向かって引き上げるようにマッサージする。
- 後頭部(首の付け根あたり)から頭頂部へ向かって指圧するように押していく。
紫外線対策(帽子、日傘、UVスプレー)
分け目部分の頭皮を紫外線ダメージから守ることが非常に重要です。外出時には帽子や日傘を使用しましょう。
特に日差しの強い季節や時間帯は必須です。帽子は通気性の良いものを選び、蒸れに注意してください。
また、髪や頭皮に使えるスプレータイプの日焼け止めを活用するのも手軽で効果的です。分け目を中心に、頭皮全体にスプレーしておくと安心です。
紫外線対策グッズ
| グッズ | ポイント |
|---|---|
| 帽子 | UVカット効果のあるもの、通気性の良い素材 |
| 日傘 | UVカット率の高いもの、遮光性の高い色 |
| 頭皮用UVスプレー | スプレータイプで手軽、白くならないもの |
薄毛を目立たせない髪型とスタイリングの工夫
分け目の薄さや髪全体のボリュームダウンが気になる場合、髪型やスタイリングを少し工夫するだけで、見た目の印象を大きく変えられます。
分け目を変える、ジグザグにする
最も手軽な方法は、分け目の位置を変えることです。センター分けからサイドパート(左右どちらかに寄せる)にするだけで、薄さが目立ちにくくなります。
また、分け目を直線ではなくジグザグにするのも効果的です。
コームの柄などを使って分け目をジグザグにとり、根元を少し立ち上げるようにスタイリングすると、地肌の露出が抑えられてトップに自然なボリューム感が出ます。
前髪を作るスタイル
前髪を作ると視線が顔周りに集まり、分け目や頭頂部の薄さから注意をそらす効果が期待できます。
厚めの前髪やサイドに流す長めの前髪(斜めバング)などは、気になる部分をカバーしつつ、おしゃれな印象を与えます。
美容師さんと相談して、ご自身の顔型や髪質に合った前髪スタイルを見つけましょう。
トップにボリュームを出すスタイリング術
髪の根元を立ち上げてトップにボリューム感を出すと、薄毛が目立ちにくくなります。
ドライヤーで髪を乾かす際に、髪の根元を下から持ち上げるように風を当てたり、分け目と逆方向から乾かしたりすると自然なボリュームが出やすくなります。
マジックカーラーやヘアアイロンを使って根元を巻くのも効果的です。仕上げに、キープ力のある軽い質感のスタイリング剤を少量使うと、ボリューム感を維持しやすくなります。
トップにボリュームを出すアイテム
| アイテム | 使い方 |
|---|---|
| ドライヤー | 根元を持ち上げながら、下から風を当てる |
| マジックカーラー | 乾いた髪のトップ部分の根元に巻き、ドライヤーで温める |
| ヘアアイロン | 根元近くを挟み、軽く持ち上げるように熱を加える |
| スタイリング剤 | 根元付近にスプレーやムースを少量つけ、立ち上がりをキープ |
パーマやヘアカットの相談
パーマをかけると、髪全体にボリュームと動きを出せます。特にトップ部分にゆるめのパーマをかけると、スタイリングが楽になり、薄毛を目立たなくする効果が期待できます。
また、髪の重さでトップがぺたんとなりやすい方はレイヤー(段)を入れるカットで、軽さと動きを出すのも良いでしょう。
信頼できる美容師さんに薄毛の悩みを相談し、カバーしやすい髪型やスタイリング方法についてアドバイスをもらうと良いでしょう。
専門クリニックで相談できる薄毛治療
セルフケアや髪型の工夫だけでは改善が見られない、あるいは薄毛の原因を正確に知りたい場合は、薄毛治療専門クリニックへの相談を検討しましょう。
セルフケアで改善しない場合の選択肢
様々なセルフケアを試しても抜け毛が減らない、分け目の薄さが進行するといった場合は、FAGAなど医学的な治療が必要な薄毛の可能性があります。
自己判断でケアを続けるよりも、専門医の診察を受けると原因に応じた適切な治療を開始できます。早期に治療を始めることが、改善への近道となる場合が多いです。
クリニックでの診断の流れ
クリニックではまず、問診で生活習慣や既往歴、薄毛の悩みなどを詳しく伺います。
その後、視診や触診で頭皮や髪の状態を確認し、必要に応じてマイクロスコープで毛穴や毛髪の状態を拡大して観察したり、血液検査でホルモンバランスや栄養状態を調べたりします。
これらの結果を総合的に判断し、薄毛の原因を診断します。
女性向け薄毛治療の種類(内服薬、外用薬、注入療法など)
女性の薄毛治療には、内服薬や外用薬、注入療法といった選択肢があります。原因や症状の程度、患者さんの希望に合わせて治療法を選択します。
主な女性向け薄毛治療法
女性の薄毛には、スピロノラクトンのようなホルモンバランスに働きかける内服薬が処方される場合があります。
また、外用薬としてミノキシジル配合の発毛剤も存在します。頭皮に直接塗布し、毛母細胞の活性化や血行促進効果を期待できる塗り薬です。
頭皮に直接、髪の成長を促す成分(成長因子など)を注入する注入療法を行うクリニックもあります。具体的には、メソセラピーやHARG療法といった治療法です。
| 治療法 | 特徴 |
|---|---|
| 内服薬 | ホルモンバランス調整など(医師の処方が必要) |
| 外用薬 | ミノキシジル配合の発毛剤(市販薬もあるが、クリニック処方も) |
| 注入療法 | 頭皮に直接有効成分を注入(メソセラピー、HARG療法など) |
治療を選択する際のポイント
薄毛治療は、効果が現れるまでに時間がかかるのが一般的です。また、治療によっては副作用のリスクも考慮する必要があります。
治療法を選択する際は、医師からそれぞれの治療法の効果、期間、費用、メリット・デメリットについて十分な説明を受け、ご自身の生活スタイルや考えに合った方法を納得した上で選ぶことが重要です。
疑問や不安な点は遠慮なく医師に質問しましょう。
よくある質問
センター分けや女性の薄毛に関して、患者さんからよくいただく質問とその回答を以下にまとめました。
- Q分け目を変える頻度は?
- A
A理想は毎日変えることですが、難しい場合は2~3日ごと、最低でも1週間ごとに変えるのをおすすめします。同じ分け目を長期間続けないことが重要です。
- Q市販の育毛剤は効果がありますか?
- A
市販の育毛剤には、頭皮環境を整える成分や血行を促進する成分が含まれているものが多いですが、発毛効果が医学的に認められている成分(ミノキシジルなど)の濃度は医療用医薬品より低い場合があります。
軽度の薄毛予防や頭皮ケアとしては有効な場合もありますが、FAGAなど進行性の薄毛に対しては、専門クリニックでの診断と治療が推奨されます。
- Q治療にはどれくらいの期間がかかりますか?
- A
治療法や薄毛の進行度、個人差によって異なりますが、一般的に効果を実感するまでには3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。
ヘアサイクル(毛周期)の関係上、すぐに効果が出るものではありません。根気強く治療を続けましょう。
- Q治療の費用は?
- A
女性の薄毛治療は、基本的に健康保険適用外の自由診療となるため、費用はクリニックや治療内容によって大きく異なります。
内服薬や外用薬は比較的安価ですが、注入療法などは高額になる傾向があります。治療を開始する前に、必ず費用について確認し、無理なく続けられる計画を立てましょう。
カウンセリング時に詳細な費用を確認しておくと安心です。
参考文献
BIRCH, M. P.; MESSENGER, J. F.; MESSENGER, A. G. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2001, 144.2: 297-304.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
BIRCH, M. P.; LALLA, S. C.; MESSENGER, A. G. Female pattern hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 383-388.
LEVY, Lauren L.; EMER, Jason J. Female pattern alopecia: current perspectives. International journal of women’s health, 2013, 541-556.
LUCKY, Anne W., et al. A randomized, placebo-controlled trial of 5% and 2% topical minoxidil solutions in the treatment of female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2004, 50.4: 541-553.
STENN, K. S.; PAUS, Ralf. Controls of hair follicle cycling. Physiological reviews, 2001, 81.1: 449-494.
PRICE, Vera H. Treatment of hair loss. New England Journal of Medicine, 1999, 341.13: 964-973.
WERNER, Betina; MULINARI-BRENNER, Fabiane. Clinical and histological challenge in the differential diagnosis of diffuse alopecia: female androgenetic alopecia, telogen effluvium and alopecia areata-part I. Anais brasileiros de dermatologia, 2012, 87: 742-747.