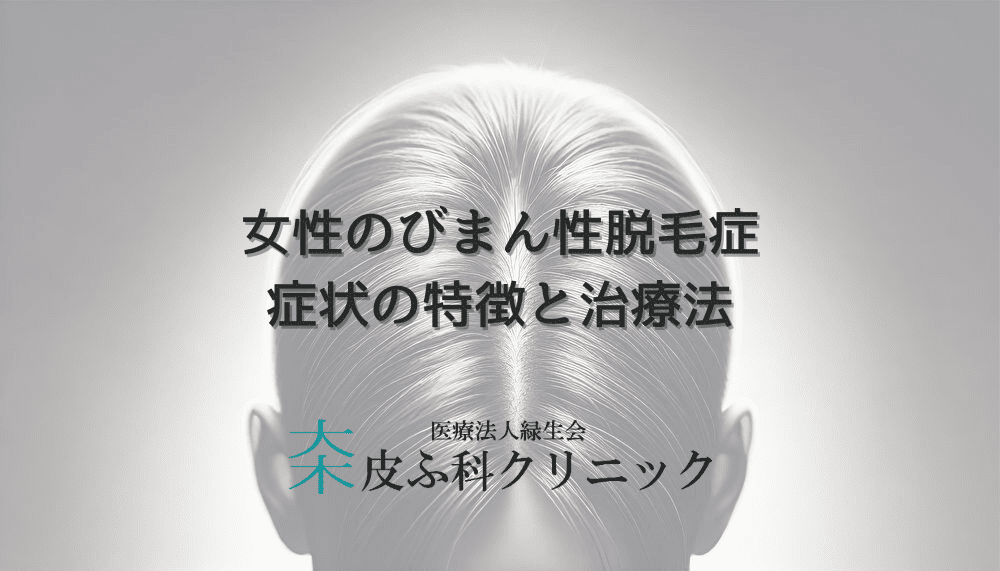最近、髪全体のボリュームが減ってきた、分け目が目立つようになったと感じていたら、それは「びまん性脱毛症」のサインかもしれません。
びまん性脱毛症は、特に女性に多く見られる薄毛の状態で、髪が全体的に薄くなるのが特徴です。
特定の部位だけが抜ける円形脱毛症とは異なり、気づきにくいケースもありますが、進行すると見た目の印象に大きく影響します。
びまん性脱毛症とは?女性に多い脱毛症の特徴
はじめに、女性によく見られる「びまん性脱毛症」の基本的な情報と、他の脱毛症との違いについて説明します。
びまん性脱毛症の基本的な定義
びまん性脱毛症は、特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる脱毛症です。
「びまん」とは「全体に広がる」という意味を持ち、その名の通り、髪の密度が全体的に低下します。
髪の毛一本一本が細くなったり、ハリやコシが失われたりするのも特徴です。男性型脱毛症(AGA)のように生え際が後退したり、頭頂部が薄くなったりするパターンとは異なります。
女性特有の脱毛パターン
女性の薄毛は、男性とは異なるパターンを示す例が多いです。びまん性脱毛症は、その代表的な例と言えるでしょう。
頭頂部の分け目を中心に、地肌が透けて見える範囲が徐々に広がっていくのが典型的な症状です。
髪全体のボリュームダウンとして自覚される場合が多く、進行しても完全に脱毛することは稀ですが、見た目の印象に変化が現れます。
他の脱毛症との主な違い
女性が経験する脱毛症には様々な種類があります。びまん性脱毛症の他に、円形脱毛症や牽引性脱毛症、分娩後脱毛症などが知られています。
円形脱毛症は、円形または楕円形の脱毛斑が突然現れる自己免疫疾患と考えられています。牽引性脱毛症は、ポニーテールなど髪を強く引っ張る髪型を長期間続けると起こります。
それぞれの脱毛症は原因や症状の現れ方が異なるため、正確な診断が治療への第一歩となります。
主な女性の脱毛症の種類と比較
| 脱毛症の種類 | 主な特徴 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| びまん性脱毛症 | 頭部全体の髪が均等に薄くなる | ホルモンバランス、生活習慣、加齢、ストレス、疾患など |
| 円形脱毛症 | 円形・楕円形の脱毛斑が突然出現する | 自己免疫疾患、ストレス、遺伝など |
| 牽引性脱毛症 | 髪を強く引っ張ることで生え際などが薄くなる | 特定の髪型(ポニーテールなど) |
| 分娩後脱毛症 | 出産後に一時的に抜け毛が増加する | 女性ホルモンの急激な変化 |
| 脂漏性脱毛症 | 過剰な皮脂分泌により頭皮環境が悪化し脱毛 | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖 |
びまん性脱毛症の具体的な症状
ここでは、びまん性脱毛症がどのように現れるのか、具体的な症状について解説します。早期発見のために、ご自身の髪や頭皮の状態をチェックしてみましょう。
初期症状を見逃さないために
びまん性脱毛症の初期症状は、非常に気づきにくいことがあります。
以下のような変化に注意してください。
- シャンプーやブラッシング時の抜け毛が以前より増えた
- 髪の毛が細くなり、ハリやコシがなくなった
- 髪全体のボリュームが減り、スタイリングが決まりにくくなった
- 分け目が以前より目立つようになった、地肌が透けて見える
これらのサインは、単なる髪のダメージや一時的な体調不良と思われがちですが、びまん性脱毛症の始まりである可能性も考えられます。
進行すると現れる症状
初期症状に気づかず放置してしまうと、症状は徐々に進行します。
頭頂部を中心に地肌の見える範囲が広がり、髪全体の密度が明らかに低下します。髪の毛はさらに細く、弱々しくなり、ツヤも失われがちです。
側頭部や後頭部の髪も薄くなるケースがありますが、男性型脱毛症のように生え際が大きく後退する方は少ないです。
自己チェックの方法
ご自身の髪の状態を客観的に把握するために、定期的なセルフチェックをおすすめします。
明るい場所で手鏡などを使い、分け目、つむじ周り、生え際などを観察しましょう。スマートフォンのカメラで頭頂部などを撮影し、過去の写真と比較するのも有効です。
抜け毛の本数を毎日数える必要はありませんが、枕カバーや排水溝に溜まる毛量に著しい変化がないか意識すると良いです。
びまん性脱毛症の進行度チェック
- 抜け毛の量が増えたと感じる
- 髪の毛が細くなった、コシがなくなったと感じる
- 髪全体のボリュームが減ったと感じる
- 分け目が目立つ、地肌が透けて見えるようになった
- 髪のツヤが失われたように感じる
複数の項目に該当する場合は、専門医への相談を検討しましょう。
びまん性脱毛症の考えられる原因
びまん性脱毛症は単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発症するケースが多いと考えられています。
ホルモンバランスの乱れ
女性ホルモン(エストロゲン)は髪の成長を促進し、その維持に重要な役割を果たしています。
加齢、妊娠・出産、更年期、ストレス、不規則な生活、婦人科系の疾患などによってホルモンバランスが乱れると髪の成長期が短縮され、休止期に入る毛包が増えることで抜け毛が増加し、びまん性脱毛症を引き起こす可能性があります。
特に、閉経後はエストロゲンの分泌が急激に減少するため、薄毛の悩みが増える傾向があります。
生活習慣の影響(食生活、睡眠、ストレス)
髪の健康は、日々の生活習慣と密接に関連しています。
偏った食生活による栄養不足、特に髪の主成分であるタンパク質や、髪の成長を助ける亜鉛、ビタミンB群などの不足は、髪の毛を細く弱くする原因となります。
睡眠不足は成長ホルモンの分泌を妨げ、髪の成長サイクルに悪影響を与えます。
また、過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を引き起こすことで、頭皮環境を悪化させて抜け毛を促進する可能性があります。
脱毛に関連する栄養素と食品例
| 栄養素 | 役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類、チーズ |
| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を促進する | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、カツオ、卵、納豆 |
| ビタミンC | コラーゲン生成、抗酸化作用 | 果物(柑橘類、キウイなど)、野菜(ピーマン、ブロッコリーなど) |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、植物油、うなぎ |
| 鉄分 | 酸素運搬、毛母細胞への栄養供給 | レバー、赤身肉、ほうれん草、小松菜、ひじき |
加齢による変化
年齢を重ねるとともに、体の様々な機能が変化します。髪の毛も例外ではなく、毛母細胞の活動が低下して髪の成長サイクル(ヘアサイクル)が乱れやすいです。
成長期が短くなり、休止期や退行期にとどまる毛髪の割合が増えるため、髪全体のボリュームが減少して薄毛が目立つようになります。
また、加齢に伴う血行不良や女性ホルモンの減少も、びまん性脱毛症の進行に関与します。
その他の要因(遺伝、薬剤、疾患)
薄毛になりやすい体質は、遺伝的な要因も関与すると考えられています。ただし、遺伝が全てではなく、生活習慣や環境要因も大きく影響します。
特定の薬剤(抗がん剤、一部の降圧剤など)の副作用として脱毛が起こる方もいます。
また、甲状腺機能低下症や膠原病などの全身性の疾患、あるいは頭皮の皮膚炎(脂漏性皮膚炎など)が原因で脱毛が引き起こされるケースもあります。
貧血、特に鉄欠乏性貧血も抜け毛の原因となる場合があります。
びまん性脱毛症と円形脱毛症の違い
薄毛の悩みの中でも、びまん性脱毛症と円形脱毛症は混同されることがありますが、その原因や症状の現れ方には明確な違いがあります。
ここでは、二つの脱毛症の違いについて詳しく解説します。
脱毛範囲とパターンの違い
最も大きな違いは、脱毛する範囲とパターンです。
びまん性脱毛症は頭部全体の髪が徐々に、そして均等に薄くなるのが特徴です。分け目を中心に地肌が透けて見えるようになりますが、脱毛範囲の境界は不明瞭です。
一方、円形脱毛症は多くの場合、コインのような円形または楕円形の脱毛斑が突然現れます。脱毛部分の境界は比較的はっきりしており、地肌が完全に見える状態になります。
円形脱毛症の脱毛斑は1箇所だけでなく、複数箇所に現れたり、頭部全体に広がったりするケースも少なくありません。
発症の原因の違い
発症の原因も異なります。びまん性脱毛症は、ホルモンバランスの乱れ、加齢、生活習慣、栄養不足、ストレスなど、複数の要因が複合的に関与して発症すると考えられています。
対照的に、円形脱毛症は、免疫系の異常により自身の毛包組織を攻撃してしまう自己免疫疾患が主な原因と考えられています。
精神的なストレスが発症や悪化の引き金になるケースもありますが、ストレスだけが原因ではありません。
アトピー素因(アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎など)を持つ人に発症しやすい傾向も指摘されています。
びまん性脱毛症と円形脱毛症の比較
| 項目 | びまん性脱毛症 | 円形脱毛症 |
|---|---|---|
| 脱毛パターン | 頭部全体の髪が均等に薄くなる、境界不明瞭 | 円形・楕円形の脱毛斑、境界明瞭 |
| 進行 | 徐々に進行 | 突然発症することが多い |
| 主な原因 | ホルモンバランス、加齢、生活習慣、ストレスなど | 自己免疫疾患、ストレス(誘因)、アトピー素因、遺伝など |
| 好発年齢 | 中高年女性に多い | 年齢・性別問わず発症する |
| 併発疾患 | 甲状腺疾患、貧血などとの関連が指摘される | 自己免疫疾患(甲状腺疾患、尋常性白斑など)との合併あり |
併発の可能性について
基本的には異なる原因で発症する二つの脱毛症ですが、稀に併発する可能性も否定できません。
例えば、びまん性脱毛症の背景がある方が、ストレスなどをきっかけに円形脱毛症を発症するというケースも考えられます。
自己判断は難しいため、脱毛の症状に気づいたら早めに専門医に相談し、正確な診断を受けることが重要です。脱毛症の種類によって適切な対処法や治療法が異なります。
クリニックでの診断と検査
薄毛や抜け毛の悩みを抱えてクリニックを受診した場合、どのような診察や検査が行われるのでしょうか。
ここでは、びまん性脱毛症を診断するための一般的な流れについて説明します。
専門医による問診の重要性
診断において、問診は非常に重要です。
いつから脱毛が気になり始めたか、どのような症状があるか(抜け毛の量、髪質の変化、頭皮のかゆみや痛みなど)、進行の程度、既往歴、家族歴(血縁者に薄毛の人がいるか)、生活習慣(食事、睡眠、ストレス、喫煙・飲酒習慣)、使用中の薬剤、ヘアケアの方法などについて、詳しく質問します。
これらの情報は、脱毛の原因を探り、適切な診断を下すための重要な手がかりとなります。月経周期や妊娠・出産の経験など、女性特有の項目についても確認します。
視診と触診
問診に続いて、医師が直接頭皮や毛髪の状態を確認します。視診では脱毛の範囲やパターン、程度、頭皮の色や状態(赤み、湿疹、フケ、乾燥など)、毛髪の太さや密度などを詳細に観察します。
マイクロスコープなどを用いて頭皮や毛穴の状態を拡大して観察する場合もあります。
触診では、髪の毛を軽く引っ張ってみて、抜けやすさ(抜け毛抵抗)を確認したり、頭皮の硬さや弾力性を確かめたりします。
血液検査でわかること
びまん性脱毛症の原因として、全身性の疾患や栄養状態が関与している可能性が考えられるときは、血液検査を行います。
血液検査では甲状腺機能(甲状腺ホルモン)、貧血の有無(ヘモグロビン、フェリチンなど)、亜鉛などのミネラル、女性ホルモンの値などを調べられます。
これらの検査結果は、脱毛の原因特定や治療方針の決定に役立ちます。例えば、甲状腺機能低下症や鉄欠乏性貧血が見つかれば、その治療を優先する必要があります。
びまん性脱毛症の診断で用いられる主な検査
| 検査の種類 | 目的 | 検査内容 |
|---|---|---|
| 問診 | 症状、既往歴、生活習慣などの情報を収集し、原因を探る | 発症時期、進行度、家族歴、服用薬、ストレス状況などの聴取 |
| 視診・触診 | 頭皮・毛髪の状態を直接観察・評価する | 脱毛範囲・パターン確認、頭皮の色・炎症チェック、毛髪の太さ・密度評価 |
| 血液検査 | 全身疾患や栄養状態の影響を調べる | 甲状腺ホルモン、鉄、フェリチン、亜鉛、女性ホルモンなどの測定 |
| 頭皮マイクロスコープ検査 | 頭皮や毛穴の状態を拡大して詳細に観察する | 毛穴の詰まり、皮脂量、炎症、毛髪の太さなどの確認 |
| (必要に応じて)生検 | 他の脱毛症との鑑別が難しい場合などに、頭皮組織を採取して検査 | 病理組織学的検査 |
頭皮マイクロスコープ検査
頭皮マイクロスコープ検査は、肉眼では確認できない頭皮や毛穴の状態、髪の毛の太さなどを数十倍から数百倍に拡大して観察する検査です。
毛穴の詰まり具合、皮脂の分泌量、頭皮の炎症の有無、生えている毛髪の太さや密度などを詳細に評価できます。
これにより、びまん性脱毛症の診断補助や、脂漏性皮膚炎など他の頭皮トラブルの合併の有無を確認するのに役立ちます。治療効果の判定にも用いられるときがあります。
女性のびまん性脱毛症に対する治療法
びまん性脱毛症と診断された場合、クリニックでは、原因や症状の程度、患者さんの希望などを考慮して様々な治療法を組み合わせて行います。
内服薬による治療(ミノキシジル、スピロノラクトンなど)
内服薬は体の内側から発毛を促進したり、抜け毛の原因に働きかけたりする治療法です。
ミノキシジルはもともと高血圧の治療薬として開発されましたが、発毛効果があることがわかり、薄毛治療薬として用いられています。血管を拡張して頭皮の血流を改善し、毛母細胞を活性化させる作用が期待されます。
スピロノラクトンは利尿薬ですが、男性ホルモン(アンドロゲン)の働きを抑制する作用があるため、女性のびまん性脱毛症の一部(特に男性ホルモンの影響が考えられる場合)に使用される場合があります。
ただし、これらの内服薬は医師の処方が必要であり、副作用のリスクもあるため、必ず医師の指示に従って服用してください。
主な内服薬の種類と特徴
| 薬剤名 | 主な作用 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| ミノキシジル | 血行促進、毛母細胞活性化 | 医師の処方が必要。初期脱毛、多毛、動悸などの副作用の可能性あり。 |
| スピロノラクトン | 抗アンドロゲン作用、利尿作用 | 医師の処方が必要。ホルモンバランスへの影響、電解質異常に注意。 |
| その他栄養補助 | 髪の成長に必要な栄養素(ビタミン、ミネラル) | 補助的な役割。食事での摂取が基本。 |
外用薬による治療(ミノキシジル外用薬など)
外用薬は、頭皮に直接塗布するタイプの治療薬です。最も代表的なのはミノキシジル外用薬です。
日本皮膚科学会のガイドラインでも、女性のびまん性脱毛症(女性型脱毛症)に対して推奨されています。ミノキシジル内服薬と同様に、頭皮の血行を促進し、毛母細胞に働きかけて発毛を促します。
女性向けには、濃度の低い製品(1%など)から使用を開始するのが一般的です。効果を実感するには、通常、数ヶ月以上の継続的な使用が必要です。
使用初期に一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」が見られる場合がありますが、これは治療効果が現れ始めている兆候と考えられます。
主な外用薬の種類と特徴
| 薬剤名 | 主な作用 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| ミノキシジル外用薬 | 血行促進、毛母細胞活性化 | 市販薬もあるが、医師の診断に基づく使用が望ましい。初期脱毛、頭皮のかゆみ・かぶれなど。 |
| カルプロニウム塩化物 | 血行促進 | 保険適用の場合あり。発汗、刺激感などの副作用。 |
| その他育毛剤 | 保湿、血行促進、抗炎症など | 医薬部外品など多様。効果は製品による。 |
注入療法(メソセラピーなど)
注入療法は、発毛効果が期待できる薬剤や成長因子などを、注射器や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する治療法です。
代表的なものに「ヘアフィラー」や「HARG療法」、「メソセラピー」などがあります。
注入療法の種類
- ヘアフィラー
- HARG療法
- メソセラピー(成長因子、ミノキシジルなど)
有効成分を毛根に直接届けられるため、内服薬や外用薬だけでは効果が不十分な場合やより積極的な治療を希望する場合に選択肢となるケースが多いです。
治療内容や使用する薬剤によって効果や費用、必要な回数などが異なります。
その他の治療選択肢(自毛植毛など)
上記の治療法で改善が見られない場合や、より永続的な効果を求める場合には、自毛植毛が検討されることもあります。
自毛植毛は後頭部など薄毛になりにくい部位から自身の毛髪を毛根ごと採取し、薄毛の気になる部分に移植する外科的な手術です。移植した毛髪は、元の部位の性質を保ったまま生え続けることが期待できます。
ただし、手術であるため、費用が高額になる点やダウンタイムが必要になる点、全ての方に適応となるわけではない点などを理解しておく必要があります。
日常生活でできる予防とセルフケア
クリニックでの治療と並行して、あるいはびまん性脱毛症を予防するために、日常生活でできることも多くあります。
バランスの取れた食事を心がける
髪の毛は、私たちが摂取する栄養素から作られます。特定の食品だけを食べるのではなく、多様な食品からバランス良く栄養を摂ることが重要です。
特に、髪の主成分であるタンパク質(肉、魚、大豆製品、卵など)、ケラチンの合成を助ける亜鉛(牡蠣、レバー、ナッツ類など)、頭皮の血行を促進するビタミンE(ナッツ類、アボカドなど)、頭皮環境を整えるビタミンB群(豚肉、レバー、青魚など)を意識して摂取しましょう。
過度なダイエットは栄養不足を招き、薄毛の原因となる可能性があるため注意が必要です。
ストレス管理の方法
過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こすなど、髪の健康に悪影響を与えます。
ストレスを完全になくすのは難しいですが、自分に合った方法で上手に解消すると良いです。
趣味に没頭する時間を作る、適度な運動をする、ゆっくり入浴する、友人や家族と話す、十分な睡眠をとるなど、リラックスできる方法を見つけましょう。瞑想やヨガなどもストレス軽減に効果的です。
正しいヘアケアと頭皮ケア
間違ったヘアケアは頭皮や髪にダメージを与え、薄毛を進行させる可能性があります。
シャンプーは洗浄力が強すぎないアミノ酸系などのマイルドなものを選び、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。すすぎ残しがないように、しっかりと洗い流すことも重要です。
洗髪後は、ドライヤーで髪だけでなく頭皮もしっかり乾かします。ただし、熱風を当てすぎるとダメージの原因になるため、頭皮から20cm程度離し、同じ場所に集中しないように注意しましょう。
ブラッシングは、無理に引っ張らず、毛先から優しくとかします。
頭皮ケアのポイント
| ケア項目 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| シャンプー | アミノ酸系などマイルドな洗浄成分のものを選ぶ。指の腹で優しく洗う。 | 爪を立てない、ゴシゴシこすらない、すすぎ残しに注意。 |
| 洗髪後のケア | 吸水性の良いタオルで優しく水分を拭き取る。ドライヤーで頭皮まで乾かす。 | タオルで強くこすらない、ドライヤーの熱風を当てすぎない。 |
| ブラッシング | 毛先から優しくとかす。頭皮への適度な刺激は血行促進につながる場合もある。 | 無理に引っ張らない、静電気を起こしにくいブラシを選ぶ。 |
| 頭皮マッサージ | 指の腹で頭皮全体を優しく動かすように行う。 | 爪を立てない、強く押しすぎない。 |
良質な睡眠の確保
睡眠中には、体の成長や修復に欠かせない成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは毛母細胞の分裂を活性化させ、髪の成長を促す働きがあります。
そのため、質の高い睡眠が健やかな髪を育む上で非常に重要です。
毎日決まった時間に寝起きする、寝る前のカフェインやアルコールの摂取を控える、スマートフォンやパソコンの使用を就寝1時間前にはやめるなど、睡眠環境を整える工夫をしましょう。
よくある質問
ここでは、女性のびまん性脱毛症に関して、患者さんから寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
- Q治療期間はどのくらいですか?
- A
びまん性脱毛症の治療効果が現れるまでには、時間がかかるのが一般的です。
髪の毛にはヘアサイクル(成長期・退行期・休止期)があり、新しい髪が成長し、効果を実感できるようになるまでには、少なくとも3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要する方が多いです。
治療法や個人の状態によって効果の現れ方や必要な期間は異なります。治療を始めてすぐに効果が出なくても、根気強く継続しましょう。
- Q治療費はどのくらいかかりますか?
- A
治療費は選択する治療法や治療期間、通院頻度によって大きく異なります。
内服薬や外用薬による治療は、薬剤の種類や処方量によって費用が変わります。注入療法や自毛植毛などの自由診療は、保険適用外となるため、比較的高額になる傾向があります。
初診料や再診料、検査費用なども別途必要になる場合があります。具体的な費用については、治療を開始する前に、クリニックにしっかりと確認しておくと良いでしょう。
- Q保険適用になりますか?
- A
びまん性脱毛症(女性型脱毛症)の治療は原則として美容目的とみなされるため、健康保険の適用外(自由診療)となるケースがほとんどです。
ミノキシジル外用薬や内服薬、スピロノラクトン、注入療法、自毛植毛などは自由診療です。
ただし、脱毛の原因が甲状腺疾患や貧血など、他の保険適用となる疾患である場合は、その疾患自体の治療は保険適用となります。
また、カルプロニウム塩化物外用薬など一部の薬剤は、診断名によっては保険適用となる場合もありますが、限定的です。
- Qクリニック選びのポイントは?
- A
女性の薄毛治療を専門とするクリニックや、皮膚科の中でも脱毛症治療に力を入れているクリニックを選ぶのが望ましいです。
女性の薄毛治療の実績やカウンセリングの丁寧さ、治療法の豊富さや明確な料金体系、通いやすさなどのポイントを確認し、ご自身に合ったクリニックを見つけましょう。
信頼できる医師を見つけ、納得のいく治療を受けることが、悩みの解決につながります。
参考文献
SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
CHARTIER, Molly Beth; HOSS, Diane Marie; GRANT-KELS, Jane Margaret. Approach to the adult female patient with diffuse nonscarring alopecia. Journal of the American Academy of Dermatology, 2002, 47.6: 809-818.
MESINKOVSKA, Natasha Atanaskova; BERGFELD, Wilma F. Hair: What is New in Diagnosis and Management?: Female Pattern Hair Loss Update: Diagnosis and Treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 119-127.