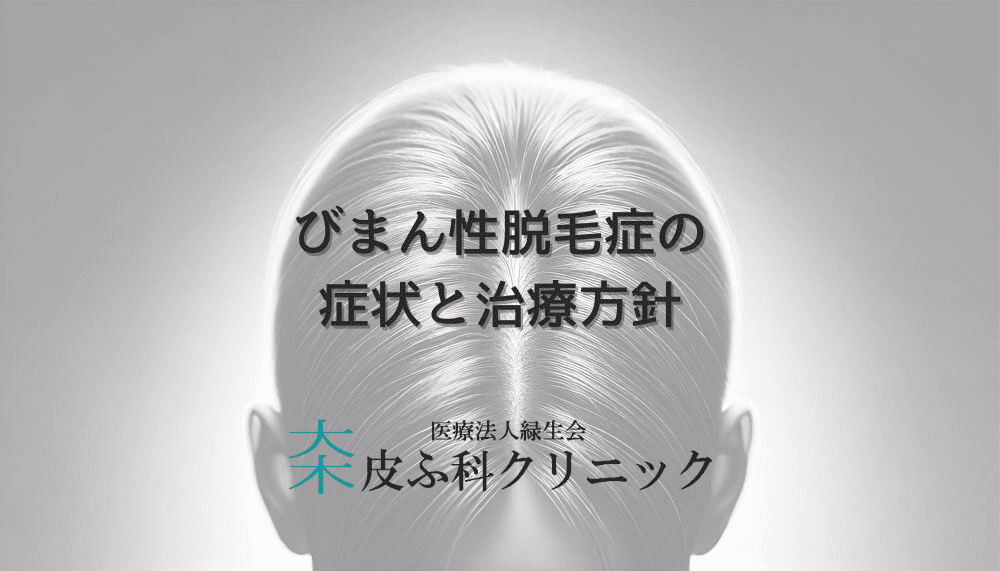最近、髪全体のボリュームが減ってきた、分け目が広がってきた、抜け毛が増えた気がするなど、ご自身の髪の変化に不安を感じていたら、それはもしかすると女性特有の薄毛「びまん性脱毛症」のサインかもしれません。
この症状は髪が全体的に薄くなるため、初期には気づきにくいケースもあります。
この記事では、女性のびまん性脱毛症の症状や原因、そしてクリニックで行われる治療方針について詳しく解説します。
特に治療薬として知られるミノキシジルの役割や、薄毛の兆候を見逃さないためのポイント、日常生活でのケア方法まで、幅広い情報をまとめます。
女性のびまん性脱毛症とは?その特徴と原因の概要
女性の薄毛に関するお悩みの中でも、びまん性脱毛症は比較的多く見られます。
びまん性脱毛症の定義
びまん性脱毛症とは、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる状態を指します。
特定の部位だけが脱毛するのではなく、髪一本一本が細くなったり全体の密度が低下したりするため、全体的にボリュームダウンして見えるのが特徴です。
男性型脱毛症(AGA)のように生え際が後退したり、頭頂部だけが薄くなったりするパターンとは異なります。
他の脱毛症との違い
女性の脱毛症には、びまん性脱毛症以外にも円形脱毛症や牽引性脱毛症、分娩後脱毛症など様々な種類があります。
円形脱毛症は円形や楕円形の脱毛斑が突然現れる自己免疫疾患と考えられています。牽引性脱毛症はポニーテールなど髪を強く引っ張る髪型が原因で起こります。
分娩後脱毛症は出産後のホルモンバランスの変化による一時的なものです。
びまん性脱毛症はこれらの脱毛症とは異なり、頭部全体の髪が徐々に薄くなるのが特徴です。
なぜ女性に多いのか?
びまん性脱毛症は特に女性に多く見られる傾向があります。
その背景には、女性ホルモンの影響やライフイベントに伴うホルモンバランスの変動、ダイエットによる栄養不足、ストレスなどが複雑に関与していると考えられています。
男性とは薄毛のパターンや原因が異なるため、女性に特化した視点での理解と対策が必要です。
びまん性脱毛症の主な原因(概要)
びまん性脱毛症の原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っているケースが多いです。
加齢による髪質の変化、妊娠・出産や更年期に伴うホルモンバランスの乱れ、過度なダイエットや偏食による栄養不足、睡眠不足やストレスといった生活習慣、そして貧血や甲状腺疾患などの病気、服用している薬剤の影響などが挙げられます。
これらの原因を特定することが、適切な治療方針を立てる上で重要になります。
もしかして?びまん性脱毛症の初期症状と薄毛の兆候
ここでは、びまん性脱毛症の初期に見られるサインや、自分で気づきやすい薄毛の兆候について説明します。
変化はゆっくり進むため、日々の小さなサインを見逃さないことが大切です。
髪全体のボリュームダウン
以前と比べて髪全体のボリュームがなくなった、髪型が決まりにくくなったと感じる場合、びまん性脱毛症の初期症状かもしれません。
髪一本一本が細くなる(軟毛化)ため全体の密度が低下し、ふんわり感が失われます。特に髪が濡れた時に地肌が透けて見えやすくなる場合があります。
分け目が目立つようになる
いつも同じ分け目にしている方は、その部分の地肌が以前より目立つようになっていないか確認してみてください。
びまん性脱毛症では、頭頂部から分け目にかけての髪が薄くなる方が多く、地肌の露出が増える傾向があります。
鏡でチェックしたり、ご家族に確認してもらったりするのも良いでしょう。これが薄毛の兆候の一つである可能性があります。
抜け毛の増加とその質
シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が増えたと感じるのも、注意すべきサインです。ただし、髪にはヘアサイクルがあり、1日に50本から100本程度の抜け毛は正常範囲です。
問題は、その量だけでなく、抜けた毛の質です。細く短い毛や、毛根がついていない毛が増えている場合は、ヘアサイクルが乱れている可能性があります。
頭皮が透けて見える感覚
髪をかき上げた時や光が当たった時に、以前よりも頭皮が透けて見えるように感じる場合もびまん性脱毛症が進行している可能性があります。
髪の密度が低下し、地肌が露出しやすくなっている状態です。特に頭頂部は自分では見えにくいため、合わせ鏡を使ったり、スマートフォンのカメラで撮影したりして確認すると良いでしょう。
びまん性脱毛症の進行パターンとセルフチェック
びまん性脱毛症がどのように進行していくのか、また自宅でできる簡単なチェック方法を紹介します。早期に気づき、対策を始めることが進行を抑える鍵となります。
進行の仕方(ルードウィッグ分類)
女性のびまん性脱毛症の進行度を示す分類法として、ルードウィッグ分類がよく用いられます。
これは頭頂部の髪の毛の状態によって、3段階に分類するものです。
ルードウィッグ分類の概要
| 分類 | 状態 |
|---|---|
| I 型 | 頭頂部の分け目部分の脱毛が軽度に見られる |
| II 型 | 分け目部分の脱毛範囲が広がり、明瞭になる |
| III 型 | 頭頂部全体の脱毛が広範囲に及び、顕著になる |
この分類はあくまで目安ですが、ご自身の状態を客観的に把握する参考になります。
自宅でできる簡単なチェックポイント
日常生活の中で、びまん性脱毛症のサインに気づくためのチェックポイントをいくつか紹介します。
薄毛の兆候セルフチェック
- 最近、髪のハリやコシがなくなった気がする。
- シャンプーやドライヤー時の抜け毛が増えた。
- 分け目の地肌が以前より目立つ。
- 髪全体のボリュームが減り、スタイリングが決まりにくい。
- 頭皮が透けて見える部分がある。
- 枕につく抜け毛が増えた。
- 髪が細くなった、うねりやすくなった。
これらの項目に複数当てはまる場合は、一度専門医への相談を検討しましょう。
早期発見の重要性
びまん性脱毛症は、進行してしまうと改善に時間がかかる場合があります。
初期の段階で薄毛の兆候に気づき、原因を特定して適切な対策や治療を開始することが、症状の進行を食い止め、改善を図る上で非常に重要です。
少しでも気になる変化があれば、早めに専門クリニックを受診しましょう。
びまん性脱毛症の主な原因
びまん性脱毛症を引き起こす可能性のある様々な要因について、より詳しく掘り下げていきます。原因は一つとは限らず、複合的な場合が多いです。
加齢による変化
年齢を重ねるとともに髪の毛を作り出す毛母細胞の働きが低下したり、ヘアサイクル(毛周期)が乱れたりする場合があります。
成長期が短くなり休止期にとどまる毛包が増えるため、髪が細くなったり抜け毛が増えたりして、びまん性脱毛症につながるケースがあります。
また、頭皮の血行不良や乾燥も加齢に伴い起こりやすくなります。
ホルモンバランスの乱れ
女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、髪の成長を促進してハリやコシを保つ働きがあります。
しかし、妊娠・出産、更年期、ストレス、不規則な生活などによってホルモンバランスが乱れ、エストロゲンの分泌が減少すると相対的に男性ホルモンの影響が強まり、抜け毛や薄毛を引き起こす可能性があります。
ホルモンバランスを乱す主な要因
| 要因 | 影響 |
|---|---|
| 妊娠・出産 | 出産後のエストロゲン急減による一時的な脱毛(分娩後脱毛症) |
| 更年期 | エストロゲンの分泌量低下 |
| ストレス | 自律神経やホルモン分泌の乱れ |
| 過度なダイエット | 栄養不足によるホルモン産生への影響 |
| 睡眠不足 | 成長ホルモン分泌の低下、自律神経の乱れ |
生活習慣の影響
日々の生活習慣も、髪の健康に大きく関わっています。
特に栄養バランスの偏り、睡眠不足、過度なストレスは、びまん性脱毛症のリスクを高める要因となります。
栄養バランスの偏り
髪の主成分であるケラチン(タンパク質)や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類などが不足すると、健康な髪が育ちにくくなります。
インスタント食品や外食が多い、極端な食事制限をするなどの食生活は注意が必要です。
睡眠不足
髪の成長には、睡眠中に分泌される成長ホルモンが関与しています。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。
ストレス
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こします。
血行が悪くなると髪の毛を作る毛母細胞へ十分な栄養が届かず、抜け毛や薄毛の原因となりやすいです。
薄毛につながる可能性のある生活習慣
| 生活習慣 | 影響 |
|---|---|
| 栄養バランスの偏り | 髪の成長に必要な栄養素(タンパク質、亜鉛、ビタミンなど)の不足 |
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下、自律神経の乱れ |
| ストレス | 自律神経の乱れ、頭皮の血行不良 |
| 喫煙 | 血行不良、ビタミンCの破壊 |
| 過度の飲酒 | 肝臓への負担、栄養素の吸収阻害 |
| 運動不足 | 全身の血行不良 |
頭皮環境の問題
頭皮の乾燥、過剰な皮脂分泌、フケ、かゆみといった頭皮トラブルも、健康な髪の育成を妨げる要因となります。
間違ったヘアケアや洗浄力の強すぎるシャンプーの使用、紫外線ダメージなどが頭皮環境を悪化させるケースがあります。
病気や薬剤の影響
貧血(特に鉄欠乏性貧血)や甲状腺機能の異常(甲状腺機能低下症、亢進症など)といった病気が、びまん性脱毛症の原因となるケースがあります。また、特定の薬剤の副作用として脱毛が起こる場合もあります。
治療中の病気がある方や常用している薬がある方は、医師に相談しましょう。
脱毛を引き起こす可能性のある薬剤
| 薬剤の種類 | 用途 |
|---|---|
| 抗がん剤 | がん治療 |
| 抗うつ薬 | うつ病治療 |
| 降圧剤 | 高血圧治療 |
| 抗凝固薬 | 血栓予防 |
| 経口避妊薬(ピル) | 避妊、月経困難症治療(中止後に影響が出ることも) |
上記は一般的な情報であり、全ての薬剤で脱毛が起こるわけではありません。
クリニックでのびまん性脱毛症の診断方法
専門クリニックでは問診や視診、各種検査を通じてびまん性脱毛症の原因を特定し、適切な治療方針を立てます。自己判断せず、専門医による正確な診断を受けることが大切です。
問診の重要性
まず、患者様の自覚症状、抜け毛が気になり始めた時期、生活習慣(食事、睡眠、ストレスなど)、既往歴、服用中の薬剤、家族歴などを詳しく伺います。
これらの情報は、脱毛の原因を探る上で非常に重要な手がかりとなります。特に、最近の生活の変化や体調の変化について詳しくお話しください。
視診と触診
医師が直接、頭皮と髪の状態を目で見て確認します。脱毛の範囲やパターン、髪の密度、太さ、頭皮の色や状態(乾燥、炎症、皮脂量など)を詳細に観察します。
また、実際に髪や頭皮に触れて、髪のハリやコシ、頭皮の硬さなども確認します。
マイクロスコープによる頭皮・毛髪検査
マイクロスコープ(ダーモスコピー)という特殊な拡大鏡を用いて、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察します。
肉眼では確認できない毛穴の詰まり、頭皮の炎症、毛髪の太さの変化、毛根の状態などを把握できます。
これにより、より正確な診断と原因の推定が可能になります。
マイクロスコープ検査でわかること
| 観察項目 | 確認できる状態 |
|---|---|
| 頭皮の色 | 正常(青白い)、赤み(炎症)、黄色(皮脂過多) |
| 毛穴の状態 | 詰まり、汚れ、炎症 |
| 皮脂の量 | 乾燥、普通、過剰 |
| 毛髪の太さ | 太い毛、細い毛(軟毛化)の混在具合 |
| 毛髪の密度 | 1つの毛穴から生えている毛髪の本数 |
| 毛根の状態 | 正常な毛根、萎縮した毛根 |
血液検査とその目的
びまん性脱毛症の原因として全身性の疾患や栄養状態が関与している可能性があるときは、血液検査を行います。
貧血の有無(ヘモグロビン、フェリチンなど)、甲状腺ホルモンの値、亜鉛などのミネラルやビタミン類の不足がないかなどを調べます。これにより、内科的な原因が隠れていないかを確認します。
血液検査で確認する項目
| 検査項目 | 確認する目的 |
|---|---|
| 血算 | 貧血の有無(ヘモグロビン、赤血球数など) |
| フェリチン | 体内の貯蔵鉄量(潜在的な鉄欠乏の確認) |
| 甲状腺ホルモン | 甲状腺機能異常(低下症・亢進症)の有無 |
| 亜鉛 | 髪の成長に必要なミネラルの不足確認 |
| ビタミン類 | 髪の健康に関わるビタミン(B群など)の不足確認 |
鑑別診断の必要性
女性の薄毛の原因は多岐にわたるため、他の脱毛症(円形脱毛症、牽引性脱毛症など)や皮膚疾患との鑑別が重要です。
また、全身性疾患が背景にある可能性も考慮し、必要に応じて他の専門科との連携も行います。
正確な診断に基づいて個々の患者様に合った治療計画を立てることが、効果的な治療への第一歩となります。
びまん性脱毛症の治療方針(ミノキシジルの役割とその他治療法)
ここでは、びまん性脱毛症の治療の考え方と、代表的な治療薬であるミノキシジル、その他の治療選択肢について解説します。
原因や症状の程度に応じて、様々な治療法を組み合わせて行うのが一般的です。
治療の基本的な考え方
びまん性脱毛症の治療はまず原因を特定し、それに対する働きかけを行うのが基本です。
例えば、栄養不足が原因であれば食事指導やサプリメントの補充、ホルモンバランスの乱れが疑われる場合はホルモン療法や関連する薬剤の使用、ストレスが大きな要因であればその軽減策などを検討します。
それに加えて、発毛を促進してヘアサイクルを正常化させるための治療薬の使用や、頭皮環境を改善するケアなどを組み合わせて行います。根気強い治療の継続が重要です。
ミノキシジル外用薬の効果と注意点
ミノキシジルは日本で唯一、女性の壮年性脱毛症(びまん性脱毛症を含むことが多い)に対する発毛効果が認められている外用薬の成分です。
多くの女性の薄毛治療において、ミノキシジルは重要な選択肢の一つとなります。
ミノキシジルの作用
ミノキシジルは頭皮の血管を拡張して血流を改善し、毛母細胞を活性化させることで発毛を促すと考えられています。
また、毛髪の成長期を延長し、休止期から成長期への移行を促進する効果も期待されます。
これにより、細くなった髪を太く育て、抜け毛を減らす効果が期待できます。
女性向けミノキシジル製剤
ミノキシジル外用薬には、男性用と女性用があります。女性の場合、男性よりも低い濃度の製剤(例:1%濃度)が推奨されています。
クリニックでは、患者様の状態に合わせて適切な濃度の製剤を処方します。
市販薬もありますが、自己判断で使用する前に、必ず医師の診察を受けるようにしてください。
ミノキシジル使用上の注意点
ミノキシジル外用薬は、効果が現れるまでに通常数ヶ月以上の継続使用が必要です。すぐに効果が出なくても、諦めずに根気強く続けることが大切です。
使用初期に一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」が見られる場合がありますが、これはヘアサイクルが改善する過程で起こる現象であり、通常は1〜2ヶ月程度で治まります。
副作用として、頭皮のかゆみ、かぶれ、発疹などが現れるケースがあります。
ミノキシジル外用薬の主な副作用
| 副作用の種類 | 症状 |
|---|---|
| 皮膚症状 | かゆみ、発疹、かぶれ、フケ、熱感、乾燥 |
| 循環器系 | 動悸、めまい、低血圧(まれ) |
| その他 | 頭痛、むくみ(まれ) |
副作用が現れた場合は使用を中止し、速やかに医師に相談してください。
その他の内服薬・外用薬
ミノキシジル以外にも、びまん性脱毛症の治療に用いられる薬剤があります。これらは医師の診断と処方が必要です。
スピロノラクトンなど(医師の処方が必要)
スピロノラクトンは元々は利尿薬や高血圧治療薬ですが、男性ホルモンの働きを抑える作用があるため、女性のホルモンバランスによる薄毛治療に用いられるケースがあります。
ただし、副作用のリスクもあるため、医師の慎重な判断のもとで使用されます。
その他、患者さんの状態に応じて、血行促進薬や栄養補助を目的とした内服薬、頭皮環境を整える外用薬などが処方される場合もあります。
代表的な治療薬(外用・内服)
- ミノキシジル外用薬
- スピロノラクトン内服薬(医師の処方が必要)
- 各種ビタミン・ミネラル製剤(内服)
- 血行促進薬(内服・外用)
- 抗炎症外用薬
栄養療法・サプリメント
食事だけでは不足しがちな髪の成長に必要な栄養素(タンパク質、亜鉛、鉄、ビタミンB群、ビオチンなど)を、サプリメントで補うのも有効な場合があります。
ただし、過剰摂取は逆効果になる場合もあるため、医師や管理栄養士に相談の上、適切なものを選びましょう。
クリニックによっては、オリジナルのサプリメントを提供している場合もあります。
クリニックでの専門的な治療
内服薬や外用薬による治療に加えて、クリニックではより専門的な方法も行っています。
低出力レーザー治療など
頭皮に低出力のレーザーを照射することで毛母細胞を活性化させ、血行を促進して発毛をサポートする治療法です。痛みはほとんどなく、副作用のリスクも低いとされています。
その他、頭皮に直接有効成分を注入するメソセラピーや、自身の血液から抽出した成長因子を利用するPRP療法など、様々な治療選択肢があります。
クリニックで提供される治療法の例
| 治療法の種類 | 概要 |
|---|---|
| ミノキシジル処方 | 患者の状態に合わせた濃度のミノキシジル外用薬や内服薬(海外製など)の処方 |
| スピロノラクトン処方 | 男性ホルモンの影響を抑える内服薬の処方 |
| 栄養療法・サプリメント | 血液検査に基づいた栄養指導、医療用サプリメントの処方 |
| 低出力レーザー治療 | 頭皮にレーザーを照射し、毛母細胞の活性化や血行促進を図る |
| メソセラピー | 発毛効果のある薬剤や成長因子などを頭皮に直接注入する |
| PRP療法 | 自身の血液から抽出した多血小板血漿(PRP)を頭皮に注入する |
どの治療法が適しているかは、患者さんの症状や原因、生活スタイルによって異なります。医師とよく相談し、納得のいく治療方針を決定することが重要です。
日常生活でできる薄毛対策と予防法
クリニックでの治療と並行して、または将来の薄毛を予防するために日常生活で取り組めるケアについて紹介します。健やかな髪を育むためには、日々の生活習慣の見直しが大切です。
バランスの取れた食事
髪は主にケラチンというタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質を十分に摂取するのが基本です。
また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、髪の成長に関わるビタミンB群なども意識して摂りましょう。
髪に必要な栄養素
- タンパク質(肉、魚、大豆製品、卵など)
- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類など)
- 鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじきなど)
- ビタミンB群(豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆、卵など)
- ビタミンC(果物、野菜、いも類など)
- ビタミンE(ナッツ類、アボカド、植物油など)
特定の食品に偏らず、様々な食材をバランス良く摂る工夫が大切です。
正しいヘアケア習慣
間違ったヘアケアは頭皮にダメージを与え、薄毛を悪化させる可能性があります。
ご自身の頭皮タイプに合ったシャンプーを選び、優しく洗うことを心がけましょう。
シャンプーの選び方と方法
洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥やバリア機能の低下を招く場合があります。アミノ酸系など、マイルドな洗浄成分のシャンプーを選ぶのがおすすめです。
洗髪時は爪を立てず、指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないようにしっかりと洗い流しましょう。ドライヤーは髪から離して使い、熱によるダメージを防ぎます。
頭皮マッサージ
頭皮マッサージは血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。シャンプー時やリラックスタイムに、指の腹を使って頭皮全体を優しく揉みほぐしましょう。
ただし、強く擦りすぎると逆効果になるため注意が必要です。
ストレス管理
過度なストレスは自律神経のバランスを崩し、血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こして薄毛の原因となります。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身をリラックスさせる時間を作る心がけが重要です。
リラックス方法の見つけ方
- 軽い運動(ウォーキング、ヨガなど)
- 趣味に没頭する時間を作る
- アロマテラピーや音楽鑑賞
- 友人や家族との会話
- 十分な睡眠
自分なりのリラックス方法を日常生活に取り入れましょう。
質の高い睡眠の確保
睡眠中に分泌される成長ホルモンは、髪の毛の成長に欠かせません。毎日決まった時間に寝起きするなど、規則正しい睡眠習慣を心がけ、質の高い睡眠を確保しましょう。
寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用は避け、リラックスできる寝室環境を整えるのも有効です。
睡眠の質を高めるためのポイント
| ポイント | 具体的な行動 |
|---|---|
| 規則正しい生活 | 毎日同じ時間に寝起きする |
| 寝る前の習慣 | カフェイン、アルコール、喫煙を避ける、スマホ操作を控える |
| 寝室環境 | 静かで暗い、快適な温度・湿度に保つ |
| 日中の活動 | 適度な運動をする、日光を浴びる |
| リラックス | 就寝前にぬるめのお風呂に入る、軽いストレッチをする |
これらの生活習慣の改善は、びまん性脱毛症の治療効果を高めるだけでなく、全身の健康維持にもつながります。できることから少しずつ取り入れてみてください。
よくある質問(FAQ)
びまん性脱毛症やその治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q治療はどのくらいの期間続けますか?
- A
びまん性脱毛症の治療期間は、原因や症状の程度、選択する治療法、そして患者様の反応によって大きく異なります。
一般的に、効果を実感するまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。ヘアサイクルを正常化させ、目に見える変化が現れるには時間がかかります。
治療効果を見ながら、医師と相談の上で治療期間を調整していきます。根気強く続けることが大切です。
- Q治療の効果はいつ頃から現れますか?
- A
こちらも個人差が大きいですが、多くの場合、治療開始から3ヶ月から6ヶ月ほどで抜け毛の減少や産毛の発生といった初期の変化が見られ始める方が多いです。
髪のボリュームアップなど、より明確な効果を実感するには、半年から1年以上の期間が必要となるケースもあります。
特にミノキシジルなどの発毛剤は、効果発現までに時間がかかる点を理解しておく必要があります。
- Qミノキシジルを使うと初期脱毛があると聞きましたが本当ですか?
- A
ミノキシジルの使用開始後、1ヶ月前後で一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」という現象が起こる場合があります。
これは、ミノキシジルの作用によって乱れていたヘアサイクルが正常化する過程で、休止期にあった古い髪が新しい髪に押し出されるために起こると考えられています。
多くの場合初期脱毛は一時的なもので、その後、太く健康な髪が生えてくる準備段階と捉えられます。心配な場合は、自己判断で中止せず、医師にご相談ください。
- Q保険は適用されますか?
- A
一般的に、びまん性脱毛症を含む薄毛治療は容姿を改善する目的とみなされるため、健康保険の適用外となり、自由診療(自費診療)となるケースがほとんどです。
ただし、脱毛の原因が甲状腺疾患や貧血など、他の保険適用となる病気によるものである場合は、その原因疾患の治療に対しては保険が適用されることがあります。
治療費については、カウンセリング時にクリニックに詳しく確認すると良いでしょう。
参考文献
SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.
CHARTIER, Molly Beth; HOSS, Diane Marie; GRANT-KELS, Jane Margaret. Approach to the adult female patient with diffuse nonscarring alopecia. Journal of the American Academy of Dermatology, 2002, 47.6: 809-818.
WERNER, Betina; MULINARI-BRENNER, Fabiane. Clinical and histological challenge in the differential diagnosis of diffuse alopecia: female androgenetic alopecia, telogen effluvium and alopecia areata-part I. Anais brasileiros de dermatologia, 2012, 87: 742-747.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
LIN, Chia-Shuen, et al. Diagnosis and treatment of female alopecia: Focusing on the iron deficiency-related alopecia. Tzu Chi Medical Journal, 2023, 35.4: 322-328.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
VAN ZUUREN, E. J.; FEDOROWICZ, Z.; CARTER, B. Evidence‐based treatments for female pattern hair loss: a summary of a Cochrane systematic review. British Journal of Dermatology, 2012, 167.5: 995-1010.
KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.