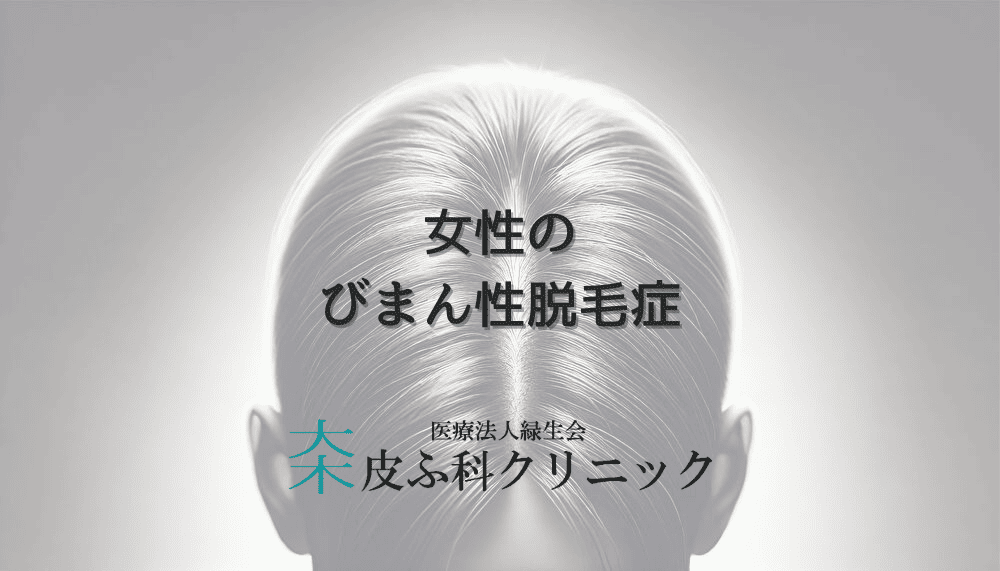「最近、髪全体のボリュームが減ってきた気がする」「分け目や頭頂部の地肌が目立つようになった」と感じている方が多いようです。
そのような症状は、もしかしたら、女性に多い「びまん性脱毛症」のサインかもしれません。
びまん性脱毛症は男性の薄毛とは異なり、髪が全体的に薄くなるのが特徴です。原因は一つではなく、加齢やホルモンバランスの変化、ストレス、生活習慣など、様々な要因が複雑に関係しています。
びまん性脱毛症とは?女性特有の薄毛の悩み
はじめに、女性の薄毛の代表的な原因である「びまん性脱毛症」について、基本的な知識となぜ女性に多いのかを解説します。
びまん性脱毛症の基本的な定義
びまん性脱毛症とは、特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛が均一に薄くなる脱毛症のことです。
「びまん」とは「広範囲に広がる」という意味で、その名の通り髪全体の密度が低下し、ボリュームダウンが起こります。
髪の毛一本一本が細くなったり抜け毛が増えたりするため、徐々に地肌が透けて見えるようになります。進行には個人差がありますが、多くの女性が悩む脱毛症の一つです。
男性型脱毛症(AGA)との違い
男性に多い男性型脱毛症(AGA)は主に生え際や頭頂部から薄毛が進行するのに対し、びまん性脱毛症は頭部全体が薄くなるという特徴があります。
原因も異なり、AGAは男性ホルモンの影響が大きいですが、びまん性脱毛症は女性ホルモンの減少や加齢、ストレスや生活習慣など、複数の要因が関与していると考えられています。
脱毛症の主な違い
| 特徴 | びまん性脱毛症(女性に多い) | 男性型脱毛症(AGA) |
|---|---|---|
| 薄くなる範囲 | 頭部全体 | 生え際、頭頂部 |
| 主な原因 | 複合的要因(ホルモン、加齢、ストレス等) | 男性ホルモン、遺伝 |
| 進行パターン | 全体的に徐々に薄くなる | 特定部位から進行 |
びまん性脱毛症が女性に多い理由
女性のびまん性脱毛症は、特に女性ホルモンの影響が大きいと考えられています。
女性ホルモンの一つであるエストロゲンには髪の成長を促進し、ハリやコシを保つ働きがあります。
しかし、加齢や出産、ストレスなどによってエストロゲンの分泌量が減少すると髪の成長期が短くなり、休止期に入る毛包が増えるため、薄毛につながりやすくなります。
また、女性は男性に比べてダイエットによる栄養不足や頻繁なヘアカラー・パーマによる頭皮への負担、ストレスなど、薄毛を引き起こす要因にさらされる機会が多い点も、女性にびまん性脱毛症が多い理由の一つと考えられます。
女性におけるびまん性脱毛症の症状とセルフチェック
ここでは、びまん性脱毛症で現れる具体的な症状と、ご自身で簡単に確認できるチェック方法を紹介します。早期に気づくことが効果的な対策への第一歩です。
頭部全体のボリュームダウン
以前と比べて髪全体のボリュームが減ったと感じるのは、びまん性脱毛症の代表的な初期症状です。
髪を束ねた時の太さが細くなったり、スタイリングが決まりにくくなったりします。
一本一本の髪が細くなったり、髪の密度が低下したりするのが原因です。
地肌が透けて見える
特に髪の分け目やつむじ、頭頂部を中心に、地肌が以前よりも透けて見えるようになります。髪全体の密度が低下するために起こる症状です。
明るい場所で鏡を見たり、写真を見返したりした際に気づく方が多いでしょう。
髪のハリ・コシの低下
髪の毛にハリやコシがなくなり全体的に元気がなく、ぺたんとした印象になるのも特徴です。
髪の成長サイクルが乱れ、十分に成長しきれない細く弱い髪の毛が増えるために起こります。手触りでも変化を感じるケースがあります。
簡単なセルフチェック方法
ご自身の状態を確認するために、以下の点をチェックしてみましょう。
- 以前より髪全体のボリュームが減ったと感じる
- 分け目やつむじの地肌が目立つようになった
- 髪の毛が細く、柔らかくなった気がする
- 抜け毛が増えた(特にシャンプー時やブラッシング時)
- 髪にハリやコシがなく、スタイリングがしにくい
これらの項目に複数当てはまる場合は、びまん性脱毛症の可能性があります。一度専門のクリニックに相談することをおすすめします。
女性がびまん性脱毛症になる原因
びまん性脱毛症は単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発症するケースが多いです。ここでは、女性がびまん性脱毛症を発症する主な原因について解説します。
加齢とホルモンバランスの変化
年齢を重ねるとともに、髪の成長に関わる女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が自然に減少します。
特に閉経前後の更年期にはホルモンバランスが大きく変動し、髪の成長期が短縮されて休止期の毛髪が増える傾向があります。
これにより、髪全体のボリュームダウンや薄毛が進行しやすくなります。これは、びまん性脱毛症の女性にとって非常に一般的な原因です。
ストレスや生活習慣の乱れ
過度な精神的ストレスや身体的ストレスは自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こし、頭皮の血行不良を招く場合があります。
血行が悪くなると毛根に十分な栄養が届きにくくなり、髪の健やかな成長が妨げられます。
また、睡眠不足、偏った食生活、過度なダイエットなども髪の成長に必要な栄養素の不足やホルモンバランスの乱れにつながり、びまん性脱毛症の原因となりえます。
誤ったヘアケアや頭皮環境の悪化
洗浄力の強すぎるシャンプーの使用、頻繁なヘアカラーやパーマ、間違ったブラッシングなどが頭皮や毛髪にダメージを与え、頭皮環境を悪化させる可能性があります。
頭皮の乾燥や炎症、毛穴の詰まりなどが健康な髪の育成を妨げ、抜け毛や薄毛の原因となります。
自分の髪質や頭皮の状態に合った、適切なヘアケアを行うことが重要です。
病気や薬剤の影響
甲状腺機能の異常(甲状腺機能低下症など)や膠原病といった全身性の疾患が、脱毛の原因となっている方も見受けられます。
また、特定の薬剤(抗がん剤、一部の降圧剤、抗うつ薬など)の副作用として脱毛が起こる場合もあります。
急激な抜け毛や他の体調不良を伴う場合は、まず内科などを受診し、原因となる病気がないか確認すると良いです。
びまん性脱毛症の主な原因カテゴリ
| カテゴリ | 具体的な要因例 |
|---|---|
| 内的要因(身体) | 加齢、ホルモンバランスの変化(妊娠・出産・更年期)、遺伝的素因、病気(甲状腺疾患等) |
| 外的要因(生活) | ストレス、睡眠不足、栄養バランスの偏り、過度なダイエット、喫煙習慣 |
| 外的要因(ケア) | 不適切なヘアケア、頭皮への負担(カラー・パーマ)、紫外線ダメージ |
びまん性脱毛症を診断する際のクリニックでの流れ
「もしかして、びまん性脱毛症かも?」と思ったら、自己判断せずに専門のクリニックを受診することが大切です。
医師による問診と視診
まず、医師が患者さんの悩みや症状について詳しくお話を伺います。いつから薄毛が気になり始めたか、どのような症状があるか、生活習慣、既往歴、服用中の薬、家族歴などを丁寧に確認します。
その後、医師が直接頭皮や毛髪の状態を目で見て確認します。薄毛の範囲や程度、頭皮の色や状態、毛髪の太さや密度などを観察します。
頭皮・毛髪の状態チェック
視診に加えて、マイクロスコープなどの専用機器を用いて頭皮や毛髪の状態をより詳しく観察する場合があります。
これにより、肉眼では分かりにくい毛穴の状態や皮脂の詰まり、毛髪の太さの変化や毛根の状態などを詳細に把握できます。
これらの情報は、脱毛の原因を特定して適切な治療方針を立てる上で重要です。
頭皮・毛髪チェックで確認する主なポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 頭皮の色 | 健康な状態(青白い)、炎症(赤い)、血行不良(黄色っぽい)など |
| 頭皮の状態 | 乾燥、皮脂の過剰分泌、フケ、湿疹、毛穴の詰まりの有無 |
| 毛髪の密度 | 脱毛の進行度合い、部位による密度の違い |
| 毛髪の太さ | 軟毛化(細くなっている毛)の割合、部位による太さの違い |
血液検査などの必要な検査
問診や視診、頭皮チェックの結果、全身性の疾患やホルモンバランスの乱れ、栄養不足などが疑われる場合には血液検査を行うときがあります。
血液検査では甲状腺ホルモンや女性ホルモン、鉄分(貧血の有無)や亜鉛などのミネラル、その他の栄養状態などを調べます。
原因を特定することで、より的確な治療法の選択につながります。必要に応じて、他の専門科への紹介を行うケースもあります。
女性のびまん性脱毛症の改善に向けた治療法
クリニックでは診断結果に基づき、患者さん一人ひとりの状態や原因に合わせた治療法を提案します。
内服薬による治療
女性のびまん性脱毛症治療において、内服薬が選択肢の一つです。主に、毛髪の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントや血行を促進する薬などが用いられます。
代表的な成分としては、パントテン酸カルシウムやL-シスチン、ケラチンやビタミンB群などが配合されたものが挙げられます。これらの成分は毛母細胞の働きを活性化させ、健康な髪の成長をサポートします。
医師の処方が必要となる薬もあります。効果や副作用について十分に説明を受けた上で開始しましょう。
外用薬による治療
頭皮に直接塗布するタイプの外用薬もびまん性脱毛症の治療に広く用いられます。
ミノキシジルは、男女ともに使用が認められている代表的な発毛成分です。毛母細胞に働きかけて血行を促進することで、発毛を促して髪の成長期を延長させる効果が期待できます。
女性の場合、男性用よりも濃度の低い製剤が推奨されます。
ミノキシジル以外にも女性ホルモン様作用を持つ成分や、頭皮環境を整える成分が配合された外用薬もあります。
主な治療薬の種類
| 治療法カテゴリ | 薬剤・成分 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 内服薬 | パントテン酸カルシウム、L-シスチン、ケラチン、ビタミンB群、ミノキシジル(処方薬の場合あり) | 毛髪の栄養補給、毛母細胞の活性化、血行促進 |
| 外用薬 | ミノキシジル、アルファトラジオール(女性ホルモン様作用)、各種保湿・抗炎症成分 | 発毛促進、抜け毛抑制、頭皮環境改善 |
注入療法(メソセラピーなど)
注入療法(ヘアフィラー、メソセラピーとも呼ばれます)は、髪の成長に必要な有効成分を注射や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する治療法です。
代表的な有効成分には成長因子やビタミン、ミネラルやアミノ酸などがあります。
有効成分を毛根周辺に直接届けられるため、内服薬や外用薬と比べてよりダイレクトな効果が期待できる場合があります。
痛みが少なく、ダウンタイムもほとんどない治療法もありますが、複数回の施術が必要となるのが一般的です。
生活習慣の改善指導
薬物療法や注入療法と並行して、生活習慣の改善指導も行います。
バランスの取れた食事や十分な睡眠、ストレス管理や適切なヘアケアなど、髪の健康に良い生活習慣を身につけると、治療効果を高めて再発を防ぎやすいです。
クリニックでは患者さんの生活スタイルに合わせて、具体的なアドバイスを行います。
女性のびまん性脱毛症の改善には、治療とセルフケアの両面からの取り組みが大切です。
治療を受ける上での注意点と費用
びまん性脱毛症の治療を始めるにあたり、効果や期間、副作用や費用について理解しておくことが大切です。
治療効果と期間の目安
びまん性脱毛症の治療効果が現れるまでには個人差がありますが、一般的に時間がかかります。
ヘアサイクル(毛周期)の関係上、効果を実感し始めるまでには少なくとも3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。
すぐに効果が出なくても、焦らずに根気強く治療を続けることが重要です。治療効果の現れ方や期間については、治療開始前に医師から十分に説明を受けてください。
副作用のリスクについて
どのような治療法にも副作用のリスクが伴います。
内服薬では、まれに胃腸症状やアレルギー反応などが起こる可能性があります。
外用薬(ミノキシジルなど)では、頭皮のかゆみやかぶれ、初期脱毛(治療開始後に一時的に抜け毛が増える現象)などがみられるケースがあります。
注入療法では注入部位の赤みや軽い痛み、内出血などが起こる可能性がありますが、通常は一時的なものです。
治療開始前には起こりうる副作用について医師から説明を受け、理解しておくと良いでしょう。
主な治療法の副作用
| 治療法 | 考えられる主な副作用 |
|---|---|
| 内服薬 | 胃腸症状、アレルギー反応、頭痛など(薬剤による) |
| 外用薬 | 頭皮のかゆみ、かぶれ、発赤、初期脱毛、多毛(ミノキシジルなど) |
| 注入療法 | 注入部位の赤み、腫れ、痛み、内出血、感染(まれ) |
治療費用の相場
びまん性脱毛症の治療は多くの場合、健康保険適用外の自由診療となります。そのため、クリニックや治療内容によって費用は異なります。
一般的に、内服薬や外用薬による治療は月々数千円から数万円程度、注入療法は1回あたり数万円から十数万円程度が相場となります。
治療を開始する前に、必要な費用総額や支払い方法についてクリニックにしっかりと確認しましょう。
治療費用の目安(自由診療の場合)
| 治療内容 | 費用の目安(月額または1回あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 内服薬 | 5,000円~15,000円/月 | 薬剤の種類による |
| 外用薬 | 5,000円~20,000円/月 | 薬剤の種類や濃度による |
| 注入療法 | 30,000円~100,000円/回 | 薬剤の種類や注入範囲による、複数回必要 |
上記はあくまで目安であり、実際の費用はクリニックによって異なります。
クリニック選びのポイント
女性の薄毛治療を専門に行っているクリニックや皮膚科専門医、形成外科専門医などが在籍しているクリニックを選ぶのが望ましいです。
カウンセリングが丁寧で症状や治療法について分かりやすく説明してくれるか、費用体系が明確であるか、プライバシーへの配慮があるかなども重要なポイントです。
複数のクリニックで相談し、ご自身が納得でき、信頼できると感じる医師やクリニックを選ぶことをお勧めします。
自宅でできるびまん性脱毛症の予防と対策
びまん性脱毛症の予防と改善には、クリニックでの治療と合わせてご自宅でできるセルフケアも重要です。
バランスの取れた食事と栄養
髪の毛は主にタンパク質(ケラチン)でできています。そのため、良質なタンパク質の摂取は非常に大切です。肉、魚、卵、大豆製品などをバランスよく食事に取り入れましょう。
また、髪の成長にはビタミンやミネラルも欠かせません。特に、亜鉛はタンパク質の合成を助け、ビタミンB群は頭皮環境を整える働きがあります。
ビタミンEは血行促進に役立ちます。緑黄色野菜やナッツ類、海藻類なども積極的に摂取して栄養バランスの整った食事を心がけることが、女性のびまん性脱毛症改善の基本です。
髪の健康に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける、毛母細胞の活性化 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類、チーズ |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝促進、皮脂分泌の調整 | レバー、豚肉、マグロ、カツオ、納豆、卵、緑黄色野菜 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、植物油、うなぎ |
正しいシャンプーとヘアケア
頭皮を清潔に保つのは大切ですが、洗いすぎや間違ったシャンプー方法は、かえって頭皮環境を悪化させる可能性があります。
ご自身の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌など)に合った、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーを選びましょう。
洗髪時は爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないようにしっかりと洗い流します。
| 工程 | ポイント |
|---|---|
| シャンプー選び | アミノ酸系などマイルドな洗浄成分のもの |
| 洗い方 | 指の腹で優しくマッサージするように |
| すすぎ | しっかりと洗い流す |
| 乾燥 | ドライヤーで頭皮から優しく乾かす |
洗髪後はドライヤーで頭皮から優しく乾かすことが大切です。濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなります。
ストレスケアと質の高い睡眠
ストレスは自律神経のバランスを乱して血行不良を引き起こすため、髪の成長に悪影響を与えます。
自分なりのストレス解消法を見つけ、リラックスできる時間を作る工夫が大切です。軽い運動、趣味の時間、友人との会話なども良いでしょう。
また、髪の成長ホルモンは主に睡眠中に分泌されますので、質の高い睡眠を十分にとるのも重要です。寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用を控えるなど、睡眠環境を整えましょう。
頭皮マッサージの効果
頭皮マッサージは頭皮の血行を促進し、毛根への栄養供給を助ける効果が期待できます。シャンプー時やリラックスタイムなどに指の腹を使って、頭皮全体を優しく揉みほぐしましょう。
強くこすりすぎると頭皮を傷つける可能性があるので注意が必要です。心地よいと感じる程度の力加減で行うのがポイントです。
少しの時間でも継続すると頭皮環境の改善につながる可能性があります。
びまん性脱毛症に関するよくある質問(FAQ)
最後に、びまん性脱毛症に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q治療はいつから始めるべきですか?
- A
薄毛や抜け毛が気になり始めたら、できるだけ早めに専門のクリニックに相談することをおすすめします。
びまん性脱毛症は進行性のものもあり、早期に原因を特定して適切な対策や治療を開始すると改善の効果が高まる可能性があります。
自己判断で放置せず、まずは専門医の診断を受けましょう。
- Q市販の育毛剤は効果がありますか?
- A
市販の育毛剤には、頭皮環境を整える成分や血行を促進する成分が含まれているものが多いです。
軽度の抜け毛予防や頭皮ケアとしては一定の効果が期待できる場合もありますが、発毛効果が医学的に認められている成分(ミノキシジルなど)の配合濃度が低い、あるいは配合されていない製品もあります。
すでに進行しているびまん性脱毛症に対しては、市販品だけでの改善は難しい場合が多いです。確実な効果を求める場合は、クリニックで処方される医薬品の使用を検討しましょう。
- Q治療をやめると元に戻りますか?
- A
びまん性脱毛症の原因や治療内容によって異なります。
例えば、ミノキシジルなどの発毛効果のある薬剤を使用している場合は使用を中止すると、数ヶ月かけて治療前の状態に戻ってしまう可能性があります。
これは、薬剤の効果によって維持されていた毛髪が、本来のヘアサイクルに戻るためです。
生活習慣の改善など根本的な原因への取り組みも重要ですが、薬剤治療に関しては、効果を維持するために継続が必要となるケースが多いです。
治療の中止については自己判断せず、必ず医師に相談してください。
- Qウィッグやヘアピースの使用について
- A
薄毛が気になる間のカバー方法として、ウィッグやヘアピースは有効な選択肢です。精神的な負担を軽減し、QOL(生活の質)を向上させる助けになります。
最近では自然で高品質な製品も多くあります。ただし、長時間の着用や通気性の悪い製品の使用は頭皮が蒸れてしまい、かえって頭皮環境を悪化させる可能性もあります。
使用する場合は清潔に保ち、適切なケアを行うことが大切です。クリニックによっては、ウィッグに関する相談も受け付けている場合があります。
参考文献
SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
MOUNSEY, Anne L.; REED, Sean W. Diagnosing and treating hair loss. American family physician, 2009, 80.4: 356-362.
MALKUD, Shashikant. A hospital-based study to determine causes of diffuse hair loss in women. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 2015, 9.8: WC01.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
TRÜEB, Ralph M. Systematic approach to hair loss in women. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2010, 8.4: 284-297.
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
CHARTIER, Molly Beth; HOSS, Diane Marie; GRANT-KELS, Jane Margaret. Approach to the adult female patient with diffuse nonscarring alopecia. Journal of the American Academy of Dermatology, 2002, 47.6: 809-818.