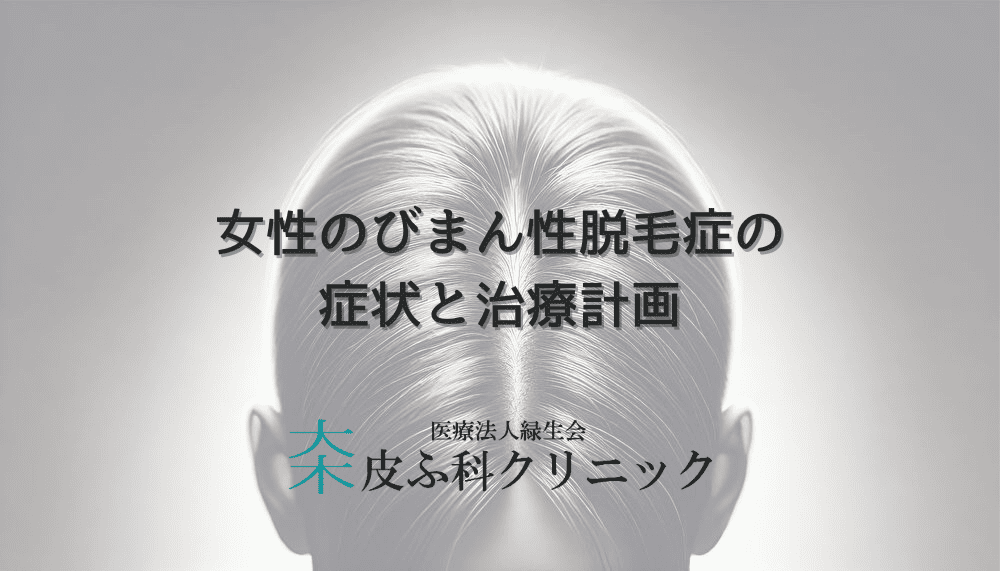「最近、分け目が目立つようになった」「髪全体のボリュームが減ってきた気がする」「急に髪が薄くなったかもしれない」と感じたら、それは「びまん性脱毛症」のサインかもしれません。
びまん性脱毛症は、女性特有の薄毛の悩みとして多く見られる症状です。
この記事では、女性のびまん性脱毛症の症状や原因、そしてクリニックでの診断から具体的な治療計画、ご自身でできるセルフケアまでを詳しく解説します。
びまん性脱毛症とは?女性に多い薄毛の悩み
はじめに、女性のびまん性脱毛症の基本的な情報について解説します。どのような脱毛症なのか、なぜ女性に多いのか、そして最近の傾向について見ていきましょう。
びまん性脱毛症の定義と特徴
びまん性脱毛症とは、特定の部位だけでなく頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる脱毛症を指します。「びまん」とは「広範囲に広がる」という意味です。
髪の毛一本一本が細くなったり全体の密度が低下したりするため、地肌が透けて見えるようになります。
男性型脱毛症(AGA)のように生え際が後退したり、頭頂部だけが薄くなったりするのとは異なるパターンを示すのが特徴です。
多くの女性が悩む薄毛の症状の一つであり、早期に気づき対策を始めることが大切です。
女性に起こりやすい理由と男性型脱毛症との比較
女性のびまん性脱毛症は、男性型脱毛症(AGA)とは異なる原因や症状の現れ方をします。
女性ホルモンの変動が大きく関わっていると考えられており、特に加齢や出産、ストレスなどが引き金となる場合があります。
男性の場合は男性ホルモンの影響で生え際や頭頂部が薄くなるケースが多いですが、女性の場合は頭部全体の毛髪が薄くなる傾向があります。
びまん性脱毛症と男性型脱毛症(AGA)の主な違い
| 特徴 | 女性のびまん性脱毛症 | 男性の男性型脱毛症(AGA) |
|---|---|---|
| 主な症状 | 頭部全体の毛髪が薄くなる | 生え際の後退、頭頂部の薄毛 |
| 進行パターン | 全体的に徐々に進行 | 特定のパターンで進行 |
| 主な要因 | ホルモンバランス、加齢、ストレスなど | 男性ホルモン、遺伝 |
「急に髪が薄くなった」と感じる女性が増えていることについて
近年「急に髪が薄くなった」と感じ、クリニックを受診される女性が増えています。
これは、生活スタイルの変化や社会的なストレスの増加、薄毛に関する情報が増えてご自身の状態に気づきやすくなったことなどが背景にあると考えられます。
以前は加齢による変化と捉えられがちでしたが、若い世代でも発症するケースがあり、幅広い年齢層の女性にとって身近な悩みとなっています。
びまん性脱毛症で見られる主な症状
ここでは、びまん性脱毛症の具体的な症状について詳しく見ていきます。ご自身の状態と照らし合わせながら確認してみましょう。
頭部全体の毛髪ボリュームの低下
びまん性脱毛症の最も代表的な症状は、頭部全体の髪の毛の量が減ることです。以前と比べて髪をまとめたときの太さが細くなった、ヘアスタイルが決まりにくくなった、と感じる場合があります。
特定の部位だけではなく全体的に髪が少なくなるため、初期段階では気づきにくいケースもありますが、進行すると地肌が透けて見えるようになります。
分け目やつむじ周辺が目立つようになる
頭頂部や分け目の部分の地肌が以前よりも目立つようになるのも、びまん性脱毛症によく見られる症状です。
髪全体の密度が低下するため、特に分け目やつむじ周辺の地肌が露出しやすくなります。鏡を見たときや写真を見たときに、分け目の幅が広がったように感じたら注意が必要です。
症状のセルフチェックポイント
| チェック項目 | 以前との比較 |
|---|---|
| 髪全体のボリューム | 全体的に減った、ペタンとしやすくなった |
| 分け目・つむじ | 幅が広がった、地肌が目立つようになった |
| 髪質 | 細くなった、ハリやコシがなくなった |
| 抜け毛 | シャンプー時やブラッシング時の量が増えた |
細毛化やハリ・コシの喪失などの髪質の変化
髪の毛そのものが細く弱々しくなる「細毛化(軟毛化)」も、びまん性脱毛症の症状の一つです。髪にハリやコシがなくなり、全体的に元気がない印象になります。
髪が細くなると同じ本数でもボリュームが少なく見え、スタイリングも難しくなります。手触りの変化や、髪が切れやすくなったと感じる方もいます。
抜け毛が増えたと感じるサイン
シャンプーやブラッシングの際に、以前よりも明らかに抜け毛が増えたと感じる場合も注意が必要です。排水溝にたまる髪の毛の量や、枕についている髪の毛の量などを意識してみましょう。
ただし、髪にはヘアサイクル(毛周期)があり、1日に50本から100本程度の抜け毛は正常な範囲です。急激に量が増えたと感じる場合に、びまん性脱毛症の可能性を考えます。
女性のびまん性脱毛症の考えられる原因
女性のびまん性脱毛症は、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発症するケースが多いです。
加齢やライフステージによるホルモンバランスの変化
女性ホルモン(エストロゲン)には、髪の成長を促進して成長期を維持する働きがあります。
加齢に伴いエストロゲンの分泌量が減少すると相対的に男性ホルモンの影響が強まり、ヘアサイクルが乱れて抜け毛が増えたり、髪が細くなったりする場合があります。
特に更年期世代の女性にびまん性脱毛症が多く見られるのはこのためです。
また、妊娠・出産後の一時的なホルモンバランスの急激な変化も、抜け毛(産後脱毛症)を引き起こしやすいです。
生活習慣の乱れやストレス、睡眠不足など
過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こす可能性があります。血行が悪くなると、髪の毛の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなり、脱毛の原因となり得ます。
また、睡眠不足も髪の成長を妨げる要因です。髪は睡眠中に成長ホルモンの分泌が活発になることで健やかに育つため、質の高い睡眠を十分にとる工夫が重要です。
不規則な生活や喫煙習慣なども頭皮環境や全身の健康に悪影響を与え、薄毛につながる可能性があります。
ストレスとなりうる要因の例
以下のようなものが、知らず知らずのうちにストレスとなっている場合があります。
- 仕事や学業上のプレッシャー
- 人間関係の悩み
- 家庭環境の変化
- 経済的な問題
- 将来への不安
ダイエットや食生活の乱れによる栄養状態の偏り
髪の毛は主にタンパク質(ケラチン)で構成されており、その生成には亜鉛や鉄、ビタミン類など様々な栄養素が必要です。
過度なダイエットや偏った食生活によってこれらの栄養素が不足すると健康な髪の毛を作れなくなり、抜け毛や細毛の原因となります。
特に女性は月経や妊娠・出産などで鉄分が不足しやすいため、意識的な摂取が求められます。バランスの取れた食事は健やかな髪を育むための基本です。
髪の健康に関わる主な栄養素
| 栄養素カテゴリー | 栄養素 | 役割 |
|---|---|---|
| タンパク質 | ケラチン | 髪の主成分 |
| ミネラル | 亜鉛、鉄 | 毛髪生成の補助、毛母細胞の活性化 |
| ビタミン | ビタミンB群、C、E | 頭皮環境の維持、血行促進 |
不適切なヘアケアで起こる頭皮環境の悪化
間違ったシャンプー方法や洗浄力の強すぎるシャンプーの使用、頻繁なカラーリングやパーマなどが頭皮にダメージを与え、炎症や乾燥、血行不良を引き起こしている方も見受けられます。
頭皮環境が悪化すると健康な髪が育ちにくくなり、抜け毛や薄毛の原因となります。また、頭皮の毛穴が皮脂や汚れで詰まるのも、髪の成長を妨げる一因です。
不適切なヘアケアの例
- 洗浄力の強すぎるシャンプーの使用
- 爪を立ててゴシゴシ洗うシャンプー
- すすぎ残し
- ドライヤーの熱風を当てすぎる
- 頻繁なカラーリングやパーマ
特定の病気や薬剤使用による影響
甲状腺機能の異常(甲状腺機能低下症や亢進症)や膠原病などの自己免疫疾患、鉄欠乏性貧血などが、びまん性脱毛症の原因となるケースがあります。
また、特定の薬剤(抗がん剤、一部の降圧剤、抗うつ剤など)の副作用として脱毛が起こるケースもあります。これらの場合は、原因となる病気の治療や薬剤の変更・中止によって、脱毛症状が改善する可能性があります。
思い当たる病気や服用中の薬がある場合は、必ず医師に相談してください。
クリニックで行う診断の流れ
びまん性脱毛症が疑われる場合、専門のクリニックで正確な診断を受けることが重要です。
初診時の問診
まず、患者さんの状態を詳しく把握するために問診を行います。
問診で聞かれる情報は、脱毛の原因を探り、適切な治療方針を立てる上で非常に重要です。些細なことでも気になる点があれば、遠慮なく医師に伝えてください。
問診で確認する項目
| 確認項目カテゴリー | 具体的な質問例 |
|---|---|
| 症状について | いつから気になり始めたか、どの部位が気になるか |
| 抜け毛について | 量は増えたか、いつ増えたと感じるか |
| 生活習慣 | 食事内容、睡眠時間、喫煙・飲酒習慣、ストレスの有無 |
| 病歴・服薬歴 | これまでにかかった病気、現在服用中の薬、サプリメント |
| 家族歴 | ご家族に薄毛の方はいらっしゃるか |
医師による視診と触診
次に、医師が直接、頭皮と髪の毛の状態を観察します。頭皮の色や乾燥、炎症、フケの有無、毛穴の状態などを詳しくチェックします。
また、髪の毛の密度、太さ、ハリ・コシの状態、抜け毛のパターンなどを確認します。視診と触診により、びまん性脱毛症の進行度や他の脱毛症の可能性などを判断します。
必要に応じた血液検査
びまん性脱毛症の原因として、全身性の疾患(甲状腺機能異常や貧血など)や栄養不足が疑われる場合には血液検査を行うときがあります。
ホルモンバランスの状態や鉄分、亜鉛などのミネラルやビタミンなどの栄養状態を調べると、脱毛の根本的な原因特定に役立ちます。
検査結果に基づき、内科的な治療や栄養指導が必要となる場合もあります。
血液検査で確認することがある項目例
| 検査項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 甲状腺ホルモン | 甲状腺機能低下症・亢進症の有無 |
| 血算(貧血検査) | 鉄欠乏性貧血などの有無 |
| 血清鉄・フェリチン | 体内の鉄分の貯蔵量 |
| 亜鉛 | 髪の成長に必要なミネラルの充足度 |
マイクロスコープ検査
マイクロスコープ(拡大鏡)を用いて、頭皮や毛穴、髪の毛の状態をより詳細に観察します。
肉眼では確認できない毛穴の詰まりや炎症、皮脂の分泌状態や髪の毛の太さのばらつき、成長途中の細い毛の有無などを確認できます。
これにより、頭皮環境の問題点やヘアサイクルの乱れの程度などを客観的に評価し、診断の精度を高めます。
びまん性脱毛症に対する治療計画の立て方
診断結果に基づき、患者さん一人ひとりの状態や原因に合わせた治療計画を立てます。
治療開始前のカウンセリングと目標設定
治療を開始する前に、医師から診断結果と推奨される治療法について詳しい説明があります。治療の選択肢や期待できる効果、治療期間の目安や費用、考えられる副作用などについて十分に理解することが大切です。
患者さんの希望や生活スタイルも考慮しながら、相談の上で具体的な治療目標を設定し、納得のいく形で治療を開始します。
体の内側から働きかける内服薬治療
びまん性脱毛症の治療では、内服薬が用いられる場合があります。
女性の薄毛治療でよく用いられるのは、髪の毛の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントや、血行を促進する薬、ホルモンバランスを整える薬などです。
男性型脱毛症(AGA)治療薬として知られるフィナステリドやデュタステリドは、原則として女性への適用がありません。
女性の薄毛治療で検討される内服薬の例
- パントガール
- ミノキシジル
- スピロノラクトン
パントガール(Pantogar)は毛髪の成長に必要なアミノ酸、タンパク質、ビタミンB群などを配合した栄養補助サプリメントです。
ミノキシジル(内服)は血行を促進し、毛母細胞を活性化させる効果が期待されます。医師の厳格な管理下で使用します。
スピロノラクトンは利尿薬ですが、男性ホルモンの作用を抑制する効果があり、女性のホルモンバランスによる脱毛に用いられる場合があります。
頭皮に直接作用させる外用薬治療
頭皮に直接塗布するタイプの外用薬も、びまん性脱毛症治療の重要な選択肢です。最も一般的に用いられるのはミノキシジルを配合した外用薬です。
ミノキシジルは毛母細胞に直接働きかけてヘアサイクルを正常化し、発毛を促進する効果が認められています。女性の場合は、男性用よりも低濃度の製品(例: 1%濃度など)から開始する方が多いです。
医師の指示に従って、正しい用法・用量を守って使用しましょう。
ミノキシジル外用薬の作用
ミノキシジルは、毛包に直接作用して以下のような効果を発揮すると考えられています。
- 毛母細胞の活性化
- ヘアサイクルの成長期延長
- 頭皮の血行促進
発毛を促す注入療法やその他の施術
内服薬や外用薬に加えて、より積極的に発毛を促すために、頭皮に直接有効成分を注入する治療法も行われます。メソセラピーやHARG(ハーグ)療法などが代表的です。
これらの治療では、発毛に必要な成長因子(グロースファクター)やビタミン、ミネラルなどを注射や特殊な機器を用いて頭皮の深層部に届けます。
これにより毛母細胞を直接刺激し、発毛を促す効果が期待できます。また、低出力レーザーを頭皮に照射する治療法などもあります。
主な注入療法の種類
| 治療法名称 | 特徴 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 発毛メソセラピー | 成長因子、ビタミン等を直接頭皮に注入 | 毛母細胞の活性化、発毛促進 |
| HARG療法 | ヒト脂肪幹細胞由来の成長因子等を注入 | 発毛促進、毛髪再生 |
治療効果を補助する栄養療法やサプリメント
薬物療法と並行して、食生活の改善指導や髪の成長に必要な栄養素を補うサプリメントの摂取が推奨される場合があります。
特に、血液検査などで栄養不足が確認されたときは、鉄分や亜鉛、ビタミンなどを補う工夫が治療効果を高める上で役立ちます。
ただし、サプリメントはあくまで補助的な役割であり、治療の基本は医師の処方する薬剤や施術となります。自己判断で過剰に摂取するのは避け、医師に相談の上で利用しましょう。
治療期間の目安と効果について
びまん性脱毛症の治療はすぐに効果が現れるものではなく、根気強く続けることが重要です。
効果を実感し始めるまでの一般的な期間
治療効果が現れるまでの期間には個人差がありますが、一般的には治療を開始してから3ヶ月から6ヶ月程度で抜け毛の減少や産毛の発生といった変化を感じ始める方が多いです。
髪の毛にはヘアサイクルがあるため、新しい髪が成長して見た目の変化として実感できるようになるまでには時間がかかります。焦らず、医師の指示に従って治療を継続すると良いです。
治療効果の段階的な目安
| 期間 | 期待される変化の例 |
|---|---|
| 1~3ヶ月 | 初期脱毛(一時的な抜け毛増加)が見られることも |
| 3~6ヶ月 | 抜け毛の減少、産毛の発生、髪質の改善 |
| 6ヶ月以降 | 毛量の増加、髪のボリュームアップの実感 |
なぜ継続的な治療が必要なのか
びまん性脱毛症の多くは加齢や体質など、根本的な原因を完全に取り除くことが難しい場合があります。
そのため、治療によって改善が見られたとしても、治療を完全に中止すると再び症状が進行してしまう可能性があります。
効果を維持して良好な状態を保つためには、医師と相談しながら治療を継続したり、維持療法に移行したりするのが一般的です。
治療のゴールや継続の必要性については、定期的な診察の中で医師とよく話し合いましょう。
治療効果を高めるために大切なこと
治療効果を最大限に引き出すためには、生活習慣の見直しも重要です。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレスの管理、適切なヘアケアなどを心がけると頭皮環境が整い、治療薬の効果が出やすくなります。
クリニックでの治療とセルフケアを両立させることが、改善への近道です。
治療中に留意すべき副作用の可能性
どのような治療にも、副作用のリスクは伴います。例えば、ミノキシジル外用薬では使用初期にかゆみや赤み、初期脱毛(一時的に抜け毛が増える現象)が見られるケースがあります。
内服薬では、種類によってむくみや動悸、体毛の増加などの副作用が現れる可能性があります。
治療開始前に医師から考えられる副作用について十分な説明を受け、理解しておくことが大切です。治療中に何か異常を感じた場合は、自己判断で中止せず、速やかに医師に相談してください。
日常生活で取り組めるセルフケア
クリニックでの治療と合わせて日々の生活の中でできるセルフケアも、健やかな髪を育むためには重要です。
髪の健康を支える食生活と栄養バランス
髪の毛は、日々の食事から摂取する栄養素をもとに作られます。特に、髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)を十分に摂取することが基本です。肉、魚、卵、大豆製品などをバランス良く取り入れましょう。
また、タンパク質の合成を助ける亜鉛(牡蠣、レバー、ナッツ類など)、頭皮の血行を促進するビタミンE(アーモンド、アボカドなど)、頭皮環境を整えるビタミンB群(豚肉、マグロ、カツオなど)やビタミンC(果物、野菜など)も意識して摂取したい栄養素です。
健やかな髪のための栄養素と食材例
| 栄養素 | 働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチン合成の補助 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | アーモンド、アボカド、うなぎ |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝促進 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |
ストレスとの上手な付き合い方と良質な睡眠
過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を招いて髪の成長に悪影響を与えます。
自分なりのストレス解消法を見つけ、リラックスできる時間を作る工夫が大切です。軽い運動、趣味の時間、友人との会話なども良いでしょう。
また、質の高い睡眠も重要です。髪の成長を促す成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。毎日決まった時間に寝起きするなど、規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。
寝る前のスマートフォン操作は避け、リラックスできる環境を整えるのも効果的です。
頭皮を健やかに保つ正しいシャンプー方法
毎日のシャンプーは頭皮を清潔に保つための基本ですが、間違った方法は逆効果になりやすいです。
まず、シャンプー前にブラッシングをして、髪の絡まりやホコリを取り除きましょう。次に、ぬるま湯で頭皮と髪を十分に予洗いします。
シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは避けましょう。
すすぎは時間をかけて、シャンプー剤が残らないように丁寧に行います。洗髪後は、タオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで頭皮から乾かします。
頭皮マッサージのやり方と注意点
頭皮マッサージは頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を行き渡りやすくする効果が期待できます。リラックス効果もあるため、ストレス緩和にもつながります。
指の腹を使って頭皮全体を優しく揉みほぐすように行いましょう。生え際から頭頂部へ、側頭部から頭頂部へ、襟足から頭頂部へ、といったように、下から上へ向かって行うのがポイントです。
ただし、力を入れすぎたり、爪を立てたりすると頭皮を傷つける可能性があるため注意が必要です。1回あたり数分程度、心地よいと感じる強さで行いましょう。
よくある質問
最後に、びまん性脱毛症の治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q治療に伴う痛みはありますか?
- A
治療法によって異なります。内服薬や外用薬による治療では、基本的に痛みはありません。
注入療法(メソセラピーなど)では、注射による軽い痛みを伴う場合がありますが、冷却や麻酔クリームなどを用いて痛みを軽減する工夫をします。
痛みの感じ方には個人差がありますので、不安な場合は事前に医師にご相談ください。
- Q治療にかかる費用はどの程度ですか?
- A
びまん性脱毛症の治療は、多くの場合、健康保険適用外の自由診療となります。そのため、費用はクリニックや治療内容によって大きく異なります。
内服薬、外用薬、注入療法などを組み合わせる場合、月々の費用も変わってきます。
初診時のカウンセリングで具体的な治療プランとそれにかかる費用について、詳しく説明を受けるようにしましょう。
- Q他の脱毛症と自分で見分けることはできますか?
- A
びまん性脱毛症は頭部全体の髪が薄くなるのが特徴ですが、円形脱毛症のように一部分だけが抜けたり、牽引性脱毛症のように特定の髪型が原因で抜けたりするのとは異なります。
しかし、自己判断は難しく、他の脱毛症や皮膚疾患が隠れている可能性もあります。正確な診断のためには、必ず専門の医師の診察を受けるようにしてください。
- Q治療を中断した場合、髪の状態はどうなりますか?
- A
びまん性脱毛症の原因が加齢や体質などの継続的なものである場合、治療を中断すると再び薄毛が進行し、治療前の状態に戻ってしまう可能性があります。
治療によって得られた効果を維持するためには、医師の指示に従って治療を継続することが重要です。
治療のやめどきや、維持療法への移行については、医師とよく相談して決めるようにしましょう。
参考文献
SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
SHAPIRO, Jerry. Hair loss in women. New England Journal of Medicine, 2007, 357.16: 1620-1630.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
BERGFELD, Wilma. Diffuse hair loss: its triggers and management. Cleve Clin J Med, 2009, 76.6: 361-370.