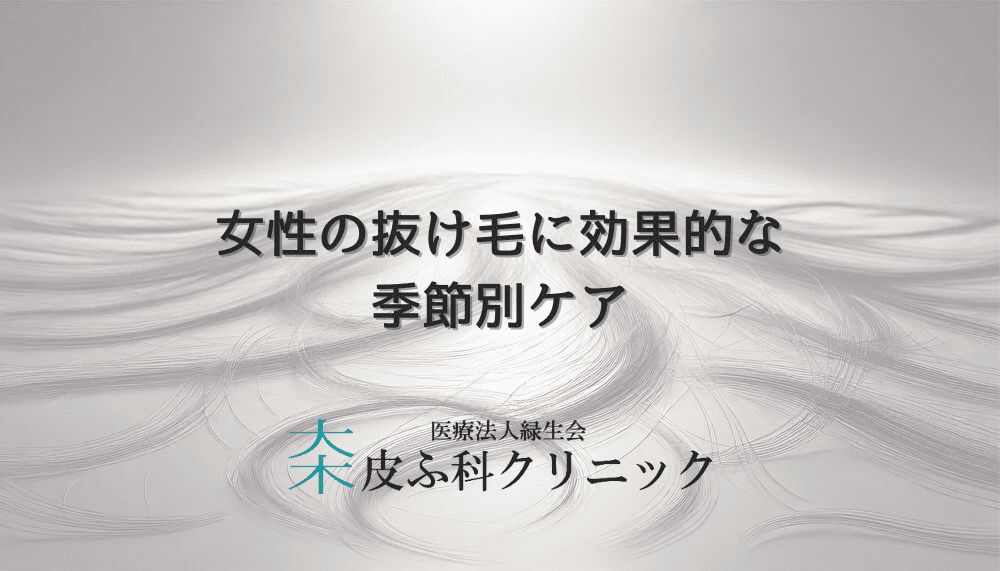日差しが強くなり始める季節は、紫外線や湿度の変化などにより頭皮環境が乱れやすくなります。
5月の抜け毛、6月の抜け毛に悩む方は、気候が大きく変わる時期に髪や頭皮に負担がかかりやすいことを実感しているのではないでしょうか。
また、9月の抜け毛を経験した方も多いように、夏から秋への移り変わりも抜け毛が増えやすい時期です。
春から夏にかけて髪を守るためには、適切な頭皮ケアや生活習慣の見直しが必要です。
春から夏にかけての抜け毛が増える理由
春から夏への移行期は気温と湿度が上昇し、頭皮の皮脂分泌量も変動します。
抜け毛を意識し始める方の多くが、この時期に髪が抜けやすいと感じているようです。その背景には複数の要因が影響しています。
気温上昇による頭皮への影響
気温が高くなると、体は熱を逃がすために皮膚の血管を拡張します。頭皮も同様で、皮脂の分泌が盛んになる場合があります。
皮脂が増えたまま放置すると、毛穴の詰まりや雑菌の繁殖を招くケースがあり、抜け毛のリスクが高まります。
紫外線の強まりと髪への負担
春から夏は紫外線が急激に強まります。紫外線が頭皮に直接当たると、毛根周辺の細胞がダメージを受ける可能性があります。
髪自体にも影響が及びやすく、乾燥やパサつき、切れ毛につながることもあります。
湿度変化とヘアダメージ
湿度が高くなると、髪の内部や頭皮の水分バランスが崩れがちです。
髪が広がりやすくなったり、頭皮がベタついたりすると、無意識に頭皮を触ってしまいがちになります。その結果、知らぬ間にダメージの蓄積が起こりやすいです。
ストレスとの関連
新生活がスタートする春は、人間関係や生活環境の変化がストレスを引き起こす場合があります。
ストレス過多になると、ホルモンバランスが乱れやすく、髪の成長サイクルに影響が及ぶ場合があります。
春から夏にかけて頭皮環境が変化しやすい要因
| 要因 | 具体的な影響 | 注意点 |
|---|---|---|
| 気温上昇 | 皮脂分泌の増加 | シャンプー方法の見直し |
| 紫外線強化 | 毛根周辺細胞へのダメージ | 日傘や帽子、UVカットの対策 |
| 湿度の上昇 | ベタつきやすい頭皮 | 通気性のよいヘアスタイル |
| ストレス増大 | ホルモンバランスの乱れ | ストレスケア、十分な睡眠 |
春から夏にかけて抜け毛が増える原因をいくつか挙げましたが、複合的に重なり合うことで髪や頭皮にとって負担が大きくなるときがあります。
日常的なケアを大切にすると、負担を軽減できる可能性があります。
5月と6月に増える抜け毛の特徴
春の終わりから初夏にかけては、気温と湿度の上昇だけでなく、連休や梅雨の影響などさまざまな外部要因も重なる時期です。
5月の抜け毛や6月の抜け毛を実感する方は、その特徴を知ると対策を立てやすくなるでしょう。
5月の環境変化に伴う頭皮トラブル
ゴールデンウィークなどの長期休暇によって生活リズムが乱れたり、外出が増えたりします。
また、紫外線が思ったより強くなっている場合も多く、対策を怠ると頭皮と髪の負担が増えます。
休み明けから仕事や学校が本格化し、ストレスが増大する傾向も抜け毛に影響するかもしれません。
6月の梅雨と頭皮の湿度対策
6月は梅雨のシーズンに入り、空気中の湿度が大幅に上昇します。頭皮の通気性が低下すると、皮脂や汗が混ざり合い、雑菌の増殖を招きやすくなります。
髪がまとまりにくくなるだけでなく、痒みなどの頭皮トラブルが起こると抜け毛につながるケースも考えられます。
春先から初夏への生活リズムの崩れ
5月の抜け毛や6月の抜け毛が気になる時期は、新しい環境に慣れる過程で無理を重ねてしまいやすいとも言われます。
睡眠不足や栄養バランスの乱れは、髪の成長サイクルを鈍化させてしまうおそれがあります。
ホルモンバランスの変動
女性はホルモンバランスの変化により、抜け毛の量が増えるタイミングがあります。特に季節の変わり目は体調を崩しやすく、ホルモンの変動も激しくなる場合があります。
体調管理を意識するだけでなく、専門家に相談してバランスを整えるケアが大切です。
5月と6月に増えやすい抜け毛の要因と対策
| 要因 | 抜け毛に直結しやすい理由 | 取り組みやすい対策 |
|---|---|---|
| 長期休暇の生活リズム乱れ | 睡眠不足や栄養不足に陥る | 食事管理・睡眠時間の確保 |
| 紫外線対策不足 | 毛根へのダメージが蓄積しやすい | UVカットスプレーや帽子を活用 |
| 梅雨時の高湿度 | 雑菌が繁殖しやすい頭皮環境 | 抗菌作用が期待できるシャンプーを使用 |
| ストレス増加 | ホルモンバランスの乱れを招きやすい | 気分転換・適度な運動 |
原因ごとに適した対策を行っていきましょう。
生活習慣を意識するポイント
- 夜更かしの習慣を改める
- バランスのよい朝食を摂取する
- 通勤時に帽子や日傘で紫外線対策を行う
- お風呂でしっかり頭皮をマッサージする
5月と6月は紫外線と湿度に注意しつつ、生活リズムの見直しが大切です。
9月に注目した抜け毛の特徴
夏の終わりから秋にかけては、気温と湿度が徐々に下がり始めますが、夏の間に受けた髪や頭皮のダメージが表面化しやすい時期でもあります。
9月の抜け毛を訴える方が多い理由には、夏の過ごし方が大きく関係しています。
夏のダメージが蓄積した頭皮環境
夏は紫外線が強く、海やプールなどで髪を濡らす機会も増えます。紫外線や塩素によるダメージが毛髪に蓄積すると、抜け毛に直結する場合があります。
秋口に入る9月は、こうした夏の影響が目に見え始める時期です。
夏バテや食欲不振による栄養不足
暑い季節は食欲が落ちやすく、栄養バランスが崩れがちになります。
髪の健康を保つためには良質なたんぱく質やビタミン、ミネラルの補給が重要です。夏バテや不規則な食生活が続くと、髪の成長を妨げるリスクが高まります。
汗・皮脂の過剰分泌と頭皮トラブル
夏は汗をかく機会が多く、皮脂と汗が混ざると頭皮がベタつきやすいです。充分に洗髪できなかったり、きちんと乾かさなかったりすると、毛穴に老廃物が蓄積して抜け毛を招きやすくなります。
9月はこのような頭皮トラブルが顕在化する時期ともいえます。
秋への移行時期のストレス
夏休みが終わり、新しい環境や行事が始まる9月は、気候変化に加えて心の疲れが溜まりやすい時期です。
ストレスが髪に与える負担は決して小さくありません。ストレスケアを怠ると、抜け毛の量が増加する可能性があります。
9月に抜け毛が増える原因とポイント
| 原因 | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 夏の紫外線やプールのダメージ | 髪内部のタンパク質変性、枝毛や切れ毛に直結 | 保湿ケアやトリートメントの徹底 |
| 夏バテによる栄養不足 | 毛髪への栄養が不足して成長力が低下 | タンパク質やビタミンの積極的摂取 |
| 汗・皮脂の過剰分泌 | 毛穴詰まりや雑菌繁殖で頭皮環境が悪化 | シャンプーや洗髪後の乾燥を徹底 |
| 秋の行事によるストレス | ホルモンバランスの乱れにつながる可能性 | 適度なリフレッシュや専門医への相談 |
9月の抜け毛対策を意識する場合は、夏をどう過ごしたかを振り返りながら、髪と頭皮を労わるケアを継続するとよいでしょう。
抜け毛を抑えるための食事と栄養管理
髪の生成や成長には、さまざまな栄養素が関わっています。日々の食事から栄養を取り入れる工夫が、健康な頭皮環境づくりにとって重要です。
良質なタンパク質の摂取
髪の主成分はケラチンというタンパク質です。
鶏肉や魚、大豆製品、卵などを積極的にメニューに加えると、髪の強度を支える材料を補給できます。
ビタミンとミネラルのバランス
ビタミンB群や亜鉛、鉄などは髪の生成や頭皮の血流促進に関与している栄養素です。
栄養バランスを整えるために、野菜や果物、海藻類などをまんべんなく摂取するとよいでしょう。
抗酸化作用のある食品
酸化ストレスは髪や頭皮に影響を与えやすい要因の一つです。
ビタミンCやビタミンE、ポリフェノールなどを含む食品(柑橘類、ナッツ類、ベリー類)を取り入れると、髪の健康をサポートできます。
髪の成長に役立つ栄養素と食品
| 栄養素 | 働き | 食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料 | 鶏肉、魚、大豆製品、卵 |
| 亜鉛 | 毛髪細胞の合成サポート | 牡蠣、牛肉、ナッツ類 |
| 鉄 | 血液を介した酸素供給の促進 | レバー、ほうれん草、ひじき |
| ビタミンB群 | 代謝のサポート、頭皮の皮脂バランス調整 | 豚肉、納豆、乳製品 |
| ビタミンC | 抗酸化作用、コラーゲン生成 | 柑橘類、ピーマン、キウイ |
| ビタミンE | 血流促進、酸化ストレスの軽減 | アーモンド、アボカド、うなぎ |
食事と生活リズムの関係
朝食を抜くと、血糖値が急激に変動しやすく、ホルモンバランスが乱れがちになります。夕食の過剰摂取やアルコールの摂りすぎも、髪の健康には望ましくありません。
規則正しい食生活を送るだけでなく、睡眠の質を意識することも髪の維持にとって大切です。
毎日の食事に取り入れやすい工夫
- 朝食に卵や納豆を加えてタンパク質を確保
- 間食にはナッツ類やヨーグルトを選ぶ
- 魚や海藻を意識的に料理に取り入れる
- 野菜を茹でたり蒸したりして簡単に摂取量を増やす
適切な栄養管理を行うと、髪だけでなく全身の健康状態も向上しやすくなります。
季節別のヘアケア実践法
季節ごとの特徴に合わせたケアを行うと、抜け毛を減らすだけでなく髪の質感を高める効果も期待できます。
春から夏にかけては、気候と湿度の急激な変化に対応したケアがとくに大切です。
春のケアポイント
春先は花粉や黄砂、ホコリなどが舞いやすく、頭皮や髪が汚れやすい時期です。外出後はこまめなブラッシングや洗髪を心がけると、毛穴の詰まりを防ぎやすくなります。
また、紫外線が徐々に強くなるため、早めのUV対策を行うとダメージを減らせます。
梅雨のケアポイント
湿度が高い梅雨時期は、頭皮が蒸れないように通気性のよいヘアスタイルを心がけましょう。
髪を結ぶ際はきつく束ねすぎず、頭皮を締め付けないようにすると血行不良を防ぎやすいです。抗菌成分を含むシャンプーを使用するのも有効です。
湿度が高い日に意識したい洗髪のポイント
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| シャンプー前のブラッシング | 髪と頭皮の汚れを浮かせて洗浄をスムーズにする |
| 丁寧なすすぎ | シャンプー剤の残留を防ぎ、頭皮のかゆみや臭いを軽減 |
| トリートメントの適度な量 | 過剰に使うとベタつきやすくなるので量を調整する |
| ドライヤーの適切な温度 | 熱によるダメージを回避しつつ、頭皮をしっかり乾かす |
夏のケアポイント
夏は紫外線が強烈で、髪だけでなく頭皮もダメージを受けやすいです。UVカット効果のあるヘアケア製品や帽子の活用が大切になります。
汗や皮脂が多く分泌されるため、シャンプー後のしっかり乾燥と頭皮のマッサージを行うと毛穴トラブルを防ぎやすいです。
夏の終わりに備える予防策
夏が終わりに近づくにつれ、日差しのピークを過ぎる反面、頭皮や髪のダメージが蓄積しているかもしれません。
頭皮に優しい成分を含むローションやエッセンスを使って、毛根周辺の健康を取り戻すケアを取り入れるとよいでしょう。十分な保湿を行うと秋口の抜け毛を抑える力になります。
女性に多い頭皮トラブルへの対処
女性ならではのホルモンバランスの変化や生活リズムによって、頭皮トラブルが起こるケースは少なくありません。
抜け毛の原因になりやすい頭皮トラブルを把握して、早期に対処することが重要です。
フケやかゆみの対処
頭皮の乾燥や脂性のどちらが原因となっているかで対処法が異なります。
洗浄力が強すぎるシャンプーは乾燥を悪化させる場合があるので、自分の頭皮タイプに合った製品を選択してください。掻きむしると炎症を悪化させるので、注意が必要です。
皮脂過剰による毛穴のつまり
皮脂過剰の原因としてホルモンバランスの乱れが挙げられます。
女性特有の生理周期によっても皮脂分泌が増えるタイミングがあり、皮脂と汗、汚れが混ざると毛穴がつまりやすくなります。
洗髪時に頭皮をマッサージして毛穴の汚れを落とすのが望ましいです。
頭皮ニキビや炎症
ストレスや睡眠不足、食生活の乱れが続くと、頭皮にニキビや炎症が起こる場合があります。放置すると毛根を傷めて抜け毛につながる可能性が高いです。
悪化が見られるときは、皮膚科や薄毛治療の専門クリニックで相談すると安心です。
トラブル別のケアと有効な頭皮ケア成分
| トラブル | 有効成分・ケア方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| フケ・かゆみ | 保湿成分(ヒアルロン酸、セラミド)、低刺激シャンプーなど | 洗いすぎやこすりすぎを避ける |
| 皮脂過剰 | 抗菌成分(ピロクトンオラミン等)、頭皮マッサージ | 洗髪後のしっかり乾燥を心がける |
| 頭皮ニキビや炎症 | 抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)、専門医の診断 | 無理に潰さず専門家に相談する |
自宅ケアで心がける予防策
- シャンプーは自分の頭皮タイプに合ったものを選ぶ
- 頭皮を掻かずにマッサージや保湿を意識する
- 負担の大きいカラーリングやパーマの頻度を見直す
- お風呂上がりは速やかに髪を乾かして頭皮の蒸れを防ぐ
トラブルの早期発見とケアを徹底すると、抜け毛を抑える可能性が高まります。
専門クリニックでの相談メリット
抜け毛対策は自宅でのケアや市販製品で十分に行える場合もあります。
しかし、抜け毛の原因が複雑化していたり、なかなか改善しない場合は、女性の薄毛治療を得意とする専門クリニックを利用するのが一つの選択肢です。
正確な原因の特定
専門の医師は問診や頭皮の状態チェック、血液検査などを通じて抜け毛の原因を詳細に分析します。
自分では気づきにくい栄養状態の不足やホルモンバランスの乱れなどを見極められるため、的確なケア方法を提示しやすくなります。
個々の症状に合わせた治療計画
同じ抜け毛でも、ストレス起因や遺伝的要因、生活習慣など、人によって背景が異なります。
専門クリニックではカウンセリングを丁寧に行い、一人ひとりの症状に合わせた治療計画を提案することが期待できます。
メディカルケア製品や治療薬の活用
一般的なヘアケア製品では実感しにくい効果を、医療機関専売のヘアケア製品や治療薬を用いることで得られる可能性があります。
これは専門的な判断に基づいて処方や提供が行われるので、安心して使用できます。
専門クリニック受診時に重視されるポイント
| チェック項目 | 具体例 |
|---|---|
| 生活習慣の聞き取り | 食習慣、睡眠時間、ストレスの有無など |
| 頭皮・毛髪のチェック | マイクロスコープによる毛穴の状態観察 |
| ホルモンバランスの確認 | 血液検査による女性ホルモン値の測定 |
| 治療計画と費用の説明 | 治療方法、通院回数、費用の見通し |
専門クリニックへ通うことを検討するときのポイント
- 自分の抜け毛が増える時期や生活リズムをメモしておく
- 事前に質問内容をリストアップしておく
- ホルモンや栄養状態の検査を受けられるか確認する
- 費用や通院頻度に納得できるかカウンセリングで確かめる
専門クリニックへの相談は安心感を得やすく、適切な治療で早期改善を狙いやすいです。
よくある質問
抜け毛が気になる女性から多く寄せられる疑問について、いくつかまとめました。
- Q季節によって抜け毛の量が変わるのは普通ですか?
- A
ある程度は自然な現象ともいえます。髪には生え変わりのサイクルがあり、季節の変化やストレス、生活習慣の乱れなどで抜け毛の量が増減するのは珍しくありません。
ただし、明らかに抜け毛の量が急増したり、自分で見ても髪が細くなったと感じる場合は専門家への相談を検討するとよいでしょう。
- Q5月の抜け毛や6月の抜け毛が増えたらすぐに医療機関を受診すべきですか?
- A
全員がすぐに受診する必要はありませんが、生活習慣を見直しても抜け毛が続く時は専門家の診断を受けることがおすすめです。
例えば、十分な睡眠とバランスのよい食事を意識しても改善が見られない場合や、頭皮に異常があると感じる場合は専門クリニックで相談すると解決策が見つかるかもしれません。
- Q抜け毛対策のシャンプーを選ぶ基準は?
- A
髪や頭皮に優しいアミノ酸系や低刺激性のシャンプーを選ぶとよいでしょう。頭皮の皮脂量やトラブルの有無によって適切な成分は異なります。
抗菌作用が期待できる成分や保湿成分が含まれている製品、または無添加タイプなどを検討して、自分に合うものを探すのがポイントです。
- Q専門クリニックの通院はどのくらいの頻度になりますか?
- A
治療内容や個人の症状によって大きく異なります。
軽度の場合は月に1回程度の受診で十分なケースもあれば、症状が進行している方は週1回や2週間に1回など継続的な通院が必要となる場合もあります。
クリニックの方針や治療計画を事前にしっかり確認してから治療を開始するのが望ましいです。
参考文献
LYAKHOVITSKY, Anna, et al. Changing spectrum of hair and scalp disorders over the last decade in a tertiary medical centre. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2023, 37.1: 184-193.
KUNZ, Michael; SEIFERT, Burkhardt; TRÜEB, Ralph M. Seasonality of hair shedding in healthy women complaining of hair loss. Dermatology, 2009, 219.2: 105-110.
HSIANG, E. Y., et al. Seasonality of hair loss: a time series analysis of Google Trends data 2004–2016. British Journal of Dermatology, 2018, 178.4: 978-979.
BUONTEMPO, Michael G., et al. Seasonal trends in hair loss: A big data analysis of Google search patterns and their association with seasonal factors. Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, 2023, 37.12.
YEAR-ROUND, Optimizing Hair Growth. Does Hair Grow Faster in Summer? Science-Backed Facts & Myths.
RANDALL, Valerie Anne. Androgens and hair growth. Dermatologic therapy, 2008, 21.5: 314-328.
ABELL, Jessica G., et al. Assessing cortisol from hair samples in a large observational cohort: The Whitehall II study. Psychoneuroendocrinology, 2016, 73: 148-156.
GEYFMAN, Mikhail, et al. Resting no more: re‐defining telogen, the maintenance stage of the hair growth cycle. Biological Reviews, 2015, 90.4: 1179-1196.