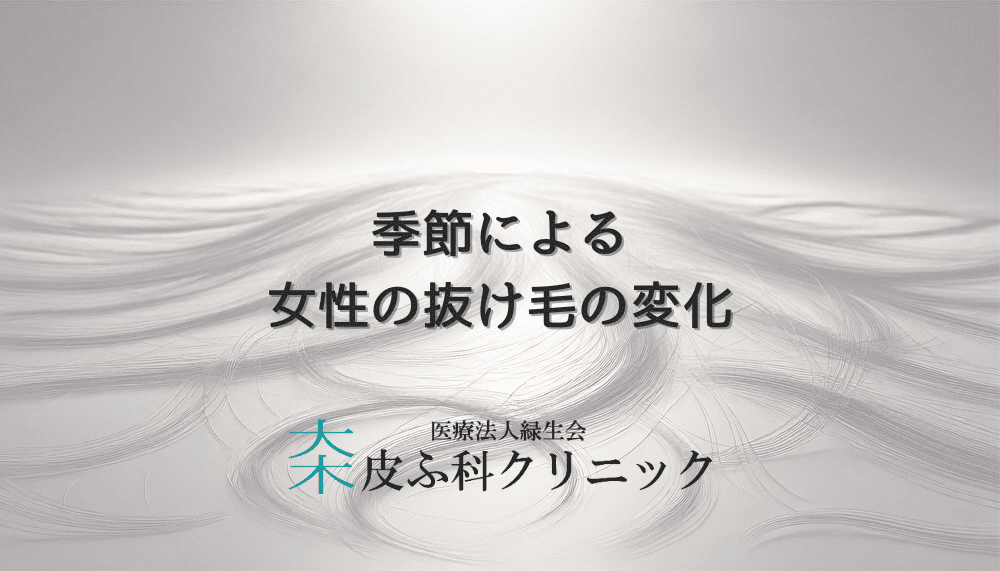季節の移り変わりとともに、女性の頭皮や髪の状態も揺らぎやすくなります。気温や湿度、紫外線量の変化は、抜け毛や薄毛につながるリスクを高める要因になります。
特に5月の抜け毛や6月の抜け毛、そして9月・10月・11月の抜け毛は、季節の影響を受けやすいといわれています。
この記事では、季節別に考えられる抜け毛の特徴と対策、女性の薄毛治療で検討すべき方法などを詳しく解説します。
季節による抜け毛の特徴
季節の変化によって気温や湿度、紫外線の強さなどが変動すると、頭皮や髪へのダメージに影響を及ぼしやすくなります。
気温と頭皮環境の関係
気温が高いと皮脂の分泌量が増加しやすくなり、頭皮がベタつきやすい状態になります。皮脂が増えると毛穴が詰まりやすくなり、抜け毛の一因になりやすいです。
一方で寒い時期には血行が滞りやすくなり、毛母細胞への栄養供給が減少するリスクが高まります。
気温の上下によって頭皮環境が変動すると、髪の寿命にも影響が及びます。季節に合わせたヘアケアを意識しないと、ダメージを受けやすい時期に抜け毛が増えてしまうかもしれません。
紫外線量の増減による影響
紫外線は頭皮にもダメージを与え、髪のキューティクルを傷つける原因になります。
紫外線量が増える時期には、帽子などで頭皮を守らないとトラブルが起こりやすくなります。特に日差しが強くなる初夏から真夏にかけては頭皮が熱を持ちやすくなり、抜け毛の原因になりやすいです。
対策を考えるうえで、次のようなポイントを意識すると頭皮への負担が軽減しやすくなります。
紫外線から頭皮を守るために意識したいこと
- 通気性のよい帽子や日傘を活用する
- 髪専用の日焼け止めスプレーを利用する
- 外出後はクールダウンも兼ねて優しく洗髪する
- 紫外線ダメージを受けた髪には保湿系のトリートメントを使う
湿度の変化による頭皮トラブル
梅雨や雨の多い時期は高湿度になるため、頭皮が蒸れて雑菌が繁殖しやすくなります。頭皮に雑菌が増えるとフケやかゆみが生じ、抜け毛のリスクが高まります。
逆に空気が乾燥する秋から冬にかけては頭皮の水分が不足し、かゆみや炎症が起こりやすい状態になります。
湿度の上がり下がりが激しい時期には、頭皮ケア用品やヘアケア商品の選び方にも注意が必要です。保湿成分を含むシャンプーを使うなど、頭皮の環境を整えるケアが重要になります。
季節ごとに見られる共通点
気温や紫外線、湿度といった環境要因は、それぞれの季節ごとに異なる特徴を持っています。
しかし、「頭皮の状態が乱れる→髪に負担がかかる→抜け毛が増える」という流れには共通点があり、どの季節でも適切に頭皮や髪を守る工夫が大切です。
季節ごとの抜け毛要因と対策
| 季節 | 主な抜け毛要因 | 対策の例 |
|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 気温の上昇、紫外線の増加 | 帽子や日傘で紫外線対策、皮脂コントロール |
| 夏(6〜8月) | 強い紫外線、汗や皮脂の過剰分泌 | 通気性の良い帽子、清涼感のあるシャンプー |
| 秋(9〜11月) | 夏のダメージの蓄積、乾燥への移行 | ダメージケア用シャンプー、保湿強化トリートメント |
| 冬(12〜2月) | 乾燥、血行不良 | 保湿ケア、頭皮マッサージによる血行促進 |
時期ごとの頭皮環境を把握しながら抜け毛を予防する意識を持つと、髪のコンディションを保ちやすくなります。
5月と6月の抜け毛の原因と対策
春先から初夏にかけては、急激に気温や湿度が変化することが多く、頭皮環境が乱れやすくなります。
5月の抜け毛や6月の抜け毛に悩む女性は、紫外線対策や頭皮ケアを入念に行うと効果的です。初夏ならではの原因を理解し、予防や対策を整えることが大切です。
春先の体調変化と頭皮への影響
春は寒暖差が大きく、体調が不安定になりやすい時期です。花粉症やホルモンバランスの乱れによって、頭皮の皮脂分泌が偏る場合もあります。
気温が上がると汗や皮脂の分泌が増加する一方、まだ肌寒い日もあるため、血行が不十分になりがちです。
このアンバランスさが5月の抜け毛の一因になるケースがあります。
5月の抜け毛を悪化させる要因
5月になると紫外線が徐々に強くなり始めるため、日差しの下で長時間過ごす場合は頭皮の日焼けに注意が必要です。
また、新しい環境でのストレスや生活リズムの乱れによって、ホルモンバランスが崩れる可能性もあります。
こうした要因が重なると、抜け毛が顕著になることがあるため、早めの対策が重要になります。
初夏の抜け毛対策
| 対策項目 | 具体的なケアのポイント |
|---|---|
| 紫外線対策 | 日傘や帽子の使用、髪用の日焼け止めスプレーの活用 |
| ストレスケア | 十分な睡眠時間の確保、軽い運動やリラックス法で精神的負担を軽減 |
| 栄養バランスの見直し | タンパク質やビタミン、ミネラルを意識した食事で髪の健康をサポート |
| 洗髪方法の改善 | 皮脂汚れをやさしく落とすシャンプーを選び、洗いすぎを避ける |
適度な紫外線対策と頭皮ケア、さらに生活習慣を整える心がけが5月の抜け毛を抑える鍵になります。
6月の抜け毛を引き起こす主な原因
6月は梅雨に突入する地域が多く、高湿度によって頭皮の蒸れやすさが大きくなる時期です。
皮脂や汗が頭皮に溜まりやすく、雑菌が繁殖しやすい環境に陥ると抜け毛が増える傾向にあります。
また、長雨による気圧の変化で体調や精神面が不安定になりやすく、ホルモンバランスが崩れやすい点も6月の抜け毛の原因の1つです。
湿度と皮脂コントロールのポイント
6月の抜け毛を軽減するためには、湿度と皮脂コントロールが鍵になります。蒸れにくい通気性の良い帽子を選び、外出後は速やかに頭皮を洗浄して清潔に保つよう心掛けましょう。
ただし、洗いすぎると頭皮が乾燥を防ぐために皮脂分泌が過剰になるケースもあるため、適度な洗浄を意識します。
寝具を清潔に保つことや、ドライヤーでしっかり乾かすことも意識すると頭皮環境の安定につながります。
9月から11月にかけての抜け毛の特徴
暑い夏を終えた直後から気温が急に下がり始める9月の抜け毛、秋が深まる10月の抜け毛、そして冬へ向かって空気がさらに乾燥する11月の抜け毛は、多くの女性が悩みやすい傾向にあります。
紫外線ダメージの蓄積や気候の変動による頭皮トラブルが発生しやすい季節といえます。
夏のダメージが秋に響く理由
夏は紫外線が強く、海やプールに行く機会が増えるなど、髪と頭皮に負担がかかりやすい季節です。そのダメージが9月以降に表面化すると、抜け毛が増える要因になります。
夏場の汗や皮脂の過剰分泌が落としきれずに毛穴に残留していると、頭皮のトラブルに発展しやすいです。
紫外線による乾燥ダメージも秋に受け継がれ、キューティクルの剥がれが進むと髪の抜けやすさが増す可能性が高まります。
9月の抜け毛と気候変動
9月は残暑が厳しい日もあれば、急に気温が下がる日もあり、頭皮環境が不安定になります。
外でのスポーツやイベントが多い方は、日中の紫外線と夜の涼しさで頭皮が冷えやすく、血行不良につながる場合もあります。
このような気候変動への不十分な対策が9月の抜け毛を悪化させる要因になります。
秋口に意識しておきたい対策
- 外出時の帽子やスプレーなどによる紫外線ケア
- 日中の運動後はすぐにシャワーで頭皮を洗い清潔を保つ
- 寒暖差による血行不良を防ぐために、入浴やマッサージで頭皮を温める
- 髪の乾燥を防ぐため、保湿成分入りのトリートメントを使う
10月の抜け毛と乾燥対策
10月になると徐々に湿度が下がり、空気が乾燥し始めます。頭皮の乾燥は皮脂の過剰分泌を誘発し、毛穴づまりを起こすときがあります。
乾燥を感じる前に、保湿を意識したシャンプーやトリートメントを選ぶと頭皮への負担が軽減しやすくなります。
また、室内では加湿器を活用し、必要に応じて頭皮用のローションなどを取り入れて潤いを保つ工夫がポイントです。
11月の抜け毛を増やす要因
11月は本格的な冬に差し掛かるため、外気の冷え込みと室内の暖房による乾燥が同時に発生しやすいです。
外気で頭皮の血行が滞り、室内の暖房で頭皮の水分が奪われるというダブルパンチで髪が抜けやすくなるケースがあります。
10月同様に保湿ケアを継続しながら、マッサージで血行を促進する工夫が大切になります。
秋から冬にかけての抜け毛対策
| 時期 | 主な原因 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 9月 | 夏の紫外線ダメージ、残暑 | 紫外線ケア、頭皮を清潔に保つ、適度な保湿 |
| 10月 | 乾燥の始まり、寒暖差 | 保湿系シャンプーやトリートメント、室内加湿 |
| 11月 | 本格的な冷え込み、暖房乾燥 | 血行促進マッサージ、ローションによる頭皮保湿 |
早い段階で秋冬のダメージケアを念頭に置くと、抜け毛の増加を抑えやすくなります。
抜け毛が増えやすい時期のストレスと女性ホルモンの関係
季節の変わり目に抜け毛が増えやすい背景には、気候要因だけでなく精神的なストレスやホルモンバランスの乱れが絡み合う場合が多いです。
女性ホルモンは髪の成長サイクルと密接な関係があるため、その変動が髪質や抜け毛に大きく影響します。
ストレスが髪に与える負担
ストレスを過度に受けると、自律神経やホルモンのバランスが崩れ、血行不良につながるケースが多いです。血行が悪くなると毛根に栄養が届きづらくなり、抜け毛や髪の細りが目立ちやすくなります。
特に新生活が始まる春や年末年始を迎える冬などにストレスが増幅する女性は、時期的な頭皮ケアと精神面のケアを並行して行うのが望ましいです。
女性ホルモンの変動と抜け毛
女性の髪の健康はエストロゲン(卵胞ホルモン)に支えられており、ホルモンの分泌量が低下する更年期などの時期には抜け毛が増える傾向があります。
季節的なストレスや睡眠不足、過剰なダイエットなどによりホルモンのバランスが乱れると、季節に関係なく抜け毛が増えやすいです。
女性ホルモンバランスと髪の状態
| ホルモンバランスの状態 | 髪の状態 | 主な対策 |
|---|---|---|
| エストロゲン豊富 | ツヤがあり、コシが強い | タンパク質とビタミンの摂取、適度な睡眠 |
| バランスが乱れている | 抜け毛が増え、髪が細くなる | 睡眠や食生活の改善、医療機関でのホルモン相談 |
女性ホルモンはストレスや生活習慣にも左右されるため、季節の変化と合わせて健康管理が必要になります。
ホルモンバランスを整えるための心がけ
ホルモンバランスを整えるには、まず睡眠の質を高めることが大切です。就寝前のスマートフォンやパソコンの利用を控え、ぬるめのお湯で入浴し、リラックスできる環境を作ると良いでしょう。
加えて、栄養バランスの取れた食事や適度な運動を心掛けると、自律神経とホルモンの働きをサポートしやすくなります。
無理なダイエットや極端な食事制限はホルモンバランスを崩すリスクが高いため、髪を守るうえでも避けたいところです。
ストレスケアと抜け毛予防
人によってストレスの原因や受け取り方は異なります。仕事や家庭環境の変化など避けられないストレスに直面する場合は、カウンセリングや専門家のアドバイスを受けるのも一つの方法です。
軽いウォーキングやヨガ、呼吸法などのリラクゼーションを日常に取り入れると、ストレスの蓄積を緩和しやすくなります。
日常生活でできる抜け毛対策
季節に左右されずに行える日常的な対策を意識すると、5月の抜け毛や6月の抜け毛、さらに9月・10月・11月の抜け毛の悩みを軽減しやすくなります。
普段のヘアケアや生活習慣のちょっとした工夫で、頭皮や髪の状態を改善しやすくなる点が大きな利点です。
シャンプー・トリートメントの見直し
洗浄力が強すぎるシャンプーは頭皮の脂を取り除きすぎ、乾燥や皮脂の過剰分泌につながる場合があります。
自分の髪質や頭皮の状態を把握して、適度な洗浄力と保湿力を併せ持つ商品を選ぶのが大切です。
トリートメントは頭皮に直接つけず、髪の中間から毛先にかけて塗布するのが望ましいです。過剰な使用によって毛穴を詰まらせるリスクを避けましょう。
正しいドライヤーの使い方
髪を乾かさずに就寝すると頭皮が蒸れ、雑菌の繁殖を招くリスクが高まります。
ただ、ドライヤーを使用する際は、頭皮に熱風を集中させすぎないよう注意が必要です。キューティクルが傷みやすいため、髪から少し離しながら風を当てるとダメージを軽減しやすくなります。
温度を高くしすぎず、最後は冷風で仕上げると髪のキューティクルが整いやすいです。
ヘアドライ時に意識したいポイント
- タオルドライでしっかり水分をふき取る
- ドライヤーは髪から20cm程度離して使う
- 温風と冷風を使い分けて髪を保護する
- 頭皮をマッサージしながら乾かして血行を促進する
頭皮マッサージによる血行促進
頭皮の血行を改善すると毛根へ栄養が行き渡りやすくなります。シャンプー時や入浴中に指の腹を使って円を描くように揉みほぐすと、頭皮が柔らかくなり、毛穴詰まりの軽減にもつながります。
過度に力を入れると頭皮を傷めるので、適度な力加減を保ちながら行うと良いでしょう。
抜け毛を減らすヘアスタイルの選び方
結び目がきついポニーテールやまとめ髪は、長時間続けると髪や頭皮に大きな負担を与えます。
特に髪が湿っている状態で強く結ぶと、キューティクルへのダメージが増えやすく抜け毛の誘因となります。
ヘアスタイルをよく変える、もしくはゴムの位置を変えて結ぶなどの工夫で、頭皮の同じ部分に負担が集中しないようにするのがポイントです。
日常ケアのチェック
| ケア項目 | 具体的な実践ポイント |
|---|---|
| シャンプー選び | 自分の頭皮環境に合うものを選択する |
| ドライヤーの使い方 | 熱風を集中させすぎない |
| 頭皮マッサージ | 指の腹で優しく揉みほぐす |
| ヘアスタイルの工夫 | 同じ髪型を長時間続けない |
小さな習慣を積み重ねると抜け毛のリスクを下げやすくなります。
食事や栄養面から考える抜け毛予防
髪の元になるタンパク質やビタミン、ミネラルなどの栄養素をバランス良く摂ることは、季節を問わず抜け毛を予防するうえで重要です。
食生活の乱れは、ストレスやホルモンバランスの不調につながりやすいため、食事面も一緒に整えるとより効果的です。
髪の主成分ケラチンとタンパク質
髪の主成分であるケラチンはタンパク質から合成されます。タンパク質が不足すると新しい髪を育てる材料が足りなくなり、抜け毛が増える可能性があります。
動物性と植物性のタンパク質をバランスよく摂るのが大切で、肉だけでなく大豆製品や魚介類などを積極的に活用すると良いでしょう。
抜け毛予防に役立つ栄養素
ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEなどの抗酸化作用を持つ栄養素は、頭皮の老化を遅らせる効果が期待できます。
また、亜鉛や鉄分も髪の生成に深く関与しており、不足すると抜け毛が増えやすくなります。
バランスの良い食事を目指すうえで、以下のようなポイントを整理しておくと頭皮ケアの意識を高めやすくなります。
髪に良い栄養素と食品
| 栄養素 | 食材 |
|---|---|
| タンパク質 | 肉、魚、豆腐、納豆 |
| ビタミンA | にんじん、かぼちゃ、ほうれん草 |
| ビタミンC | 柑橘類、キウイ、いちご |
| ビタミンE | ナッツ類、アボカド、オリーブオイル |
| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、玄米 |
| 鉄分 | レバー、赤身の肉、ほうれん草 |
栄養バランスを崩すNG習慣
ジャンクフードの多用や偏食、過剰な糖分摂取などは血糖値の乱高下を招き、ホルモンバランスを崩すきっかけになります。
極端なダイエットによる栄養不足も毛髪の成長を阻害し、抜け毛を増やす原因になります。
糖質や脂質を全く摂らない食事は体に負担をかけ、疲れやストレスを増加させる可能性も高まります。
水分補給と頭皮の関連性
髪や頭皮の乾燥を防ぐためには、外側からの保湿だけでなく内側からの水分補給も重要になります。水分が不足すると頭皮の血行が悪くなり、髪に栄養が行き渡りにくくなります。
適度な水分摂取は老廃物の排出を助けるため、健康的な髪を育てやすくなる要素の1つです。
栄養面からの抜け毛対策
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| タンパク質の摂取 | 肉・魚・大豆製品などをバランスよく |
| 抗酸化ビタミン | ビタミンA・C・Eを含む食品を積極的に摂る |
| ミネラル補給 | 亜鉛や鉄分で毛髪の生成をサポート |
| 適度な水分補給 | 血行促進と老廃物の排出を助け、頭皮を健やかに保つ |
体の内側から健やかな髪を育てる意識を持つことが抜け毛対策に結びつきます。
女性の薄毛治療の選択肢
日常的なヘアケアや生活習慣の改善だけでは抜け毛や薄毛が改善しない場合、専門的な治療を検討することも選択肢の1つです。
特に5月や6月、9月・10月・11月など季節の変化による抜け毛が続く場合は、早めに専門家の意見を求めると原因を特定しやすくなります。
医療機関で行う薄毛治療
女性の薄毛治療専門クリニックでは、問診や血液検査、頭皮の状態チェックなどを通じて原因を突き止め、適切な治療法を提案します。
治療法としては外用薬や内服薬、育毛メソセラピーや発毛促進を目的とした注入治療などが挙げられます。
個人の症状や体質に合わせて治療方針を決めるため、効果を感じやすい場合があります。
ホルモン治療との連携
ホルモンバランスの乱れによる抜け毛であれば、婦人科や内科でのホルモン治療の併用も検討されます。
月経不順や更年期など、女性ホルモンの減少やアンバランスが抜け毛の原因と考えられる場合は、専門の医療機関で総合的に取り組むことが大切です。
治療法と特徴
| 治療法 | 特徴 |
|---|---|
| 外用薬(育毛剤) | 頭皮に直接塗布して毛根を刺激 |
| 内服薬 | 抜け毛に関わるホルモンや血行改善をサポート |
| 育毛メソセラピー | 栄養成分を頭皮に注入し、毛母細胞を活性化 |
| ホルモン療法 | 更年期やホルモンの乱れが原因の抜け毛に対処 |
自己判断で民間療法だけを続けるよりも、医師の指導を受けたうえで治療計画を立てるほうが抜け毛の原因を明確化しやすいです。
自宅でのセルフケアと専門治療の併用
専門クリニックでの治療と、日常生活でのセルフケアを併用すると、相乗効果が期待できます。
シャンプーの仕方や食事指導など、クリニックでアドバイスされるセルフケアを実践すると治療効果をより実感しやすくなります。
早期受診のメリット
抜け毛や薄毛が気になり始めた段階で医療機関を受診すると、原因を特定しやすく、悪化を防ぎやすいです。
長期間放置してしまうと髪の密度が大きく低下し、治療に時間がかかる場合があります。
早めの対策と適切な治療を組み合わせると、季節ごとに増減する抜け毛の悩みを軽減させやすくなります。
専門治療を受けるタイミング
| タイミング | 理由 |
|---|---|
| 抜け毛が増え始めた初期 | 早期発見・早期治療で進行を抑えやすい |
| 日常ケアの効果を実感できない場合 | 医療機関での検査で原因を明確にできる |
| 生理不順や更年期の症状が強い場合 | ホルモンバランスの乱れによる抜け毛を見極めやすい |
| 生活習慣の改善に限界を感じた場合 | プロのアドバイスや治療で効率的に改善が期待できる |
自分の抜け毛の原因を特定して対策を講じると、薄毛の進行抑制を狙えます。
よくある質問
抜け毛や薄毛に関する疑問は人それぞれです。季節による抜け毛の変化について、よくある質問をまとめます。
- Q季節によって抜け毛が増えるのはなぜですか?
- A
気温や湿度、紫外線などの環境要因が変化すると、頭皮の皮脂分泌や血行状態に影響が出るため、抜け毛が増えやすいと考えられます。
5月の抜け毛や6月の抜け毛は紫外線や湿度の上昇、9月・10月・11月の抜け毛は夏のダメージや乾燥などが影響しているケースが多いです。
- Q抜け毛が増えるときのストレスケアはどのようにすればいいですか?
- A
ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、抜け毛を増やす要因になります。適度な運動や趣味を楽しむ時間を確保したり、疲れを感じたら早めに休息をとると良いでしょう。
呼吸法や軽いストレッチなどのリラックス方法も役立ちます。また、十分な睡眠とバランスの良い食事を組み合わせると、ストレス緩和の効果が高まりやすいです。
- Q抜け毛と髪質の変化を感じた場合、まず何をすればいいですか?
- A
髪質の変化は頭皮環境の乱れのサインである可能性があります。まずはシャンプーやドライヤーなどの日常ケアを見直し、頭皮に負担をかけない工夫を始めてみてください。
5月や6月、9月〜11月など抜け毛が増えやすい時期を意識して対策を強化することも大切です。
改善が見られない場合は、女性の薄毛治療専門クリニックなどで相談すると早期対処がしやすくなります。
- Qクリニックでの治療と自宅ケアはどのように両立すればいいでしょうか?
- A
医師の指導に沿って治療を進めると同時に、正しいシャンプー方法やヘアケア製品の活用を徹底すると相乗効果を得やすくなります。
栄養バランスを考慮した食事や頭皮マッサージなど、自宅で取り入れられるケアも継続すると、治療効果を感じやすくなるケースが多いです。
参考文献
KUNZ, Michael; SEIFERT, Burkhardt; TRÜEB, Ralph M. Seasonality of hair shedding in healthy women complaining of hair loss. Dermatology, 2009, 219.2: 105-110.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
RANDALL, VALERIE A.; EBLING, F. J. G. Seasonal changes in human hair growth. British Journal of Dermatology, 1991, 124.2: 146-151.
BUONTEMPO, Michael G., et al. Seasonal trends in hair loss: A big data analysis of Google search patterns and their association with seasonal factors. Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, 2023, 37.12.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
COURTOIS, M., et al. Periodicity in the growth and shedding of hair. British Journal of Dermatology, 1996, 134.1: 47-54.
TRÜEB, Ralph M. Systematic approach to hair loss in women. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2010, 8.4: 284-297.