女性の髪は年齢や体調、ライフイベントによって変化しやすく、20代から50代にかけて薄毛や抜け毛の悩みを抱える方も少なくありません。

薄毛にはさまざまなタイプがあり、それぞれ原因や症状が異なります。本記事では、
- びまん性脱毛症
- 女性型脱毛症(FAGA)
- 牽引性脱毛症
- 円形脱毛症
- 産後の抜け毛(休止期脱毛症)
- 栄養不足による脱毛
- 甲状腺疾患による脱毛
- 更年期による脱毛
について、それぞれ医学的根拠に基づいた対策と治療法を解説します。自分の薄毛タイプを正しく知り、適切なアプローチを理解することで、健やかな髪を取り戻す一歩を踏み出しましょう。
びまん性脱毛症の対策と治療法
原因と特徴
びまん性脱毛症とは、頭髪全体のボリュームが徐々に減っていく脱毛症です。男性型脱毛症のように部分的に禿げ上がるのではなく、「髪全体が一様に薄くなる」のが特徴です。

そのため気づきにくく、症状がかなり進行してからようやく発見されるケースもあります。
原因は一つに限定できず、加齢によるホルモンバランスの変化、ストレス、自律神経の乱れ、血行不良、栄養不足、睡眠不足、誤ったヘアケア習慣など複数の要因が絡み合って起こります。
特に女性ホルモン(エストロゲン)の減少は髪の成長サイクルを乱し、びまん性脱毛症に大きく関与します 。20代から発症することもあり誰にでも起こり得ますが、更年期以降に増える傾向があります。
症状としては、髪が全体的に細く弱くなり、抜け毛が増えて地肌が透けて見えるようになります。初期には短い毛(成長しきる前に抜けた毛)が増えるのも特徴です 。
- 主な原因要因
- 加齢に伴うホルモン低下(エストロゲン減少)
- 慢性的なストレス・生活リズムの乱れ
- 栄養不足(タンパク質・鉄分など欠乏)
- 血行不良(運動不足や喫煙など)
- 不適切なヘアケア(過度なカラーやパーマ、ブラッシング)
対策(生活習慣の改善)
原因が多岐にわたるびまん性脱毛症では、生活習慣の見直しが重要です。髪の成長には栄養と血流が不可欠です。まずはバランスの良い食事を心がけ、タンパク質・鉄分・亜鉛・ビタミン類を十分に摂取しましょう。
過度なダイエットは髪にも悪影響を及ぼすため避けます。また、質の良い睡眠と適度な運動で血行を促進し、頭皮への血流を改善します 。
ヘアケアでは、強い刺激を与えないように注意します。例えばシャンプーは指の腹で優しく洗い、熱すぎるお湯は避けます。ドライヤーの高温を長時間当てることも控え、頭皮に負担をかけないようにしましょう 。
整髪料やカラーリングも頻度を見直し、必要以上に髪を傷めないことが大切です。
- 髪と頭皮に良い生活習慣のポイント
- 栄養バランスの良い食事(特に良質なたんぱく質や鉄分を摂る)
- 十分な睡眠(成長ホルモン分泌を促し髪の回復を助ける)
- 適度な運動(血行促進で毛根への栄養供給アップ)
- 禁煙・節酒(血流障害やホルモン代謝への悪影響を減らす)
- ストレスケア(リラックス法や趣味で自律神経の安定を図る)

頭皮マッサージも有効です。シャンプー時や就寝前に指で頭皮を揉みほぐすと血行が改善し、毛根への栄養供給がスムーズになります。

また抜け毛が気になるときほど過度にブラッシングしたり何度もシャンプーしたりしがちですが、洗いすぎ・触りすぎは逆効果です。
頭皮の皮脂バランスが乱れるとさらに抜け毛を招く可能性があるため、適度なヘアケアに留めましょう。
治療法(医療的アプローチ)
生活改善だけでは改善が難しい場合、医療的な治療法も検討します。びまん性脱毛症の治療として一般的なのは外用薬のミノキシジルです。
ミノキシジルは血行を促進し毛包を刺激する発毛剤で、女性のびまん性脱毛にも有効性が認められています。日本皮膚科学会のガイドラインでも女性の慢性的な薄毛に対しミノキシジル外用が推奨されています。
市販の女性用育毛剤(ミノキシジル1~5%配合液など)を用いるか、症状に応じて皮膚科で処方を受けます。内服薬では「パントガール」というビタミン・アミノ酸含有のサプリメントが知られています。
パントガールはドイツで開発された女性向けの治療薬で、世界で初めて女性の薄毛に対する有効性が認められた経口薬です。
特にびまん性脱毛症に対する効果が報告されており、3か月の服用で約70%の患者に抜け毛の減少が見られたとのデータもあります。副作用リスクも低いとされ、栄養補給により毛髪の成長を内側からサポートします。
ただし栄養不足が原因でない場合、サプリメントだけでは大きな改善が期待できない点に留意が必要です。
さらに、メソセラピー(育毛メソセラピー)と呼ばれる治療も選択肢です。これは頭皮に直接発毛を促す成分を注入する方法で、ビタミンや成長因子などを含むカクテルを細い注射針で頭皮に届けます。
外用薬と併用することで相乗効果が期待できるとされます。また、症状が進行している場合には自毛植毛(自分の後頭部の毛を薄い部分に移植する手術)も検討されます。
しかしびまん性脱毛症では頭髪が一様に薄くなるため、AGAのように局所的に無毛になるケースは稀であり、植毛をするよりもまずは外用薬やメソセラピーによる全体的な発毛促進が一般的です。
治療はいずれも継続が重要で、効果が出るまで数か月単位の時間がかかります。一度改善しても治療をやめればまた元の状態に戻り得るため、医師と相談しながら根気強く治療を続けることが大切です。
| 治療法 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| ミノキシジル外用 | 発毛剤を頭皮に塗布(1日2回など) | 毛包を刺激し発毛・育毛を促す ([Hair Loss: Common Causes and Treatment |
| パントガール内服 | ビタミンB群・シスチンなど含有サプリ | 栄養補給で毛髪の成長を助ける ([パントガールの効果は?成分・副作用・飲み方などと合わせて解説 |
| 育毛メソセラピー | 成長因子やビタミンを頭皮に注射 | 毛母細胞にダイレクトに栄養を供給し発毛を促進 ([〖医師監修〗びまん性脱毛症の治療方法は? |
| 自毛植毛 | 自身の毛を外科手術で移植 | 薄毛部分に毛量を補填(重度の場合検討) |
備考: びまん性脱毛症は原因が多面的なだけに、単一の治療で劇的に治るものではありません。生活習慣の改善と治療を組み合わせ、総合的にアプローチすることが重要です。
また精神的な不安や焦りもストレスとなり脱毛を悪化させる可能性があるため、適度にリラックスしながら長い目で対処していきましょう。

女性型脱毛症(FAGA)の対策と治療法
原因と特徴
女性型脱毛症(FAGA: Female Androgenetic Alopecia)は、いわゆる女性のAGA(androgenetic alopecia)です。
男性のAGAが額の生え際や頭頂部から後退・薄毛化していくのに対し、女性の場合は頭頂部の地肌が透けるように薄くなるのが典型です。
前髪の生え際は保たれ、男性のようにM字型に後退したり完全に禿げ上がったりすることは稀ですが、分け目を中心に全体が薄毛になっていきます。

FAGAの根本原因には遺伝的要素が強く関与し、男性ホルモン(アンドロゲン)の作用も一因と考えられます 。男性ホルモン(テストステロン)が毛包内の酵素でジヒドロテストステロン(DHT)に変換されると、毛の成長期を短縮させてしまいます。
女性でも卵巣や副腎から少量の男性ホルモンが分泌されており、特に閉経後は女性ホルモンが減少する分相対的に男性ホルモンの影響が強まり薄毛が進行しやすくなります。実際、女性の薄毛は加齢とともに増加し、閉経前後に症状が顕著になる傾向があります。
FAGAは20〜30代で発症するケースもありますが、多くは40代以降に徐々に進行します。症状の進み方は個人差が大きく、ゆっくりと進行する人もいれば、急激に薄毛が目立つようになる人もいます。
なお、FAGAの進行度は「ルートヴィヒ分類」という基準で3段階に分けられます。I型は分け目の軽度な薄毛で髪型で隠せる程度、II型は頭頂部のボリューム低下と分け目の拡大が見られ、III型になると頭頂部全体が透けるようになり深刻な薄毛状態です。
| ルートヴィヒ分類 | 薄毛の程度 | 特徴 |
|---|---|---|
| I型(軽度) | 分け目がやや薄く感じる | 髪型の工夫でカバー可能なレベル 。薄毛範囲は狭い |
| II型(中等度) | 分け目が拡がりボリューム低下が明らか | 頭頂部の地肌が見え始める 。カバーが難しくなる |
| III型(高度) | 頭頂部が広範囲に薄毛 | 地肌が透けて見える。女性では稀だが重度の場合 |
対策(セルフケアと工夫)
女性型脱毛症は進行性ではあるものの、髪型の工夫やセルフケアで目立ちにくくすることが可能です。
ボリュームが減ってきた場合、分け目を時々変えることで特定の部分への負担を減らし、地肌の日焼けも防ぎます。
またトップにボリュームが出るような髪型(レイヤーを入れる、パーマでふんわりさせる等)にすると薄毛がカバーしやすくなります。ウィッグやヘアピースの利用も選択肢の一つです。
部分ウィッグなら薄くなった箇所だけを自然に補え、心理的負担の軽減に役立ちます。

セルフケアとしては、びまん性脱毛症の場合と同様に生活習慣の改善が基本です。特に女性ホルモンの減少を緩やかにするため、更年期世代では規則正しい生活を送り体調管理に努めます。
喫煙はDHTを増やす可能性が指摘されているため避けましょう。また頭皮環境を整える市販の育毛トニックやシャンプーも補助的に使えます。
カフェインやアミノ酸、植物エキスなどが配合された女性用育毛シャンプーは、直接発毛効果はなくとも頭皮の皮脂汚れを適切に落とし健やかに保つのに役立ちます。
頭皮マッサージも引き続き有効で、血行を促すことでミノキシジルなどの外用薬の効果も高めやすくなります。
精神面のケアも重要です。髪の悩みは女性にとって大きなストレスとなり得ます。必要に応じて家族や友人に相談したり、同じ悩みを持つ人のコミュニティで情報交換したりするのもよいでしょう。
ストレスはホルモンバランスを乱し脱毛を悪化させる可能性があるため、ポジティブな気持ちを保つことも対策の一つです。
治療法(薬物療法・医療技術)
女性型脱毛症の治療では、発毛効果が科学的に認められた薬剤を用いることが基本となります。
第一選択はミノキシジル外用です。前述のびまん性脱毛症の場合と同様に、ミノキシジルを定期的に頭皮に塗布することで毛母細胞を活性化し発毛を促します。
日本では女性用リアップ(1%ミノキシジル液)が市販されていますが、症状に応じては5%濃度のものを医師の指導の下で使用するケースもあります。
ミノキシジルは即効薬ではないため、効果判定には通常3~6か月ほどかかります。使い始めてすぐ抜け毛が減らなくても焦らず継続することが重要です。

一方、刺激の強い成分でもあるため、人によっては頭皮のかぶれ(接触皮膚炎)が起こることがあります。その場合は使用頻度を減らすか、フォームタイプ(泡状)など低刺激の製剤に変更すると症状が改善することがあります 。
ホルモン療法としては、男性ホルモンの作用を抑える内服薬が検討されることもあります。
日本では女性への使用が正式には認められていませんが、海外ではスピロノラクトン(利尿薬で抗アンドロゲン作用あり)を低用量で用いることがあります。
特に多毛症やニキビを伴う多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性では有効との報告があります。ただし内服薬は副作用もあり妊娠中は禁忌など制約が多いため、必ず専門医の指導の下で検討されます。
またフィナステリド(5α還元酵素阻害薬)は男性AGA治療薬として有名ですが、女性(特に妊娠可能年齢)には安全性の問題から基本的に使用されません。
ただ閉経後の女性には医師判断で処方される場合もあります。しかし現時点でフィナステリドの女性への発毛効果は明確に証明されておらず、メインの治療法ではありません。
その他の医療技術として、低出力レーザー治療(LLLT)やPRP療法(自己多血小板血漿注入)も試みられています。低出力レーザーは頭皮にレーザー光を当て細胞を活性化させる方法で、自宅で使えるレーザー帽子・ヘアバンド型の機器も市販されています。
一部の研究では毛髪の密度が増す効果が示されていますが、単独で十分な発毛を得られるケースは多くなく、他の治療との併用が一般的です。
一方、PRP療法は自分の血液を採取・濃縮して血小板を取り出し頭皮に注射する治療で、成長因子により毛包を刺激する狙いがあります。
これもまだ保険適用外の先進治療であり、効果には個人差がありますが、他の治療で改善しない場合に検討されます 。
最終手段として、自毛植毛手術も選択肢となります。特にIII型に至る重度の女性型脱毛症では、残っている後頭部の毛髪を移植して薄毛部分をカバーすることが可能です。

植毛術は近年技術が進歩し、毛髪を株単位で移植することで自然な仕上がりになります。ただし女性は男性と違い後頭部もある程度薄毛が進行していることが多く、移植できるドナー毛の量に限りがあります 。
また費用も高額で1回で終わりではなく複数回の施術が必要なケースもあります。植毛は誰にでも適応できるわけではないため、専門医と十分相談し、他の治療と比較してメリット・デメリットを検討する必要があります。
いずれの治療においても、治療を中断すれば再び脱毛が進行する点に注意が必要です。
女性型脱毛症は慢性の症状であるため、例えばミノキシジル外用などは発毛効果があってもやめてしまえば数か月で元の状態に戻ってしまいます。
そのため、「維持療法」として治療を続けることが求められます。根気強く取り組みつつ、定期的に経過を確認して治療内容を調整していくのが良いでしょう。
牽引性脱毛症の対策と治療法
原因と症状の特徴
牽引性脱毛症は、長期間にわたり髪の毛が強く引っ張られ続けることで生じる脱毛症です。
ポニーテールやお団子ヘア、三つ編み、編み込み(コーンロウ)、エクステンションの装着、タイトなヘアバンドやカチューシャの常用など、髪に過度なテンション(牽引)がかかるヘアスタイルが原因となります。
主に前頭部の生え際やこめかみ、分け目の周辺など、引っ張りの力が集中する部分の毛が薄くなります。初期には抜け毛とともに頭皮の赤みやヒリヒリ感、フケ・炎症などが起こることもあります。
毛が途中で切れて短い毛が目立つことも特徴です 。この段階では毛包(毛根)は破壊されておらず、原因を取り除けば自然に回復する可能性があります。
しかし引っ張りが長年続くと、毛包が弱ってミニチュア化(産毛のような細い毛しか生えなくなる)し、やがて毛穴が閉じてしまいます。
この末期には毛根が瘢痕化(かんか化)してしまい、永久的な脱毛となります。
具体的には、生え際に沿って細い産毛だけが残り、奥の方はつるっと地肌が露出する「フリンジサイン」と呼ばれる所見が見られることがあります 。

対策(ヘアスタイルの見直し)
牽引性脱毛症は原因を取り除くことが最良の対策です。早期であれば、髪型を変えて頭皮への負担をなくすだけで自然に治癒するケースも多いとされています。
具体的な対策として、以下のような点に注意します。
- 髪を締め付けない: 毎日同じ場所でポニーテールを作ったり、きつく三つ編みにしたりすることをやめましょう。どうしても束ねる必要がある場合は位置を変えたり、ゆるめに結んだりして負荷を分散させます。
- ローテーション: ヘアスタイルを固定せず、ダウンスタイル、アップスタイル、三つ編みなど複数の髪型をローテーションします。同じ毛根に毎日負担をかけないようにします。
- 長い髪はカットも検討: 髪が長く重いとそれ自体が引っ張りの力になります。思い切って少しカットし、髪の重量を減らすのも有効です。

- 装飾品の使用を控える: ヘアピンやバレッタ、エクステ、編み込みなどは時々休みましょう。エクステは自毛に負荷をかけやすいので、牽引性脱毛症の間は外しておくのが無難です。
- 頭皮を労わる: 髪を洗う際やブラッシングの際も、優しく扱います。なるべく自然乾燥に近い形で乾かし、アイロンやコテなど高温の器具は避けます 。整髪料も炎症を起こしている時は刺激になるので控えます。
以上のように「髪を引っぱらないこと」が第一です。

特に初期症状(抜け毛の増加や生え際の赤み)に気付いた段階でヘアスタイルを見直せば、毛包がダメージを受けず休んでいるだけの場合が多く、数か月~1年程度で元の毛量に戻ることも期待できます。
反対に、症状が進んでいるのに引き続き牽引を加えていると、取り返しがつかなくなる恐れがあるため注意が必要です。
治療法(医療的措置)
牽引性脱毛症ですでに毛根が弱っていたり炎症が起きている場合は、皮膚科での治療を検討します。基本は保存的治療(非外科的治療)となり、以下のようなアプローチがあります。
- 抗炎症療法: 頭皮に炎症やかゆみ、赤みがある場合は、ステロイドの外用薬(ローションやクリーム)を塗布して炎症を抑えます。また必要に応じてステロイドの局所注射(患部へのトリアムシノロン注射)を行うこともあります 。炎症が収まれば毛包の回復を助けられます。
- 感染予防: 引っ張りによる傷みから毛穴に細菌が感染し毛囊炎(ニキビのようなブツブツ)ができている場合は、抗生剤の内服や抗菌シャンプーを使って治療します 。
- 発毛促進: 毛根が生きている場合、ミノキシジル外用を併用することで発毛を促します。牽引性脱毛症そのものに特効薬はありませんが、ミノキシジルによって休止期に入ってしまった毛を成長期に戻す手助けをします。
- 栄養補給: ビオチン(ビタミンH)などを含むサプリメントが処方されることもあります。毛髪や爪の健康維持に必要な栄養素で、不足を補うことで毛の成長をサポートします。
- その他: 状況に応じて、血行を改善するための成分が含まれた外用剤や、低出力レーザー照射による育毛効果を狙った治療が行われることもあります。
これらの治療によって毛根が回復し毛髪が生えてくるまでには、数か月~一年程度のスパンで経過を見ます。
改善がみられればそのまま経過観察し、改善が不十分な場合や毛根が消失している場合には外科的対応を検討します。具体的には自毛植毛が挙げられます。
牽引で失った生え際部分に対し、後頭部などから毛を採取して植え込む方法です。これによって見た目を回復させることは可能ですが、原因がスタイルにある以上、植毛後も同じヘアスタイルを続ければまた脱毛が進行してしまいます。
従って植毛は牽引の習慣を完全にやめた上で、最終的な手段として行われます。
まとめ: 牽引性脱毛症は他の脱毛症と異なり、自分の習慣次第で予防・改善が可能なタイプの脱毛です。「引っ張る髪型はできるだけしない」というシンプルな対策が何より重要であり、これに尽きます。
そしてもし抜け毛に気付いたら早めに対処し、毛根にダメージが残らないうちにケアを始めましょう。
一度損傷した毛根は完全には元に戻らないこともありますので、日頃から髪と頭皮をいたわることが何よりの予防策となります。
円形脱毛症の対策と治療法
原因と症状
円形脱毛症は、自己免疫反応によって生じると考えられる脱毛症です。免疫系が誤って毛根を攻撃してしまい、結果としてその部分の髪が抜け落ちます。
はっきりとした原因は未解明ですが、遺伝的素因に加え、ストレスやアトピー素因などが誘因として指摘されています。
特徴的な症状は円形または楕円形のはげた斑(脱毛斑)が突然現れることです。大きさはコイン大から数センチまで様々で、1箇所だけの場合もあれば複数箇所に生じる場合もあります。

患部の皮膚は滑らかで炎症やかゆみは通常なく、抜ける時も痛みはありません。ただし発症前に局所的なチクチク感や違和感を覚える人もいます。
髪が抜け落ちる際、根元近くが細くなった「感嘆符毛」と呼ばれる特徴的な折れ毛が見られることがあります。また、重症例では爪に点状のくぼみ(凹点状爪)や筋状の凹凸が現れることもあり、患者の10~40%に爪の変化が伴うとされています。
円形脱毛症はいくつかの型に分類されます。1~2箇所程度の脱毛斑に留まるものを単発型、複数箇所に発生するものを多発型と呼びます。
症状が進行すると脱毛斑同士が融合して広範囲になり、最終的に頭部の髪が全て失われる場合(汎発型ないし全頭型)もあります。
また、頭だけでなく眉毛やまつ毛、体毛を含め全身の毛が抜けてしまう汎発性脱毛症(全身型)に及ぶケースもあります。
一方、頭の後ろから側面に帯状に脱毛が起こる蛇行型(オフィアシス型)という特殊なパターンもあります。症状の程度や範囲は人により大きく異なりますが、患者の約半数は初発から1年以内に自然回復するとも言われています。
ただし再発率も高く、特に若年発症や多発型の人ほど再発しやすい傾向があります。
| 円形脱毛症の型 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 単発型 | 脱毛斑が1箇所のみ | 最も一般的。比較的軽症 |
| 多発型 | 脱毛斑が2箇所以上生じる | 脱毛斑が増減を繰り返すことも |
| 全頭型(汎発型) | 頭髪が全て抜け落ちる | 重症。自然回復は稀 |
| 汎発性(全身型) | 眉毛・体毛など全身の毛が抜ける | 最も重篤なタイプ |
| 蛇行型(オフィアシス型) | 後頭部から側頭部にかけ帯状に脱毛が進行する | 治りにくく慢性化しやすい |
精神的影響も大きく、髪の喪失によるショックや社会生活でのストレスがさらに症状に影響する悪循環も懸念されます。
円形脱毛症それ自体は体に害のある病気ではありませんが、患者のQOL(生活の質)を大きく低下させることが知られています。
対策(セルフケアとメンタル面)
円形脱毛症は原因が自分では制御できない免疫反応であるため、発症そのものを予防する明確な方法はありません。しかし、悪化因子を取り除き再発を防ぐ観点での対策が考えられます。
まず、ストレス管理は重要です。ストレスそのものが発症原因かどうかは明確ではありませんが、多くの患者さんが発症前に強い精神的緊張や環境の変化を経験しているという報告もあります。
趣味やリラクゼーション法(深呼吸、ヨガ、入浴など)で適度にリフレッシュし、心身のバランスを保ちましょう。
また、自己免疫疾患の側面から規則正しい生活と栄養バランスも大切です。睡眠不足や過労が続くと免疫機能が乱れる可能性があるため、十分な睡眠時間を確保します。
食事ではビタミンやミネラルをしっかり摂り、体調を整えます。特に亜鉛やビタミンDは免疫調節に関与し、毛髪の生成にも関わるため不足しないように意識しましょう。
脱毛斑ができてしまった後のセルフケアとしては、その部分を上手にカバーする工夫があります。例えば、小さな脱毛斑であれば周囲の髪をアレンジして隠したり、スプレー式の毛髪パウダーで地肌を目立たなくすることができます。
ウィッグや帽子の活用も心理的負担を軽減する助けになります。医療用ウィッグは通気性もよく自然なので、人目を気にせず外出できるでしょう。
周囲の理解を得ることも重要です。職場や学校で信頼できる人に相談し、状況を知ってもらうだけでも気持ちが楽になります。円形脱毛症は誰にでも起こり得る自己免疫疾患であり恥ずかしいことではありません。

隠すばかりでなく、ときにはオープンにすることでストレスが軽減し、それが治療にも良い影響を与えるかもしれません。
治療法(症状の程度に応じた医療)
円形脱毛症の治療は、症状の範囲(重症度)によって異なる方法がとられます。残念ながら今のところ完璧に治す「特効薬」はなく、様々な治療法を組み合わせて発毛を促す形になります。
以下に主な治療法を症状別にまとめます。
軽症(脱毛箇所が頭部の50%未満)
比較的軽いケースでは、まず局所治療が行われます。代表的なのはステロイド局所注射(ケナコルトなどを脱毛部分に複数箇所注射)です。
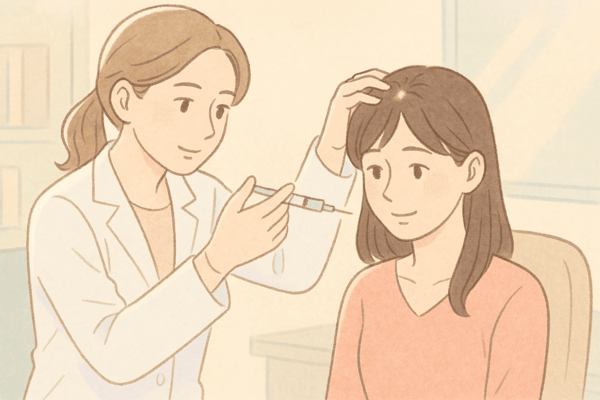
これは免疫の攻撃を抑え、毛髪の再生を早める効果があります。4~6週間ごとに繰り返し、発毛したら中止します。
併用療法として、外用薬も使われます。strongクラスのステロイド外用剤(液体やクリーム)を脱毛斑に塗布したり、ミノキシジル外用を併用することもあります。
ミノキシジル自体は円形脱毛症の根本治療ではありませんが、他の治療と組み合わせることで毛が生えるスピードを上げる効果が期待されます。
また、アンチラリン(ディフェリン軟膏)という刺激を与える薬を塗り、意図的にかぶれさせて免疫の攻撃対象をそらす治療もあります。これは髪が明るい色の人には色素沈着するリスクがあるため、注意しながら行われます。
中等症~重症(脱毛箇所が50%以上、または全頭型・汎発型)
: 脱毛範囲が広い場合や長期にわたり再生しない場合、全身的な治療に移行します。一つは局所免疫療法(接触免疫療法)です。
代表的な薬剤はDPCP(ジフェニルシクロプロペノン)で、脱毛部に塗布してわざと軽い皮膚炎(かぶれ)を起こします。こうすると免疫細胞がそちらに気を取られ、本来攻撃していた毛根への攻撃が減ると考えられています 。
週1回の頻度で徐々に濃度を上げながら塗布し、毛が生えてくれば中止します。ただし強いかぶれや蕁麻疹、リンパ節の腫れなど副作用もあり得るため、慎重に行う必要があります。
もう一つは全身投与の薬物療法です。広範囲の場合、経口ステロイド(飲み薬)を短期集中的に投与するステロイドパルス療法が行われることがあります。
これは副腎皮質ホルモン(ステロイド)の大量投与で強力に免疫抑制し、一時的に脱毛の進行を止めるものです。ただし長期使用はできず、副作用管理のため入院が必要な場合もあります。
その他、古くからある方法では光線療法(PUVA療法)といって紫外線と感作剤を用いた治療もありますが、効果はまちまちです。
最新の治療
近年注目されているのがJAK阻害薬(ジャック阻害薬)という新しい種類の内服薬です。これは免疫のシグナル伝達に関わるJAK酵素をブロックし、毛根への自己免疫攻撃を抑える仕組みです。
米国では2022年にバリシチニブ(商品名オルミエント)が重度の円形脱毛症に対してFDA承認されました 。日本でも同様に承認され、重症の円形脱毛症に対する初の内服治療薬として使用可能になっています(保険適用は条件あり)。
臨床試験では36週間(約9か月)の服用で、4割近くの患者が頭髪の80%以上が再生したという結果が報告されています。

他にもリトレシチニブ、デュルクセチニブといったJAK阻害薬が開発・承認されつつあり、今後の治療の主軸になることが期待されています。
ただしJAK阻害薬は副作用として感染症リスクの増加や血栓傾向、肝機能障害などがあり、また投与中止すると再び脱毛することも多いため、現状では重症例に限った選択肢です。
以上のように、円形脱毛症の治療は「髪を生やす」より「自己免疫を抑える」ことに主眼が置かれます。
そのため治療過程では副作用との兼ね合いや効果判定に時間がかかることもあり、患者さんの忍耐が必要です。治療を始めたら短期間で結果を求めず、医師と二人三脚で経過を見守ることが大切です。
また、必要に応じてウィッグの活用やカウンセリングなど心理社会的サポートも並行して受け、総合的にQOLを維持しながら回復を目指すことが望ましいでしょう。
休止期脱毛症・産後の抜け毛の対策と治療法
原因とメカニズム
「休止期脱毛症(Telogen Effluvium、TE)」とは、何らかのきっかけで大量の毛髪が一斉に休止期に移行し抜け毛が増える現象を指します。
健康な髪は普段、約85~90%が成長期(伸びている状態)にあり、残りが休止期(抜けるのを待つ状態)にあります。しかし強いストレスや体調不良などの事件」が体に起こると、本来成長期にいるはずの髪が早めに休止期へと移行してしまいます 。
その後1~3か月の潜伏期間を経て、休止期に入った毛が一気に抜け出すため、突然大量の抜け毛が起こります。これが休止期脱毛症です。
典型的な原因としては、高熱を伴う病気、大手術や外傷、大きな精神的ストレス、急激なダイエット、栄養失調、出産などが挙げられます。
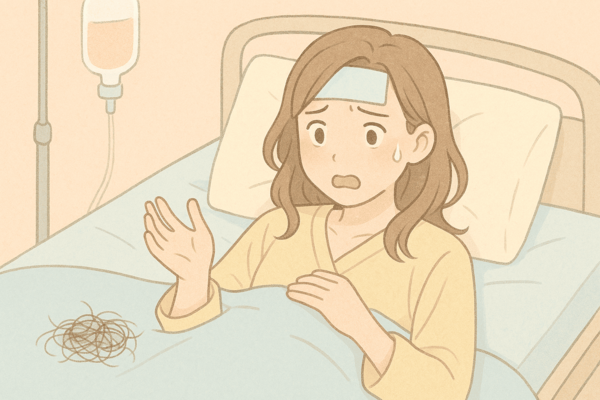
薬剤の副作用(抗がん剤以外でも一部の薬で起こることがあります)や、甲状腺機能異常などの内分泌疾患も誘因となり得ます。
特に女性に多い休止期脱毛症として有名なのが「産後の抜け毛(産後脱毛症)」です。妊娠中はエストロゲンが高く維持されることで髪の成長期が延長し、通常なら抜けるはずの髪がとどまる傾向があります。
しかし出産を終えるとホルモンバランスが急激に変化し、多くの毛髪が休止期に入り替わりに抜け始めます 。早い人では出産1か月後から抜け毛が増え、産後3~6か月頃にピークを迎えます 。
ブラシに束になって髪が抜けたり、シャンプー後の排水溝が髪でいっぱいになったり、朝起きると枕に大量の抜け毛が付着していたりと、その抜け毛の多さに驚く方も少なくありません。
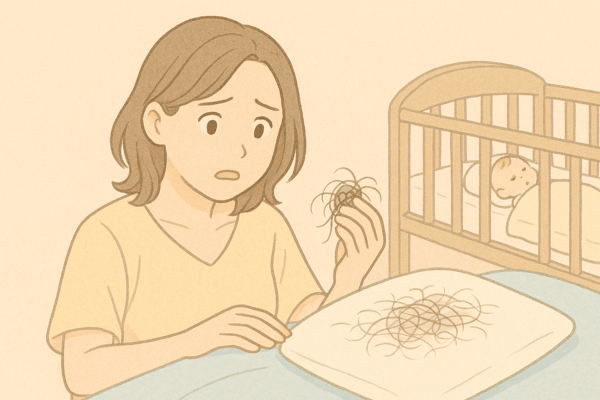
しかし産後脱毛症は一時的な現象であり、多くの場合産後1年ほどで妊娠前の毛量に戻るとされています。事実、産後脱毛症は産後女性の半数以上が経験するといわれますが、ほとんどは時間とともに自然回復していく良性のものです。
一方、一般的な休止期脱毛症も、原因となったイベントが解決すれば徐々に落ち着きます。たとえば高熱の病気にかかった場合は回復後数か月で抜け毛が収まり、また髪は再び生えてきます。
通常、休止期脱毛症では頭髪全体が均一に薄くなるので、円形脱毛症のようなはげた斑にはなりません。髪全体のボリュームダウンとして感じられる程度ですが、短期間に大量に抜けるため不安になるでしょう。
しかし、毛根自体は破壊されていないので将来的に再生可能です。
| 休止期脱毛症の主な原因 | 抜け毛が増える時期 | 説明 |
|---|---|---|
| 出産(産後脱毛) | 産後1~3か月後に開始、6か月頃ピーク | 出産による急激なホルモン変化が原因。1年程で自然回復 |
| 高熱の伴う重い病気 | 発熱後2~3か月後から | インフルエンザなど。成長期→休止期への移行増加で一時的脱毛 |
| 手術・大怪我 | 術後・外傷後約2~3か月後 | 身体への大きな侵襲がストレスとなり脱毛 |
| 極度の精神的ストレス | ストレス発生後1~3か月後 | ショックな出来事、過労など心因性要因 |
| 急激なダイエット・栄養失調 | ダイエット開始から数か月後 | 栄養不足が毛の成長を止め大量脱毛 |
| 甲状腺機能低下症・貧血など | 徐々に(気付きにくいことも) | ホルモン不足や鉄欠乏が毛周期乱れを引き起こす |
対策(セルフケアと経過観察)
休止期脱毛症はその名の通り「毛髪が休んでいる状態」であり、基本的には時間経過とともに自然に回復することが期待できます。
従って、過度に恐れる必要はありません。ただし、その間のセルフケアによって髪の戻り方が変わることもあります。最も大切なのは原因に心当たりがあればそれを取り除くことです。
例えば無理なダイエット中であれば中止し、バランスの良い食事に戻します。
ストレスが続いている場合は休養を取るか、環境を改善できるように働きかけます。また服薬中の薬剤が原因と思われるなら、主治医に相談して代替薬へ切り替えられないか検討します。
甲状腺機能低下症や貧血など基礎疾患がある場合はその治療が最優先です。甲状腺ホルモン薬や鉄剤の服用で全身状態が改善すれば、数か月遅れて髪も元の状態に戻っていきます。
産後の抜け毛に対しては特別な治療は通常必要ありませんが、育児で忙しい中でもできる限り自身の体を労わることが大切です。
産後はホルモン変化だけでなく睡眠不足や授乳による栄養消耗など、母体に負担がかかる要因が多々あります。可能な範囲で栄養をしっかり取り(産後は鉄分やタンパク質が不足しがちです)、休める時に休息をとりましょう。
抜け毛が多いと驚きますが、「これは一時的なものだ」と理解し必要以上に心配しないことも大事です。ストレスが増すと母乳の出にも影響しかねず、悪循環になってしまいます。家族の協力も仰ぎながら、自分の体調を整えることに専念してください。

髪の扱い方としては、抜け毛が多い時期は髪に負担をかけないよう心掛けます。ブラッシングやシャンプーは丁寧に優しく行い、刺激の強いヘアケア剤は避けます。洗髪は毎日でなくても構いません(2日に1回などでもOKです)。
シャンプー後の抜け毛を見ると憂鬱になる場合は、洗髪頻度を少し減らしても良いでしょう。その代わり頭皮が不衛生にならない程度に、低刺激シャンプーで洗うようにします。
また髪型も、ポニーテールなどは控えてダウンスタイルにするか、緩くまとめる程度にします。
髪をまとめない方が抜け毛が散らばって気になるという方は、ゆるい三つ編みにするか、シルクのナイトキャップを被って休むのも一法です。
治療法(必要な場合の対応)
一般に休止期脱毛症(産後脱毛症含む)は治療の必要がない場合が多いです。なぜなら、上述したように原因さえ解消されれば半年から1年程度で自然回復するからです。医師も経過観察と生活指導にとどめ、特別な薬は出さないことがほとんどでしょう。
ただし、抜け毛の量があまりに多く日常生活に支障を来すレベルであったり、精神的につらい場合には、対症療法的に治療を行うこともあります。
ひとつはミノキシジル外用療法です。休止期脱毛症自体の原因治療ではありませんが、発毛を促す作用があるため一時的に毛量を増やす助けになります。
産後の女性の場合、授乳中はミノキシジルの使用を控えるのが一般的ですが、離乳後であれば医師と相談の上で開始してもよいでしょう。ただし前述の通り、ミノキシジルで生えた髪も塗布をやめれば再び抜けてしまうため、あくまで一時的な措置と割り切る必要があります。
もう一つは栄養補給です。特に産後やダイエット後では、鉄欠乏性貧血や低タンパク血症になっていることがあります。血液検査でフェリチン(貯蔵鉄)が低値であれば鉄剤を処方し、ヘモグロビン値を改善させます。鉄不足の改善は毛にも良い影響を与えます。
また必要に応じてビタミンDや亜鉛などのサプリメントが出されることもあります。
ただし、血液検査で明らかな欠乏がない栄養素を闇雲に摂っても効果は乏しく、過剰摂取による害もあり得ます。医師の指導の下で、不足を補う目的で利用するに留めましょう。
産後脱毛症に限って言えば、「治療」より「安心すること」が一番の薬かもしれません。
実際、専門家も「産後の抜け毛のほとんどは一時的で心配のないもの。きちんと体をケアすれば順調に元の髪に戻る」と述べています。ですから、あまり悩みすぎず育児に集中する方が結果的に早い回復につながるでしょう。
最後に、休止期脱毛症と思っていたら他の脱毛症だった、というケースもゼロではありません。例えば産後の抜け毛がきっかけでそのまま女性型脱毛症(FAGA)に移行することも稀にあります。
休止期脱毛症のはずが1年以上経っても改善しない場合や、明らかに頭の一部だけが薄くなるなど様子が違う場合は、皮膚科専門医に相談して正確な診断を受けることをお勧めします。
栄養不足による脱毛の対策と治療法
原因と影響
髪の健やかな成長にはさまざまな栄養素が必要です。
特に重要なのはタンパク質(髪の主成分ケラチンの原料)、鉄分(毛母細胞への酸素供給に必要)、亜鉛(細胞分裂とタンパク合成に関与)、ビタミン類(代謝を助ける)などです。
極端な栄養不足に陥ると、身体は生命維持に必要な臓器へ優先的に栄養を送り、髪への供給は後回しになります。その結果、毛は細く弱くなり抜けやすくなります。特に女性に多いのが鉄欠乏による脱毛です。

月経や妊娠・出産で鉄を失いやすい女性では、貧血まではいかなくとも潜在的な鉄不足がしばしば見られます。鉄が不足すると毛根への酸素供給が低下し、休止期脱毛症を引き起こすことがあります。
実際、甲状腺疾患や栄養失調などと並んで鉄欠乏性貧血はびまん性の脱毛の原因としてよく知られています。
また、急激なダイエットも髪にとって大敵です。短期間で体重を減らすようなダイエットでは十分なタンパク質や必須脂肪酸、ミネラルが摂れず、体は飢餓状態と判断して省エネモードになります。
すると毛髪の成長は真っ先に止められ、多くの毛が休止期に入ってしまいます 。実際、無理なダイエットの2~3か月後に大量の抜け毛が起こるのは典型的なパターンです。
その他、偏食(特定のものしか食べない)、過度な菜食主義(プラントベースは健康に良い側面もありますが、不適切なヴィーガン食は鉄やB12不足につながることがあります)、摂食障害(拒食症など)も、栄養不足による脱毛を引き起こします。
栄養不足による脱毛は一般的にびまん性脱毛症(髪全体のボリューム低下)という形で現れます。特に髪だけでなく爪や皮膚の状態も悪化している場合、栄養状態を疑う手がかりとなります(爪が割れやすい、肌がかさつく等)。
また疲れやすい、めまいがするなど全身のサインも伴いやすいです。
対策(食生活の改善)
もっとも基本的かつ重要なのは、栄養バランスの取れた食生活への改善です。
まずタンパク質を意識しましょう。毛髪はケラチンというタンパク質でできているため、毎日の食事で十分な量のタンパク質(肉・魚・卵・大豆製品・乳製品など)を摂ることが土台となります。
次に鉄分です。赤身の肉やレバー、魚介、緑の葉物野菜、豆類など鉄豊富な食品を取り入れます。鉄の吸収を助けるビタミンCも同時に摂ると効果的です。
亜鉛は牡蠣、牛肉、ナッツ類、卵黄などに含まれ、細胞増殖を支えるので不足しないようにします。
ビタミンB群(特にB2・B6・B7<ビオチン>)、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンEなども髪の成長環境に関与しますが、普通の食事をしていれば極端に不足することは少ないです。
いろいろな食品をバランスよく摂ることが結果的に毛髪に必要な栄養を届けることになります。
具体的には、「主食・主菜・副菜」を揃える和食スタイルが理想的です。一汁三菜にこだわらずとも、例えば「ご飯+焼き魚+野菜炒め+味噌汁」といった食事なら、炭水化物・タンパク質・ビタミン・ミネラルがバランス良く取れます。

忙しい場合はコンビニでも、サラダチキンやゆで卵、サラダ、ヨーグルト、ナッツなどを組み合わせれば比較的バランスが取れます。反対にジャンクフードや極端な糖質制限は髪にはマイナスです。
油っこい食品ばかりだとビタミン不足になりがちですし、炭水化物ゼロの食事はエネルギー不足からタンパク質がエネルギーに回され、髪の原料が欠乏します。
どうしても食が細い人や特定の栄養が不足しがちな人は、サプリメントの活用も検討します。ただし闇雲にたくさん摂れば良いわけではありません。
例えば鉄のサプリは、鉄欠乏がない人が摂っても意味がないどころか胃腸障害など副作用が出る可能性があります 。自分の血液検査結果などを確認し、不足が疑われる場合に限って補うようにします。
- 髪に良い栄養素と食材の例
| 栄養素 | 働き | 多く含む食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | ケラチンの材料。毛根の細胞分裂に必須。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 鉄分 | 酸素運搬を担い毛母細胞を活性化。 | 赤身肉、レバー、カツオ、ほうれん草 |
| 亜鉛 | 細胞増殖とタンパク合成を助ける。 | 牡蠣、牛肉、うなぎ、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 代謝促進(B2・B6は皮脂分泌調整、B7はケラチン合成)。 | 豚肉、レバー、卵黄、玄米 |
| ビタミンC | コラーゲン合成と鉄の吸収を助ける。 | 柑橘類、イチゴ、ブロッコリー |
| オメガ3脂肪酸 | 抗炎症作用で頭皮環境を整える。 | 魚油(サバ、サーモン)、亜麻仁油 |
上記のような栄養素を満遍なく摂取することで、毛髪が育つ土壌が整います。急がば回れで、極端な方法よりも日々の食事改善が結局は遠回りのようで確実な近道です。
治療法(不足栄養の補充)
食生活の改善だけでは追いつかないレベルの栄養不足がある場合、医療的な介入が必要になります。
まず考えられるのは鉄剤の投与です。女性の薄毛で血液検査をすると、フェリチン値(貯蔵鉄)が低い人が少なくありません。
フェリチンが低下している=体内の鉄在庫が不足しているサインで、そのような場合に鉄剤(内服または点滴)で鉄を補うと、抜け毛の改善につながることがあります。

鉄剤内服は胃の不快感や便秘を起こすことがありますが、必要に応じてビタミンC併用や製剤の変更などで対処します。
亜鉛不足が疑われる場合は、亜鉛製剤(プロペシア錠に含まれるポラプレジンクなど)を処方することもあります。ただ亜鉛は過剰症も問題になるため、軽々に処方されるものではありません。
ビオチン(ビタミンB7)はサプリメントとして市販されていますが、明確な欠乏症がなければ必須ではありません。
必要な栄養素を補給する治療として、パントガールという内服薬も選択肢になります。前述のとおりパントガールは各種ビタミンやアミノ酸を配合した女性向けの育毛サプリで、びまん性脱毛症や産後脱毛症にも用いられます。
これ自体が特定の栄養欠乏を治すというより、広範囲な栄養サポートによって毛髪の成長環境を整える位置づけです。3か月以上継続して服用することで徐々に抜け毛の減少・コシのある毛の発生などが期待できます。
また、栄養不足による脱毛が見られる場合、その背景に摂食障害などの病気が潜んでいることもあります。
拒食症の患者さんでは深刻な脱毛が起こることがありますが、まず食事摂取量そのものを回復させることが先決です。その場合は栄養療法と精神科的治療を平行して行う必要があります。
栄養不足は全身状態の改善が第一であり、髪の治療はそれに付随して行われます。
まとめると、栄養不足による脱毛は可逆的(元に戻る可能性が高い)である点が救いです。しっかり栄養補給を行えば、毛根は再び活動を再開し髪を生やしてくれます。
逆にいえば、このタイプの脱毛で大事なのは「毛を生やす薬」より「足りない栄養を補うこと」です。サプリメントや薬に頼る前に、日々の食事をもう一度見直してみましょう。
それが遠回りなようで、一番確実な治療法なのです。
ホルモン異常(甲状腺疾患・更年期)による脱毛の対策と治療法
甲状腺機能異常による脱毛
体内のホルモンバランスの乱れは髪の成長にも大きく影響します。代表的なのが甲状腺ホルモンの異常です。
甲状腺ホルモンは新陳代謝を調節する重要なホルモンで、この分泌が低下する甲状腺機能低下症では、全身の代謝が落ちるため毛髪の成長も鈍くなります。
具体的には、髪が全体的に細く乾燥して抜けやすくなり、休止期脱毛症のようなびまん性の脱毛が現れます。また眉毛の外側が薄くなる徴候(Hertoghe徴候)も古典的には知られています。
反対に甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)では代謝が活発になりすぎてしまい、やはり毛の成長サイクルが乱れて脱毛につながります。こちらは髪質が柔らかく細くなるのが特徴で、やはり全体的な薄毛となります。
甲状腺の異常が原因の場合、脱毛以外にも症状が出ていることが多いです。低下症なら体重増加・倦怠感・寒がり・むくみ・脈拍低下など、亢進症なら体重減少・イライラ・暑がり・動悸・手指の震えなどが見られます。
髪のトラブルと同時にこうした症状が当てはまる場合、甲状腺の検査(血液中のTSHやフリーT3/T4測定)を受けることが望ましいです。
甲状腺疾患による脱毛への対策と治療は、まず甲状腺そのものの治療です。
機能低下症なら不足している甲状腺ホルモンを補充するレボチロキシン(チラーヂン)という薬の内服、機能亢進症ならメチマゾール(メルカゾール)など抗甲状腺薬の服用や場合によってはアイソトープ治療・手術などがあります。
甲状腺ホルモン値が正常に戻れば、時間とともに髪の状態も改善していきます。

実際、甲状腺機能異常症では治療開始後数か月で抜け毛が落ち着くことがほとんどです。従って、この場合は髪自体の治療というより内科的治療が中心になります。
セルフケアとしては、甲状腺が安定するまでは髪に無理をかけないよう心掛けます。低下症では皮膚や髪が乾燥しがちなので、保湿系のシャンプーやコンディショナーでケアすると良いでしょう。
亢進症では暑がりで汗をかきやすいため頭皮が蒸れやすく、清潔を保つように注意します。ただし1日に何度もシャンプーするのは逆効果なので、適度な頻度で洗髪してください。
いずれにせよ、甲状腺が正常化すれば髪は再生可能性が高いので、焦らず治療に専念することが大切です。
更年期による脱毛
女性にとってもう一つ大きなホルモン変化の節目が更年期です。閉経前後の約10年間(45~55歳頃)を更年期と呼び、この時期には卵巣機能が衰えて女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少します。
エストロゲンは女性の髪の成長を促進し、ハリやコシを保つ作用があるため、これが減ることで髪のボリュームダウンや細毛化が起こりやすくなります。
更年期以降に女性型脱毛症(FAGA)が顕在化するのもエストロゲン低下と関係しています。
それまで髪がフサフサだった方でも、閉経を境に分け目が広がってきた、地肌が透けるようになったと感じるケースは珍しくありません。

さらに更年期世代は白髪も増えてくるため、毛が細くなる+色が抜けることで、余計に髪が少なく見えてしまうこともあります。
更年期の脱毛対策としてまず考えられるのは、基本的には女性型脱毛症(FAGA)への対策に準じるということです。つまり、ミノキシジルなどの発毛剤を使った治療が有効となります。
閉経後であれば、前述のようにフィナステリド等の内服治療も選択肢に入ってきます(妊娠のリスクがないため)。海外では閉経後の女性にフィナステリドやデュタステリド(5α還元酵素阻害薬)を投与し効果を上げた報告もあります。
ただし、日本で女性にそれらを処方することは少ないのが現状です。むしろスピロノラクトンのような抗アンドロゲン薬が海外ではよく使われますが、日本では馴染みが薄いため、やはり基本はミノキシジル外用が中心になるでしょう。
ホルモン補充療法(HRT)も間接的に効果を持つ可能性があります。
更年期症状(ほてり、発汗、不眠、情緒不安定など)が強い方はエストロゲン補充療法を受けることがありますが、これによって女性ホルモンが増えるため髪の状態が改善することもあります。
ただしHRTはあくまで更年期症状の緩和が目的であり、脱毛だけを理由に行うことは普通ありません。HRTを開始した結果として髪にも良い変化があればラッキーくらいの位置づけです。
更年期の脱毛をサポートするセルフケアとしては、まず生活習慣の見直しが大切です。
ホルモンバランスは生活習慣に影響されますので、睡眠を十分にとり、極端なダイエットは避け、適度な運動で血行を保つことが基本となります。
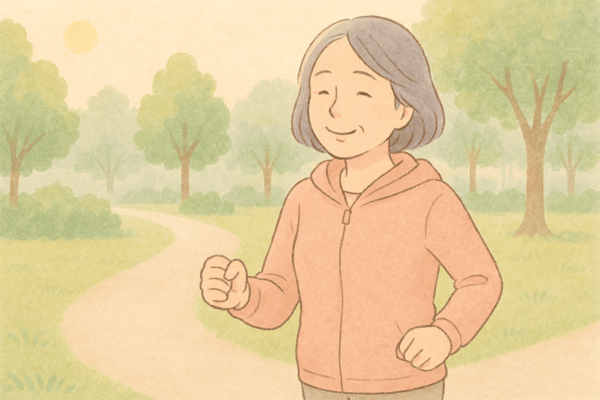
また、女性ホルモン様作用を持つイソフラボン(大豆製品)などを摂取するのも一つの手です。
科学的エビデンスは限定的ですが、更年期症状の緩和にイソフラボンが役立つという報告もありますので、豆腐・納豆・豆乳などを積極的に食事に取り入れるのは悪くありません。
髪型の工夫やウィッグの活用も心理的負担を軽くします。特にトップピース(頭頂部用ウィッグ)は更年期以降の女性に愛用者が多く、薄くなった分け目やつむじに自然なボリュームを出せます。

最近は価格も手頃で品質の良い製品が出ているので、ファッション感覚で試してみるのも良いでしょう。
更年期の脱毛はどうしても完全には避けられない老化現象の一部でもあります。あまり抗いすぎてストレスを溜めるより、受け入れつつ上手に付き合うことも大切です。
その上で「できる範囲の対策をする」というスタンスで、前向きにケアを続けましょう。医師に相談すれば、自分の状態に合った治療法を提案してくれるはずです。
よくある質問(FAQ)
- Qびまん性脱毛症は自然に治りますか?
- A
残念ながら、びまん性脱毛症は何もしないで元通りに治る可能性は低いです。実際には進行性で、放置すると徐々に悪化してしまうケースが多いです。
原因が色々と絡んでいるため、自然回復はあまり期待できません。そのため、生活習慣の改善や育毛剤の使用など何らかの対策・治療を早めに始めることが望まれます。
特に毛根が弱って細い毛しか生えなくなる前に対処したほうが、回復もしやすいです。
一度細くなった毛を元の太さに戻すのは時間がかかりますので、「おかしいな」と思ったらできる範囲で早め早めにケアを始めましょう。ただし過度に心配しすぎてストレスを溜めないことも重要です。

- Q出産後の抜け毛はいつまで続きますか?
- A
個人差はありますが、一般的には産後6か月頃が抜け毛のピークで、その後落ち着いていき、産後1年前後までに元の状態に戻ることが多いです。
産後1~2か月で抜け毛が始まり、どんどん増えていって半年くらいでようやく減り始め、「気づけば1年くらいで元通り」という流れです。
ただし授乳期間が長引く場合や、寝不足・栄養不足が続く場合は、もう少し時間がかかることもあります。逆に言えば、産後抜け毛は永遠に続くものではなく一時的な現象ですので安心してください。
もし産後1年以上経っても明らかに薄毛が改善しない場合は、他の脱毛症(例えば女性型脱毛症)が潜在していないか皮膚科で相談してみてもよいでしょう。
- Q女性でも男性用の育毛治療を受けられますか?
- A
基本的な育毛治療は男女共通の部分も多いですが、男性用(AGA用)の薬の中には女性には使えないものがあります。
例えばフィナステリド(プロペシア)やデュタステリド(ザガーロ)といったAGA治療内服薬は、女性(特に妊娠中の女性)には禁忌です。妊娠の可能性がある女性が服用すると胎児に影響を及ぼす恐れがあるためです。
一方、ミノキシジルの外用薬は女性でも使用できます。男性用の高濃度(5%以上)のものは女性には刺激が強い場合もありますが、症状に応じて専門医の管理下で使うこともあります。
また低用量のミノキシジル内服(海外では認められている治療法)を女性に処方するケースも最近はありますが、日本では適応外です。
男性用の育毛シャンプーや育毛トニックなど市販品に関しては、成分を見る限り女性が使っても差し支えないものがほとんどです。ただしメントールが強すぎたりアルコール度数が高かったりすると刺激になるので、心配なら女性向けの商品を選ぶと良いでしょう。
まとめると、女性には女性に合った治療法があるので、男性と全く同じ治療をする必要はありません。クリニックでも女性専門外来があるところも増えており、女性の薄毛には女性用の治療薬や方法で対応してくれます。

- Q円形脱毛症はまた再発しますか?
- A
残念ながら円形脱毛症は再発しやすい疾患です。初回で小さな円形脱毛斑が1つだけできたような軽症例でも、その後繰り返す人は少なくありません。
特に多発型で発症した方や、小児期に発症した方は再発率が高い傾向があります。また、完治したと思ってもしばらくしてストレスや体調不良をきっかけに再発することもあります。
一説には患者の約3割程度が複数回再発を経験するとも言われます。ただし、再発するたびに適切に治療すればその都度治る可能性も高いです。
再発時も今回学んだ対策(ストレス管理や生活習慣整備)を活かしつつ、早めに皮膚科を受診して治療を開始しましょう。症状が軽いうちに治療すれば、それだけ早く回復する傾向があります。
また、重症例向けの新しい治療(JAK阻害薬など)も登場してきていますので、諦めず専門医と相談しながら対処していくことが大事です。
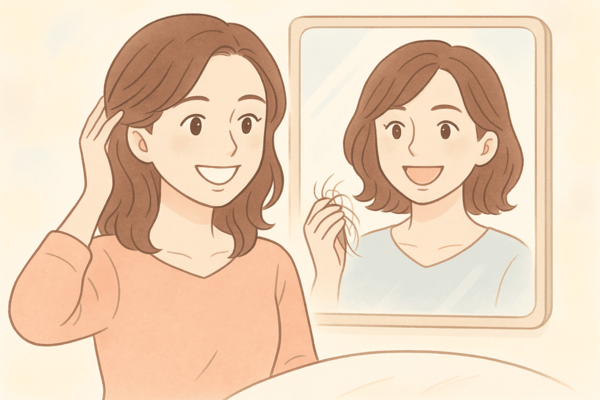
次に知ってほしいこと(薄毛対策と治療)
薄毛対策と治療法についてある程度理解できたら、以下をクリックして育毛剤について勉強しましょう。

