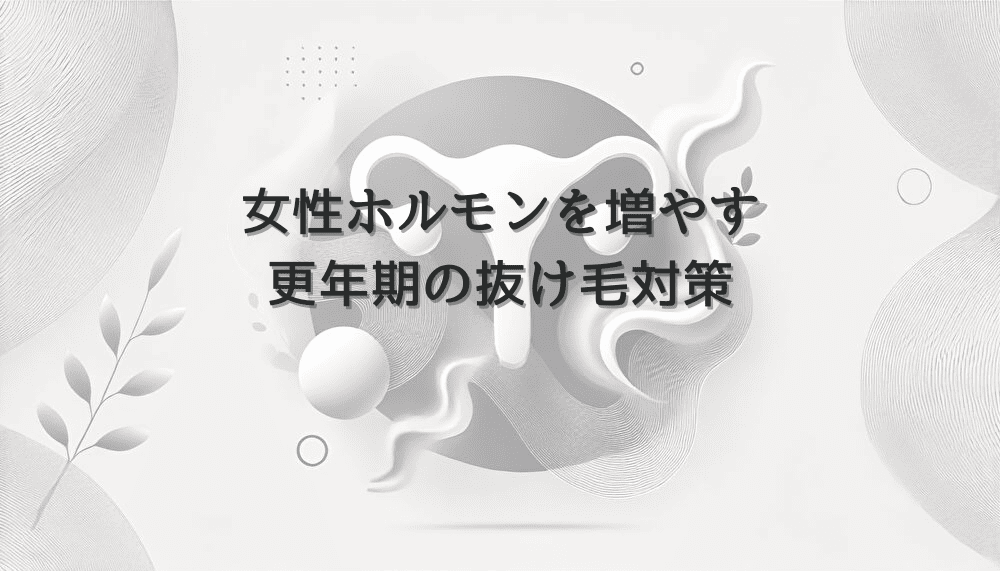更年期に差し掛かり、髪質の変化や抜け毛の増加に悩む女性は少なくありません。これは女性ホルモンの変動が大きく関わっています。
この記事では、更年期における女性ホルモンの変化と抜け毛の関係を解説し、食事や生活習慣、適切なヘアケアを通じて女性ホルモンバランスを整え、健やかな髪を育むための対策を詳しく紹介します。
ご自身の状態を理解し、前向きな気持ちで対策に取り組むための一助となれば幸いです。
更年期と女性ホルモンの関係とは
更年期は、女性の身体にさまざまな変化が現れる時期で、特に女性ホルモンの変動は、心身の健康や美容面に大きな影響を与えます。髪の健康も例外ではありません。
更年期とは何か
更年期とは、一般的に閉経を迎える前後の約10年間を指し、日本人女性の平均閉経年齢は約50歳なので、多くの場合45歳から55歳頃が更年期にあたります。
この時期は、卵巣の機能が徐々に低下し、女性ホルモンの分泌量が大きく揺らぎながら減少していくのが特徴です。
女性ホルモンの種類と役割
女性ホルモンには、主にエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)があり、女性らしい身体づくりや妊娠・出産だけでなく、自律神経の安定、骨の健康維持、皮膚や粘膜の潤い保持、そして髪の成長にも深く関わっています。
女性ホルモンの主な働き
| ホルモン名 | 主な働き | 髪への影響 |
|---|---|---|
| エストロゲン | 丸みのある体つき、自律神経の安定、コラーゲン生成促進、血管・骨の健康維持 | 髪の成長期を持続させ、ハリやコシを与える。頭皮の血行を促進する。 |
| プロゲステロン | 妊娠の維持、子宮内膜の調整、体温上昇 | 髪の成長サイクルには直接的な大きな影響はないが、バランスが重要。 |
更年期における女性ホルモンの変化
更年期に入ると、卵巣機能の低下に伴い、エストロゲンの分泌量が急激に減少し、プロゲステロンの分泌も不安定になります。
このホルモンバランスの大きな変化が、いわゆる更年期症状(ほてり、のぼせ、イライラ、不眠など)を引き起こす原因の一つです。
女性ホルモン減少が引き起こす髪への影響
エストロゲンには、髪の成長期を長く保ち、髪のハリやコシを維持する働きがあるため、更年期にエストロゲンが減少すると、髪の成長サイクルが乱れやすくなります。
成長期が短縮し、休止期に入る髪の毛が増えるため、抜け毛が増加したり、髪全体が薄く感じられたりすることがあり、また、髪が細くなったり、ツヤが失われたりといった髪質の変化も現れやすいです。
更年期の抜け毛 女性ホルモン以外の原因も
更年期の抜け毛は女性ホルモンの減少が主な要因の一つですが、それ以外にもいくつかの原因が複合的に関わっている場合があります。
加齢による影響
年齢を重ねるとともに、身体全体の細胞の働きが徐々に低下し、頭皮や毛母細胞も同様です。毛母細胞の分裂・増殖能力が衰えると、健康な髪が作られにくくなり、髪が細くなったり、成長しにくくなったりします。
これは自然な老化現象の一つですが、適切なケアで進行を緩やかにすることは期待できます。
ストレスの影響
更年期は、身体的な変化だけでなく、家庭環境や社会的な立場の変化など、精神的なストレスを感じやすい時期で、過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮への血流を悪化させます。
血流が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根に届きにくくなり、抜け毛や薄毛を助長する可能性があります。
生活習慣の乱れ
不規則な生活、睡眠不足、偏った食事、運動不足などの生活習慣の乱れも、髪の健康に悪影響を与え、特に睡眠不足は、髪の成長を促す成長ホルモンの分泌を妨げます。
また、栄養バランスの悪い食事は、髪の材料となるタンパク質や、髪の成長をサポートするビタミン・ミネラルが不足し、健康な髪が育ちにくくなります。
生活習慣と髪への影響
| 生活習慣の乱れ | 髪への主な影響 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下、血行不良 | 質の高い睡眠を7-8時間確保する |
| 偏った食事 | 髪に必要な栄養素の不足 | バランスの取れた食事を心がける |
| 運動不足 | 血行不良、新陳代謝の低下 | 適度な運動を習慣化する |
頭皮環境の悪化
頭皮は髪が育つ土壌で、頭皮が乾燥したり、逆に皮脂が過剰に分泌されたり、炎症を起こしたりすると、健康な髪が育ちにくくなります。
間違ったヘアケア、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用、紫外線ダメージなども頭皮環境を悪化させる原因となるので、頭皮環境を健やかに保つことが、抜け毛予防には重要です。
女性ホルモンを補うための食事法
更年期における女性ホルモンの減少を緩やかにし、その働きをサポートするためには、日々の食事が非常に重要です。「更年期 女性ホルモン 増やす」という観点からも、食事によるアプローチは基本となります。
大豆イソフラボンを積極的に摂取
大豆に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た化学構造を持ち、体内でエストロゲン様作用を発揮することが知られています。
そのため、更年期におけるエストロゲンの減少を補い、ホルモンバランスの乱れからくる不調や、髪への影響を和らげる効果が期待できます。
大豆イソフラボンの働き
大豆イソフラボンは、体内のエストロゲンが不足している場合には働きを補い、逆に過剰な場合にはその作用を抑えるように働く、調整機能を持ち、ホルモンバランスを整える手助けをします。
髪に対しては、エストロゲン様の作用により、髪の成長をサポートし、ハリやコシを保つ効果が期待されます。
大豆製品の選び方と摂取量の目安
大豆イソフラボンは、納豆、豆腐、豆乳、味噌、きな粉などの大豆製品に豊富に含まれていて、日常的にバランス良く取り入れることが大切です。
ただし、サプリメントなどで過剰に摂取すると、かえってホルモンバランスを崩す可能性もあるため、まずは食事からの摂取を心がけましょう。
1日の摂取目安量は、食品安全委員会により上限値として70~75mg/日(大豆イソフラボンアグリコン換算)とされています。
大豆イソフラボンを多く含む食品例(可食部100gあたり)
| 食品名 | イソフラボン含有量(mg) | 備考 |
|---|---|---|
| きな粉 | 約266 | 少量で効率的に摂取可能 |
| 納豆(1パック約45g) | 約33 | 発酵により吸収率アップ |
| 豆腐(木綿) | 約20 | 調理しやすく日常的に摂取しやすい |
バランスの取れた栄養摂取
特定の成分だけでなく、全体的な栄養バランスを整えることが、女性ホルモンの働きをサポートし、髪の健康を維持するために必要です。
タンパク質の重要性
髪の主成分はケラチンというタンパク質です。そのため、良質なタンパク質を十分に摂取することが、健康な髪を作るための基本となり、肉、魚、卵、乳製品、大豆製品などからバランス良く摂取しましょう。
ビタミン・ミネラルの役割
ビタミンやミネラルは、タンパク質の代謝を助けたり、頭皮の血行を促進したり、ホルモンバランスを整えたりと、髪の健康に多方面から関わっています。
特にビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE、亜鉛、鉄分などは重要です。
髪の健康に必要な主な栄養素
- タンパク質:髪の主成分
- 亜鉛:タンパク質の合成を助ける
- 鉄分:酸素を運び、毛母細胞の働きを活発にする
- ビタミンB群:頭皮の新陳代謝を促す
- ビタミンE:血行を促進し、抗酸化作用がある
血行を促進する食材
頭皮の血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなるので、血行を促進する食材を意識して摂ることも大切です。
例えば、ビタミンEを多く含むナッツ類や植物油、カプサイシンを含む唐辛子、アリシンを含むニンニクや玉ねぎなどが挙げられます。
腸内環境を整える食事
腸内環境は、栄養素の吸収や免疫機能、さらにはホルモンバランスにも影響を与えることが分かってきました。
善玉菌を増やす発酵食品(ヨーグルト、味噌、納豆など)や、食物繊維が豊富な野菜、きのこ、海藻類を積極的に摂り、腸内環境を整えましょう。
大豆イソフラボンの吸収効率も、腸内細菌の状態によって変わります。
生活習慣で女性ホルモンバランスを整える
食事だけでなく、日々の生活習慣を見直すことも、更年期の女性ホルモンバランスを整え、抜け毛対策を行う上で非常に重要です。「更年期 女性ホルモン 増やす」ためには、身体の内側からのケアが欠かせません。
質の高い睡眠を確保する
睡眠は、身体の修復やホルモンバランスの調整に不可欠な時間で、特に、髪の成長を促す成長ホルモンは、深い眠りの間に多く分泌されます。
睡眠不足がホルモンバランスに与える影響
睡眠不足が続くと、自律神経が乱れやすくなり、ホルモンバランスも不安定になります。
また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増え、これが女性ホルモンの働きを妨げることもあり、髪の成長サイクルが乱れ、抜け毛が増える原因になり得ます。
質の高い睡眠のための工夫
質の高い睡眠を得るためには、寝る前のカフェイン摂取を避ける、寝室の環境(温度、湿度、光、音)を整える、毎日同じ時間に寝起きするなど、生活リズムを整えることが大切です。
また、寝る前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのは避け、リラックスできるような習慣(軽い読書、温かい飲み物を飲むなど)を取り入れると良いでしょう。
睡眠の質を高めるポイント
| 項目 | 具体的な工夫 |
|---|---|
| 就寝前の行動 | カフェイン・アルコールを避ける、スマホ・PC操作を控える |
| 寝室環境 | 静かで暗い、適切な温度・湿度(例:室温26℃前後、湿度50-60%) |
| 生活リズム | 毎日同じ時間に就寝・起床する、朝日を浴びる |
適度な運動を取り入れる
適度な運動は、血行を促進し、ストレス解消にもつながるため、ホルモンバランスを整えるのに役立ちます。また、筋力を維持することは、基礎代謝を高め、健康維持にも重要です。
運動が女性ホルモンに与える好影響
運動をすることで、血流が改善し、全身の細胞に酸素や栄養が行き渡りやすくなり、これは頭皮も同様で、毛母細胞の活性化につながります。
また、運動は自律神経のバランスを整える効果も期待でき、間接的にホルモンバランスの安定に寄与します。
更年期におすすめの運動
更年期には、体に大きな負担をかけない有酸素運動がおすすめで、ウォーキング、ジョギング、水泳、ヨガ、ストレッチなどが良いでしょう。
無理のない範囲で、楽しみながら続けられる運動を見つけることが大切で、週に数回、30分程度から始めてください。
ストレスを上手に管理する
ストレスは万病のもとと言われますが、ホルモンバランスや髪の健康にも大きな影響を与え、更年期はストレスを感じやすい時期でもあるため、意識的なストレス管理が重要です。
ストレスとホルモンバランスの関係
強いストレスを感じると、体はストレスホルモンであるコルチゾールを分泌し、コルチゾールの過剰な分泌が続くと、自律神経のバランスが崩れ、女性ホルモンの分泌にも影響が出ます。
また、ストレスは血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させるため、抜け毛の原因となります。
自分に合ったリラックス方法を見つける
ストレスを完全に無くすことは難しいですが、自分に合ったリラックス方法を見つけて、こまめにストレスを発散することが大切です。
趣味に没頭する、音楽を聴く、アロマテラピーを楽しむ、友人と話す、自然の中で過ごすなど、心が安らぐ時間を作りましょう。
ストレス対処法の例
- 趣味の時間を持つ(読書、映画鑑賞、ガーデニングなど)
- 適度な運動をする
- 瞑想や深呼吸を行う
- 親しい人と話す
- 十分な睡眠をとる
禁煙と節度ある飲酒
喫煙は、血管を収縮させて血行を悪化させるだけでなく、女性ホルモンのエストロゲンの分泌を抑制し、その代謝を早めることが知られていて、これは髪の健康にとって大きなマイナス要因です。
抜け毛対策を考えるなら、禁煙は必須で、また、過度な飲酒も肝臓に負担をかけ、栄養素の代謝を妨げたり、睡眠の質を低下させたりする可能性があるため、節度ある量を心がけることが大切になります。
頭皮ケアで抜け毛を予防・改善
健康な髪は、健康な頭皮から育ちます。毎日の適切な頭皮ケアは、抜け毛を予防し、育毛環境を整えるためにとても重要です。
正しいシャンプー方法
シャンプーは、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とし、清潔に保つために行いますが、間違った方法では頭皮を傷つけたり、必要な潤いまで奪ってしまったりすることがあります。
シャンプー選びのポイント
更年期の頭皮は乾燥しやすくなる傾向があるため、洗浄力がマイルドで、保湿成分が配合されたアミノ酸系やベタイン系のシャンプーを選ぶと良いでしょう。
また、自分の頭皮の状態(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合ったものを選ぶことが大切で、香料や着色料が無添加のものも、刺激が少なくおすすめです。
洗髪の手順と注意点
洗髪時は、まずお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、汚れを浮かせ、シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。
爪を立ててゴシゴシ洗うのは頭皮を傷つける原因になるので避け、すすぎは、シャンプー剤が残らないように、時間をかけて丁寧に行うことが重要です。
正しい洗髪のステップ
| ステップ | ポイント |
|---|---|
| 予洗い | 38℃程度のぬるま湯で髪と頭皮を1~2分洗い流す |
| シャンプー | 適量を手に取り泡立て、指の腹で頭皮をマッサージするように洗う |
| すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧に洗い流す |
頭皮マッサージの効果と方法
頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待でき、また、頭皮のコリをほぐし、リラックス効果も得られます。シャンプー時や、育毛剤を塗布した後などに行うと良いでしょう。
指の腹を使って、頭皮全体を優しく揉みほぐすようにマッサージし、気持ち良いと感じる程度の力加減で行います。
育毛剤・発毛剤の選び方と使い方
育毛剤は、頭皮環境を整え、今ある髪を健康に育てることを目的とし、発毛剤は、毛母細胞に働きかけて新しい髪の毛を生やす効果が認められた医薬品です。
女性向けの製品には、女性ホルモン様成分や血行促進成分、保湿成分などが配合されているものがあり、自分の状態や目的に合わせて選び、説明書に従って正しく使用することが大切です。
育毛剤と発毛剤の違い
| 種類 | 目的 | 分類 |
|---|---|---|
| 育毛剤 | 頭皮環境を整え、抜け毛予防、毛髪の育成 | 医薬部外品 |
| 発毛剤 | 新しい毛髪を生やし、毛髪の成長を促す | 医薬品(ミノキシジル配合など) |
紫外線対策の重要性
顔や腕と同じように、頭皮や髪も紫外線のダメージを受け、紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を起こしたり、毛母細胞にダメージを与えたりして、抜け毛や薄毛の原因になることがあります。
外出時には、帽子をかぶったり、日傘をさしたり、髪用の日焼け止めスプレーを使用するなどして、頭皮と髪を紫外線から守りましょう。
医療機関で相談できること
セルフケアだけでは抜け毛や薄毛の改善が見られない場合や、原因がはっきりしない場合は、専門の医療機関に相談することを検討してください。
医師による診断のもと、適切なアドバイスや治療を受けられます。
婦人科でのホルモン補充療法(HRT)とは
ホルモン補充療法は、更年期に減少するエストロゲンを少量補うことで、ほてりやのぼせ、発汗といった血管運動神経症状や、気分の落ち込み、不眠などの精神神経症状、腟の乾燥感などの泌尿生殖器症状を改善する治療法です。
また、全身の健康維持にも寄与すると考えられています。
HRTのメリットとデメリット
HRTは、更年期症状の緩和に高い効果が期待できる一方、いくつかのメリットとデメリットがあります。医師とよく相談し、自分の状態やリスクを理解した上で検討することが重要です。
ホルモン補充療法(HRT)の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主なメリット | 更年期症状(ほてり、発汗、不眠、イライラなど)の改善、骨粗しょう症予防、皮膚の潤い改善など |
| 考えられるデメリット・副作用 | 不正出血、乳房の張り・痛み、吐き気など(治療初期に多い)。血栓症や乳がんのリスクがわずかに上昇する可能性(使用する薬剤の種類や期間、個人の状態による) |
HRTが抜け毛改善に与える影響
HRTによってエストロゲンが補充されると、髪の成長期が維持されやすくなり、抜け毛の減少や髪質の改善が期待できる場合があります。
ただし、HRTは抜け毛治療を主目的とするものではなく、あくまで更年期症状全般の改善を目的として行われる治療法の一つで、抜け毛への効果には個人差があります。
皮膚科・薄毛治療専門クリニックでの治療
抜け毛や薄毛を専門的に扱っているのは、皮膚科や女性の薄毛治療を専門とするクリニックで、より直接的な抜け毛・薄毛治療を受けられます。
専門医による診断
まず、医師が問診や視診、場合によっては血液検査や頭皮のマイクロスコープ検査などを行い、抜け毛の原因を特定します。女性の薄毛の原因は多岐にわたるため、正確な診断が治療の第一歩です。
内服薬・外用薬による治療
診断に基づき、内服薬や外用薬による治療が行われることがあります。
女性の薄毛治療に用いられる代表的な薬剤には、ミノキシジル外用薬(発毛効果)や、スピロノラクトン内服薬(男性ホルモンの影響を抑える)、各種ビタミン剤、ミネラル剤などがあります。
医師の指示に従い、正しく使用することが大切です。
薄毛治療で用いられる主な薬剤(女性向け)
- ミノキシジル外用薬:毛母細胞を活性化し発毛を促す
- スピロノラクトン内服薬:男性ホルモンの働きを抑制する(医師の判断による処方)
- パントガールなどのサプリメント:髪の成長に必要な栄養素を補給
医療機関を選ぶ際のポイント
医療機関を選ぶ際には、女性の薄毛治療の実績が豊富であるか、カウンセリングが丁寧で、治療法や費用について納得できる説明があるかなどを確認すると良いでしょう。
また、通いやすさも継続的な治療には重要です。いくつかの医療機関で相談し、比較検討することも一つの方法です。
相談するタイミング
抜け毛が急に増えた、地肌が透けて見えるようになってきた、髪のボリュームが明らかに減ったなど、気になる変化を感じたら、早めに専門医に相談することをおすすめします。
早期に対処することで、症状の進行を遅らせたり、改善したりする可能性が高まります。一人で悩まず、専門家の意見を聞いてみましょう。
更年期の抜け毛に関するよくある質問
- Q女性ホルモンを増やせば必ず抜け毛は改善しますか?
- A
女性ホルモンの減少は更年期の抜け毛の大きな原因の一つですが、それだけが原因とは限りません。加齢、ストレス、生活習慣、遺伝など、他の要因も関わっている可能性があります。
そのため、女性ホルモンを補うこと(例えば食事療法やHRTなど)で改善が見られることもありますが、必ずしも全てのケースで抜け毛が完全に改善するわけではありません。
- Qサプリメントで女性ホルモンを補給するのは効果がありますか?
- A
大豆イソフラボンやエクオールなど、女性ホルモン様の作用を持つとされる成分を含むサプリメントがあり、一部の方には体調改善や抜け毛予防のサポートとして役立つ可能性があります。
ただし、効果には個人差があり、サプリメントだけで女性ホルモンを「増やす」あるいは「補給する」と考えるのは適切ではありません。
あくまで食事の補助として考え、過剰摂取には注意が必要です。
- Q抜け毛は何歳くらいから気をつけるべきですか?
- A
抜け毛は年齢とともに誰にでも起こりうる自然な現象ですが、特に女性ホルモンの変動が大きくなる更年期(一般的に40代半ば以降)は、抜け毛が増えやすい時期です。
しかし、それ以前でもストレスや生活習慣の乱れ、不適切なヘアケアなどで抜け毛が気になることもあります。
- Qどのような状態になったら医療機関を受診すべきですか?
- A
以下のような状態が見られたら、医療機関(皮膚科、薄毛専門クリニック、婦人科など)の受診を検討することをおすすめします。
医療機関受診を検討する目安
- シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が急に増えた
- 髪の分け目が以前より目立つようになった
- 髪全体のボリュームが減り、地肌が透けて見える
- 頭皮にかゆみやフケ、炎症などが続く
- セルフケアを続けても改善が見られない
参考文献
Zouboulis CC, Blume-Peytavi U, Kosmadaki M, Roó E, Vexiau-Robert D, Kerob D, Goldstein SR. Skin, hair and beyond: the impact of menopause. Climacteric. 2022 Sep 3;25(5):434-42.
Georgala S, Katoulis AC, Georgala C, Moussatou V, Bozi E, Stavrianeas NG. Topical estrogen therapy for androgenetic alopecia in menopausal females. Dermatology. 2004 Mar 29;208(2):178-9.
Desai K, Almeida B, Miteva M. Understanding hormonal therapies: overview for the dermatologist focused on hair. Dermatology. 2021 Jan 19;237(5):786-91.
Hall G, Phillips TJ. Estrogen and skin: the effects of estrogen, menopause, and hormone replacement therapy on the skin. Journal of the American Academy of Dermatology. 2005 Oct 1;53(4):555-68.
Camacho-Martinez FM. Hair loss in women. InSeminars in cutaneous medicine and surgery 2009 Mar 31 (Vol. 28, No. 1, pp. 19-32).
Blume-Peytavi U, Atkin S, Gieler U, Grimalt R. Skin academy: hair, skin, hormones and menopause–current status/knowledge on the management of hair disorders in menopausal women. European Journal of Dermatology. 2012 May 1;22(3):310-8.
Endo Y, Obayashi Y, Murakoshi M, Saito J, Ueki R. Clinical and phototrichogrammatic evaluation of estradiol replacement therapy on hair growth in postmenopausal Japanese women with female pattern hair loss: a pilot study. International Journal of Women’s Dermatology. 2023 Dec 1;9(4):e109.