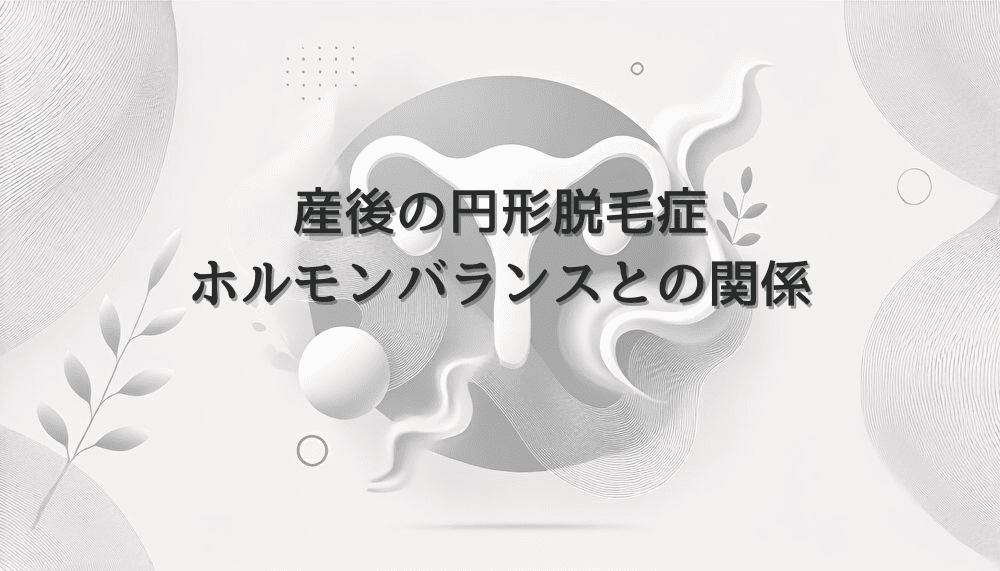出産という大きな仕事を終えたお母さんたちの中には、産後の抜け毛に加えて、ある日突然、円形に髪が抜けてしまう「円形脱毛症」に悩む方がいます。
この記事では、産後の円形脱毛症の原因、ホルモンバランスとの関連、ご自身でできる対策、そして医療機関での対応について、分かりやすく解説します。
一人で悩まず、正しい知識を得て、適切な一歩を踏み出しましょう。
産後の円形脱毛症とは?その特徴と一般的な経過
産後に経験する脱毛にはいくつかの種類がありますが、円形脱毛症は特に心配になる症状の一つです。ここでは、基本的な情報と産後特有の側面について説明します。
円形脱毛症の基本的な定義
円形脱毛症は、頭部やその他の体毛のある部分に、コインのような円形または楕円形の脱毛斑が突然現れる疾患です。
多くの場合、自覚症状はほとんどありませんが、軽いかゆみや違和感を伴うこともあります。
一つの脱毛斑で自然に治ることもあれば、複数できたり、脱毛斑が大きくなったり、再発を繰り返したりすることもあり、自己免疫反応が関与していると考えられています。
産後に見られる円形脱毛症の主な特徴
産後の円形脱毛症も、基本的な症状は一般的な円形脱毛症と変わりませんが、出産によるホルモンバランスの急激な変化、育児によるストレス、睡眠不足などが引き金となりやすい点が特徴です。
また、産後によく見られる「分娩後脱毛症(びまん性脱毛)」とは異なり、部分的にまとまって毛が抜けるのが円形脱毛症です。これらの脱毛症が併発することもあります。
産後の脱毛の種類
| 脱毛の種類 | 主な特徴 | 発症時期の目安 |
|---|---|---|
| 分娩後脱毛症 | 全体の髪が薄くなる(びまん性) | 産後2~6ヶ月頃 |
| 産後の円形脱毛症 | 円形・楕円形の脱毛斑 | 産後数ヶ月~1年以上経過後も |
| 牽引性脱毛症 | 髪を強く結ぶことで生じる | 習慣による |
発症から回復までの一般的な期間
円形脱毛症の経過は個人差が非常に大きいです。単発型で数ヶ月以内に自然に治癒するケースもあれば、数年にわたり症状が続いたり、一度治っても再発したりするケースもあります。
産後の場合、ホルモンバランスが整い、育児の負担が軽減してくるとともに改善に向かうことが多いですが、1年以上続く場合は、他の要因も考慮して専門医に相談することが大切です。
他の脱毛症との違い
産後に起こりうる脱毛症には、円形脱毛症の他にも、全体的に髪が薄くなる「分娩後脱毛症(産後びまん性脱毛症)」や、髪を強く引っ張ることで起こる「牽引性脱毛症」などがあります。
円形脱毛症は、境界が比較的はっきりした脱毛斑ができる点で区別できますが、正確な診断は医師が行うため、自己判断せずに相談しましょう。
なぜ産後に円形脱毛症が起こりやすいのか?ホルモンバランスの変動
出産は女性の体に大きな変化をもたらします。特にホルモンバランスの劇的な変動は、髪の健康にも深く関わっています。ここでは、産後のホルモン変動と円形脱毛症の関係について掘り下げます。
妊娠中と産後のホルモン量の変化
妊娠中は、女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンの分泌量が大幅に増加し、ホルモンは、髪の成長期を維持する働きがあるため、妊娠中は髪が抜けにくく、豊かに感じることが多いです。
しかし、出産を終えるとこれらのホルモンの分泌量は急激に減少し、通常のレベルに戻り、この急激な変化が、毛髪サイクルに影響を与えます。
エストロゲンの役割と産後の急減
エストロゲンは、髪の成長を促進し、成長期を長く保つ働きがあります。
妊娠中に高濃度に保たれていたエストロゲンが産後に急減すると、多くの毛が一斉に休止期に入り、抜け毛が増える「分娩後脱毛症」を起こします。
このホルモンバランスの乱れが、円形脱毛症の引き金の一つとなる可能性も指摘されています。
プロラクチンの影響
プロラクチンは、母乳の分泌を促すホルモンで、産後に分泌が高まります。
プロラクチン自体が直接的に脱毛を起こすわけではなく、分泌が高い状態が続くと卵巣機能を抑制し、エストロゲンの回復を遅らせ、ホルモンバランスの乱れが長引き、髪への影響が続く可能性があります。
産前産後の主なホルモン変化
| ホルモン | 妊娠中の状態 | 産後の状態 |
|---|---|---|
| エストロゲン | 大幅に増加 | 急激に減少 |
| プロゲステロン | 大幅に増加 | 急激に減少 |
| プロラクチン | 徐々に増加 | 授乳により高値を維持 |
ホルモンバランスの乱れと毛周期への影響
髪の毛には、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクル(毛周期)があり、ホルモンバランスが乱れると、この毛周期が正常に機能しなくなり、成長期が短縮されたり、休止期に入る毛が増えたりします。
円形脱毛症の場合、免疫系の異常が毛根を攻撃することが主な原因とされますが、ホルモンバランスの乱れがその免疫系の変調を助長する可能性があります。
免疫系の変化と自己免疫疾患の可能性
円形脱毛症は、免疫細胞が誤って自身の毛包を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種です。
妊娠中は、胎児を異物として攻撃しないように免疫機能が抑制される傾向にありますが、産後は抑制が解かれ、免疫系が過剰に反応しやすくなることがあります。
この免疫系の変化が、円形脱毛症の発症に関与する可能性が指摘されています。
産後1年経過しても円形脱毛症が続く場合の考えられる要因
産後1年が経過しても円形脱毛症が改善しない、あるいは悪化する場合は、単なる産後の影響だけではない可能性も考えられます。いくつかの要因が複雑に絡み合っていることもあります。
ホルモンバランスの回復遅延
通常、産後のホルモンバランスは数ヶ月から1年程度で妊娠前の状態に戻るといわれますが、授乳期間の長さ、体質、生活環境などにより、回復に時間がかかる人もいます。
エストロゲンの分泌が低い状態が続くと、髪の健康にも影響が出やすくなります。
育児による慢性的なストレスや睡眠不足
産後1年が経過しても、育児の負担は依然として大きいことが多いです。
夜泣き対応による睡眠不足、自分の時間が持てないことによる精神的なストレスなどが慢性化すると、自律神経のバランスが乱れ、円形脱毛症の誘因となったり、症状を長引かせたりする要因となります。
ストレスが体に与える影響の例
- 免疫力の低下
- 自律神経の乱れ
- ホルモンバランスの不調
- 血行不良
栄養状態の偏りや不足
育児に追われる中で、自身の食事がおろそかになりがちな方もいます。
髪の毛はタンパク質を主成分とし、ビタミンやミネラルも成長に必要で、授乳中は母乳を通じて赤ちゃんに栄養を分け与えるため、母親自身が栄養不足に陥りやすいです。
鉄分、亜鉛、ビオチンなどの不足は、髪の健康に影響を与える可能性があります。
髪の成長に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| 鉄分 | 頭皮への酸素供給 | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
甲状腺疾患など他の病気の可能性
産後は甲状腺機能に異常が出やすい時期でもあり、甲状腺ホルモンの異常(バセドウ病や橋本病など)は、脱毛の原因となることがあります。
円形脱毛症自体が自己免疫疾患であるため、他の自己免疫疾患(甲状腺疾患、膠原病など)を合併している可能性も考慮することが必要です。
長引く場合は、一度内科や内分泌科での検査も検討すると良いでしょう。
自宅でできる産後の円形脱毛症セルフケア方法
円形脱毛症の治療は専門医に相談することが基本ですが、日常生活でのセルフケアも症状の改善や悪化防止に役立ちます。ここでは、自宅で取り組めるケアについて紹介します。
頭皮環境を整えるシャンプーの選び方と洗い方
健康な髪は健康な頭皮から育ち、頭皮環境を整えることは、脱毛症ケアの第一歩です。
頭皮への刺激が少ない製品選び
産後の頭皮はデリケートになっていることがあり、アミノ酸系やベタイン系など、洗浄力がマイルドで低刺激性のシャンプーを選びましょう。
香料、着色料、防腐剤などが無添加、あるいは少ないものを選ぶと、より安心で、自分の頭皮に合うか、少量で試してみるのも良い方法です。
正しい洗髪の手順
洗髪は、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように行い、シャンプー剤は直接頭皮につけず、手のひらでよく泡立ててから髪全体になじませます。
すすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流しましょう。洗髪後は、ドライヤーで頭皮からしっかり乾かすことが大切ですが、高温の風を長時間当てすぎないように注意します。
洗髪時の注意点
| ポイント | 具体的な方法 | 理由 |
|---|---|---|
| シャンプー選び | 低刺激性、アミノ酸系など | 頭皮への負担軽減 |
| 洗い方 | 指の腹で優しく、よく泡立てる | 摩擦や刺激を避ける |
| すすぎ | 時間をかけて丁寧に | 残留物の付着防止 |
頭皮マッサージのやり方と注意点
頭皮マッサージは血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待でき、指の腹を使って、頭皮全体を優しく揉みほぐすように行います。
特に脱毛部分や周辺は、強くこすりすぎないように注意が必要で、リラックス効果もあるため、入浴時や就寝前などに行うのがおすすめです。
頭皮マッサージの簡単な手順
- 両手の指の腹で、生え際から頭頂部へ向かって優しく押す
- 側頭部を円を描くようにマッサージする
- 後頭部も同様に、首筋から頭頂部へ向かって揉み上げる
力を入れすぎず、気持ち良いと感じる強さで行いましょう。
生活習慣の見直しと改善ポイント
健康な髪を育むためには、規則正しい生活習慣が重要で、十分な睡眠時間を確保し、質の高い睡眠を心がけましょう。適度な運動は血行促進やストレス解消に繋がります。
禁煙も大切です。喫煙は血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させる可能性があります。
生活習慣で見直したいこと
| 項目 | 改善のポイント | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 質の高い睡眠を6-8時間確保 | 成長ホルモン分泌促進、ストレス軽減 |
| 運動 | ウォーキングなど軽い運動を習慣に | 血行促進、気分転換 |
| 食事 | バランスの取れた食事を3食 | 髪に必要な栄養補給 |
円形脱毛症と向き合うための食事と栄養のポイント
体は食べたもので作られます。髪も例外ではなく、日々の食事がその健康状態を左右します。特に産後は栄養が不足しやすいため、意識的な栄養摂取が大切です。
髪の成長に必要な栄養素
髪の主成分はケラチンというタンパク質で、良質なタンパク質の摂取は欠かせません。また、タンパク質の合成を助ける亜鉛、頭皮の血行を良くするビタミンE、細胞分裂を助けるビタミンB群なども重要です。
タンパク質の重要性
肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などに含まれるタンパク質は、髪の毛を作る上で最も基本的な材料なので、毎食、これらの食品をバランス良く取り入れるように心がけましょう。
特に動物性タンパク質と植物性タンパク質を偏りなく摂取することが望ましいです。
ビタミンとミネラルの役割
ビタミンやミネラルは、タンパク質が効率よく髪の毛になるのを助けたり、頭皮環境を整えたりする働きがあります。
亜鉛は髪の成長に、鉄分は酸素運搬に、ビタミンCはコラーゲン生成や鉄の吸収促進に、ビタミンEは血行促進に役立ちます。また、緑黄色野菜や果物、海藻類、ナッツ類などを積極的に食事に取り入れましょう。
髪に良いとされる栄養素と食品
| 栄養素 | 役割 | 食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 頭皮の新陳代謝促進 | 緑黄色野菜(人参、かぼちゃ)、レバー |
| ビタミンB群 | タンパク質の代謝、頭皮の健康維持 | 豚肉、魚介類、穀類 |
| ビタミンC | コラーゲン生成、鉄分吸収促進 | 果物(柑橘類、いちご)、野菜(ピーマン、ブロッコリー) |
バランスの取れた食事の具体的な献立例
主食(ごはん、パン、麺類)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品)、副菜(野菜、きのこ、海藻類)を揃えることを意識すると、自然とバランスの取れた食事になります。
例えば、ごはんに焼き魚、ほうれん草のおひたし、豆腐とわかめの味噌汁といった組み合わせは、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取できます。
栄養摂取で気を付けたいこと
特定の栄養素だけを過剰に摂取しても、効果が高まるわけではなく、バランスが崩れると逆効果になることもあります。
サプリメントを利用する場合は、過剰摂取に注意し、基本は食事からの摂取を心がけましょう。
また、極端な食事制限を伴うダイエットは、髪に必要な栄養素が不足し、脱毛を悪化させる可能性があるので避けるべきです。
ストレスと産後の円形脱毛症の関係と対策
「病は気から」という言葉があるように、ストレスは心身の健康に大きな影響を与え、産後の円形脱毛症においても、ストレスは無視できない要因の一つです。
産後のストレス要因とその影響
産後は、生活が赤ちゃん中心になり、自分のペースで物事を進めにくくなり、ホルモンバランスの乱れによる気分の浮き沈みも加わり、ストレスを感じやすい時期です。
育児の負担と精神的なプレッシャー
24時間体制での授乳やおむつ替え、夜泣き対応など、育児は体力的に大きな負担を伴います。
また、「良い母親でいなければ」というプレッシャーや、思うようにいかない育児への焦りが精神的なストレスとなることもあります。
社会からの孤立感
育児中は外出の機会が減り、大人と話す時間が少なくなることで、社会から取り残されたような孤立感を抱くことがあります。特に初めての育児では、相談相手がいないことへの不安も大きくなりがちです。
産後の主なストレス要因
- 睡眠不足
- 育児への不安・プレッシャー
- ホルモンバランスの乱れによる情緒不安定
- 自由な時間の喪失
- 社会との隔絶感
ストレスが免疫系やホルモンバランスに与える影響
慢性的なストレスは、自律神経のバランスを崩し、免疫機能を低下させたり、逆に過剰に反応させたりすることがあります。
円形脱毛症は自己免疫疾患と考えられているため、ストレスによる免疫系の変調が発症や悪化に関与する可能性に留意してください。
ストレスはホルモン分泌をコントロールする脳の視床下部や下垂体にも影響を与え、ホルモンバランスの乱れを助長することがあります。
日常生活でできるストレス軽減法
完全にストレスをなくすことは難しいですが、上手に付き合っていく方法を見つけることが大切です。
まずは、完璧を目指さず、「まあ、いいか」と許容範囲を広げること。家族やパートナーに頼れる部分は頼り、一人で抱え込まないようにしましょう。
リラックス方法の例
| 方法 | ポイント | 期待できること |
|---|---|---|
| 深呼吸・瞑想 | 静かな場所で数分間行う | 心身の緊張緩和 |
| 趣味の時間 | 短時間でも好きなことに集中 | 気分転換、達成感 |
| 軽い運動 | 散歩、ストレッチなど | 血行促進、セロトニン分泌 |
医療機関での相談と一般的な治療法について
円形脱毛症の症状が見られたら、自己判断せずに皮膚科などの専門医に相談することが重要です。特に産後1年を経過しても改善しない場合や、脱毛範囲が広がっている場合は、早めの受診をおすすめします。
専門医(皮膚科)を受診する目安
以下のような場合は、医療機関を受診することを検討しましょう。
- 初めて円形の脱毛斑を見つけたとき
- 脱毛斑が複数ある、または大きくなってきたとき
- 産後1年以上経過しても改善しない、または悪化しているとき
- 脱毛以外にも頭皮のかゆみや痛み、体調不良などがあるとき
- 強い不安を感じているとき
不安な場合は、上記の目安に関わらず、一度相談してください。
診察時に伝えるべき情報
医師が正確な診断を下し、適切な治療方針を立てるためには、詳細な情報が必要で、受診時には以下の情報を整理して伝えるとスムーズです。
医師に伝える情報リスト
| 情報カテゴリ | 伝える内容の例 |
|---|---|
| 症状について | いつから、どこに、どのくらいの大きさの脱毛があるか、進行しているか |
| 産後の状況 | 出産日、授乳の有無、月経の再開状況、育児の状況 |
| 既往歴・家族歴 | これまでの病気、アレルギー、家族に円形脱毛症の人がいるか |
| 生活習慣 | 食事、睡眠、ストレスの状況、使用中の薬やサプリメント |
一般的な検査内容
通常、円形脱毛症の診断は視診(脱毛の状態を見る)で行われ、ダーモスコピーという拡大鏡を使って頭皮や毛髪の状態を詳しく観察することもあります。
必要に応じて、血液検査を行い、甲状腺機能異常や自己免疫疾患、栄養状態(鉄欠乏など)の有無を調べることがあり、まれに、皮膚の一部を採取して調べる皮膚生検を行うこともあります。
代表的な治療法の選択肢と概要
円形脱毛症の治療法は、脱毛の範囲や進行度、患者さんの年齢や健康状態などを考慮して選択し、産後の場合は、授乳への影響も考慮することが必要です。
治療法は、ステロイド外用薬(塗り薬)、ステロイド局所注射、抗アレルギー薬や免疫抑制作用のある内服薬、局所免疫療法(かぶれを起こさせて発毛を促す治療法)、紫外線療法などがあります。
どの治療法が適しているかは医師とよく相談して決定します。治療には時間がかかることもありますが、焦らずに取り組むことが大切です。
よくある質問
- Q産後の円形脱毛症は必ず治りますか?
- A
産後の円形脱毛症の多くは、ホルモンバランスの安定や生活環境の改善とともに、数ヶ月から1年程度で自然に軽快することが期待できます。
しかし、症状の範囲や個人の体質、ストレスの状況などによって経過は異なり、長引いたり再発したりすることもあります。
1年以上続く場合や症状が広範囲な場合は、他の要因が関わっている可能性もあるため、専門医に相談し、適切なアドバイスや治療を受けることが重要です。
- Q遺伝は関係しますか?
- A
円形脱毛症の発症には遺伝的な要因も関与すると考えられていて、家族(特に親子や兄弟姉妹)に円形脱毛症の方がいる場合、発症する可能性がやや高くなるとの報告があります。た
だし、遺伝的要因だけが原因ではなく、ホルモンバランス、ストレス、免疫系の状態など、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
遺伝的な素因があっても必ず発症するわけではありません。
- Q育毛剤やサプリメントは効果がありますか?
- A
市販の育毛剤やサプリメントの中には、頭皮環境を整えたり、髪に必要な栄養を補給したりすることを目的とした製品があります。
これらが間接的に髪の健康をサポートする可能性はありますが、円形脱毛症の直接的な治療効果が医学的に証明されているものは限られています。
症状が進行している場合や広範囲な場合は、自己判断で使用するのではなく、まず専門医に相談し、適切な治療法について指導を受けることが大切です。
- Q治療中も授乳は続けられますか?
- A
円形脱毛症の治療法によっては、授乳中の使用に注意が必要な薬剤もあります。例えば、内服薬や一部の強力な外用薬は、母乳を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性があります。
医師は、症状と授乳の状況を総合的に判断し、授乳中でも安全に使用できる治療法を選択したり、治療のタイミングを調整したりします。治療を開始する際には、必ず授乳中であることを医師に伝え、よく相談してください。
参考文献
Eastham JH. Postpartum alopecia. Annals of Pharmacotherapy. 2001 Feb;35(2):255-8.
Hirose A, Terauchi M, Odai T, Fudono A, Tsurane K, Sekiguchi M, Iwata M, Anzai T, Takahashi K, Miyasaka N. Postpartum hair loss is associated with anxiety. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2024 Dec;50(12):2239-45.
Ansari K, Pourgholamali H, Sadri Z, Ebrahimzadeh-Ardakani M. Investigating the prevalence of postpartum hair loss and its associated risk factors: a cross-sectional study. Iranian Journal of Dermatology. 2021;24(4):295-9.
Hirose A, Terauchi M, Odai T, Fudono A, Tsurane K, Sekiguchi M, Iwata M, Anzai T, Takahashi K, Miyasaka N. Investigation of exacerbating factors for postpartum hair loss: a questionnaire-based cross-sectional study. International Journal of Women’s Dermatology. 2023 Jun 1;9(2):e084.
Jagadeesan S, Nayak P. Disorders of Hair in Pregnancy and Postpartum. InSkin and Pregnancy 2025 (pp. 58-70). CRC Press.
Wallace ML, Smoller BR. Estrogen and progesterone receptors in androgenic alopecia versus alopecia areata. The American journal of dermatopathology. 1998 Apr 1;20(2):160-3.
Pringle T. The relationship between thyroxine, oestradiol, and postnatal alopecia, with relevance to women’s health in general. Medical hypotheses. 2000 Nov 1;55(5):445-9.