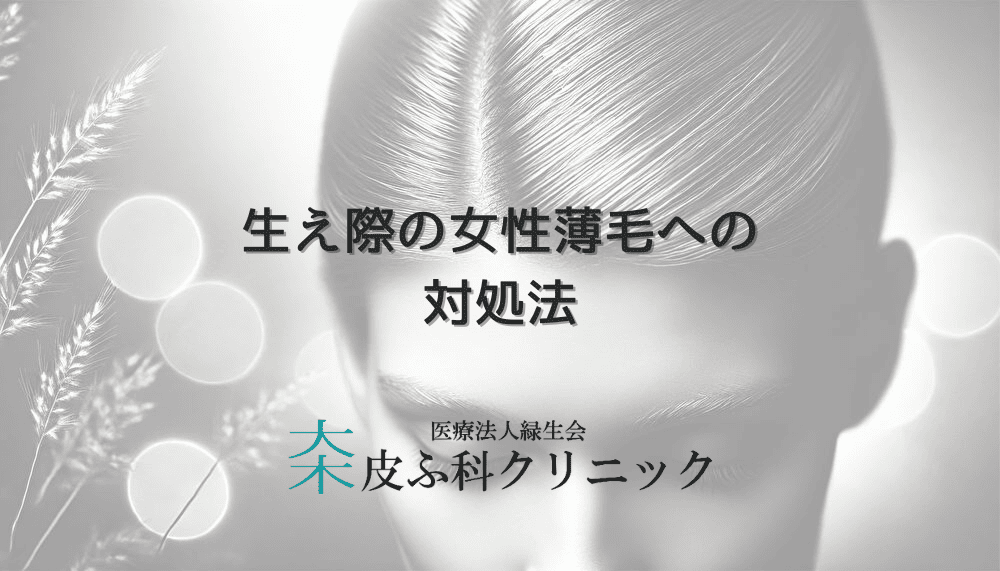生え際の薄毛は見た目の印象に大きく影響するため、悩んでいる女性が少なくありません。特に前髪で隠しにくいため、人目が気になりやすい部位です。
この記事では、女性の生え際が薄くなる原因を解説し、ご自身でできるケア方法や、専門的な治療法について紹介します。
女性の生え際が薄くなる主な原因
女性の生え際の薄毛は、さまざまな要因が絡み合って起こります。原因を特定することが、適切なケアや治療への第一歩となります。
ホルモンバランスの変化や特定の脱毛症、生活習慣などが影響している可能性があります。
ホルモンバランスの乱れ
女性ホルモンであるエストロゲンは、髪の成長を促進し、ハリやコシを保つ働きがあります。
しかし、加齢(特に更年期)や出産後、ストレスなどによってエストロゲンの分泌量が減少すると相対的に男性ホルモンの影響が強まり、髪が細くなったり抜け毛が増えたりする場合があります。
特に生え際はホルモンの影響を受けやすい部位の一つです。
ホルモンバランスの変化を引き起こす要因
| 要因 | 説明 | 影響 |
|---|---|---|
| 加齢(更年期) | 閉経に伴いエストロゲンが急激に減少します。 | 髪全体のボリュームダウンや生え際の後退につながることがあります。 |
| 出産後 | 妊娠中に増加したエストロゲンが出産後に急減します。 | 一時的に抜け毛が増加する「分娩後脱毛症」が起こることがあります。 |
| ストレス | 過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱します。 | 血行不良やホルモン分泌の異常を引き起こし、抜け毛を誘発します。 |
牽引性(けんいんせい)脱毛症
髪を強く引っ張るヘアスタイルを長時間続けて毛根に負担がかかり、生え際の髪が抜けやすくなる状態を牽引性脱毛症といいます。
ポニーテールやきつい編み込み、いつも同じ分け目などが原因となります。
初期段階であればヘアスタイルを変えると改善が見込めますが、長期間続くと毛根がダメージを受け、髪が生えにくくなるケースもあります。
FAGA(女性男性型脱毛症)
FAGAは、男性のAGA(男性型脱毛症)と同様に、男性ホルモンの影響で起こる脱毛症です。
女性の場合は男性のように生え際が後退したり、頭頂部が完全に禿げたりする方は稀ですが、生え際を含む頭部全体の髪が細くなり、地肌が透けて見えるようになる傾向があります。
遺伝的な要因も関与すると考えられています。
生活習慣の乱れ
不規則な生活や栄養バランスの偏った食事、睡眠不足などは、髪の健やかな成長を妨げる要因となります。
髪の毛は主にタンパク質でできており、その合成には亜鉛やビタミン類が必要です。また、睡眠中に分泌される成長ホルモンは毛母細胞の分裂を促し、髪の成長に重要です。
髪の成長に必要な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)を作る材料となります。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助けます。 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮環境を整え、代謝を促進します。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |
生え際が薄毛になりやすい理由
顔周りに位置する生え際は他の部位に比べて薄毛が目立ちやすく、また薄毛が進行しやすい要因もいくつか存在します。なぜ生え際が特に影響を受けやすいのか、その理由を解説します。
外部からの刺激を受けやすい
生え際は洗顔料やシャンプー、整髪料などが付着しやすく、すすぎ残しがあると毛穴の詰まりや炎症の原因となります。
また、紫外線も直接当たりやすいため、頭皮がダメージを受けやすい部位です。紫外線は頭皮を乾燥させ、毛母細胞の働きを低下させる可能性があります。
血行不良が起こりやすい
頭皮、特に生え際周辺はもともと毛細血管が少なく、血行が悪くなりやすい傾向があります。
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けたり、眼精疲労があったりすると首や肩のコリにつながり、頭部への血流がさらに滞りやすくなります。
血行不良は、髪の成長に必要な栄養や酸素が毛根に届きにくくなる原因です。
髪が細く弱い傾向がある
一般的に、生え際の髪は他の部位の髪に比べて細く、弱々しい傾向があります。
そのため、少しのダメージやホルモンバランスの変化でも影響を受けやすく、抜け毛や細毛化が目立ちやすいと考えられます。
生え際へのダメージ要因
| 要因 | 具体的な内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 物理的刺激 | 洗顔・シャンプーのすすぎ残し、強いブラッシング | 丁寧なすすぎ、優しいブラッシング |
| 化学的刺激 | 整髪料の付着、カラー・パーマ液の刺激 | 頭皮への付着を避ける、低刺激製品の選択 |
| 環境的要因 | 紫外線、乾燥 | 帽子や日傘の使用、頭皮用保湿剤の使用 |
自宅でできる生え際薄毛のセルフケア
生え際の薄毛が気になり始めたら、まずは日常生活の中でできるケアから始めてみましょう。
生活習慣の見直しや適切なヘアケアは、頭皮環境を整え、薄毛の進行を緩やかにする助けとなります。
食生活の改善
髪の健康は、体の中から作られます。バランスの取れた食事を心がけ、髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類を積極的に摂取しましょう。
特に、大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをするといわれ、薄毛対策として注目されています。
過度なダイエットは栄養不足を招き、髪に悪影響を与えるため避けるべきです。
質の高い睡眠の確保
髪の成長に欠かせない成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。入眠後の深いノンレム睡眠時に多く分泌されるため、質の高い睡眠をとることが重要です。
毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のカフェインやアルコールの摂取を控える、スマートフォンなどのブルーライトを避けるといった工夫で、睡眠の質を高めましょう。
正しいヘアケアの実践
頭皮環境を清潔に保ち、健やかに保つためのヘアケアは基本です。シャンプーは爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流します。
洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮の乾燥を招く場合があるため、アミノ酸系などマイルドな洗浄成分のものを選ぶとよいでしょう。
洗髪後は、ドライヤーで頭皮からしっかり乾かすのが大切です。濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなります。
正しいシャンプーの手順
- ブラッシングで髪のもつれを解き、汚れを浮かす。
- ぬるま湯で髪と頭皮を十分に予洗いする。
- シャンプーを手のひらで泡立て、髪全体になじませる。
- 指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗う。
- すすぎ残しがないよう、時間をかけて丁寧に洗い流す。
頭皮マッサージ
頭皮マッサージは血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。指の腹を使って、生え際から頭頂部に向かって優しく揉みほぐすようにマッサージします。
リラックス効果もあるため、入浴時や就寝前などに行うのがおすすめです。ただし、強くこすりすぎると頭皮を傷つける可能性があるので注意が必要です。
頭皮マッサージのポイント
| ポイント | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| タイミング | 入浴中や洗髪後など、血行が良い時 | 乾いた状態で行う場合は、摩擦を避ける |
| 方法 | 指の腹で優しく揉む、押す | 爪を立てない、強くこすらない |
| 頻度 | 毎日数分程度 | やりすぎは逆効果になることも |
注意したい自己流ケアと誤った情報
薄毛の悩みが深いほどさまざまな情報に頼りたくなりますが、中には効果が期待できないばかりか、かえって頭皮環境を悪化させてしまう可能性のあるケア方法も存在します。
誤った情報に惑わされず、正しい知識を持ってケアを行いましょう。
洗浄力の強すぎるシャンプーの使用
頭皮の皮脂を気にしすぎて洗浄力の非常に強いシャンプーを使い続けると、必要な皮脂まで奪ってしまい、頭皮の乾燥を招きやすいです。
頭皮が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなったり、かえって皮脂が過剰に分泌されたりするケースもあります。
自分の頭皮タイプに合った、マイルドな洗浄力のシャンプーを選びましょう。
過度なブラッシングやマッサージ
頭皮の血行促進を期待してブラシで強く叩いたり、ゴシゴシと力を入れてマッサージしたりするのは逆効果です。頭皮を傷つけ、炎症を引き起こしたり、抜け毛を助長したりする可能性があります。
ブラッシングは髪のもつれを解く程度に、マッサージは優しく行うのを心がけてください。
育毛剤の自己判断での使用
市販の育毛剤にはさまざまな種類がありますが、自分の薄毛の原因や頭皮の状態に合わないものを使用しても十分な効果は期待できません。
例えば血行促進を主目的とする育毛剤は、ホルモンバランスの乱れが原因の薄毛には効果が薄い可能性があります。また、成分によっては頭皮に合わず、かぶれなどのトラブルを引き起こす方もいます。
育毛剤選択の注意点
| 注意点 | 理由 | 推奨される対応 |
|---|---|---|
| 原因との不一致 | 薄毛の原因に合わない成分では効果が薄い | 専門医に相談し、原因を特定する |
| 頭皮への刺激 | 成分が合わないと、かぶれや痒みを引き起こす | 使用前にパッチテストを行う、低刺激性のものを選ぶ |
| 過度な期待 | 育毛剤だけで劇的に改善するとは限らない | 生活習慣改善など、他の対策と併用する |
専門クリニックでの診断
セルフケアを続けても改善が見られない場合や、薄毛が急速に進行している場合は、専門クリニックの受診を検討しましょう。
医師による正確な診断を受けると、原因を特定してご自身に合った適切な治療法を見つけられます。
問診
薄毛が気になり始めた時期や進行の程度、既往歴や家族歴、生活習慣やヘアケアの方法、使用中の薬剤などを医師が詳しく伺います。
これらの情報は、薄毛の原因を探る上で非常に重要です。気になることや不安な点は、遠慮なく医師に伝えましょう。
視診・触診
医師が直接、頭皮や髪の状態を目で見て確認します。生え際だけでなく、頭部全体の薄毛の範囲やパターン、髪の太さや密度、頭皮の色や炎症の有無などを観察します。
また、実際に髪や頭皮に触れて、硬さや弾力、皮脂の状態などを確認する場合もあります。
マイクロスコープ検査
マイクロスコープ(ダーモスコピー)という特殊な拡大鏡を使って、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察します。
肉眼では見えない毛穴の詰まり具合や頭皮の炎症、髪の太さの変化や生えている毛の本数などを確認でき、脱毛症の種類の特定や進行度の評価に役立ちます。
マイクロスコープで確認できること
- 毛穴の状態(詰まり、炎症)
- 頭皮の色や血管の状態
- 髪の太さ(細い毛の割合)
- 1つの毛穴から生えている毛の本数
- 毛髪の形状異常
血液検査
薄毛の原因として、甲状腺機能の異常や貧血、栄養不足などが疑われるときには血液検査を行うクリニックが多いです。
ホルモン値(甲状腺ホルモン、性ホルモンなど)や、鉄分、亜鉛などのミネラル、ビタミン類の不足がないかなどを調べて全身的な健康状態と薄毛との関連性を評価します。
血液検査で調べる項目例
| 検査項目 | 薄毛との関連 | 基準値(目安) |
|---|---|---|
| 甲状腺ホルモン(TSH, FT3, FT4) | 甲状腺機能低下症や亢進症は脱毛の原因となる | クリニックにより異なる |
| 鉄(フェリチン) | 鉄欠乏性貧血は抜け毛を引き起こすことがある | クリニックにより異なる |
| 亜鉛 | 亜鉛不足は髪の成長を妨げる | クリニックにより異なる |
クリニックで行われる主な治療法
専門クリニックでは、診断結果に基づき医学的根拠のある様々な治療法の中から、患者さん一人ひとりの状態や希望に合わせた治療計画を提案します。
内服薬や外用薬による治療から、より積極的な注入療法や植毛術まで、選択肢は多岐にわたります。
内服薬・外用薬治療
女性の薄毛治療で主に用いられるのは、ミノキシジル外用薬です。ミノキシジルは、毛母細胞を活性化させて発毛を促進する効果が認められている成分で、頭皮に直接塗布して使用します。
日本では女性の薄毛に対する内服薬として承認されているものはありませんが、医師の判断により、スピロノラクトン(利尿薬ですが、男性ホルモンの働きを抑える作用がある)などが処方される場合もあります。
ただし、副作用のリスクもあるため、医師の説明をよく聞いて理解した上で使用しましょう。
主な治療薬
| 薬剤名 | 種類 | 主な作用 |
|---|---|---|
| ミノキシジル | 外用薬 | 毛母細胞の活性化、血行促進 |
| スピロノラクトン | 内服薬(保険適用外) | 抗アンドロゲン作用(男性ホルモン抑制) |
注入療法(メソセラピー)
発毛効果が期待できる薬剤や成長因子などを、注射や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する治療法です。薬剤を直接毛根周辺に届けられるため、より効果が期待できるとされています。
注入する薬剤の種類はクリニックによってさまざまで、ミノキシジルや各種ビタミン、アミノ酸や成長因子などが用いられます。痛みを伴う場合があるため、麻酔を使用するケースもあります。
低出力レーザー治療(LLLT)
特定の波長の低出力レーザーを頭皮に照射する治療法です。レーザー光が細胞を活性化させて血行を促進し、毛母細胞の働きを高める効果が期待されています。
痛みや副作用がほとんどなく、自宅用の機器も販売されていますが、クリニックで用いられる機器のほうがより高い出力で効果的な照射が可能です。他の治療法と組み合わせて行われる場合もあります。
自毛植毛
薄毛の影響を受けにくい部位から自身の毛髪を毛根ごと採取し、生え際などの薄くなった部分に移植する外科的な治療法です。
移植した毛髪は元の部位の性質を保ったまま生え続けるため、効果が持続しやすいのが特徴です。
ただし、外科手術であるため費用が高額になりやすく、ダウンタイム(回復期間)も必要となります。傷跡が残る可能性も考慮する必要があります。
主な治療法の比較
| 治療法 | 主な効果 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 薬物療法(ミノキシジル外用) | 発毛促進、抜け毛抑制 | 継続が必要、初期脱毛の可能性 |
| 注入療法 | 発毛促進、頭皮環境改善 | 薬剤を直接注入、複数回の施術が必要な場合が多い |
| 低出力レーザー | 血行促進、細胞活性化 | 痛みが少ない、他の治療と併用可能 |
| 自毛植毛 | 薄毛部分に毛髪を増やす | 外科手術、効果の持続性が高い、費用・ダウンタイムが必要 |
日常生活でできる予防と対策
薄毛の進行を抑えて健やかな髪を維持するためには、日々の生活習慣を見直し、継続的なケアを行うことが大切です。
治療と並行して、あるいは将来的な薄毛のリスクに備えて、できることから始めてみましょう。
ストレスを溜めない工夫
過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を引き起こすなど、髪に悪影響を与えます。自分なりのストレス解消法を見つけ、心身をリラックスさせる工夫が重要です。
趣味に没頭する時間を作る、軽い運動をする、友人や家族と話す、アロマテラピーを取り入れるなど、自分に合った方法でストレスを上手にコントロールしましょう。
紫外線対策
紫外線は、髪の毛だけでなく頭皮にもダメージを与えます。頭皮が日焼けすると乾燥や炎症を引き起こし、毛根の働きを弱めてしまう可能性があります。
外出時には、帽子をかぶる、日傘をさす、頭皮用の日焼け止めを使用するなどして、紫外線から頭皮を守りましょう。特に、分け目やつむじ周り、生え際は紫外線が当たりやすいので注意が必要です。
ヘアスタイルへの配慮
毎日同じ分け目にしたり髪を強く引っ張るポニーテールや編み込みを長時間続けたりすると、特定の部位の毛根に負担がかかり、牽引性脱毛症の原因となります。
定期的に分け目を変える、髪を結ぶ際は緩めにする、就寝時は髪を下ろすなど、頭皮への負担が少ないヘアスタイルを心がけましょう。
頭皮に優しいヘアスタイルのポイント
- 分け目を定期的に変える
- 髪をきつく結びすぎない
- ヘアアクセサリーは軽いものを選ぶ
- 就寝時は髪への負担が少ない状態にする
よくある質問
生え際の薄毛治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q治療を開始してから効果が出るまでどのくらいかかりますか?
- A
治療法や個人差によって異なりますが、一般的に効果を実感し始めるまでには数ヶ月単位の時間が必要です。
例えば、ミノキシジル外用薬の場合、効果が現れるまでに最低でも4ヶ月から6ヶ月程度の継続使用が必要とされています。
毛髪にはヘアサイクル(毛周期)があるため、すぐに効果が現れるわけではありません。焦らず、根気強く治療を続けましょう。
- Q治療の費用はどのくらいかかりますか?
- A
女性の薄毛治療は多くの場合、健康保険が適用されない自由診療となります。そのため治療費用は全額自己負担となり、クリニックや治療内容によって大きく異なります。
内服薬や外用薬の処方であれば月々数千円から数万円程度、注入療法や植毛となると数十万円から数百万円かかる場合もあります。
カウンセリング時に治療内容ごとの費用や、おおよその総額について、しっかりと確認すると良いでしょう。
- Q治療の副作用はありますか?
- A
どのような治療法であっても、副作用のリスクはゼロではありません。ミノキシジル外用薬では頭皮のかゆみやかぶれ、初期脱毛(使用開始後に一時的に抜け毛が増える現象)などが報告されています。
スピロノラクトンなどの内服薬では、めまいや血圧低下、生理不順などの可能性があります。注入療法では注入時の痛みや内出血、腫れなどが起こるケースがあります。
治療を開始する前に、医師から考えられる副作用について十分な説明を受けましょう。
- Q市販の育毛剤とクリニックの治療はどう違いますか?
- A
市販の育毛剤の多くは医薬部外品に分類され、主に頭皮環境を整えて抜け毛を予防することを目的としています。
一方、クリニックで処方されるミノキシジル外用薬などは医薬品であり、発毛を促進する効果が医学的に認められています。
また、クリニックでは、医師が診察に基づき、薄毛の原因や状態に合わせた治療法を提案できる点が大きな違いです。より積極的な改善を望む場合は、専門医に相談することをお勧めします。
参考文献
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
SINCLAIR, Rodney; WEWERINKE, M.; JOLLEY, D. Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens. British Journal of Dermatology, 2005, 152.3: 466-473.
BHAT, Yasmeen Jabeen, et al. Female pattern hair loss—an update. Indian dermatology online journal, 2020, 11.4: 493-501.
SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.