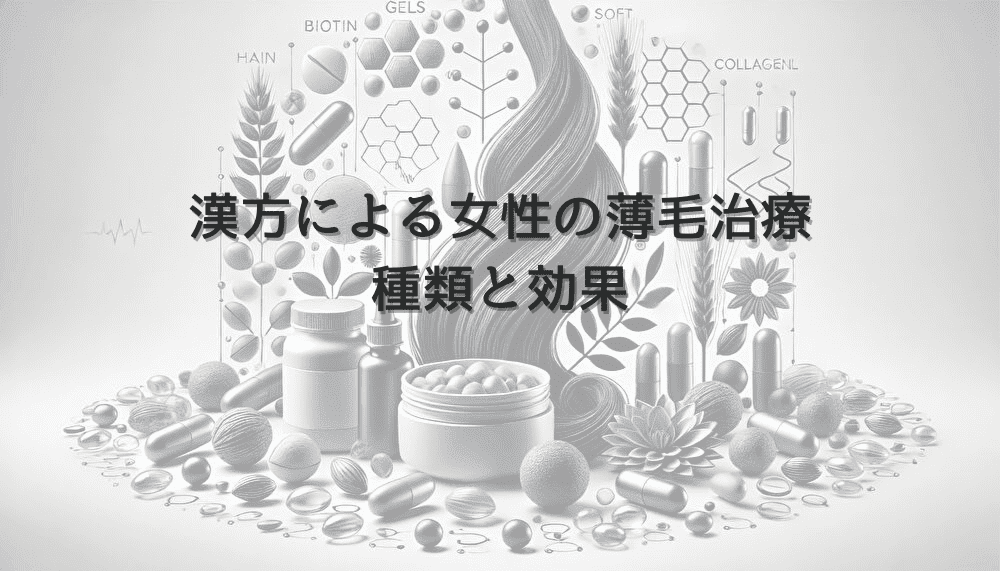女性の薄毛や抜け毛の悩みは深刻です。その原因は様々ですが、東洋医学の視点、特に漢方を用いた方法が注目されています。
漢方は体全体のバランスを整えることで、髪の健康を取り戻す手助けをします。
この記事では、女性の薄毛の主な原因を漢方の考え方から解説し、体質や症状に合わせた漢方薬の種類とその効果、選び方について詳しく説明します。
漢方とは何か?女性の薄毛治療における基本的な考え方
漢方医学は古代中国から伝わる伝統医学であり、日本で独自の発展を遂げました。
西洋医学が病気の原因となる特定の部位や病原体に着目するのに対し、漢方では心と体は一体(心身一如)と考え、全体のバランスの乱れが不調を引き起こすと考えます。
薄毛や抜け毛も単に頭皮の問題として捉えるのではなく、体全体のバランスの乱れが髪に現れたサインと捉えるのが特徴です。
治療では、個々の体質や症状に合わせて生薬を組み合わせた漢方薬を用い、体質改善を目指します。
気・血・水とは?体のバランスを示すものさし
漢方では、私たちの体を構成して生命活動を維持する基本的な要素として「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の3つを考えます。
これらが体内をスムーズに巡り、バランスが保たれている状態が健康であるとします。
- 「気」生命エネルギー。元気や気力、体を温める力、内臓の働きなどを指します。
- 「血」血液とその働き。全身に栄養を運び、精神活動を支えます。
- 「水」血液以外の体液全般。体を潤し、関節の動きを滑らかにします。
これらのいずれかが不足したり、滞ったりすると様々な不調が現れます。薄毛も気・血・水のバランスの乱れが原因の一つとなる場合があります。
気・血・水のバランス異常の例
| 要素 | 不足(虚) | 滞り(滞・瘀) |
|---|---|---|
| 気 | 元気がない、疲れやすい、食欲不振、風邪をひきやすい | イライラ、気分の落ち込み、胸や喉のつかえ感 |
| 血 | 顔色が悪い、めまい、動悸、乾燥肌、髪のパサつき | 肩こり、頭痛、生理痛、シミ、くすみ |
| 水 | のぼせ、ほてり、口や喉の渇き、寝汗 | むくみ、めまい、体が重い、下痢や軟便 |
虚実とは?体質を見極める重要な指標
漢方では病気に対する体の反応や体力、抵抗力などから、その人の体質を「虚(きょ)」と「実(じつ)」に分けて考えます。これは治療方針を決める上で重要な指標となります。
虚証
「虚証(きょしょう)」は体力や抵抗力が低下し、体の機能が全体的に弱っている状態を指します。
顔色が悪く、疲れやすい、食欲がない、声が小さいなどの特徴が見られます。
薄毛においては、髪に必要な栄養が不足したり、髪を育むエネルギーが足りなかったりすることが考えられます。
実証
一方、「実証(じっしょう)」は体力や抵抗力は比較的あるものの、体内に余分なもの(邪気)が溜まっていたり、気の流れが悪くなっていたりする状態を指します。
体力があり声が大きい、便秘がち、イライラしやすいなどの特徴が見られます。
薄毛においては、ストレスや生活習慣の乱れからくる気血の滞りなどが原因となるケースがあります。
五臓との関わり – 髪と深い関係にある「腎」と「肝」
漢方では内臓を「五臓(肝・心・脾・肺・腎)」として捉え、それぞれが特定の生理機能や精神活動を担っていると考えます。髪の健康に特に深く関わるのが「腎」と「肝」です。
腎
「腎」は生命エネルギーの根源であり、成長や発育、生殖を司ります。
髪は「腎の華」とも呼ばれ、腎の機能が充実していると髪は黒く艶やかになりますが、腎の働きが衰える(腎虚)と白髪や薄毛、抜け毛が増えると考えます。
加齢による薄毛は、多くの場合、この腎虚が関係しています。
肝
「肝」は血液を貯蔵し、その量を調整する働き(蔵血)や、気血の流れをスムーズに保ち、精神状態を安定させる働き(疏泄)を担います。
肝の機能が低下すると、血流が悪くなり髪に十分な栄養が届かなくなったり、ストレスによって気の流れが滞り頭皮環境が悪化したりして、薄毛につながる場合があります。
五臓と髪の関係性の概要
| 五臓 | 主な働き | 髪との関連 |
|---|---|---|
| 腎 | 生命エネルギー貯蔵、成長・発育・生殖 | 髪の成長、色艶(腎虚は薄毛・白髪の原因) |
| 肝 | 血液貯蔵、気血の流れ調整、精神安定 | 髪への栄養供給、ストレス性脱毛との関連 |
| 脾 | 飲食物の消化吸収、気血の生成 | 髪の栄養源生成(間接的に関与) |
漢方から見た女性の薄毛・抜け毛の主な原因
女性の薄毛や抜け毛は、様々な要因が複雑に絡み合って起こります。漢方では、これらの原因を気・血・水のバランスの乱れや五臓の機能低下として捉え、体質改善を目指します。
気血両虚(きけつりょうきょ) – エネルギーと栄養の不足
気血両虚とは、「気」と「血」の両方が不足している状態です。気虚によるエネルギー不足と、血虚による栄養不足が同時に起こるため、体全体の機能が低下します。
髪は血の余り(血余)とも言われ、血が不足すると髪に栄養が行き渡らず細くなったり、抜けやすくなったりします。
また、気を消耗するような過労や睡眠不足、胃腸機能の低下による栄養吸収不良なども原因となります。
気血両虚の主な症状
- 疲れやすい、息切れ
- 顔色が青白い、または黄色っぽい
- めまい、立ちくらみ
- 髪の毛が細く、パサつく、抜けやすい
- 爪がもろい、割れやすい
腎虚(じんきょ) – 生命エネルギーの衰え
腎は生命活動の根本を支え、髪の成長にも深く関わっています。
加齢とともに腎の機能は自然と衰えていきますが(腎虚)、若い人でも過労や睡眠不足、慢性的なストレスや大きな病気などによって腎のエネルギーが消耗し、腎虚の状態になるときがあります。
腎虚になると髪を十分に育てられなくなり、薄毛や抜け毛、白髪といった老化現象が早く現れるケースがあります。
腎虚のタイプと関連症状
| 腎虚のタイプ | 主な関連症状 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 腎陽虚(じんようきょ) | 冷え、腰痛、頻尿、むくみ、気力低下 | 抜け毛、髪の成長遅延 |
| 腎陰虚(じんいんきょ) | ほてり、のぼせ、寝汗、耳鳴り、口の渇き | 髪のパサつき、細毛、抜け毛 |
瘀血(おけつ) – 血行不良による栄養供給の滞り
瘀血とは、血の流れが悪くなり、滞っている状態を指します。ストレスや冷え、運動不足や食生活の乱れなどが原因で起こります。
血行が悪くなると頭皮の毛細血管まで栄養が十分に届かなくなり、毛根が栄養不足に陥ってしまいます。その結果、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりします。
肩こりや頭痛、生理痛やシミ、くすみなども瘀血のサインとして現れやすい症状です。
気滞(きたい) – ストレスによる気の流れの停滞
気滞とは、気の流れがスムーズでなくなり、停滞している状態です。主に精神的なストレスや感情の抑圧などが原因で起こります。
気の流れが滞ると血行も悪くなりやすく、頭皮への栄養供給が妨げられます。また、自律神経のバランスが乱れ、頭皮環境が悪化する場合もあります。
円形脱毛症などは、気滞が関与しているケースが多いと考えられます。イライラしやすい、気分が落ち込む、胸や喉がつかえる感じがするなどの症状が見られます。
薄毛治療に用いられる代表的な漢方薬
女性の薄毛治療には、原因となる体質や症状に合わせて様々な漢方薬が用いられます。ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。
ただし、漢方薬は個々の状態に合わせて選ぶことが重要ですので、自己判断せず、専門医や薬剤師に相談しましょう。
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん) – 血虚と水滞の改善
比較的体力がなく、冷え症で貧血傾向があり、疲れやすい方のむくみや生理不順などに用いられる漢方薬です。
血行を促進し(駆瘀血作用)て体を温め、余分な水分を取り除く(利水作用)働きがあります。
血行不良や冷えによる頭皮環境の悪化、栄養不足(血虚)が原因と考えられる薄毛に効果を期待します。
加味逍遙散(かみしょうようさん) – 気滞と血虚の改善
体力が中程度以下で疲れやすく、精神不安やイラ立ち、肩こりやのぼせなどの症状がある方に用いられます。
気の流れを良くし(疏肝解鬱作用)、血を補い(補血作用)、体の熱を冷ます働きがあります。
ストレスによる気滞や血行不良、ホルモンバランスの乱れなどが関与する薄毛や、更年期障害に伴う抜け毛などに適しています。
人参養栄湯(にんじんようえいとう) – 気血両虚の改善
病後や術後などで体力が著しく低下し、食欲不振や寝汗、手足の冷えや貧血などの症状がある方に用いられます。
気と血の両方を強力に補い(補気補血作用)、胃腸の働きを高める効果を期待します。
全身の衰弱に伴う栄養不足が原因の薄毛や抜け毛、髪のパサつきなどに適しています。
薄毛タイプと代表的な漢方薬
| 主な原因(証) | 代表的な漢方薬 | 主な作用 |
|---|---|---|
| 血虚・水滞 | 当帰芍薬散 | 補血、駆瘀血、利水 |
| 気滞・血虚 | 加味逍遙散 | 疏肝解鬱、補血、清熱 |
| 気血両虚 | 人参養栄湯 | 大補気血、健脾 |
その他の漢方薬 – 症状に合わせた選択
上記以外にも、薄毛の原因や体質に合わせて様々な漢方薬が用いられます。
例えば、腎虚が顕著な場合には「八味地黄丸(はちみじおうがん)」や「六味丸(ろくみがん)」、瘀血が強い場合には「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」などが選択肢となることがあります。
また、胃腸が弱く栄養吸収が悪い場合には、胃腸機能を整える漢方薬を併用するときもあります。
個々の状態を詳細に診察し、適した処方を選択することが漢方治療の鍵となります。
漢方薬の効果が現れるまでの期間と注意点
漢方治療は体質そのものを改善していくことを目的とするため、効果を実感するまでにはある程度の時間がかかります。焦らず、じっくりと取り組む姿勢が大切です。
効果実感までの目安期間
漢方薬の効果の現れ方は症状の程度や体質、生活習慣などによって個人差が大きいですが、一般的には数週間から数ヶ月程度かかる方が多いです。
体質改善を目的とする場合、最低でも3ヶ月程度は服用を続けることが推奨されます。
髪の毛にはヘアサイクルがあるため、抜け毛の減少や新しい髪の成長を実感するには、さらに時間がかかるケースもあります。
服用における注意点
漢方薬は天然の生薬から作られていますが、医薬品であることに変わりはありません。そのため、副作用が全くないわけではありません。
体質に合わない場合や、他の薬との飲み合わせによっては、胃腸症状や皮膚症状が現れます。
服用中に何か異変を感じたときは、すぐに服用を中止し、処方を受けた医師や薬剤師に相談してください。
漢方薬服用時の一般的な注意点
| 注意点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 用法・用量 | 医師や薬剤師の指示通りに、決められた量を守って服用する。 |
| 飲み合わせ | 他の薬(西洋薬、他の漢方薬、サプリメント等)を服用している場合は、必ず事前に相談する。 |
| アレルギー | 特定の生薬に対するアレルギーがある場合は、必ず事前に伝える。 |
| 副作用 | 体調に変化があった場合は、速やかに医師・薬剤師に相談する。 |
妊娠中・授乳中の服用について
妊娠中や授乳中は、母体や胎児、乳児への影響を考慮する必要があります。
漢方薬の中には、妊娠中に避けるべき生薬が含まれているものもあります(例えば、血行を促進しすぎるものや子宮収縮作用のあるものなど)。
自己判断での服用は絶対に避け、必ず医師に相談してください。授乳中の場合も同様に、母乳を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性のある生薬がありますので、医師の指示に従いましょう。
他の薄毛治療との併用
漢方治療は、西洋医学的な薄毛治療(ミノキシジル外用薬、内服薬、LED照射など)との併用も可能です。それぞれの治療法には異なる働きかけと利点があります。
漢方で体質改善を図りながら、西洋医学で直接的な発毛促進を行うなど、組み合わせによってより良い結果を期待できる場合もあります。
ただし、併用する際は両方の治療を担当する医師に必ず相談し、治療方針を確認しましょう。
漢方治療と合わせて行いたい生活習慣の改善
漢方薬の効果を高め、薄毛の根本的な改善を目指すためには、日々の生活習慣の見直しも非常に重要です。
食事や睡眠、ストレス管理など、体全体のバランスを整えるための工夫を取り入れましょう。
バランスの取れた食事で髪の栄養源を確保
髪の主成分はタンパク質(ケラチン)です。良質なタンパク質を十分に摂取するのが基本となります。
また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、抗酸化作用のあるビタミンC、細胞分裂を助けるビタミンB群も積極的に摂りましょう。
漢方的な観点からは、体を冷やす冷たい飲食物や、血行を悪くする可能性のある脂っこいもの、甘いものの摂りすぎには注意が必要です。
髪の健康に役立つ栄養素と食品
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質合成補助 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化 | ナッツ類、アボカド、植物油 |
| ビタミンB群 | 代謝促進、細胞分裂補助 | レバー、豚肉、うなぎ、青魚 |
質の高い睡眠で成長ホルモンの分泌を促す
髪の成長には、睡眠中に分泌される成長ホルモンが深く関わっています。特に、入眠後最初の深いノンレム睡眠時に多く分泌されるため、質の高い睡眠の確保が大切です。
毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のカフェインやアルコール摂取を控える、スマートフォンやパソコンの使用を就寝1時間前にはやめる、寝室の環境を整える(温度、湿度、光、音)などの工夫をしましょう。
睡眠不足は気の消耗や腎虚にもつながりやすいため、十分な睡眠時間を確保するのも重要です。理想的には7時間程度の睡眠を目指しましょう。
ストレスケアで気滞や血行不良を防ぐ
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こしたり、気の流れを滞らせたり(気滞)する原因となります。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、溜め込まないようにすると良いです。
軽い運動(ウォーキング、ヨガなど)、趣味に没頭する時間を作る、友人や家族と話す、ゆっくり入浴する、瞑想や深呼吸を行うなどが有効です。
ストレスを完全になくすのは難しいですが、上手に付き合っていく方法を見つけましょう。
適度な運動で血行促進と気分転換
適度な運動は全身の血行を促進し、頭皮への栄養供給を助けます。また、気分転換やストレス解消にもつながり、気の流れを良くする効果も期待できます。
激しい運動である必要はなく、ウォーキングやジョギング、水泳やサイクリング、ヨガなどの自分が続けやすいと感じるものを日常生活に取り入れましょう。
運動不足は瘀血や気滞の原因にもなりやすいため、意識的に体を動かす習慣をつける工夫が大切です。
漢方治療を受ける際のクリニック選び
漢方を用いた薄毛治療を検討する際には、信頼できる医療機関を選ぶことが重要です。いくつかのポイントを押さえて、ご自身に合ったクリニックを見つけましょう。
漢方に詳しい医師の在籍確認
漢方治療は専門的な知識と経験が必要です。医師が漢方の専門医であるか、あるいは漢方診療に十分な経験を持っているかを確認しましょう。
クリニックのウェブサイトやパンフレットで、医師の経歴や資格、漢方に関する診療実績などを確認できます。
また、日本東洋医学会認定の漢方専門医であるかどうかも一つの目安になります。
丁寧な問診と診察(四診)
漢方治療では、患者さん一人ひとりの体質や症状を詳しく把握することが基本となります。そのためには、時間をかけた丁寧な問診が欠かせません。
現在の症状だけでなく既往歴や体質、食欲や睡眠、排泄や月経の状態、ストレスの状況など多岐にわたる情報を詳しく聞き取ってくれるクリニックを選びましょう。
また、漢方独自の診察法である「四診(望診・聞診・問診・切診)」、特に脈やお腹の状態を診る診察(脈診・腹診)を丁寧に行ってくれるかどうかも重要なポイントです。
漢方における四診の概要
| 診察法 | 内容 | 診るポイントの例 |
|---|---|---|
| 望診(ぼうしん) | 視覚による観察 | 顔色、舌の状態(色、苔)、皮膚の状態、体格 |
| 聞診(ぶんしん) | 聴覚・嗅覚による観察 | 声の大きさ・質、咳の状態、体臭、口臭 |
| 問診(もんしん) | 患者への質問 | 自覚症状、既往歴、生活習慣、体質など |
| 切診(せっしん) | 体に触れて診察 | 脈の状態(脈診)、腹部の状態(腹診) |
治療方針や費用に関する十分な説明
どのような漢方薬を、どのくらいの期間使用するのか、期待できる効果や起こりうる副作用、治療にかかる費用などについて事前に十分な説明を受けられるかどうかも大切です。
疑問や不安な点があれば遠慮なく質問し、納得した上で治療を開始できるクリニックを選びましょう。
自由診療となる場合が多いので、費用の内訳や支払い方法についても明確に説明してくれるかを確認してください。
通いやすさと継続性
漢方治療の効果が現れるまでに時間がかかる方が多く、定期的な通院が必要です。自宅や職場から通いやすい場所にあるか、診療時間や予約の取りやすさなども考慮しましょう。
無理なく治療を続けられる環境を選ぶことが、結果につながる重要な要素となります。
よくある質問(FAQ)
漢方による女性の薄毛治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
漢方は奥が深いものですが、疑問を解決して前向きに薄毛治療に臨みましょう。
- Q漢方薬は保険適用になりますか?
- A
薄毛や抜け毛の治療目的で処方される漢方薬は、原則として保険適用外(自由診療)となることが多いです。
ただし、薄毛の原因となっている他の症状(例えば、冷え症、月経不順、更年期障害など)に対して漢方薬が処方され、それが結果的に薄毛改善にもつながるときは、保険適用となる可能性もあります。
詳しくは、受診する医療機関にご確認すると安心です。
- Q市販の漢方薬でも効果はありますか?
- A
ドラッグストアなどで市販されている漢方薬の中にも、薄毛に関連する症状に対応するものがあります。しかし、漢方薬は個々の体質(証)に合わせて選ぶことが最も重要です。
自己判断で選んだものがご自身の体質に合っていない場合、効果が得られないばかりか、かえって体調を崩してしまう可能性もあります。
まずは専門医に相談し、ご自身の状態に合った漢方薬を処方してもらうことをおすすめします。
- Q漢方薬の副作用が心配です。
- A
漢方薬は比較的副作用が少ないとされていますが、医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。
代表的なものとしては食欲不振や胃もたれ、下痢や便秘といった消化器症状、発疹やかゆみなどの皮膚症状があります。
また、まれに間質性肺炎や肝機能障害などの重篤な副作用が起こる例も報告されています。
服用中にいつもと違う症状が現れたときはすぐに服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。事前にアレルギー歴や既往症、服用中の他の薬について正確に伝えるのも重要です。
- Qどのくらいの期間で効果が出ますか?
- A
前述の通り、漢方薬の効果の現れ方には個人差がありますが、体質改善を目的とする場合は一般的に数ヶ月単位での服用が必要となるケースが多いです。
抜け毛の減少や発毛といった目に見える変化を感じるまでには、さらに時間がかかることもあります。
焦らず、医師の指示に従って根気強く治療を続けることが大切です。治療経過については定期的に医師と相談し、必要に応じて処方の見直しなども行います。
参考文献
YOU, Qiang, et al. Meta‐Analysis on the Efficacy and Safety of Traditional Chinese Medicine as Adjuvant Therapy for Refractory Androgenetic Alopecia. Evidence‐Based Complementary and Alternative Medicine, 2019, 2019.1: 9274148.
ZHANG, Zhiming, et al. Exploring the effects of Chinese herbal ingredients on the signaling pathway of alopecia and the screening of effective Chinese herbal compounds. Journal of Ethnopharmacology, 2022, 294: 115320.
NABAHIN, Amal; ABOU ELOUN, Alaa; ABU-NASER, Samy S. Expert system for hair loss diagnosis and treatment. 2017.
LEEM, Jungtae, et al. Exploring the combination and modular characteristics of herbs for alopecia treatment in traditional Chinese medicine: an association rule mining and network analysis study. BMC complementary and alternative medicine, 2018, 18: 1-13.
CHO, Eun Chai; KIM, Kyuseok. A comprehensive review of biochemical factors in herbs and their constituent compounds in experimental studies on alopecia. Journal of ethnopharmacology, 2020, 258: 112907.
LEE, Chien-Ying, et al. Hair growth effect of traditional Chinese medicine BeauTop on androgenetic alopecia patients: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Experimental and Therapeutic Medicine, 2017, 13.1: 194-202.
TAN, Justin JY, et al. Bioactives in Chinese proprietary medicine modulates 5α-reductase activity and gene expression associated with androgenetic alopecia. Frontiers in Pharmacology, 2017, 8: 194.
YOUSSEF, Alaa, et al. A comprehensive review of natural alternatives for treatment of alopecia with an overview of market products. Journal of Medicinal Food, 2022, 25.9: 869-881.