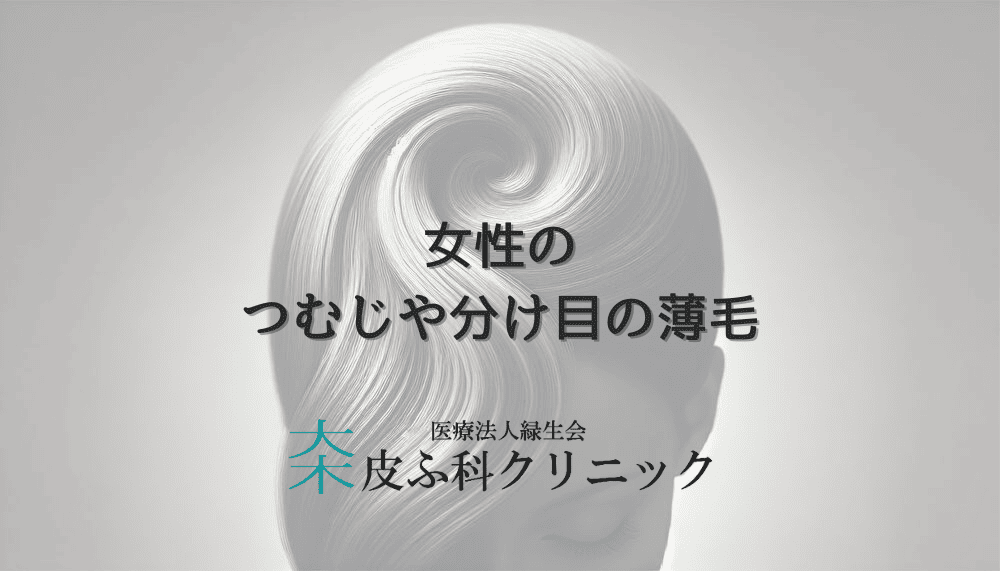「最近、つむじ周りが気になる」「分け目が以前より目立つようになった気がする」「頭頂部全体のボリュームが減ってきたかも」と感じる方もいるでしょう。
女性の薄毛は男性とは異なる原因やパターンで進行するケースが多く、特に人目に付きやすいつむじや分け目、頭頂部の変化は大きな悩みとなりがちです。
しかし、適切な知識と対策を行えば、改善の可能性は十分にあります。
なぜ?女性のつむじ・分け目・頭頂部が薄くなる原因
女性のつむじや分け目、頭頂部のボリュームダウンには、いくつかの原因が考えられます。一つだけでなく、複数の要因が絡み合っていることも少なくありません。
加齢による変化
年齢を重ねると髪の毛にも変化が現れます。髪の毛を作り出す毛母細胞の働きが徐々に低下し、一本一本の髪が細くなったり、髪の成長期が短くなったりします。
これにより全体のボリュームが減少し、特に頭頂部周辺の地肌が透けて見えやすくなる場合があります。
これは自然な変化の一部ですが、進行度合いには個人差があります。
ホルモンバランスの乱れ
女性ホルモンであるエストロゲンは、髪の成長を促進してハリやコシを保つ働きがあります。
しかし、妊娠・出産や更年期、あるいは過度なストレスや不規則な生活などによってホルモンバランスが乱れるとエストロゲンの分泌量が減少し、相対的に男性ホルモンの影響を受けやすくなります。
これが、髪が細くなったり抜け毛が増えたりする一因となり、分け目や頭頂部の薄毛につながりやすいです。
女性ホルモンと髪の関係
| ホルモン | 髪への主な働き | 減少時の影響 |
|---|---|---|
| エストロゲン | 髪の成長期を維持、ハリ・コシを保つ | 成長期短縮、髪の細毛化、抜け毛増加 |
| プロゲステロン | 髪の成長をサポート | 髪の成長サイクルへの影響 |
生活習慣の影響
日々の生活習慣も髪の健康に大きく関わっています。栄養バランスの偏った食事や睡眠不足、過度なダイエットや喫煙などは、血行不良を招いたり髪に必要な栄養素の供給を妨げたりする可能性があります。
髪の主成分であるタンパク質やその合成を助ける亜鉛、ビタミンなどが不足すると、健やかな髪の成長が阻害されて薄毛の原因となるときがあります。
頭皮環境の悪化
頭皮は髪が育つ土壌です。洗浄力の強すぎるシャンプーの使用やすすぎ残しなどの間違ったヘアケア、頭皮の乾燥や皮脂の過剰分泌などは、頭皮環境を悪化させて毛穴の詰まりや炎症を引き起こす場合があります。
また、頻繁なカラーリングやパーマ、強い力でのブラッシング、ポニーテールなど髪を強く引っ張る髪型も頭皮や毛根に負担をかけ、抜け毛や薄毛を助長する可能性があります。
分け目は紫外線の影響をとくに受けやすく、頭皮ダメージが蓄積しやすい部位です。
これって薄毛?セルフチェックの方法
「もしかして薄毛が始まっているのでは?」と不安に感じたら、まずはご自身の髪や頭皮の状態を客観的にチェックしてみましょう。いくつかのポイントを確認すると、早期に変化に気づけるでしょう。
つむじ周りのチェックポイント
つむじは元々地肌が見えやすい部分ですが、以前と比較して地肌の見える範囲が広がっていないかを確認します。
鏡を使って、つむじ周辺の髪の密度や地肌の透け具合を観察しましょう。
つむじが複数ある方や流れが複雑な方は判断が難しい場合もありますが、「以前よりも地肌が目立つようになった」と感じる場合は注意が必要です。
分け目のチェックポイント
いつも同じ位置で髪を分けている方は、その分け目が太くなってきていないか、地肌が目立つようになっていないかを確認します。
分け目部分の髪の毛が細くなっていたり、地肌の色が赤っぽくなっていたりするときも、頭皮環境が悪化しているサインかもしれません。
時々分け目を変えてみるのも、状態を確認する一つの方法です。
頭頂部全体のチェックポイント
つむじや分け目だけでなく、頭頂部全体のボリューム感も確認しましょう。
鏡で真正面から見たときや横から見たときに、以前よりも髪がぺたんとして地肌が透けて見える感じがしないか、髪全体のハリやコシが失われていないかをチェックします。
手で触ったときの感触の変化も参考になります。
頭皮の状態も確認
| チェック項目 | 観察ポイント | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 頭皮の色 | 健康な状態は青白い、赤みや黄色みがないか | 赤みは炎症、黄色みは血行不良の可能性 |
| 頭皮の硬さ | 指で動かしてみて、硬すぎたりしないか | 硬い場合は血行不良の可能性 |
| フケ・かゆみ | 乾燥や過剰な皮脂、炎症がないか | 頭皮環境の悪化 |
抜け毛の本数や質の変化
一日に抜ける髪の毛は通常50本から100本程度と言われていますが、これを正確に数えるのは困難です。シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が急に増えたと感じる場合は、注意が必要です。
また、抜けた毛の中に細く短い毛や毛根部分が細くなっている毛が多く含まれているときも、ヘアサイクルが乱れている可能性があります。
部位別|自分でできる薄毛対策と注意点
つむじや分け目、頭頂部の薄毛が気になり始めた段階で、ご自身でできる対策もあります。
ただし、セルフケアには限界がある点も理解しておく必要があります。
つむじ周りのケア
つむじ周りの薄毛が気になる場合、頭皮の血行促進が重要です。指の腹を使って優しくマッサージを行いましょう。力を入れすぎず、頭皮全体を動かすようなイメージで行います。
また、髪型を工夫して、つむじ部分が目立たないようにカバーするのも一時的な対策として有効です。
分け目を目立たなくする工夫
いつも同じ分け目にしているとその部分の頭皮に負担がかかりやすく、紫外線の影響も受けやすくなります。
定期的に分け目を変えると、負担を分散させられます。また、分け目部分にボリュームが出るようなスタイリング剤を使用したり、ドライヤーのかけ方を工夫したりするのも良いでしょう。
頭頂部全体の頭皮ケア
頭頂部全体の薄毛には、総合的な頭皮環境の改善が必要です。
まず、ご自身の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合ったシャンプーを選び、正しい方法で洗髪するのが基本です。洗いすぎや熱すぎるお湯は避け、しっかりとすすぎましょう。
洗髪後は、ドライヤーで頭皮までしっかり乾かすのも大切です。
正しいシャンプーの方法
| 流れ | ポイント |
|---|---|
| 予洗い | ぬるま湯で髪と頭皮の汚れを十分に洗い流す。 |
| 泡立て | シャンプーを手のひらでよく泡立てる。 |
| 洗う | 指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗う。爪を立てない。 |
| すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧にすすぐ。 |
セルフケアの限界と注意点
育毛剤や発毛剤の使用も選択肢の一つですが、女性の場合は使用できる製品が限られていることや、効果には個人差があることを理解しておく必要があります。
また、マッサージやヘアケアの改善はあくまで頭皮環境を整えるための補助的な手段であり、薄毛の根本的な原因によってはセルフケアだけでは改善が難しい場合も多くあります。
自己判断でケアを続けていても改善が見られない、あるいは症状が悪化するようなときは、早めに専門医に相談すると良いです。
食生活で髪を育む|摂取したい栄養素
髪の毛は、私たちが日々摂取する栄養素から作られています。健やかな髪を育むためには、バランスの取れた食事が欠かせません。
タンパク質の重要性
髪の毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。そのため、良質なタンパク質の十分な摂取が、丈夫な髪を作るための基本となります。
肉や魚、卵や大豆製品、乳製品などの様々な食品からバランス良くタンパク質を摂ることを心がけましょう。
亜鉛の役割
亜鉛は、タンパク質を髪の毛(ケラチン)に合成する際に必要なミネラルです。亜鉛が不足すると髪の成長が妨げられる可能性があります。
亜鉛は牡蠣やレバー、牛肉(赤身)やナッツ類などに多く含まれています。
ただし、亜鉛は吸収されにくい栄養素でもあるため、ビタミンCやクエン酸を多く含む食品と一緒に摂ると吸収率が高まります。
髪の成長に関わる主なミネラル
| ミネラル | 主な役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| 鉄分 | 毛母細胞への酸素供給を助ける | レバー、赤身肉、ほうれん草、小松菜 |
| 銅 | メラニン色素生成に関与、鉄分の吸収補助 | レバー、牡蠣、ナッツ類、大豆 |
ビタミンB群の効果
ビタミンB群は、エネルギー代謝や細胞の新陳代謝に関わる重要な栄養素です。
ビタミンB2は皮脂の分泌を調整し頭皮環境を整える働き、ビタミンB6はタンパク質の代謝を助け髪の毛の生成をサポートする働きがあります。ビオチン(ビタミンB7)も髪の健康維持に関与すると言われています。
ビタミンB群は豚肉やレバー、魚介類や卵、緑黄色野菜や玄米などに多く含まれています。
バランスの取れた食事の基本
特定の栄養素だけを偏って摂取するのではなく、主食、主菜、副菜を揃えて様々な食品から栄養素をバランス良く摂取する工夫が大切です。
無理なダイエットは栄養不足を招き、髪にも悪影響を及ぼす可能性があります。規則正しい時間によく噛んで食べる心がけも栄養の吸収を高める上で重要です。
生活習慣を見直して薄毛を予防・改善
健やかな髪を育むためには、食生活だけでなく、生活習慣全体の見直しが大切です。
睡眠やストレス、運動や嗜好品などが、髪の健康に影響を与える可能性があります。
質の高い睡眠の確保
髪の成長には、成長ホルモンの分泌が欠かせません。成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。
睡眠不足や質の低い睡眠は成長ホルモンの分泌を妨げ、髪の成長サイクルを乱す原因となります。
毎日決まった時間に就寝・起床し、十分な睡眠時間を確保するよう心がけましょう。寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は睡眠の質を低下させる可能性があるため、控えるのが望ましいです。
ストレス管理
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて血行不良を引き起こすケースがあります。
頭皮への血流が悪くなると髪に必要な栄養や酸素が届きにくくなり、抜け毛や薄毛の原因となる可能性があります。
自分に合ったリラックス方法を見つけ、ストレスを溜め込まないように工夫すると良いです。趣味の時間を持つ、軽い運動をする、友人と話すなど気分転換を図りましょう。
適度な運動のすすめ
ウォーキングやジョギング、ヨガなどの適度な運動は全身の血行を促進し、ストレス解消にも役立ちます。血行が改善されれば頭皮にも栄養が行き渡りやすくなり、健やかな髪の成長をサポートできます。
ただし、激しい運動はかえって活性酸素を増やして体に負担をかける可能性もあるため、無理のない範囲で継続できる運動を選びましょう。
生活習慣と髪の健康の関係
| 生活習慣 | 良い影響 | 悪い影響 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 成長ホルモン分泌促進、細胞修復 | 成長ホルモン分泌抑制、血行不良、ストレス増加 |
| ストレス管理 | 自律神経安定、血行促進 | 自律神経の乱れ、血行不良、ホルモンバランスの乱れ |
| 運動 | 血行促進、ストレス解消、代謝アップ | 過度な運動は活性酸素増加の可能性 |
| 喫煙・飲酒 | (特になし) | 血行不良、栄養吸収阻害、肝機能低下 |
喫煙・過度な飲酒の影響
喫煙は血管を収縮させ、血行を悪化させる大きな要因の一つです。頭皮の血流が悪くなれば、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなります。
また、タバコに含まれるニコチンは、ビタミンCなどの栄養素を破壊するとも言われています。
過度な飲酒も、肝臓に負担をかけて髪の毛の主成分であるタンパク質の合成を妨げる可能性があります。髪の健康のためには、禁煙し、飲酒は適量を守るのが望ましいです。
専門クリニックでの薄毛治療という選択肢
セルフケアで改善が見られない場合や薄毛が進行していると感じる場合は、専門のクリニックに相談することを検討しましょう。
女性の薄毛治療を専門に行うクリニックでは、原因を特定して一人ひとりに合った治療法を提案してくれます。
クリニックでの検査・診断
クリニックでは、まず問診で生活習慣や既往歴、家族歴などを詳しく伺います。次に、視診や触診で頭皮や髪の状態を確認し、マイクロスコープなどを用いて毛穴の状態や髪の太さなどを詳細に観察します。
必要に応じて血液検査を行い、ホルモンバランスの乱れや貧血、甲状腺機能などの全身的な要因がないかを確認する場合もあります。
これらの検査結果をもとに、薄毛の原因を診断します。
クリニックで行われる主な検査
- 問診
- 視診・触診
- マイクロスコープ検査
- 血液検査
女性向け薄毛治療の種類
女性の薄毛治療には、いくつかの選択肢があります。原因や症状の程度、患者さんの希望に合わせて、単独または複数の治療法を組み合わせて行います。
代表的な治療法としては、ミノキシジルなどの外用薬やスピロノラクトンなどの内服薬、髪の成長に必要な栄養素を補うサプリメントや頭皮に直接薬剤を注入するメソセラピー、低出力レーザー治療などがあります。
女性の薄毛治療の選択肢
| 治療法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 外用薬(ミノキシジル) | 毛母細胞を活性化し発毛を促す塗り薬 | 比較的始めやすい、継続が必要 |
| 内服薬(処方薬) | ホルモンバランス調整や血行促進などを目的とする飲み薬 | 医師の処方が必要、副作用の可能性 |
| メソセラピー | 薬剤や成長因子を頭皮に直接注入する治療 | より直接的な効果を期待、複数回必要 |
| 低出力レーザー治療 | 頭皮の血行促進や細胞活性化を促すレーザー照射 | 痛みがない、通院が必要 |
治療のメリットとデメリット
専門クリニックでの治療のメリットは、医師の診断に基づいた適切な治療を受けられる点です。
原因に応じた働きかけにより、セルフケアよりも効果を実感しやすいです。また、治療の経過を医師が定期的に確認するため、安心して治療を進められます。
一方、デメリットとしては、治療によっては費用がかかること、効果が現れるまでに時間がかかる場合があること、治療法によっては副作用のリスクがあることなどが挙げられます。
クリニック選びのポイント
女性の薄毛治療を専門としているクリニックを選ぶことが重要です。女性の治療実績が豊富か、どのような治療法を提供しているかをウェブサイトなどで確認しましょう。
また、カウンセリングが丁寧で、治療内容や費用、リスクについて十分に説明してくれるかどうかも大切なポイントです。
複数のクリニックでカウンセリングを受けて比較検討するのも良いでしょう。プライバシーへの配慮がされているかも確認しておくと安心です。
よくある質問
女性の薄毛治療に関して、患者さんからよく寄せられるご質問にお答えします。
- Q治療はどのくらいの期間が必要ですか?
- A
薄毛治療の効果が現れるまでには個人差がありますが、一般的には早くても3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。
ヘアサイクル(髪の毛が生え変わる周期)に合わせて効果が徐々に見えてくるため、根気強く治療を継続しましょう。
治療効果の判定や治療方針の見直しのため、定期的な通院が必要になります。
- Q費用はどのくらいかかりますか?
- A
治療費用は選択する治療法や治療期間、クリニックによって大きく異なります。
一般的に、内服薬や外用薬による治療は比較的費用を抑えやすい傾向にありますが、メソセラピーやレーザー治療などはより高額になる場合があります。
多くの薄毛治療は自由診療(保険適用外)となるため、カウンセリングの際に総額でどの程度の費用がかかるのか、支払い方法なども含めて、しっかりと確認すると良いです。
- Q副作用はありますか?
- A
どのような治療法でも、副作用のリスクはゼロではありません。例えば、ミノキシジル外用薬では頭皮のかゆみやかぶれ、初期脱毛(治療開始後に一時的に抜け毛が増える現象)などが報告されています。
内服薬の場合は、薬剤の種類によってむくみや動悸、肝機能への影響などが考えられます。メソセラピーでは、注入時の痛みや赤み、内出血などが起こる可能性があります。
治療を開始する前に医師から考えられる副作用について十分に説明を受け、理解しておくことが大切です。
- Q男性用の育毛剤は使ってもいいですか?
- A
男性用の育毛剤の中には、女性の使用が推奨されていない成分が含まれている場合があります。
特にフィナステリドやデュタステリドといった成分は、男性型脱毛症(AGA)の治療薬として用いられますが、女性(特に妊娠中の女性)には禁忌とされています。
自己判断で男性用製品を使用するのは避け、必ず医師に相談するか、女性向けに開発された製品を使用するようにしてください。
参考文献
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.
SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.
STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21: 69-84.
KANG, Hoon, et al. The changing patterns of hair density and thickness in South Korean women with hair loss: clinical office‐based phototrichogram analysis. International Journal of dermatology, 2009, 48.1: 14-21.
LE FLOC’H, Caroline, et al. Effect of a nutritional supplement on hair loss in women. Journal of cosmetic dermatology, 2015, 14.1: 76-82.