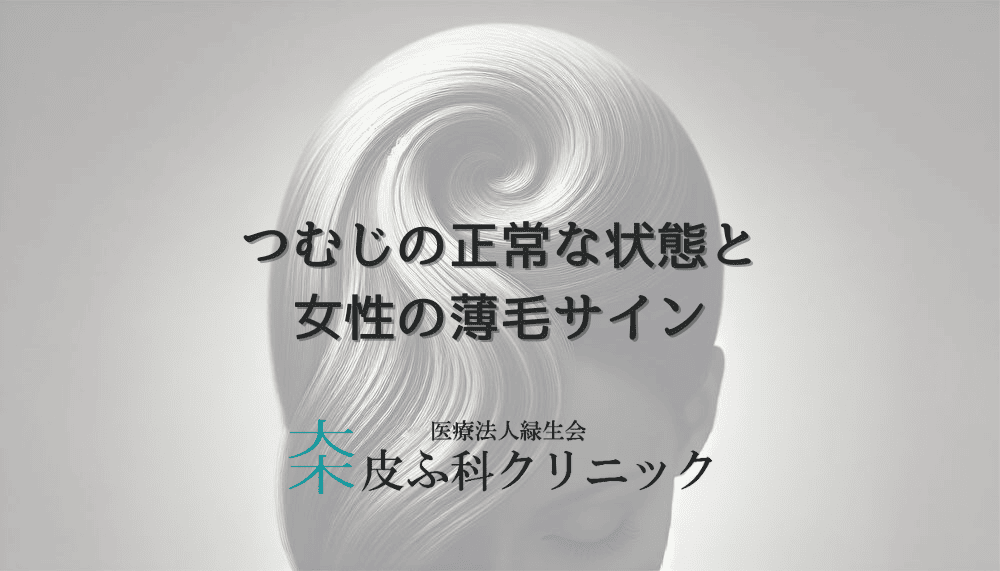つむじの状態がいつもと違う気がする、地肌が透けて見えるようになった気がする、と感じる女性が増えているようです。
つむじは頭皮の中でも特に目が行きやすい部分であり、その変化は薄毛のサインではないかと心配になる方も多いでしょう。
この記事では、つむじの正常な状態とはどのようなものかを解説し、女性特有の薄毛のサインや対策について詳しくお伝えします。
正常なつむじとは?基本的な見分け方
まず、ご自身のつむじが健康な状態なのかどうかを知ることが大切です。ここでは、正常なつむじの基本的な特徴について解説します。ポイントを押さえて、ご自身のつむじをチェックしてみましょう。
つむじの位置と数
つむじは、毛髪が渦を巻くように生えている部分です。多くの人は頭頂部に1つですが、まれに2つ以上ある人や頭頂部以外の場所にある人もいます。
つむじの数や位置には個人差があり、1つだから正常、2つだから異常というわけではありません。大切なのは、以前と比べてその状態が変化していないかという点です。
正常なつむじの毛流れ
健康なつむじは、毛髪が一定の方向に向かってはっきりとした渦巻き模様を描いています。
右巻きか左巻きかは人によって異なりますが、毛流れが自然で、髪の毛が根元から立ち上がっているのが特徴です。
毛流れが乱れていたり、ペタッと寝てしまっていたりする場合は、髪のハリやコシが失われているサインかもしれません。
正常な地肌の色と透け具合
つむじ部分は髪の毛が渦を巻いているため、他の部分に比べて地肌が見えやすいのが普通です。正常な状態であれば地肌は青白い色か、ややピンクがかった健康的な色をしています。
地肌が赤みを帯びていたり、黄色っぽくくすんでいたりするときは、炎症や血行不良の可能性があります。
また、以前よりも明らかに地肌の見える範囲が広がっている、透け感が強くなっていると感じる場合は注意が必要です。
正常なつむじの特徴まとめ
| 特徴 | 正常な状態 | 注意が必要な状態 |
|---|---|---|
| 地肌の色 | 青白い、または健康的なピンク色 | 赤みがある、黄色っぽい、茶色がかっている |
| 透け具合 | ある程度地肌が見えるのは自然 | 以前より明らかに地肌が目立つ、範囲が広い |
| 毛流れ | はっきりとした渦巻き、根元から立ち上がりがある | 渦が不明瞭、髪が寝ている |
髪の毛の太さと密度
正常なつむじ周りの髪の毛は、他の部分と同様にある程度の太さと密度があります。髪の毛1本1本にハリやコシがあり、密集して生えている状態が理想です。
つむじ部分だけ髪の毛が細くなっている、あるいは生えている本数が減って密度が低くなっていると感じるときは、薄毛が進行している可能性があります。
指で触ってみて、以前との感触の違いを確認するのも有効です。
女性のつむじ周辺に起こりやすい薄毛のサイン
つむじは薄毛のサインが現れやすい部位の一つです。特に女性の場合、男性とは異なるパターンで薄毛が進行することがあります。
つむじ周りの地肌が以前より目立つ
最も分かりやすいサインの一つが、つむじ周辺の地肌が以前よりも目立つようになることです。
つむじの正常な状態と比べて、「明らかに地肌が見える範囲が広がった」「光が当たると地肌がキラキラ反射するようになった」と感じる場合、髪の毛の密度が低下している可能性があります。
これは、髪の毛が細くなったり、本数が減ったりしているのが原因と考えられます。
つむじの渦がはっきりしなくなった
健康なつむじははっきりとした渦巻き模様をしていますが、薄毛が進行すると渦がぼやけて不明瞭になるケースがあります。
髪の毛のハリやコシが失われて1本1本が細くなり、毛流れが乱れてきれいな渦を形成できなくなるためです。つむじの形が以前と比べて曖昧になったと感じたら、注意が必要です。
女性の薄毛のサイン(つむじ周辺)
| サイン | 具体的な変化 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 地肌の目立ち | 以前より地肌が透けて見える、見える範囲が広がった | 髪の密度の低下、髪の細毛化 |
| つむじの渦の不明瞭 | 渦巻き模様がぼやけてきた、形がはっきりしない | 髪のハリ・コシ低下、毛流れの乱れ |
| 髪のボリュームダウン、細毛化 | つむじ周りの髪が細くなった、ペタッとする | 髪の成長サイクルの乱れ、栄養不足 |
| 分け目の広がり(つむじ周辺から始まる場合) | つむじから繋がる分け目が太くなったように見える | びまん性脱毛症の初期症状の可能性あり |
つむじ部分の髪の毛が細くなった、ボリュームが減った
つむじ周りの髪の毛を触ってみて、以前よりも細くなった、あるいは全体的にボリュームが減ってペタッとした感じがする場合も薄毛のサインと考えられます。
髪の毛が十分に成長できずに細いままであったり、成長期が短くなって早く抜け落ちてしまったりするのが原因です。髪質の変化は、薄毛の初期段階で見られることが多い特徴です。
分け目が広がってきたように感じる
女性の薄毛は頭部全体が均等に薄くなる「びまん性脱毛症」が多いですが、中にはつむじや分け目から薄毛が目立ち始めるケースもあります。
つむじから前頭部に向かう分け目が以前よりも太く地肌が目立つようになったと感じるときは、つむじ周辺の薄毛が進行している可能性があります。
なぜ女性のつむじは薄くなりやすい?考えられる原因
女性のつむじ部分の薄毛には、男性とは異なる女性特有の原因が関わっています。その背景を理解すると、ご自身に合った対策を見つけやすくなります。
加齢による変化
年齢を重ねると、誰でも髪の毛を作る毛母細胞の働きが徐々に低下していきます。これにより、髪の毛の成長期が短くなり、太く長く成長する前に抜け落ちてしまうことが増えます。
また、髪の毛自体も細くなり、ハリやコシが失われがちです。これらの変化がつむじ周りのボリュームダウンや地肌の透け感につながります。
ホルモンバランスの乱れ(妊娠・出産・更年期など)
女性ホルモンのなかでもエストロゲンは髪の毛の成長を促進し、成長期を維持する働きがあります。
しかし、妊娠・出産後や更年期、あるいは過度なダイエットやストレス、婦人科系の疾患などによってホルモンバランスが乱れるとエストロゲンの分泌量が減少し、相対的に男性ホルモンの影響が強まりやすいです。
これにより髪の成長サイクルが乱れ、抜け毛が増えたり髪が細くなったりして、つむじの薄毛を引き起こす場合があります。
ホルモンバランスが乱れる主な要因
- 妊娠・出産
- 更年期
- 過度なダイエット
- 強いストレス
- 睡眠不足
- 婦人科系の疾患(多嚢胞性卵巣症候群など)
- 経口避妊薬(ピル)の服用中止後
生活習慣の影響(食生活・睡眠・ストレス)
健やかな髪の毛を育むためには、バランスの取れた栄養や質の高い睡眠、そしてストレスを溜め込まない生活が重要です。
食生活
髪の主成分であるタンパク質や、髪の成長を助けるビタミン、ミネラル(特に亜鉛や鉄分)が不足すると健康な髪が作られにくくなります。
インスタント食品や外食が多い、偏った食事をしている方は注意が必要です。
睡眠
髪の毛は、私たちが眠っている間に成長ホルモンが多く分泌されることで成長します。
睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられる可能性があります。
ストレス
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こすときがあります。
血行が悪くなると髪の毛を作る毛母細胞へ十分な栄養が届かなくなり、薄毛の原因となります。
生活習慣と薄毛の関係
| 生活習慣の乱れ | 髪への影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 食生活の偏り | 栄養不足(タンパク質、ビタミン、ミネラル) | バランスの取れた食事を心がける(特にタンパク質、亜鉛、鉄分) |
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下、髪の成長阻害 | 質の高い睡眠を確保する(寝る前のスマホ操作を控えるなど) |
| 過度なストレス | 自律神経の乱れ、頭皮の血行不良、栄養供給不足 | 適度な運動、趣味、リラックスできる時間を作る |
頭皮環境の問題(血行不良・皮脂バランス)
頭皮の健康状態も髪の成長に直接影響します。頭皮の血行が悪くなると、髪の毛に必要な栄養素や酸素が毛根まで届きにくくなります。
また、皮脂の分泌量が多すぎたり少なすぎたりすると、毛穴が詰まったり逆に乾燥してフケやかゆみを引き起こしたりして、頭皮環境が悪化し、薄毛につながりやすいです。
間違ったヘアケアや洗浄力の強すぎるシャンプーの使用も、頭皮環境を悪化させる一因となります。
正常なつむじと薄毛のサインを見分けるセルフチェックポイント
変化に早期に気づいて対策を始めるためには、ご自身のつむじの状態を客観的に把握することが重要です。定期的につむじを確認する習慣をつけましょう。
鏡を使った確認方法
手鏡と洗面台などにある大きな鏡を組み合わせて、つむじの状態を確認します。明るい場所で、頭頂部がはっきりと見えるように手鏡を調整しましょう。
つむじの正常な状態と比較して、地肌の見える範囲や地肌の色、髪の毛の太さや密度、毛流れなどを観察します。
毎回同じような明るさ、同じ角度から見るようにすると、変化に気づきやすいです。
写真を使った比較方法
スマートフォンのカメラなどを利用して定期的に自分のつむじの写真を撮影し、記録しておくのも有効な方法です。
同じ角度、同じ照明条件下で撮影し、数ヶ月前や半年前の写真と比較してみましょう。
客観的な比較ができるため、わずかな変化も見逃しにくくなります。家族や友人に撮影してもらうのも良いでしょう。
セルフチェックのポイント
| チェック項目 | 確認方法 | 注目する点 |
|---|---|---|
| 地肌の見え方 | 鏡、写真 | 以前と比べて透け感が強くなっていないか、地肌の見える範囲が広がっていないか |
| 地肌の色 | 鏡 | 健康的な青白い色か、赤みや黄色っぽさがないか |
| 髪の太さ・密度 | 鏡、写真、指での触感 | つむじ周りの髪が細くなっていないか、密度が低下していないか、ボリュームが減っていないか |
| 毛流れ・渦 | 鏡、写真 | 渦巻きがはっきりしているか、毛流れが乱れていないか、髪が根元から立ち上がっているか |
| 抜け毛 | 枕元、排水溝、ブラッシング時 | 抜け毛の本数が増えていないか、細く短い毛が増えていないか |
指で触った感触の変化
つむじ周辺の髪の毛を指で優しくつまんでみたり、頭皮全体を触ってみたりして、以前との感触の違いを確認します。
髪の毛が細くなった、ハリやコシがなくなった、地肌が硬くなった、あるいは逆にブヨブヨした感じがするなど、指先の感覚で変化が分かりやすいです。
抜け毛の状態チェック
日常的な抜け毛の状態を確認するのも大切です。枕カバーについた抜け毛、シャンプー時の排水溝にたまる抜け毛、ブラッシングの際にブラシにつく抜け毛の本数を意識してみましょう。
1日の抜け毛の本数は50本から100本程度が正常範囲とされますが、明らかに本数が増えた場合や、細くて短い抜け毛が目立つようになった場合は注意が必要です。
つむじの薄毛が気になり始めたら取るべき対策
進行を食い止めて改善につなげるためには、つむじ周りの変化に気づいたら、早めに対策を始めるのが鍵です。
特別な治療を始める前に、まずは日常生活の中でできることを見直してみましょう。
生活習慣の見直し(食事・睡眠・ストレス管理)
髪の健康は、体全体の健康と密接に関係しています。まずは、日々の生活習慣の見直すから始めましょう。
食事
髪の主成分である良質なタンパク質(肉、魚、大豆製品、卵など)をしっかり摂取します。
加えて、髪の成長をサポートするビタミン(特にビタミンB群、C、E)やミネラル(亜鉛、鉄分)を多く含む食品(緑黄色野菜、果物、ナッツ類、海藻類など)をバランス良く取り入れましょう。
睡眠
質の高い睡眠を十分にとることを心がけてください。毎日同じ時間に寝起きするなど、規則正しい生活リズムを作るのも大切です。
寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用は、睡眠の質を低下させる可能性があるため控えましょう。
ストレス管理
自分に合ったストレス解消法を見つけ、溜め込まないようにしましょう。
適度な運動や趣味に没頭する時間、友人や家族との会話やゆっくり入浴するなど、リラックスできる時間を作ると良いです。
日常でできる対策(食事・睡眠・ストレス)
| カテゴリ | 具体的な対策 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 食事 | タンパク質、ビタミン、ミネラルのバランスが良い食事 | 髪の毛の材料供給、成長促進 |
| 睡眠 | 6時間以上の質の高い睡眠、規則正しい生活リズム | 成長ホルモンの分泌促進、細胞修復 |
| ストレス | 適度な運動、趣味、リラックスできる時間の確保、ポジティブな思考 | 自律神経の安定、血行促進、ホルモンバランスの調整 |
頭皮ケアの見直し(シャンプー・マッサージ)
健やかな髪を育むためには、頭皮環境を整える取り組みも欠かせません。
シャンプー
自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選びましょう。洗浄力が強すぎるものは必要な皮脂まで奪い、頭皮を乾燥させる可能性があります。
アミノ酸系など、マイルドな洗浄成分のものを選ぶのがおすすめです。洗髪時は爪を立てずに指の腹で優しく洗い、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流してください。
頭皮マッサージ
頭皮マッサージは血行を促進し、毛根への栄養供給を助ける効果が期待できます。指の腹を使って、頭皮全体を優しく揉みほぐしましょう。リラックス効果もあります。
ただし、強くこすりすぎると頭皮を傷つける可能性があるので注意が必要です。
頭皮ケアのポイント
- 適切なシャンプー選び
- 正しい洗髪方法
- 頭皮マッサージの習慣化
- 紫外線対策(帽子や日傘の使用)
ヘアスタイルの工夫
薄毛が気になる部分をカバーするヘアスタイルを工夫するのも一つの方法です。
例えば、分け目を変えてみる、トップにボリュームが出るようにパーマをかける、髪を短めにカットするなど、美容師さんに相談してみると良いでしょう。
ただし、髪を強く引っ張るようなヘアスタイル(ポニーテールなど)は、牽引性脱毛症の原因になることがあるため避けるようにしましょう。
育毛剤・発毛剤の使用検討
セルフケアだけでは改善が見られない場合、市販の女性用育毛剤や発毛剤の使用を検討するのも選択肢の一つです。
育毛剤は主に頭皮環境を整え、抜け毛を予防する効果が期待できます。一方、発毛剤には、毛母細胞に働きかけて発毛を促す成分(ミノキシジルなど)が含まれているものがあります。
ただし、効果には個人差があり、副作用のリスクもゼロではありません。使用前には説明書をよく読み、可能であれば専門医に相談することをおすすめします。
女性の薄毛治療専門クリニックでの取り組み
セルフケアを続けても改善が見られないときや、原因を特定してより効果的な治療を受けたいときは、女性の薄毛治療を専門とするクリニックへの相談を検討しましょう。
専門医による診断に基づいた、適切な治療を受けられます。
専門医による診断の重要性
自己判断で薄毛の原因を特定するのは困難です。女性の薄毛には、ホルモンバランスの乱れや内科的な疾患、皮膚疾患などさまざまな要因が考えられます。
クリニックでは問診や視診、血液検査やマイクロスコープによる頭皮チェックなどを行い、薄毛の原因を正確に診断します。原因に応じた適切な治療法の選択が、改善への近道です。
内服薬・外用薬による治療
診断結果に基づき、医学的根拠のある治療薬が処方されます。
内服薬
スピロノラクトンなど、ホルモンバランスを整える効果が期待できる薬が用いられる場合があります。また、髪の毛の成長に必要な栄養素を補うサプリメントが処方される場合もあります。
外用薬
医療用として濃度の高いミノキシジル外用薬などが代表的です。毛母細胞を活性化させ、発毛を促す効果が期待できます。
クリニックでの主な治療法(薬物療法)
| 治療薬の種類 | 主な薬剤例 | 期待される効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 内服薬 | スピロノラクトンなど | ホルモンバランス調整、抜け毛抑制 | 医師の処方が必要、副作用の可能性 |
| 外用薬 | 高濃度ミノキシジル | 毛母細胞活性化、発毛促進 | 医師の処方が必要、初期脱毛、かぶれなどの可能性 |
| サプリメント | ビタミン、ミネラル等 | 髪の成長に必要な栄養素の補給 | 補助的な役割、過剰摂取に注意 |
注入療法(メソセラピーなど)
頭皮に直接、髪の成長に必要な有効成分(ミノキシジル、成長因子、ビタミン、ミネラルなど)を注入する治療法です。内服薬や外用薬と併用すると、より効果が期待できる場合があります。
注入療法には、注射を用いる方法や針を使わない導入機器を用いる方法などがあります。
その他の治療選択肢
上記以外にも、クリニックによっては低出力レーザー治療や、自身の血液から抽出した成分を利用するPRP(多血小板血漿)療法などを提供している場合があります。
どの治療法が適しているかは、個々の症状や原因、生活スタイルによって異なりますので、医師とよく相談して決定すると良いでしょう。
よくある質問
さいごに、つむじの薄毛に関する、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Qつむじは誰にでもあるものですか?
- A
つむじは髪の毛の生え方の癖によってできるもので、ほとんどの人にあります。通常は頭頂部に1つですが、位置や数には個人差があります。
- Qつむじの薄毛は遺伝しますか?
- A
薄毛になりやすい体質は、遺伝的要因が関与する可能性があります。
特に男性型脱毛症(AGA)では遺伝の影響が大きいとされますが、女性の薄毛(FAGA)においても遺伝的素因が関係しているケースがあります。
しかし、女性の場合はホルモンバランスや生活習慣など、後天的な要因も大きく影響するため、遺伝だけが原因とは限りません。
- Q育毛剤はいつから使うべきですか?
- A
抜け毛が増えた、髪が細くなった、地肌が透けて見えるようになったなど、薄毛のサインを感じ始めたら早めに使い始めることを検討しても良いでしょう。
育毛剤は、頭皮環境を整えて抜け毛を予防するのが主な目的です。ただし、原因や症状によっては効果が限定的な場合もあります。
本格的な発毛効果を期待する方は、医療機関で処方される発毛剤(ミノキシジルなど)の使用や、他の治療法を検討する必要があります。
- Qクリニックでの治療に保険は適用されますか?
- A
一般的に、薄毛(AGAやFAGA)の治療は生命に直接関わる病気とは見なされないため、健康保険の適用外(自由診療)です。
ただし、薄毛の原因が他の病気(甲状腺疾患など)によるものである場合は、その病気の治療に対して保険が適用されることがあります。
治療費については、カウンセリング時にクリニックへ直接確認すると良いでしょう。
参考文献
VUJOVIC, Anja; DEL MARMOL, Véronique. The female pattern hair loss: review of etiopathogenesis and diagnosis. BioMed research international, 2014, 2014.1: 767628.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
HARRIES, Matthew, et al. Towards a consensus on how to diagnose and quantify female pattern hair loss–The ‘Female Pattern Hair Loss Severity Index (FPHL‐SI)’. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2016, 30.4: 667-676.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
BHAT, Yasmeen Jabeen, et al. Female pattern hair loss—an update. Indian dermatology online journal, 2020, 11.4: 493-501.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
ANASTASSAKIS, Konstantinos; ANASTASSAKIS, Konstantinos. Female pattern hair loss. Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders, 2022, 181-203.
VISHU, Michelle. Trichoscopic Analysis of Female Pattern Hair Loss and Correlation of Findings with Disease Severity: A Cross-Sectional Study. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).