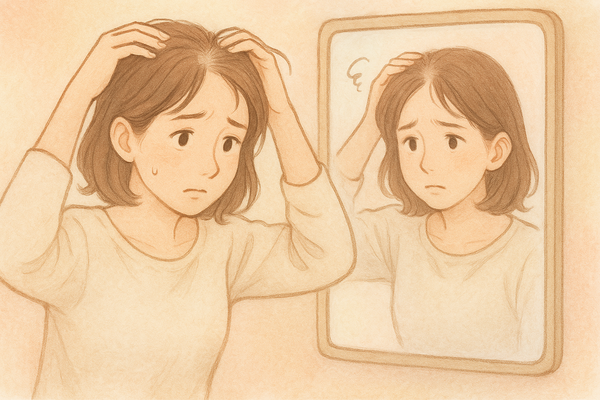近年、女性の薄毛に悩む方が増えています。男性だけでなく、20代~50代の女性でも「髪のボリュームが減った」「地肌が透けて見える」など薄毛の兆候に不安を感じることが少なくありません。
女性の薄毛は、びまん性脱毛症や女性型脱毛症(FAGA)、牽引性脱毛症など複数のタイプがあり、その原因も加齢やホルモンバランスの乱れ、ストレス、栄養不足など様々です。
本記事では、女性の薄毛についてタイプ別に原因を詳しく解説します。治療を勧める目的ではなく、情報提供として薄毛の原因を知っていただき、ご自身の髪の状態を見直す参考になれば幸いです。
| 薄毛のタイプ(脱毛症) | 主な原因(要因) |
|---|---|
| びまん性脱毛症 | ホルモンバランスの乱れ(加齢による女性ホルモン低下など)、ストレス、生活習慣の乱れ、過度なダイエット等が複合的に影響。全頭的に髪が薄くなる。 |
| 女性型脱毛症(FAGA) | 男性ホルモン(DHT)の影響によるもの。加齢や更年期に伴うエストロゲン低下、遺伝的要因、ストレス等が誘因となり、頭頂部を中心に髪が細くコシがなくなる。 |
| 牽引性脱毛症 | ポニーテール等、長期間にわたる強いヘアスタイルの牽引(引っぱり)による毛根への物理的ダメージ。生え際や分け目を中心に脱毛が起こる。 |
| 円形脱毛症 | 自己免疫の異常によって毛根が攻撃されることが原因。誘因として強い精神的ストレスや疲労、アレルギー体質、遺伝的素因などが考えられる。 |
| 産後脱毛(分娩後脱毛症) | 妊娠・出産に伴うホルモンバランスの急激な変化(エストロゲンの急低下)が主因。出産後数か月で抜け毛が増える。 |
| 休止期脱毛症 | 強い心身のストレス(手術・高熱・過労・精神的ショックなど)、急激なホルモン変化(産後など)、栄養不足、疾患や薬剤などにより髪が成長を止め休止期に入り抜ける。 |
| 栄養不足による脱毛 | 鉄分・タンパク質・亜鉛など髪の成長に必要な栄養素の不足。過度なダイエットや偏食が背景にあることが多い。 |
| 甲状腺疾患による脱毛 | 甲状腺ホルモンの分泌異常(機能低下症・亢進症)。代謝の乱れにより髪の成長サイクルが乱れ抜け毛が増える。 |
| 更年期による脱毛 | 更年期に入ると女性ホルモン(エストロゲン)が減少し、相対的に男性ホルモンの影響が強まることで薄毛が進行する。 |
まずは上記のような主なタイプ別に、それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。
びまん性脱毛症の原因

びまん性脱毛症とは、頭部全体の髪の毛が均一に薄くなる脱毛症です。分け目だけでなく髪全体のボリュームが減って地肌が透けて見えるのが特徴で、特に女性に多く見られます。
びまん性脱毛症は一つの原因ではなく様々な要因が絡み合って起こることが多く、生活習慣の影響も大きいです。このセクションでは、びまん性脱毛症を引き起こす主な原因を解説します。
ホルモンバランスの乱れ(加齢による変化)
女性の薄毛原因としてまず挙げられるのがホルモンバランスの乱れです。とくに加齢に伴う女性ホルモン(エストロゲン)の低下は大きな影響を与えます。
エストロゲンには髪の成長期を維持し、髪を太く長く育てる作用があります。しかし、年齢を重ね閉経が近づくとエストロゲン分泌量が減少し、その結果髪の成長サイクルが短縮して休止期に入る毛が増え、髪が細く短いまま抜けやすくなってしまいます。

加齢によるこうしたホルモン変化が、びまん性脱毛症の大きな原因となります。また、エストロゲン低下に伴い相対的に男性ホルモンの影響が強くなることで、後述するFAGA(女性男性型脱毛症)に似た脱毛が進行する場合もあります。
ストレスや自律神経の乱れ
ストレスもびまん性脱毛症の大きな誘因です。精神的・肉体的ストレスがかかると自律神経のバランスが崩れ、頭皮の血行不良やホルモン分泌の乱れを招きます。
過度なストレス状態では頭皮の毛細血管が収縮し、髪を作る毛母細胞への栄養供給が滞ります。その結果、髪が十分育たないまま抜けてしまい、全体的なボリュームダウンにつながります。
現代社会はストレス要因が多く、仕事や人間関係、睡眠不足など日々の積み重ねが薄毛の原因になり得ます。ストレスそのものは避けにくいですが、上手に発散し溜め込まない工夫が髪の健康にも大切です。

間違ったヘアケア・頭皮へのダメージ
日々のヘアケアやスタイリングの仕方も、びまん性脱毛症に影響します。例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーでゴシゴシ洗ったり、過度なブリーチやパーマを繰り返したりすると、頭皮や毛髪にダメージを与えます。
頭皮が炎症を起こしたり乾燥したりすると、健康な髪が育ちにくくなり抜け毛が増える原因になります。また、きついポニーテールなどで常に髪を強く引っ張っていると(これについては後述の牽引性脱毛症で詳しく説明します)、毛根に負担がかかって髪が抜けやすくなります。
このように不適切なヘアケアや美容習慣による頭皮環境の悪化も、髪全体のボリューム低下を招く一因です。
生活習慣の乱れ(睡眠不足・栄養不足など)
生活習慣の乱れも髪の健康に深く関わります。例えば、睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減り、髪の成長が阻害されます。髪は夜間に成長しますので、十分な睡眠が取れない生活は薄毛を進行させる恐れがあります。
また、偏った食生活や無理なダイエットによる栄養不足も髪に悪影響を及ぼします。髪の主成分であるケラチンはタンパク質でできており、生成には鉄分や亜鉛、ビタミン類など多くの栄養素が必要です。
極端な食事制限でこれらが不足すると、身体は生命維持を優先するため髪への栄養供給が後回しになり、抜け毛が増えてしまいます(栄養不足による脱毛については後述の章で詳しく触れます)。
その他、喫煙や運動不足も血流を悪化させ髪に栄養が届きにくくなるため、びまん性脱毛症の原因になり得ます。髪のためには規則正しい生活とバランスの良い食事が基本となります。
女性型脱毛症(FAGA)の原因
女性型脱毛症(Female Androgenetic Alopecia:FAGA)は、女性の薄毛の中でもホルモン要因と遺伝要因が大きく関与するタイプです。
男性のAGA(男性型脱毛症)と同様に、ホルモン由来の脱毛メカニズムで起こりますが、発症時期や症状の出方に男女差があります。FAGAでは主に頭頂部の髪が細く弱くなり、地肌が透けて見えるようになります。
この章では、FAGAの原因となるメカニズムや誘因について詳しく説明します。
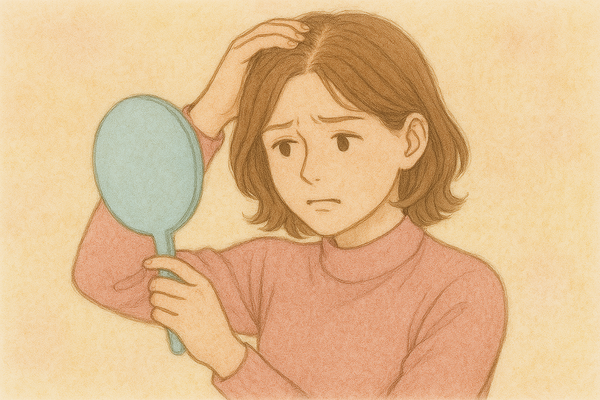
DHT(ジヒドロテストステロン)による脱毛メカニズム
FAGAの直接的な原因は、男性ホルモン由来の物質DHT(ジヒドロテストステロン)の作用です。女性の体内にも男性ホルモンは少量ながら存在し、5αリダクターゼという酵素によってテストステロンがDHTに変換されます。
DHTが毛根の毛乳頭細胞に作用すると、髪に「成長を止めて抜けなさい」という信号を与えてしまいます。その結果、髪の成長期が短くなり、十分成長しないまま抜けてしまうのです。
このメカニズム自体は男性のAGAと全く同じですが、女性の場合はエストロゲン(女性ホルモン)の減少が引き金となってDHTの影響を受けやすくなる点が異なります。
特に40代以降の更年期にかけてエストロゲンが減ってくると、相対的に男性ホルモンの作用が強まりFAGAを発症しやすくなります。
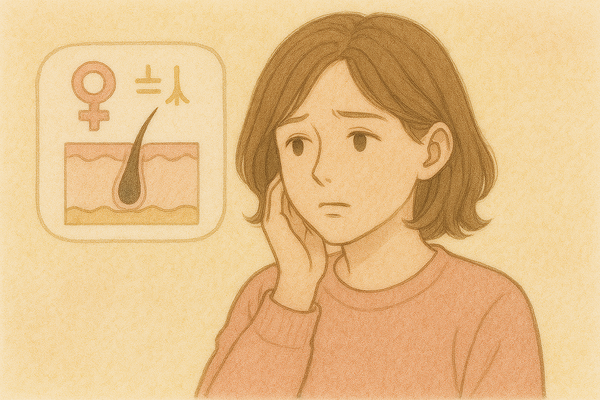
以下の表は、男性型脱毛症(AGA)と女性型脱毛症(FAGA)の比較です。男女ともDHTが毛根に作用して脱毛が起こる点は共通していますが、女性では閉経前後のエストロゲン低下が発症の引き金になります。
| 男性型脱毛症(AGA) | 女性型脱毛症(FAGA) | |
|---|---|---|
| 主な原因 | 男性ホルモン(テストステロン)がDHTに変換され毛根に作用(ホルモン要因・遺伝要因) | 男性ホルモン(DHT)の作用+女性ホルモン低下(ホルモン要因・遺伝要因) |
| 発症しやすい時期 | 思春期以降~30代に発症が多い(男性ホルモン増加に伴う) | 40~50代に発症が多い(更年期以降エストロゲン低下に伴う) |
| 脱毛の部位 | 前頭部の生え際や頭頂部が局所的に薄くなる | 頭頂部を中心に髪全体が薄くなる(びまん性に脱毛) |
| 進行の特徴 | 放置すると前髪の生え際が後退し、頭頂部の地肌も広範囲に露出する | 毛髪密度の低下・軟毛化がゆっくり進行(急激なツルツルの禿げにはならない) |
| その他 | 遺伝的要因が強い(家系に薄毛男性がいると発症リスク高) | 遺伝に加え、ストレスや栄養不足など生活習慣も影響しうる |
男性は生え際や頭頂部から脱毛が始まるのに対し、女性は頭頂部中心のびまん性脱毛となる傾向があります。
エストロゲン低下(加齢・更年期)と発症リスク
上記のように、エストロゲンの減少はFAGA発症の大きな誘因です。多くの女性は閉経を挟む40代後半~50代にかけてエストロゲンが急激に減少します。
エストロゲンには髪の成長を助け抜け毛を抑える働きがありますが、それが不足すると髪は抜けやすくなります。また、エストロゲンが減ることで男性ホルモンの割合が相対的に高くなり、毛根が男性ホルモンの影響を受けやすくなります。
つまり、更年期前後にホルモンバランスが変化することでFAGAが起こりやすい土壌ができてしまうのです。実際、AGAは20~30代で発症する男性が多いのに対し、FAGAは40~50代での発症が多いという報告があります。
ただし若い方でも妊娠・出産や極度のストレス、無理なダイエットなどで一時的にエストロゲン分泌が低下すると、20~30代でもFAGA様の脱毛が起こる可能性があります。
遺伝的要因
FAGAもAGAと同様に遺伝的な要因が関与します。髪の毛のホルモン感受性や髪質、ヘアサイクルの長さなどは家族から遺伝することがあります。
特に、毛根の男性ホルモン受容体の感受性や5αリダクターゼの活性の高さといった要素は遺伝しやすいと考えられています。そのため、親族に薄毛の方がいる場合、自分も薄毛になりやすい体質を受け継いでいる可能性があります。
もっとも、女性の場合は男性ほど遺伝の影響が顕著ではなく、後述する生活習慣やストレスなど複数の要因が重なって発症に至るケースが多いとされています。
しかし「遺伝的な素因」はFAGAの下地として存在しうるため、家系的に薄毛が多い方は早めにケアを意識すると良いでしょう。
ストレス・生活習慣によるホルモン環境の変化
ストレスや不規則な生活もFAGAを誘発・悪化させる要因です。過度なストレスは女性ホルモンの分泌を低下させたり、生理不順を引き起こすことがあります。
睡眠不足や過労が続くと自律神経の乱れからホルモン分泌量に影響を及ぼし、結果としてエストロゲン低下を招く場合があります。食生活の乱れや栄養不足も体調を崩しホルモンバランスを乱す一因です。
つまり、遺伝的な素因があっても健康的な生活習慣を維持することで発症時期を遅らせたり進行を緩やかにできる可能性があります。
逆に、遺伝的素因がなくても更年期の時期にストレス過多・栄養不良の状態だとFAGAになりやすくなるかもしれません。
女性の薄毛はこうした複数の要因が絡み合うため、「遺伝だから仕方ない」とあきらめず、生活環境を整えることも大切です。
牽引性脱毛症の原因
牽引性脱毛症(けんいんせいだつもうしょう)とは、髪の毛を強く引っ張る状態が長期間続くことで起こる脱毛症です。
ポニーテールや編み込みなど、いつも決まった髪型で髪を引っ張り上げていると、生え際や分け目など特定の部位の髪に慢性的な負荷がかかります。
これにより毛根がダメージを受けたり、頭皮の血行が悪くなったりして、徐々に抜け毛が増えていきます。牽引性脱毛症は髪型の習慣が直接的な原因であり、原因が明確な分、対処や予防がしやすい特徴があります。
この章では牽引性脱毛症を引き起こす具体的な要因を説明します。

髪型による長期間の強い牽引
牽引性脱毛症の最大の原因は、髪型による物理的な引っぱりです。以下のようなヘアスタイルを長年続けていると、髪と毛根に慢性的な負担がかかります。
- ポニーテールやお団子ヘア:髪を後頭部で強く結ぶと、生え際(前頭部やこめかみ付近)の毛が常に後方へ引っぱられます。この状態が積み重なると、生え際の毛が細く弱って抜けやすくなり、額の生え際が後退したように見えてきます。
- きつい編み込み・コーンロウ:細かい三つ編みやコーンロウなど、頭皮に密着させて編む髪型は、一部の毛に強いテンション(張力)がかかります。特に分け目や編み込みのラインに沿った部分で毛が抜けやすくなります。
- エクステンションやウィッグの多用:接着型のヘアエクステや重いウィッグを日常的に使用すると、自分の髪に余計な重さや引っぱりが加わります。装着部位の毛が負荷に耐えられず抜けたり、装着箇所周辺の髪が薄くなることがあります。
- 帽子やヘアアクセサリーの締め付け:常にきつい帽子を被る習慣や、ターバン・カチューシャで強く髪を押さえつけることも、局所的な牽引ストレスとなりうるため注意が必要です。
上記のような髪型の影響で抜け毛が増えている場合、まずは髪をゆるく結ぶ、結ぶ位置を日替わりで変える、定期的に髪を下ろす日をつくるなど、物理的負担を軽減することが大切です。
毛根への慢性的なダメージ
髪が引っ張られる状態が続くことで、毛根(毛包)への慢性的なダメージが蓄積します。毛根部分には髪を作り出す毛母細胞があり、通常は毛周期に従って成長と脱毛を繰り返しています。
しかし、強い牽引力が長期間かかると毛包周囲で炎症が起きたり、変形してしまうことがあります。牽引性脱毛症の抜け毛を観察すると、毛根の先端(毛球部)に白い角化物が付着していることがあります。
これは毛根鞘が損傷して剥がれ落ちたもので、毛根がダメージを受けているサインです。毛根が傷つくと新しい髪が生えづらくなり、休止期に入ったまま発毛しない毛穴も出てきます。
こうした毛根へのダメージが蓄積すると、生え際や分け目の毛が生えなくなり薄毛が定着してしまう恐れがあります。
頭皮の血行不良
強い牽引で髪を引っ張ると、周囲の頭皮も引き伸ばされて緊張状態になります。頭皮が常に引っぱられて硬くなると、その部分の血行不良を招きます。
頭皮の毛細血管から毛根へ栄養が届きにくくなり、髪が成長期を全うできずに抜けやすくなります。特にポニーテールで引っぱられる前頭部や、編み込み箇所の頭皮は血行障害が起きやすいです。
血流が悪い状態が長く続けば、髪は細くコシがなくなり、抜け毛も増加します。牽引性脱毛症を防ぐには、髪型による直接的な引っぱりを避けることに加え、頭皮マッサージなどで血行を促進するのも効果的です。
一度ダメージを受けた毛根でも、血流が改善され栄養が行き渡れば回復が期待できます。逆に牽引をやめても血行不良が続けば、毛根の修復が進まず発毛が遅れる可能性があります。
円形脱毛症の原因
円形脱毛症は、ある日突然コインのような円形のハゲができる脱毛症です。
10円ハゲとも呼ばれ、小さな円形脱毛斑が1か所だけできる軽症から、頭髪全体が抜け落ちる重症例(汎発性脱毛症)まで様々なタイプがあります。
円形脱毛症の明確な原因は未解明な部分もありますが、現在は自己免疫疾患の一種と考えられています。
ここでは、円形脱毛症の原因として有力視されている自己免疫の仕組みや、発症のきっかけとなる要因について説明します。

自己免疫による毛包への攻撃
円形脱毛症の主因は、自己免疫異常による毛根への攻撃です。本来、免疫細胞は体内の異物やウイルス・細菌を攻撃して体を守る役割があります。しかし円形脱毛症では、何らかの誤作動で自分の毛を作る組織(毛包)を異物とみなして攻撃してしまいます。
毛包周囲にリンパ球など免疫細胞が集まって炎症を起こし、その部分の毛がポロポロと抜け落ちてしまうのです。
なぜこのような自己免疫反応が起こるのかは完全には解明されていませんが、自己免疫疾患(例えば甲状腺疾患やアトピー性皮膚炎、白斑など)を持つ方に円形脱毛症が合併しやすいことが知られています。
一種のアレルギー反応のように、自分の毛根に対して免疫が過剰反応している状態と言えます。この自己免疫反応こそが円形脱毛症の直接の原因です。
発症の誘因となるストレス
円形脱毛症は「ストレスが原因でできる10円ハゲ」とよく言われますが、厳密にはストレスは誘因であって直接の原因ではないと考えられます。
上記の通り直接の原因は自己免疫ですが、そのきっかけとして強い精神的ストレスや極度の疲労、ショックな出来事などが引き金になるケースが多く報告されています。
過労や睡眠不足など肉体的ストレスも含め、ストレス下では免疫機能に乱れが生じやすいため、円形脱毛症を誘発するのではないかと考えられます。
ただし、ストレスを全く感じていない状況でも円形脱毛症になる人もおり、逆に強いストレスを受けても円形脱毛症にならない人もいます。したがってストレスは必ずしも必要条件ではありませんが、「誘因の一つ」として無視できない要素です。
遺伝的素因や体質
円形脱毛症には遺伝的な素因も指摘されています。家族に円形脱毛症の経験者がいる場合、自分も発症しやすい傾向があるという報告があります。
また、アトピー性皮膚炎や喘息などアレルギー体質(アトピー素因)を持つ人は円形脱毛症を発症しやすいとも言われます。こうしたことから、生まれつき免疫系が過敏に反応しやすい体質の人は、何らかの契機で自己免疫反応が暴走して円形脱毛症になりやすいのではないかと推測されています。
さらに、先述の甲状腺疾患(橋本病やバセドウ病)など他の自己免疫疾患との関連も見られるため、免疫の素因が背景にあることは確かです。
ただし遺伝や体質だけでなく、環境要因(ストレスなど)も合わさって初めて発症に至ると考えられています。
その他の要因
円形脱毛症の発症メカニズムは複合的で、上記以外にも様々な要因が研究されています。
例えば、ウイルス感染やワクチン接種がきっかけで免疫異常を起こすケース、妊娠・出産によるホルモン変化で免疫バランスが変わるケースなども報告があります。
しかしいずれも限定的で、万人に共通する原因とは言えません。現状では「自己免疫の暴走」が中心にあり、それを誘発するスイッチとして精神的ストレスや体調の変化などが関与する、とまとめられます。
円形脱毛症は原因が一つではなく人それぞれ異なるため、「この脱毛は何が引き金になったのか」を振り返ってみることが再発予防に役立つかもしれません。
産後脱毛の原因
**産後脱毛(分娩後脱毛症)**は、出産を経験した女性の多くに見られる一時的な脱毛現象です。
出産後しばらくしてシャンプー時や朝の枕元に抜け毛が増え、「ごっそり抜けるので驚いた」という声もよく聞かれます。産後の抜け毛は一時的なものとはいえ、不安になる方も多いでしょう。
産後脱毛の主な原因は、妊娠前後でのホルモンバランスの劇的な変化です。この章では、産後脱毛が起こるメカニズムと、そのほか影響しうる要因について解説します。

ホルモンバランスの急激な変化
妊娠・出産に伴うホルモンバランスの変化が、産後脱毛の最大の原因です。妊娠中、女性の体内ではエストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンが通常時の数倍にも増加します。
エストロゲンには髪の成長期を長く保つ作用があるため、妊娠中は髪が抜けにくくなり、ボリュームが保たれます。しかし出産後、これらのホルモンは一気に妊娠前の水準まで低下します。
すると、それまで成長期を維持していた髪が一斉に休止期に移行し始めます。その結果、産後2~3か月頃をピークに抜け毛が増えるのです。
この現象を専門的には分娩後脱毛症と呼び、一種の休止期脱毛症(Telogen Effluvium)の一型です。下表に、妊娠中と産後のホルモン環境と髪への影響の違いをまとめました。
妊娠中と産後におけるホルモン環境と髪の変化の比較
| 状況 | ホルモン状態 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 妊娠中 | エストロゲン・プロゲステロンが高水準で分泌される(通常の数倍) | ヘアサイクルの成長期が延長され、抜け毛が減る(髪が増えたように感じる) |
| 出産直後~産後 | エストロゲン・プロゲステロンが急激に低下し元のレベルへ戻る | 成長期にあった髪が一斉に休止期へ移行するため、産後2~3か月頃に抜け毛が急増する |
この産後脱毛はホルモン変化に体が適応する過程で起こる一時的な現象であり、個人差はありますが通常は産後6か月~1年程度で落ち着きます。
髪も徐々に元のボリュームに回復していくので、過度に心配しすぎないことが大切です。
出産・育児によるストレス
産後脱毛の主因はホルモンですが、出産自体の肉体的ストレスや、出産後の生活の変化によるストレスも抜け毛を助長する可能性があります。
出産は女性の体にとって大きなダメージであり、分娩で大量に出血したり出産の痛み・疲労で体力を消耗します。こうした身体的ストレスは先述した休止期脱毛症の引き金にもなります。
また、産後は慣れない育児が始まり、授乳や夜泣き対応で慢性的な睡眠不足に陥りがちです。十分に休めない状態が続くと体の回復が遅れ、ホルモンバランスの正常化にも時間がかかるでしょう。
さらに、初めての育児による精神的ストレスやプレッシャーも加わります。これら産後の心身のストレスは単独で脱毛症を起こすほどではなくとも、ホルモン変化による抜け毛をより顕著にする一因となり得ます。
産後の抜け毛がひどいと感じるときは、できるだけ休息をとり体をいたわることも大切です。
産後の栄養不足
妊娠・出産・授乳期は女性の体から多くの栄養が使われる時期です。出産時の出血で鉄分を失ったり、母乳生産でエネルギーや栄養素の需要が増えたりします。
産後、十分に栄養を補給しないと鉄欠乏性貧血や栄養不足に陥ることがあります。鉄分やタンパク質が不足すると、髪を作る材料や酸素が毛根に行き渡らず、抜け毛が増えてしまう可能性があります。
実際、産後の女性は貧血になりやすく、それ自体が抜け毛の一因となることも知られています。また、赤ちゃんのお世話に追われて食事がおろそかになったり、産後ダイエットを急ぐあまり食事制限をすることも危険です。
産後はまず母体の回復と栄養補給が最優先ですので、バランスの良い食事を心がけましょう。栄養状態が改善すれば、ホルモン変化で一時的に抜けた髪もしっかり新生してきます。
個人差と対処
産後脱毛の程度や期間には個人差があります。全く抜け毛が気にならない人もいれば、明らかに地肌が透けるほどボリュームダウンする人もいます。
ホルモン変化の幅や、産後の体調・育児サポート状況など様々な要因が関係するため一概には言えません。
基本的には一過性で自然回復するものですが、1年以上経っても髪が回復しない場合や、抜け毛があまりにも極端に多い場合は他の薄毛要因(例えばFAGAの発症など)も考え、専門クリニックに相談すると安心です。
産後脱毛は多くのママが経験するものですので、あまり思い詰めず、可能な範囲で休養と栄養補給に努めながら経過を見守りましょう。
休止期脱毛症(テロゲン・エフルビウム)の原因
休止期脱毛症(Telogen Effluvium:テロゲン・エフルビウム)は、髪の毛の成長サイクル(ヘアサイクル)のうち休止期に入る毛髪の割合が増加することで起こる脱毛症です。

通常、人の髪の毛は全体の約10%前後が休止期にありますが、何らかのストレスや環境要因で大量の毛が一斉に休止期へ移行すると、一時的に抜け毛が増え薄毛になります。
休止期脱毛症は急性の場合と慢性の場合がありますが、その原因は実に多岐にわたり、身近な生活上の出来事から病気まで様々です。
このセクションでは、休止期脱毛症を引き起こす代表的な原因をカテゴリー別に紹介します。
休止期脱毛症を引き起こす主な原因カテゴリーと具体例
| 原因カテゴリー | 具体的な原因例 |
|---|---|
| 身体的ストレス | 高熱を伴う感染症、大手術、大きな怪我、分娩時の大量出血など、身体に強いショックを与える出来事。 |
| 精神的ストレス | 深刻な心理的ショック(身近な人の死、不慮の事故など)、極度の精神的緊張や不安状態の継続。 |
| ホルモンの急変 | 出産後のエストロゲン低下(分娩後脱毛症)、経口避妊薬の中止、更年期のホルモン変化、甲状腺ホルモン異常など。 |
| 疾患・薬剤・栄養不足 | 甲状腺機能低下症・亢進症、膠原病、腎不全、肝疾患、糖尿病など慢性疾患の影響、抗うつ薬・ビタミンA製剤など一部薬剤副作用、極端なダイエットや栄養失調、重度の貧血など。 |
上記のように、休止期脱毛症を誘発する原因は多岐にわたります。それでは各カテゴリーごとに詳しく見ていきましょう。
身体的ストレスによるもの
大きな手術を受けたり、事故で大量出血するような身体的ストレスが加わると、その直後~数か月後に一時的な脱毛が起こることがあります。
これは身体がショック状態に陥ることで生存に不必要な機能(毛の成長など)が一時停止し、多くの毛が休止期に入ってしまうためです。
具体例としては高熱を伴う重度の感染症(40℃近い高熱が出るインフルエンザや肺炎など)、大手術や大怪我(臓器手術、骨折、出産時の大量出血など)が挙げられます。
こうした出来事の2~3か月後に抜け毛が増えるのが典型で、原因となったイベントが一過性であれば脱毛も一時的でその後自然に回復することが多いです。
このタイプの休止期脱毛症は「急性休止期脱毛症」とも呼ばれ、時間経過とともに改善するケースがほとんどです。
強い精神的ストレスによるもの
肉体ではなく精神的なショックやストレスも休止期脱毛症の原因になり得ます。
たとえば愛する家族を失った悲しみ、仕事での重大なトラブルによる極度の不安、過度なプレッシャーに晒される環境など、人が受ける心理的ストレスは計り知れません。
強いストレス下では自律神経やホルモンバランスが乱れ、免疫力も低下します。その結果、髪の成長サイクルにも乱れが生じ、大量の抜け毛という形で現れることがあります。
俗に「心労で髪が一晩で真っ白になった」という話もありますが、それほど急激でなくとも数週間~数か月の強いストレス負荷が抜け毛として表面化する場合があります。
このようなケースではストレスが軽減され心身の状態が回復すれば、再び髪の成長サイクルも正常化し脱毛は止まります。大切なのはストレスを適切にケアすることで、必要ならカウンセリング等専門家の助けを借りるのも有効です。
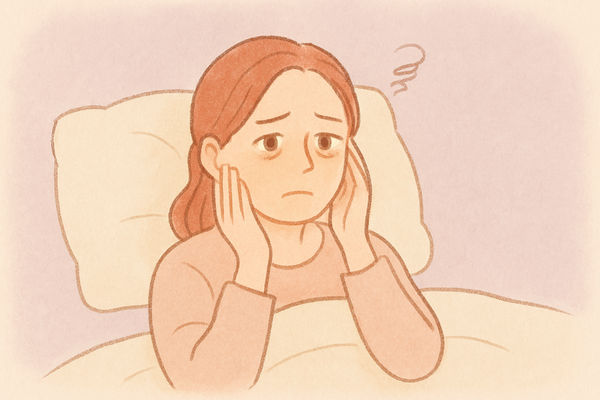
ホルモンバランスの急変によるもの
ホルモン環境の劇的な変化も休止期脱毛症を引き起こします。その代表が前述した出産後の脱毛です。産後は急激なエストロゲン低下で髪が一斉に抜ける休止期脱毛症が起こります。
同様に、経口避妊薬(ピル)の中止後に一時的な抜け毛が増えることがあります。
ピルを服用中は体が妊娠に似た状態になりエストロゲンが高めに維持されているため、中止すると産後と同じような現象が起こり得るのです。
また、甲状腺ホルモンの異常(後述する甲状腺疾患)によってもヘアサイクルが乱れ休止期毛が増加します。さらに、更年期に入って女性ホルモンが減っていく過程で一時的に抜け毛が増える人もいます。
いずれもホルモンの急激な増減が毛周期に影響を与えています。これらの場合、ホルモンバランスが安定すれば脱毛も落ち着くことが多いですが、甲状腺異常など病的な場合は適切な治療が必要です。
疾患・薬剤・栄養不足によるもの
全身性の病気や薬の副作用、栄養不足など、体内環境の変化も髪の成長を止める原因となります。
例えば、甲状腺機能障害(橋本病による機能低下症、バセドウ病による機能亢進症)は代謝異常を引き起こし、抜け毛の症状を伴いやすいです。
また膠原病(自己免疫疾患の一種)や慢性腎不全・肝障害・糖尿病など慢性的な病気では、体の恒常性が乱れるため毛周期にも影響し休止期脱毛症が起こることがあります。
休止期脱毛症を起こしやすい疾患の例:
- 甲状腺機能低下症・甲状腺機能亢進症
- 膠原病(全身性エリテマトーデスなど)
- 慢性腎不全・肝障害
- 糖尿病
- 深刻な貧血 など
また、一部の薬剤も副作用で脱毛を起こすことがあります。有名なのは抗がん剤ですが、あれは成長期の毛が抜ける「成長期脱毛(Anagen脱毛)」でメカニズムが異なります。
休止期脱毛を誘発しうる薬剤としては、ビタミンA誘導体(アキュテイン等)、抗うつ薬、抗凝固薬、降圧薬の一部などが知られています。服薬による可能性が疑われる場合は医師に相談しましょう。
さらに栄養不足も大切なポイントです。過度なダイエットや摂食障害などで栄養失調になると、休止期脱毛症が生じることがあります。
髪は生命維持に不要な組織なので、身体が飢餓状態になるとまず髪への栄養供給がカットされてしまいます。その結果、毛が成長を維持できず休止期に移行して抜け毛が増えます。
特に鉄分不足(貧血)やタンパク質不足は毛髪への影響が大きいです。この場合、栄養状態を改善することが回復への近道です。
いずれにせよ、休止期脱毛症は「原因を取り除けば治ることが多い」脱毛症です。思い当たる要因がある場合はまずそれに対処し、抜け毛の経過を見守ることになります。
栄養不足による脱毛の原因
髪は健康のバロメーターとも言われるように、栄養状態が悪いと真っ先に影響が出るのが毛髪です。
現代の日本では極端な栄養失調は稀ですが、ダイエットの流行や食生活の偏りから特定の栄養素が慢性的に不足している人も少なくありません。
女性は月経による鉄分損失もあり、栄養不足による脱毛リスクが男性より高い傾向があります。この章では、栄養不足が原因で起こる脱毛について、髪に重要な栄養素とその不足時の影響を解説します。

鉄分不足(鉄欠乏性貧血)
鉄分は毛髪の成長に欠かせないミネラルの一つです。鉄は血液中でヘモグロビンの構成要素として全身に酸素を運ぶ役割があります。毛根の毛母細胞も酸素を受け取って細胞分裂し、髪を作っています。
そのため鉄不足で貧血状態に陥ると、毛母細胞まで十分な酸素が届かず髪の成長が滞ります。結果として髪が細く弱々しくなり、抜け毛が増加することがあります。
特に女性は月経や出産で鉄を失いやすく、鉄欠乏性貧血になりやすいです。実際、女性の薄毛に悩む方の中には検査で貧血が見つかるケースも少なくありません。
鉄剤を服用して貧血を改善したら髪も改善した、という報告もあります。反対に、鉄分不足の状態が続くと休止期脱毛症を引き起こしたり、女性型脱毛症(FAGA)の進行を助長する可能性も指摘されています。
日頃からレバーや赤身肉、ほうれん草など鉄分豊富な食品を摂り、必要に応じてサプリメントや医師の指導で鉄剤を補うことが大切です。
タンパク質不足
髪の毛の主成分はケラチンという繊維状のタンパク質です。したがって、体内のタンパク質が不足すると髪の材料そのものが足りなくなり、健全な発毛ができなくなります。
極端な炭水化物ダイエットや偏った食事制限で低栄養状態になると、身体は限られたタンパク質を生命維持に重要な臓器へ優先的に回します。その結果、髪や爪のような「なくても命に支障のない部分」への供給が後回しになり、髪は細く弱くなって抜けやすくなります。
特に若い女性で無理なダイエットを繰り返している場合、びまん性の薄毛に陥ることがありますが、その背景には慢性的なタンパク質不足が潜んでいることがあります。
髪だけでなく筋肉量の低下や肌荒れ、免疫力低下など全身に影響が及ぶため注意が必要です。髪のためには肉・魚・卵・大豆製品など良質なたんぱく質を毎食適量摂取することが望ましいです。
ビタミン・ミネラル不足
ビタミン類や亜鉛などミネラルも髪の成長に重要な役割を果たしています。例えば、ビタミンB群やビオチン(ビタミンH)は細胞の代謝や分裂に関与し、毛母細胞が活発に働くのを助けます。
ビタミンAやC、Eは頭皮の健康維持や血行促進に寄与します。亜鉛はケラチン合成酵素の構成成分であり、不足すると髪の生成過程がスムーズに進みません。
実際、亜鉛不足は味覚障害とともに脱毛症状を引き起こすことが知られています。日本人女性は慢性的な亜鉛不足傾向にあるとも言われており、注意が必要です。
また、先述したビタミンD不足も休止期脱毛症の一因となる可能性があります。ビタミンDは骨の栄養として有名ですが、毛包のサイクルにも影響を与えると考えられています。
日光不足や偏食でビタミンDが欠乏すると髪に元気がなくなる恐れがあります。要するに特定の栄養素が極端に不足すると、それがスイッチとなって脱毛が起こりうるのです。
髪の成長に必要な主な栄養素と、不足した場合の影響をまとめた表
| 栄養素 | 髪への主な役割 | 不足した場合の影響 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 毛髪の主成分ケラチンの材料(アミノ酸供給) | 髪の生成に必要な材料不足で、細く弱い髪しか生えなくなる |
| 鉄分 | 毛母細胞へ酸素を届けるヘモグロビンの構成成分 | 貧血により毛根部が酸欠状態となり、成長期が短縮して抜け毛増加 |
| 亜鉛 | ケラチン合成酵素の成分、細胞増殖に必要 | ケラチン合成が滞り、髪の成長が鈍化。抜け毛・薄毛の一因になる |
| ビタミンB群・ビオチン | エネルギー代謝や細胞分裂を助ける。毛母細胞の働きをサポート | 毛母細胞の分裂が不活発となり、髪が十分成長しないまま抜けやすくなる |
| ビタミンA・C・E | 頭皮の健康維持(皮脂分泌調整や血行促進、抗酸化作用) | 頭皮環境の悪化や血行不良に繋がり、髪に栄養が届かず抜け毛を招く |
| ビタミンD | 毛包サイクルの維持に関与(詳細な作用機序は研究中) | 不足すると休止期脱毛症のリスクが高まる可能性が指摘されている |
このように多種多様な栄養素が関与するため、バランスの良い食事が髪の健康には不可欠です。特定の食品ばかり摂ったり、逆に極端に除外するダイエットは薄毛リスクを高めます。
食事だけで不足しがちな場合はサプリメントで補う方法もありますが、過剰摂取にも注意しましょう。栄養状態を改善すれば、それに伴って髪の状態も少しずつ改善していくはずです。
甲状腺疾患による脱毛の原因
甲状腺は喉ぼとけの下あたりにある小さな臓器で、体の代謝を調節する甲状腺ホルモンを分泌しています。この甲状腺の働きが異常になると、全身の様々な不調が現れますが、その一つに抜け毛・薄毛があります。
甲状腺の病気は男性より女性に多く、特に30~50代の女性で発症しやすいため、薄毛の背景要因として注意が必要です。
この章では、甲状腺機能の低下と亢進、それぞれが髪に与える影響と脱毛の原因を説明します。

甲状腺ホルモンと髪の関係
甲状腺ホルモンは全身の細胞の新陳代謝を活発にする働きがあります。具体的には、エネルギー産生を高めたり、体温や心拍数を調整したりしています。
髪の毛も例外ではなく、毛母細胞の分裂や髪の成長スピードに甲状腺ホルモンが関与しています。そのため、甲状腺ホルモンの分泌量が多すぎたり少なすぎたりする状態では、髪の成長サイクルが乱れて脱毛につながります。
甲状腺の病気には、大きく分けてホルモンが**不足する場合(甲状腺機能低下症)と過剰になる場合(甲状腺機能亢進症)があります。
どちらの場合も抜け毛の症状がみられることがありますが、原因となるメカニズムはやや異なります。
甲状腺機能低下症による脱毛
甲状腺機能低下症は、橋本病(慢性甲状腺炎)などにより甲状腺ホルモン分泌が不足した状態です。体の新陳代謝が低下するため、常にエネルギー不足・エンジン不調のような状態になります。
症状としては、疲れやすい、寒がりになる、脈拍が遅くなる、体重増加、むくみ、皮膚乾燥などが典型ですが、髪や体毛にも変化が現れます。
具体的には、毛の成長スピードが落ちるため髪が全体的に細くコシがなくなり、抜け毛が増えます。頭髪だけでなく眉毛やまつ毛が抜けることもあります(特に眉毛の外側1/3が薄くなる徴候は有名です)。
機能低下症では休止期脱毛症の形でびまん性に髪が薄くなるケースが多いです。これは低下した代謝で毛母細胞の働きが鈍くなり、髪が十分育たないまま抜けてしまうためと考えられます。
甲状腺機能低下症に伴う脱毛は、甲状腺ホルモン剤の補充療法でホルモン値が正常化すれば改善していくことが期待できます。
甲状腺機能亢進症による脱毛
一方、甲状腺機能亢進症(代表的疾患はバセドウ病)は甲状腺ホルモンが過剰に分泌される状態です。
体の代謝が必要以上に高まりすぎてオーバーヒートしたような状態になり、脈拍増加、発汗過多、体重減少、手の震え、イライラ感などの症状が出ます。
髪に関して言えば、新陳代謝が活発すぎるために毛周期が極端に短くなってしまうことが考えられます。髪が早く生えて早く抜けてしまい、常に成長途中の柔らかい毛ばかりで抜け毛も多いという状況です。
機能低下症と同様にびまん性の脱毛となりますが、髪質が軟毛化してボリュームダウンするのが特徴です。
また新陳代謝亢進により栄養消費が激しくなるため、栄養不足気味になり、それも髪に影響を与える可能性があります。
甲状腺機能亢進症の場合も、抗甲状腺薬などでホルモン量を適正化する治療を行うことで症状改善とともに抜け毛も落ち着いてくることが期待できます。
甲状腺疾患が疑われるケース
薄毛の原因が甲状腺にある場合、上記のような他の全身症状を伴うことが多いです。
例えば「近頃抜け毛が多くて疲れやすく寒がりになった」「薄毛が進行するとともに動悸や寝汗がひどい」といった場合、甲状腺機能の異常が隠れているかもしれません。
特に女性の円形脱毛症患者さんでは甲状腺疾患を合併する割合が一般より高いことも知られており、原因不明の抜け毛がある場合は念のため甲状腺ホルモンの血液検査を受けてみるのも一つです。
甲状腺の異常は放置すると他の健康面にも影響しますが、適切な治療でコントロールできる病気です。甲状腺の治療を行うことで髪の状態も改善するケースが多々あります。
いずれにせよ、抜け毛の背後に甲状腺トラブルがないか見極めることが大切です。
更年期による脱毛の原因
更年期とは、女性が閉経を迎える前後の時期(おおよそ45~55歳)を指します。
この時期の女性の体は大きく変化し、様々な不調が現れることがあります。髪の毛も例外ではなく、更年期に入ると「急に髪が細くなってきた」「ボリュームがなくなった」と感じる女性が増えます。
更年期の薄毛の主な原因は女性ホルモン(エストロゲン)の減少です。この章では、更年期におけるホルモン変動と髪の関係、そしてそれによって起こる薄毛のメカニズムを説明します。
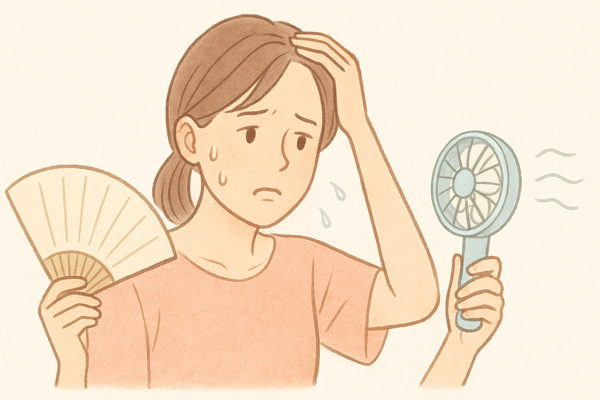
エストロゲン分泌低下によるヘアサイクルの乱れ
女性は30代後半から徐々に卵巣機能が低下し、エストロゲンの分泌量が減少し始めます。そして更年期(閉経の前後約5年間)にかけてエストロゲンは急激に低下します。
エストロゲンは髪の成長期を維持し、髪を太くしなやかに保つ重要なホルモンです。そのエストロゲンが不足すると、髪のヘアサイクルに異変が起こります。
具体的には、成長期が短くなり休止期に移行する毛が増えるため、髪の密度が徐々に減少していきます。また各毛髪の太さも細くなり、コシやハリが失われがちです。
さらに頭皮の皮脂バランスにも変化が生じ、乾燥や炎症が起こりやすくなることも髪にはマイナスです。
このように更年期のエストロゲン低下はびまん性脱毛症(髪全体のボリュームダウン)を引き起こす大きな要因となります。
相対的なアンドロゲン(男性ホルモン)影響の増加
エストロゲンが減ると、その対極にあるアンドロゲン(男性ホルモン)の相対的影響が強まることになります。
女性の体内でも副腎や卵巣からわずかに男性ホルモンが分泌されていますが、通常はエストロゲンがその作用を打ち消しています。
しかし更年期でエストロゲンが激減すると、今まで表に出ていなかった男性ホルモンの影響が目立つようになります。具体的には、毛根のホルモン受容体に男性ホルモンが結合しやすくなり、FAGA(女性男性型脱毛症)のような脱毛メカニズムが働き始めます。
閉経後の女性で生え際や頭頂部の地肌が見えるような薄毛になるのはこのためです。つまり、更年期脱毛=エストロゲン減少に伴うFAGAの発症と位置付けることもできます。
男性ホルモンの感受性は個人差があるため、更年期でも薄毛にならない方もいますが、遺伝的素因やストレスなどが重なると男性ホルモンの作用が強く出て薄毛が進行しやすくなります。
更年期以降の薄毛の特徴
更年期による脱毛は、基本的にはゆるやかな進行です。一夜にして髪がごっそり無くなるわけではなく、数年かけて徐々にボリュームが減っていくため、気づきにくいこともあります。
「気づけば分け目が広がっていた」「最近髪がやせ細ったようだ」と感じる頃には、かなり進行しているケースもあります。
また、更年期以降は髪の伸びるスピードも遅くなるため、一度薄くなるとなかなか元通りのボリュームに戻りにくいです。白髪も増える時期なので「白髪染めで髪が傷んだせいかな?」と思っていると、実はホルモン変化由来の薄毛だったということもあります。
更年期の薄毛は放置するとそのまま高齢期の薄毛(シニアの薄毛)に移行します。
髪以外にもホットフラッシュ(のぼせ)、発汗、イライラ、不眠など更年期症状が強い場合は、婦人科でホルモン補充療法(HRT)などの相談もできます。
ホルモン補充によって更年期症状が緩和すれば、髪の状態維持にもプラスに働く可能性があります。ただしホルモン補充にはリスクもあるため、薄毛だけのために安易に行うものではありません。
基本は生活習慣改善や育毛ケアで対処し、必要に応じて専門医と相談すると良いでしょう。
よくある質問(FAQ)
- Q女性の薄毛は改善できますか?
- A
原因に応じて適切に対処すれば、女性の薄毛は改善できる可能性があります。たとえば、産後や一時的なストレスによる薄毛であれば時間経過や生活環境の改善により自然に回復するケースが多いです。
栄養不足が原因なら食生活を見直すことで抜け毛が減り、新しい髪が生えてくることが期待できます。ホルモンバランスの乱れが原因の場合でも、婦人科的な治療や薬によるアプローチで改善する例があります。
また、女性型脱毛症(FAGA)のように進行性の薄毛でも、ミノキシジル外用薬やスピロノラクトン内服薬など女性向けの薄毛治療があります。
男性と違い女性は毛根が完全に死滅することは少なく、軟毛化(細く短くなる)した毛が多いので、適切な治療で太く長い毛に戻せる可能性があります。
ただし自己判断で市販薬を使う前に、皮膚科や薄毛専門クリニックで原因を特定してもらい、自分に合った対処法を取ることが大切です。
- Q薄毛が気になったら何科を受診すべきですか?
- A
薄毛治療は基本的に皮膚科が担当しています。一般の皮膚科でも薄毛や抜け毛の相談は可能です。特に女性の場合、皮膚科医は頭皮の状態や毛髪の様子から円形脱毛症なのかびまん性脱毛症なのかなど診断してくれます。
円形脱毛症であれば皮膚科でステロイド治療等を行いますし、女性型脱毛症(FAGA)であれば専門の発毛治療を行うクリニックを紹介されることもあります。
最近では女性の薄毛専門クリニックも増えており、より積極的な発毛治療(内服薬や外用薬、メソセラピーなど)を希望する場合はそのような専門施設を選ぶと良いでしょう。
また、ホルモンや甲状腺の異常が疑われる場合は婦人科や内科での検査も有用です。まず皮膚科で相談し、必要に応じて他科とも連携しながら原因にアプローチしていく形になります。
- Q薄毛予防のために日常生活で気をつけることはありますか?
- A
はい、日常生活の工夫で薄毛予防・改善に役立つことがいくつかあります。以下のポイントに留意してみてください。
- バランスの良い食事:髪の成長にはタンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミンなど様々な栄養素が必要です。極端な食事制限は避け、肉・魚・野菜・海藻・大豆製品などをバランスよく摂りましょう。特に女性は鉄分不足に注意し、レバーや赤身肉、緑黄色野菜などを意識して取り入れてください。
- 十分な睡眠:髪は夜間に成長するため、睡眠不足が続くとヘアサイクルが乱れます。理想的には毎日6~8時間の睡眠を確保し、成長ホルモンがしっかり分泌されるようにしましょう。夜更かしよりも規則正しい生活リズムが大切です。

- 適度な運動とストレス発散:軽い有酸素運動やストレッチは全身の血行を促進し、頭皮への血流も改善します。また運動はストレス解消にも有効です。ストレスは薄毛の大敵ですので、自分なりの発散法(運動、趣味、入浴など)で溜め込まないようにしましょう。
- 正しいヘアケア:頭皮に優しいシャンプーを使い、爪を立てず指の腹でマッサージするように洗髪しましょう。洗いすぎや強すぎるブラッシングは頭皮を傷めます。トリートメントで髪の保護をし、ドライヤーの熱を当てすぎないことも大切です。また、いつも同じ分け目だとその部分ばかり紫外線を浴びて負担がかかるので、たまに分け目を変えるのも良い方法です。
- 締め付けない髪型:牽引性脱毛症予防のためにも、長時間きつく髪を結ぶ髪型は控えましょう。ポニーテールはできるだけゆるく結び、家にいる時は髪を下ろして頭皮を休ませてください。
これらを心がけることで頭皮の環境が整い、健康な髪が育ちやすくなります。ただし既に進行した薄毛に対しては生活習慣の改善だけでは不十分な場合もあります。
その際は専門医の治療と併用する形で、生活面の対策も続けることが大切です。
- Qシャンプーや育毛剤で女性の薄毛は治りますか?
- A
市販のシャンプーや育毛剤は、薄毛予防や進行抑制に一定の効果を期待できますが、それだけで劇的に発毛させることは難しいです。
まずシャンプーに関しては、洗浄力のマイルドなスカルプシャンプーを使うことで頭皮の環境を健やかに保つ助けにはなります。ただ、シャンプー自体に発毛成分が入っているわけではないため、「適切な頭皮ケア」の範囲を超える効果はありません。
一方、育毛剤(発毛促進剤)には有効成分が含まれており、血行促進や頭皮の炎症を抑える効果が期待できます。市販の育毛トニックなどは爽快感がありますが、有効成分濃度は医薬品に比べ低めです。
女性の薄毛治療で有名な成分はミノキシジルですが、これは発毛効果が認められた医薬品であり、女性用は1%や5%の外用液が薬局で購入できます。
ミノキシジル外用は一定の効果がありますが、FAGAなど進行性の薄毛ではやめるとまた元に戻ってしまうため、継続使用が必要です。
総じて、シャンプーや育毛剤は補助的なケアとして取り入れるのは良いですが、原因に対する根本的な治療ではないことを理解しておきましょう。
薄毛の程度が軽い初期段階であれば、育毛剤や頭皮ケアで十分改善するケースもありますので、まずは試してみて、効果が不十分であれば専門医に相談するというステップがおすすめです。
- Q薄毛の原因を探るのに最も適した検査は?
- A
薄毛の原因を正確に突き止めるには、医師の診察のもとで総合的な検査を行うのが理想です。
具体的には、血液検査でホルモン値(甲状腺ホルモン、女性ホルモンなど)や栄養状態(鉄分や亜鉛の値)をチェックしたり、頭皮の状態を視診・撮影して毛穴の様子を観察したりします。
その中でも近年注目されているのが遺伝子検査です。遺伝子検査では、薄毛に関係する遺伝的素因(例えば男性ホルモン受容体の感受性や、毛髪の太さに関与する遺伝子など)を調べることができます。

専用のキットを用いれば自宅から郵送で検体(頬の粘膜や唾液)を送るだけで解析してもらえるため、手軽に利用できるようになっています。
遺伝子検査を行うと、「自分はFAGAになりやすい体質かどうか」「AGA治療薬が効きやすいタイプか」などが予測できます。郵送検査キットは通販やクリニック経由で購入でき、結果レポートには将来的な薄毛リスクやケアのアドバイスが記載されています。
まとめ
女性の薄毛は、びまん性脱毛症やFAGA、牽引性脱毛症、円形脱毛症など原因によってさまざまなタイプがあります。それぞれにホルモンバランスの乱れ、ストレス、栄養不足、自己免疫異常など異なる原因が関与します。
まずは原因を正しく見極めることが大切で、生活習慣の改善や必要に応じた治療で改善が期待できます。気になる抜け毛があれば早めに対策を始め、健康な美しい髪を取り戻しましょう。
次に知ってほしいこと(薄毛対策と治療)
薄毛の原因について理解できたら、以下をクリックして薄毛対策と治療について勉強しましょう。