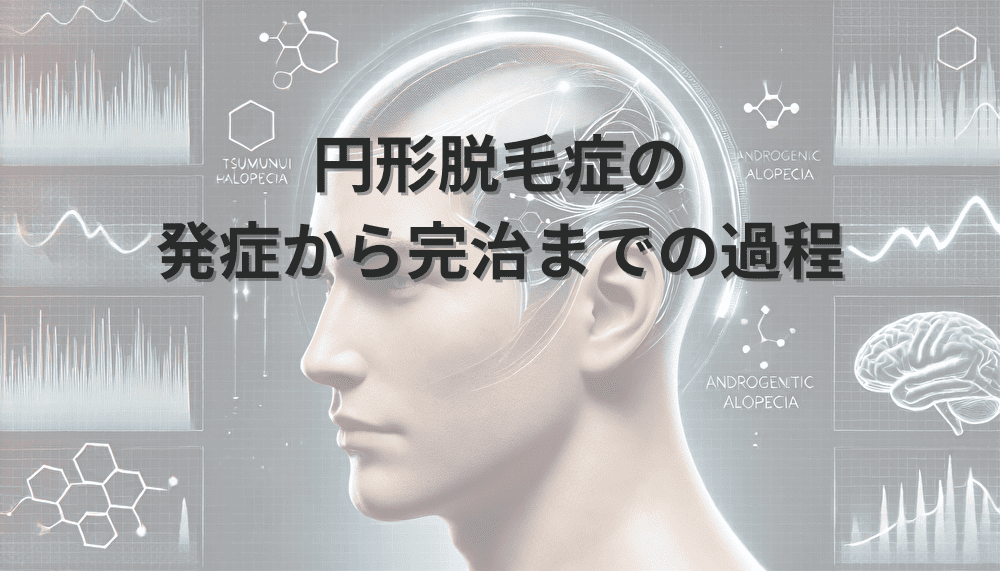円形脱毛症は、突然、丸い範囲で髪の毛が抜け落ちる症状です。
予想外の脱毛に不安を抱える方も多いかもしれませんが、原因や状態に応じた対応を行うことで、多くの場合は再び髪が生えてくる可能性があります。
この記事では、円形脱毛症の発症から完治までの流れを段階ごとにとらえ、どのように対処すればよいかを中心に詳しく解説します。
円形脱毛症とは?基本的な特徴と発症メカニズム
髪の毛が部分的に抜け落ちる円形脱毛症は、その見た目のインパクトから動揺する方が多い症状です。
しかし、円形脱毛症は誰にでも起こりうる可能性があり、思いがけないタイミングで発症することも珍しくありません。原因には複数の説がありますが、免疫に関する異常が関係しているケースが多いと考えられています。
円形脱毛症の基本的な種類
円形脱毛症には、単発型、多発型、蛇行型など、いくつかの種類があります。
単発型はその名のとおり、頭皮に1カ所のみ脱毛斑(脱毛している部分)が発生するものです。多発型は、複数の脱毛斑が同時あるいは時期をずらして現れます。
さらに、脱毛範囲が頭皮全体に広がる汎発型や全身の毛が抜ける汎発性脱毛に移行するケースもあり、一口に円形脱毛症といっても症状や広がり方に大きな幅があります。
円形脱毛症の種類
| 種類 | 特徴 | 脱毛範囲 |
|---|---|---|
| 単発型 | 脱毛斑が1カ所のみに限定される | 部分的 |
| 多発型 | 複数の脱毛斑が離れて存在する | 部分的〜広範囲 |
| 蛇行型 | 脱毛斑が帯状に広がる | こめかみ周辺など |
| 全頭型 | 頭全体の髪が抜け落ちる | 頭部全体 |
| 汎発型 | まつ毛や眉毛を含む全身の毛が抜け落ちる | 全身 |
これらの種類は脱毛の進行度や免疫機能の状態によって変わり、脱毛斑の大きさや数は経時的に変化します。
免疫異常との関連性
円形脱毛症は自己免疫疾患の一種と考えられ、免疫システムが誤って毛根を異物と認識し、攻撃することで髪の毛が抜け落ちるといわれています。
身体の免疫機能の乱れにはさまざまな要因が関わり、ストレスや生活習慣の乱れが引き金になることもあります。
| 原因 | 仕組み |
|---|---|
| 自己免疫 | 自分の細胞を誤って攻撃する仕組み |
| ストレス | 精神的負担や睡眠不足によってホルモンバランスが乱れる |
| 生活習慣 | 栄養不良や過度な疲労が免疫の働きに影響する |
免疫異常が主な原因とされる反面、必ずしも免疫だけが悪さをしているわけではなく、環境要因や遺伝要因も複合的に作用すると考えられています。
その他の要因(ストレス・遺伝など)
円形脱毛症は特定の要因だけでなく、複数の因子が組み合わさって発症に至る場合があります。
ストレスが強い時期に発症したり、家族に同様の症状を経験した方がいるケースでは遺伝的素因が疑われることもあります。
| 因子 | 具体例 | 影響度の目安 |
|---|---|---|
| ストレス | 過度な精神的負担、環境の急変 | 大きいとされる |
| 生活習慣 | 睡眠不足、偏った食事、喫煙など | 中〜大 |
| 遺伝 | 親や祖父母が円形脱毛症を経験している | ある程度の影響あり |
| 免疫異常 | 自己免疫疾患、アレルギー体質など | 高いと考えられる |
上記の要因が重なることで発症リスクが高まる可能性があります。体質や生活環境によっても異なるため、自分がどの要因に強く当てはまりそうかを把握すると対策を立てやすくなります。
円形脱毛症のステージ別の特徴
円形脱毛症は、脱毛斑が現れる初期から髪の毛が再び生え始める回復期までの間に変化が見られ、症状の度合いもステージによって異なります。
どの段階であっても、早めに頭皮の状態を把握して適切に対処することが大切です。
初期(脱毛斑の出現)
初期の円形脱毛症は、突然、頭皮の一部分の毛が円形あるいは楕円形に抜け落ちる形で現れます。鏡を見てはじめて気づく人もいれば、美容院などで指摘されて驚く人も少なくありません。
初期段階では比較的小さな脱毛斑であることが多いですが、免疫機能の乱れが生じているサインと考えられます。
脱毛斑の初期症状によくある特徴
- 脱毛部分の境界が比較的はっきりしている
- 頭皮がツルツルしていることが多い
- 痛みやかゆみはあまり感じない場合が多い
これを見過ごして放置すると、脱毛面積が拡大したり、数が増えたりする可能性があります。
中期(拡大と多発)
初期の脱毛斑が拡大したり、新たな脱毛斑が周囲に生じる段階です。髪をとかしたときに抜け毛が増えていることに気づく方もいます。
単発型から多発型へ変化し、複数の脱毛斑が同時進行で広がることもあります。頭皮のほか、まゆ毛や体毛にまで広がるケースでは不安が増しやすいでしょう。
中期の特徴
| 状態 | 見た目の変化 | 気づきやすさ |
|---|---|---|
| 脱毛斑の拡大 | 円形の斑がさらに大きくなる | 高い |
| 多発傾向 | 複数の斑が同時に現れる | 比較的高い |
| 抜け毛の増加 | ブラッシングやシャンプー時に実感する | 高い |
| まゆ毛・体毛への波及 | 髪以外にも抜け毛が広がる | 非常に高い |
この段階では原因の把握と治療方針の検討が重要になってきます。精神的ストレスも大きくなる場合が多いので、心身両面でのケアを意識したいところです。
後期(回復期と発毛の兆し)
中期からさらに進行すると、やがて免疫バランスが整ってくるケースがあります。その結果、脱毛斑の周囲や中心部にうぶ毛のような細い毛が生えてくることがあります。これが回復期の始まりです。
ただし、うぶ毛が生えていても、再発や他の部位への新たな脱毛が起こる場合もあるため、油断は禁物です。
- うぶ毛の発生は回復期のサイン
- 毛根が元気を取り戻し始める
- 毛質や色素は当初やや薄い色になる場合がある
回復期は髪が生え出す喜びと、再度抜けてしまうのではないかという不安が入り混じりやすい段階でもあります。
適切なスカルプケアと生活習慣の改善を続けると、髪を育てやすい環境を整えられます。
進行度合いの把握の重要性
円形脱毛症の経過は人によって大きく異なるため、自己判断で「このまま治るだろう」と楽観視してしまうと、気づいたときには脱毛範囲が拡大している場合もあります。
特に、中期から後期にかけては、症状が急に悪化して広範囲へ影響が及ぶこともあります。
- 医療機関で頭皮の状態や脱毛範囲をしっかり確認
- 血液検査や問診を通じて原因の推定を行う
- 生活習慣の見直しやストレス管理を早期に開始
円形脱毛症の治療で鍵になるのが、早期の段階で正確な進行度合いを把握し、発毛までの流れを長い目で見通すことです。
円形脱毛症の経過とよくある経緯
円形脱毛症が発症してから治療を検討し、場合によっては再発に悩むまで、さまざまな経緯をたどるケースがあります。
とりわけ初期のうちにどのような行動を取るかが、その後の治療効果や再発リスクに大きく関わります。
急激な脱毛に気づくまで
円形脱毛症の発症はある日突然、自分の頭皮に円形の脱毛斑を見つけることで気づく人が多いです。
特に単発型の場合は、見えづらい後頭部や側頭部で起こる例もあり、家族や美容師から指摘されて初めて発覚するケースもあります。
気づいたときにはある程度脱毛が進んでいることもあるため、違和感を覚えたらなるべく早めに頭皮を確認するとよいでしょう。
- 美容室やヘアサロンでの指摘
- 家族や友人からの指摘
- 鏡や写真で偶然気づく
急激に抜け毛が増えたと感じる場合は、抜け毛の本数や頭皮の状態を観察し、できるだけ早めに専門家へ相談すると、悪化を防ぎやすくなります。
脱毛に気づくタイミングと対処行動
| 気づくタイミング | 具体的な例 | その後の対処 |
|---|---|---|
| 美容室・ヘアサロンでの指摘 | 美容師に「脱毛斑がある」と言われる | 皮膚科を受診し、頭皮の状態を確認 |
| 家族やパートナーの指摘 | 「髪が薄くなってない?」と声をかけられる | 自分で頭皮を鏡でチェックし受診を検討 |
| 自分で鏡を見て確認 | 髪の分け目が広がっているのを発見 | 写真を撮るなどし、進行度を観察 |
皮膚科受診から治療開始まで
円形脱毛症を疑ったら、できるだけ早く皮膚科または脱毛症を扱う専門クリニックを受診することをおすすめします。
医師が頭皮の状態を直接観察し、場合によっては血液検査などを行い、自己免疫の状態や甲状腺疾患などの有無を調べます。そのうえで、症状の程度に応じた外用薬や内服薬などを検討します。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 診察 | 頭皮観察や問診 |
| 検査 | 血液検査で炎症や免疫状態を確認 |
| 治療方針決定 | 外用薬・内服薬・注射など |
受診時に、脱毛が始まった時期やきっかけ、ストレスの有無、睡眠や食生活なども医師に伝えると適切な治療計画を立てやすくなります。
日常生活での注意点
治療を始めた後も、日常生活の中で頭皮に負担をかけない工夫が大切です。過度なストレスや不規則な生活習慣は、免疫バランスを崩す原因になる可能性があります。
栄養バランスのとれた食事や十分な睡眠は、発毛をサポートするうえでも意識したいポイントです。また、カラーリングやパーマなどは頭皮に刺激を与えるので、治療中は控えめにするか担当医に相談するのが望ましいです。
| ポイント | 目的・具体策 |
|---|---|
| 睡眠の確保 | ホルモン分泌を整える |
| 栄養バランス | タンパク質・ミネラル・ビタミンを意識 |
| 頭皮ケア | 刺激の少ないシャンプーやトリートメント |
髪の毛が生え始めても、しばらくは弱くて細い毛が多い状態です。優しくケアしてあげることで、髪と頭皮に負担をかけにくくなります。
日常生活で意識したい行動
- 生活リズムの規則化
- 定期的な運動やストレッチ
- リラクゼーション法(深呼吸、ヨガなど)の活用
- バランスのよい食事と適度な休息
ストレスや生活リズムが大きく乱れると、円形脱毛症だけでなくAGAなど他の薄毛症状への移行リスクも高まることがあるため注意が必要です。
治療方法とその選択肢
円形脱毛症の治療方法は、症状の重症度や個人の体質によって変わります。
多くの場合、外用薬や内服薬による治療が中心ですが、場合によっては注射や特殊な療法を組み合わせることもあります。
ステロイド外用と内服
円形脱毛症の治療で一般的といわれているのが、ステロイド薬の外用や内服です。
特に脱毛斑が小さい場合や範囲が限られる場合には、ステロイドの塗り薬やローションを使って頭皮に直接塗布するケースが多いです。
広範囲に及ぶ場合や炎症が強い場合、ステロイドの内服や注射を検討することもあります。
ステロイド療法の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 外用剤 | 脱毛斑周辺に直接塗布する | 長期間の使用で皮膚が薄くなる可能性 |
| 内服剤 | 全身的に炎症を抑える | 副作用に注意が必要 |
| 局所注射 | 患部に直接ステロイドを注射 | 痛みや内出血が起こることがある |
ステロイド療法は強力に炎症を抑えて発毛を促しますが、自己判断で途中でやめると再び悪化する場合もあります。医師の指示を守り、用量や使用期間をきちんと守ることが重要です。
局所免疫療法や注射
ステロイド以外の治療として、SADBEやDPCPなどの薬剤を使った局所免疫療法があります。人工的にかぶれを起こして免疫反応をコントロールし、発毛を促す方法です。
また、育毛成分を含む注射を脱毛斑に直接打つことも検討される場合があります。
| 治療法 | 特徴 |
|---|---|
| 局所免疫療法 | 軽度〜中等度の円形脱毛症に用いられやすい |
| 育毛成分注射 | 毛母細胞に直接働きかける |
これらの治療は症状や体質によって効果に個人差があるため、医師との相談が欠かせません。
生活習慣の見直し
免疫異常によって生じる円形脱毛症の場合、治療薬だけでなく生活習慣を整えることも大切です。
高いストレス状態や栄養不足、睡眠不足などが続くと、円形脱毛症がなかなか改善しない原因になるケースがあります。
| 生活習慣 | 具体的な工夫 |
|---|---|
| ストレス軽減 | 趣味や休息を大切にする |
| 食事改善 | タンパク質、亜鉛、鉄分、ビタミン類の摂取 |
| 適度な運動 | 血行促進とストレス緩和 |
| 睡眠の質向上 | 寝る前のスマホ利用を控えるなど工夫 |
内服薬や外用薬の効果を引き出し、再発を予防する意味でも、これらの習慣作りは欠かせない要素となります。
生活習慣を整えるうえでよく見られる工夫
- 就寝1時間前にスマホやPCをオフにして脳を休める
- カフェインやアルコールを摂りすぎないように意識する
- 脂質の多い食事を控え、野菜や果物を中心に取り入れる
- 瞑想や軽いヨガなどで自律神経のバランスを整える
AGAや薄毛治療へつながる可能性
円形脱毛症に悩んで治療を続けるうちに、AGAなどのほかの薄毛治療にも関心を持つ方が少なくありません。たとえば、男性ホルモンの影響で頭頂部が薄くなるAGAも、早期発見・早期治療が大切です。
円形脱毛症が比較的早く治った後、将来的に髪全体のボリュームダウンや生え際の後退を感じるようであれば、一度AGA治療の検討をしてみることも大切です。同じクリニックで治療を行える場合もありますので、担当医に相談してみましょう。
円形脱毛症が自然に治るケースと治療期間の目安
円形脱毛症は、治療を受けなくても自然に髪が生えてくるケースが存在します。一方で、脱毛範囲が広がってしまう例や、再発を繰り返す例もあります。
そのため、自然経過を期待するか、積極的な治療を行うかは症状の段階や広がり、患者さんの生活背景などを踏まえて慎重に判断するのが望ましいです。
円形脱毛症が自然に治る場合
単発型で脱毛範囲が小さいケースの中には、治療をしなくても数カ月から半年ほどで髪が生えてくる場合があります。免疫バランスが比較的早く整い、身体本来の回復力によって発毛が促されると考えられます。
ただし、自然治癒に任せると、リスクもあります。脱毛範囲が予想以上に拡大したり、回復が遅れる場合には、結果的にストレスが増してしまうこともあるのです。
円形脱毛症が自然に改善しやすい要因
| 要因 | 具体例 |
|---|---|
| ストレスレベル | 休暇が取れ、精神的に落ち着いている |
| 軽度の症状 | 脱毛斑がごく小さく、単発にとどまる |
| 体質 | 免疫バランスが整いやすく、回復力が高い |
| 生活改善 | 栄養バランスや睡眠が十分確保されている |
円形脱毛症が治るまでの期間
円形脱毛症が治るまでの期間は個人差が大きいですが、小さな脱毛斑の場合は早い人で1カ月ほどで産毛が生え始め、3カ月から半年以内にほぼ元に戻ることもあります。
一方、脱毛斑が多発している場合や範囲が広い場合は、半年から1年ほど要することがあり、時にはそれ以上かかることもあります。また、途中で状態が一進一退を繰り返すこともあります。
| 状態 | かかる期間の傾向 |
|---|---|
| 小規模な単発型 | 1〜3カ月程度で改善傾向が出ることも |
| 多発型、拡大傾向 | 半年以上の治療期間を要する場合が多い |
| 再発を繰り返すタイプ | 数年単位で治療と経過観察を続ける例もある |
期間に関しては、医師の診断と治療計画によって予測できますが、「絶対に〇カ月で治る」という断言は難しいのが現状です。根気強く治療とケアを続ける姿勢が求められます。
放置によるリスク
円形脱毛症を放置すると、脱毛斑が拡大する、あるいは複数箇所に増えるリスクが高まります。
また、脱毛範囲が頭全体に及んでしまう前に対処しておくほうが、結果的に治療期間を短くできるケースも多いです。
円形脱毛症を放置するデメリット
- 脱毛範囲が拡大して治療が長引く
- 精神的負担が大きくなり、生活の質が低下する
- 根本的な原因(免疫異常など)の発見が遅れる
- 再発や慢性化のリスクが高まる
放置したからといって必ず重症化するわけではありませんが、リスクを理解したうえで適切な対応を取ることが望ましいです。
再発を防ぐための予防策
円形脱毛症は再発する例が少なくありません。治療によって一度は髪が生えても、その後に免疫バランスが崩れれば、再び同じような脱毛斑が生じる可能性があります。そのため、治療後も予防策を意識することが大切です。
ストレスと上手に向き合う
ストレスが免疫システムの乱れを引き起こすきっかけのひとつとなることは、多くの研究で示唆されています。
自分に合ったストレス解消法を見つけるのはもちろん、ストレスを必要以上に抱え込まない環境づくりも考えましょう。
| ポイント | 工夫 |
|---|---|
| 時間の管理 | 優先度を考え、詰め込みすぎない |
| 趣味の時間 | 音楽、運動、アートなどで気分転換 |
| 周囲への相談 | 家族や友人、専門家のカウンセリング |
完璧を目指しすぎるとストレスが増えることもあります。自分なりのペースを見つけることが、再発リスクを下げる鍵になります。
栄養バランスを整える
髪の毛を育てるためには、良質なタンパク質だけでなく、ビタミンやミネラル、鉄分、亜鉛なども不可欠です。
単なるサプリメントだけに頼るのではなく、まずは毎日の食事でさまざまな栄養素をバランスよく摂るよう心がけましょう。
髪や頭皮に嬉しい栄養素
| 栄養素 | 具体的な働き | 食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンの合成に必要 | 肉、魚、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質合成と細胞分裂を支える | 牡蠣、牛肉、かぼちゃの種 |
| 鉄分 | 頭皮や毛根への酸素供給を助ける | レバー、ほうれん草、赤身肉 |
| ビタミンC | コラーゲン生成をサポート | 柑橘類、イチゴ、パプリカ |
| ビタミンB群 | 細胞代謝を高め、皮膚や粘膜を健康に保つ | 豚肉、卵、豆類 |
偏った食事を続けていると、頭皮だけでなく全身のコンディションにも影響が及ぶため、食事内容の見直しが大切です。
定期的な頭皮ケア
頭皮環境を良好に保つ取り組みも再発防止に役立ちます。皮膚科や美容皮膚科で相談して、頭皮の状態に合ったシャンプーや育毛剤を選ぶのも一つの方法です。
過剰な洗浄力のシャンプーで皮脂を落としすぎると逆に頭皮が乾燥しやすくなり、炎症を招きやすくなる場合があります。
- 洗髪は1日1回〜2回を目安に
- 指の腹で優しくマッサージしながら洗う
- ドライヤーでしっかり乾かし、湿ったままにしない
髪の毛だけでなく、頭皮そのものが健康であることが、再び髪が抜け落ちないための土台づくりにつながります。
予防策として見直したい習慣
- 週に1度の頭皮クレンジング(専門アイテムを使って汚れを落とす)
- ヘアオイルや頭皮ローションで潤いを保つ
- 帽子や日傘などで紫外線を防御する
- 枕カバーや寝具を清潔に保ち、細菌の繁殖を抑える
クリニックで行う薄毛対策と受診のタイミング
円形脱毛症の診断・治療を行うだけでなく、将来的にAGAなどの薄毛リスクを抱えている方が、同時に予防や対策を考えるケースが増えています。
実際に同じクリニックで円形脱毛症とAGA治療に並行して取り組む方もいるほどです。
受診をおすすめする症状
円形脱毛症を初めて発症した場合はもちろん、再発が疑われる場合や頭髪に異常を感じた場合も、なるべく早めの受診が望ましいです。
また、以下のような症状が見られたら、専門の医師に相談すると安心です。
- 抜け毛の増加が数週間続いている
- 脱毛範囲が拡大しつつある
- 頭皮の炎症やかゆみが強い
- 髪の生え際が後退してきた(AGAの疑い)
いずれも早期に対策を講じることで、症状の悪化や広範囲化を防ぎやすくなります。
症状別の受診目安
| 症状 | 受診の目安 | 考えられる病態 |
|---|---|---|
| 突然の脱毛斑 | 1週間以内に受診が望ましい | 円形脱毛症 |
| 頭頂部の薄毛 | 数週間で拡大する場合は早めの相談 | AGA |
| かゆみ・赤み | 皮膚炎の可能性があるため早期に | 皮膚炎、湿疹 |
| 再発の兆候 | 過去の脱毛部位付近に違和感 | 円形脱毛症の再発 |
円形脱毛症からAGA治療への発展
男性の場合、もともとAGAが進行している中で、ストレスや免疫異常が重なることで円形脱毛症が起こる例もあります。逆に、円形脱毛症が回復したものの、数年後にAGAが気になり始めるケースも存在します。
円形脱毛症もAGAも、どちらも早期にケアを始めることで発毛のチャンスを高めやすくなります。同じクリニックで症状に応じたカウンセリングを行い、総合的に薄毛対策を行うほうが効率的です。
- AGA検査や血液検査などでホルモンバランスを確認
- 円形脱毛症の既往歴を把握した上で治療方針を選択
- 育毛剤や内服薬など、併用可能な治療手段を検討
カウンセリングの流れ
クリニックではまず問診を通じて、いつごろから脱毛が始まったか、どのような生活習慣を送っているか、ストレスの度合いなどを確認します。
その後、頭皮の拡大検査や血液検査で状態を把握し、治療プランを提案する流れが一般的です。
治療開始後は、定期的に通院して経過を観察し、必要に応じて薬の種類や量を調整していきます。
通院時にチェックすること
- 頭皮の広範囲撮影(脱毛面積の比較用)
- 毛髪密度や太さの測定
- 血液検査によるホルモン・免疫指標の確認
- ストレスレベルや生活習慣の継続観察
カウンセリングでは、抜け毛以外にも身体全体のコンディションや日々の過ごし方についてアドバイスを受けられるため、薄毛対策だけでなく健康管理の視点でもメリットがあります。
まとめ:円形脱毛症との向き合い方
円形脱毛症は免疫やストレスなど、さまざまな要因が絡み合って起こる脱毛症です。発症した段階で驚きや落ち込みを感じる方もいますが、早めに対処を行えば多くの場合は回復が期待できます。
また、同時にAGA治療を含む薄毛対策へと視野を広げると、将来的な髪の健康を守ることにもつながります。
自己判断と早期受診のバランス
単発型の小さな脱毛斑であれば、自然に発毛する可能性もあります。しかし、放置してしまい脱毛斑が拡大したり複数化すると、治療に時間がかかることが多いです。
抜け毛が気になり始めたら、まずは頭皮の状態を鏡などでチェックし、少しでも不安があれば専門家の診察を受けると安心です。
- 自己流のケアで改善することもある
- 早期受診で重症化を避けられるケースが多い
- 自然治癒に期待するか、治療を受けるかは症状次第
前向きにケアを続けるための工夫
円形脱毛症の治療や発毛は、短期間で劇的に進むわけではなく、ある程度の時間と根気を要します。長い治療期間を乗り越えるには、モチベーションの維持が大切です。
自分でできる頭皮マッサージや、ストレス解消法をいくつか取り入れると、前向きに治療を続けやすくなります。
前向きに治療と向き合うために
- 月に1度は頭皮写真を撮影し、少しずつでも変化を確認する
- 進捗が分かりやすいように、専用のノートに抜け毛の本数や頭皮ケアの内容を記録
- 同じ悩みを持つ人と情報交換をする(オンラインコミュニティなど)
- 医師とこまめにコミュニケーションを取り、疑問や不安を解消する
再発防止と将来への展望
円形脱毛症は繰り返すこともありますが、生活習慣の見直しやストレス管理に取り組むことで再発を減らせる可能性があります。もし再発してしまったとしても、早期に受診して必要な治療を行えば、髪の健康を保ちやすくなります。
さらに、AGAなど他の薄毛症状への移行や合併を意識しておくと、将来の頭髪の状態をより良い形で維持することを目指せます。
さまざまな治療法が存在し、クリニックでの専門的なケアを受けながら、日常生活での取り組みを並行して行うことで、より効果的に円形脱毛症と向き合えます。
治療にあたっては、医師と相談のうえで、自分の状況に合った選択肢を検討することが重要です。
参考文献
TRÜEB, Ralph M.; DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni. Alopecia areata: a comprehensive review of pathogenesis and management. Clinical reviews in allergy & immunology, 2018, 54: 68-87.
STERKENS, A.; LAMBERT, Jo; BERVOETS, A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. Clinical and experimental medicine, 2021, 21: 215-230.
SPANO, Frank; DONOVAN, Jeff C. Alopecia areata: Part 1: pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Canadian Family Physician, 2015, 61.9: 751-755.
PRATT, C. Herbert, et al. Alopecia areata. Nature reviews Disease primers, 2017, 3.1: 1-17.
STRAZZULLA, Lauren C., et al. Alopecia areata: disease characteristics, clinical evaluation, and new perspectives on pathogenesis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 78.1: 1-12.
DARWIN, Evan, et al. Alopecia areata: review of epidemiology, clinical features, pathogenesis, and new treatment options. International journal of trichology, 2018, 10.2: 51-60.
ZHOU, Cheng, et al. Alopecia areata: an update on etiopathogenesis, diagnosis, and management. Clinical reviews in allergy & immunology, 2021, 61.3: 403-423.
LEW, Bark-Lynn; SHIN, Min-Kyung; SIM, Woo-Young. Acute diffuse and total alopecia: A new subtype of alopecia areata with a favorable prognosis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2009, 60.1: 85-93.