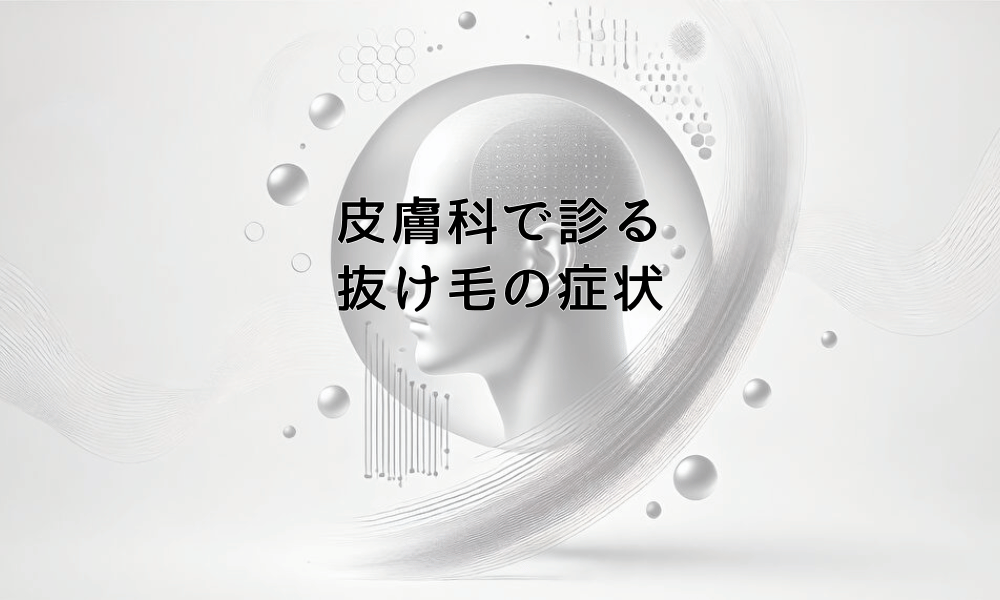抜け毛や薄毛が気になり始めた時、「病院へ行くべきか」と悩む方は少なくありません。脱毛症のなかでもAGA(男性型脱毛症)は進行性のため、早期の対応が重要です。
この記事では、抜け毛で皮膚科を受診する目安、皮膚科が診る脱毛症の種類、そして具体的な検査や治療法について詳しく解説します。
専門医による診断がなぜ大切なのか、そしてどのような治療が期待できるのかを確認して不安を解消し、適切な一歩を踏み出しましょう。
抜け毛で皮膚科を受診する重要性
抜け毛の悩みは、専門的な知識を持つ皮膚科医に相談するのが解決への最も確実な道です。
髪の毛は皮膚の一部であり、皮膚科医は毛髪や頭皮の疾患に関する専門家です。自己判断で市販の育毛剤を試す前に、まずは正確な診断を受けましょう。
なぜ抜け毛の相談は皮膚科なのか
皮膚科医は、髪の毛を作り出す毛包や頭皮の状態を医学的に診断する専門家です。
抜け毛の原因はAGA(男性型脱毛症)だけでなく、円形脱毛症や脂漏性皮膚炎に伴う脱毛、あるいは内科的な疾患が隠れている場合もあります。
皮膚科では、これらの多様な原因を鑑別し、一人ひとりの症状に合わせた適切な指導や治療を提供します。他の診療科と連携が必要な場合も、その窓口として機能します。
早期発見・早期治療のメリット
多くの脱毛症、特にAGAは進行性です。放置すると薄毛の範囲が広がり、治療による改善も難しくなる傾向があります。
「まだ大丈夫だろう」と様子を見る時間が、将来の毛髪状態に大きく影響する可能性があります。
皮膚科で早期に診断を受けて適切な治療を開始すると、抜け毛の進行を抑制し、毛髪の状態を維持・改善できる可能性が高まります。気になる症状があれば、早めに専門医の診察を受けるのが賢明です。
自己判断の危険性と専門医の役割
インターネットや広告には様々な育毛情報が溢れていますが、その情報が自分自身の抜け毛の原因に合致しているとは限りません。
間違ったセルフケアは、かえって頭皮環境を悪化させたり、治療のタイミングを逃したりする原因になります。
専門医の役割は、問診や視診、必要な検査を通じた抜け毛の根本原因の特定です。科学的根拠に基づいた診断こそが、効果的な治療の第一歩となります。
AGA(男性型脱毛症)と皮膚科の関係
AGAは皮膚科で最も多く相談される脱毛症の一つです。思春期以降に始まり、男性ホルモンの影響で徐々に進行します。
皮膚科ではAGAの進行度を客観的に評価し、「日本皮膚科学会ガイドライン」に基づいた標準的な治療(内服薬や外用薬)を提供します。
AGAは早期に治療を開始し、継続が非常に重要であり、皮膚科はそのための医学的なサポートを行う中心的な場所です。
皮膚科が診る抜け毛の種類とその原因
抜け毛を引き起こす原因は一つではありません。皮膚科では症状や所見から原因を特定し、それぞれの脱毛症に応じた治療方針を立てます。
代表的な脱毛症には、AGA(男性型脱毛症)、円形脱毛症、脂漏性脱毛症などがあります。
AGA(男性型脱毛症)
AGAは、男性ホルモンの一種であるDHT(ジヒドロテストステロン)が毛乳頭細胞に作用し、ヘアサイクル(毛周期)を短縮させるのが主な原因です。
通常、髪の毛は2年から6年の「成長期」がありますが、AGAを発症するとこの成長期が数ヶ月から1年程度に短縮されます。
その結果、髪の毛が太く長く成長する前に抜け落ち、細く短い毛(軟毛)が増えるため薄毛が目立つようになります。前頭部や頭頂部から薄くなるのが特徴です。
円形脱毛症の特徴と原因
円形脱毛症は年齢や性別に関わらず発症する脱毛症で、ある日突然、コイン大の円形または楕円形の脱毛斑(毛が抜けた部分)が現れるのが特徴です。
原因は、免疫機能の異常により、自身のリンパ球が成長期の毛根を攻撃してしまう「自己免疫疾患」と考えられています。
精神的ストレスが引き金になるケースもありますが、ストレスだけが直接の原因ではありません。脱毛斑が1ヶ所の場合もあれば、多発する場合、頭部全体に広がる場合など症状は様々です。
脂漏性脱毛症(しろうせいだつもうしょう)とは
脂漏性脱毛症は、頭皮の皮脂が過剰に分泌されるために発症する「脂漏性皮膚炎」に伴って起こる抜け毛です。
皮脂が過剰になると皮脂を栄養源とするマラセチア菌(常在菌の一種)が増殖し、その代謝物が頭皮を刺激して炎症を引き起こします。
炎症が続くと頭皮環境が悪化し、かゆみやフケ、赤みと共に抜け毛が増加します。AGAとは異なり、適切なスキンケアや皮膚炎の治療によって改善が見込めます。
皮膚科で鑑別する主な脱毛症
| 脱毛症の種類 | 主な原因 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| AGA(男性型脱毛症) | 男性ホルモン(DHT)、遺伝 | 前頭部・頭頂部から軟毛化・薄毛が進行 |
| 円形脱毛症 | 自己免疫疾患、ストレス(誘因) | 円形・楕円形の脱毛斑が突然出現 |
| 脂漏性脱毛症 | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌 | 強いフケ、かゆみ、頭皮の赤みと抜け毛 |
その他の脱毛症(休止期脱毛症など)
上記の他にも、皮膚科では様々な脱毛症を扱います。
例えば「休止期脱毛症」は、高熱や大きな手術、過度なダイエットや出産、精神的ストレスなどが引き金となり、多くの毛髪が一斉にヘアサイクルの「休止期」に入ってしまうと起こる脱毛です。
原因がはっきりしており、それが取り除かれれば数ヶ月で自然に回復する方が多いです。
また、薬剤の副作用や、甲状腺機能の異常など内科的疾患が原因で抜け毛が起こる場合もあり、皮膚科はこれらの鑑別も行います。
皮膚科受診の目安となる抜け毛のサイン
抜け毛は誰にでもありますが、その量や質、頭皮の状態に変化が見られた場合は注意が必要です。これらは脱毛症の初期サインである可能性があり、皮膚科を受診する目安となります。
日々のセルフチェックで早期発見につなげましょう。
1日の抜け毛の本数で判断する
健康な人でも、ヘアサイクルによって1日に50本から100本程度の髪の毛は自然に抜けています。この範囲内であれば、過度に心配する必要はありません。
しかし、シャンプー時や朝起きた時の枕元の抜け毛が明らかに増え、「明らかに100本を超えている」「以前の倍以上抜けている」と感じる状態が続く場合は、何らかの異常が起きている可能性があります。
特に、排水溝に詰まる毛の量が急に増えた場合は、受診を検討するサインです。
抜け毛の毛根や毛質をチェックする
抜け毛の状態を確認するのも重要です。健康な抜け毛(休止期毛)は毛根の先端が白く丸みを帯びており、マッチ棒のような形をしています。
しかし、AGAなどでヘアサイクルが乱れると、成長途中の細く短い毛や、毛根部が小さく痩せている毛が抜けるようになります。
抜け毛の中に細く力のない毛や、毛根がはっきりしない毛が多い場合は、皮膚科に相談すると良いでしょう。
抜け毛のセルフチェックポイント
| チェック項目 | 正常な状態(目安) | 注意が必要な状態(目安) |
|---|---|---|
| 抜け毛の本数(1日) | 50本〜100本程度 | 150本以上が続く、急激に増加 |
| 抜け毛の太さ・長さ | 太く、しっかりしている | 細く、短い毛が多い |
| 毛根の状態 | 先端が白く丸い(毛根鞘) | 毛根がない、または黒く細い |
頭皮の状態(赤み、かゆみ、フケ)
健康な頭皮は青白い色をしていますが、炎症が起こると赤みを帯びたり、かゆみが出たりします。また、乾燥による細かいフケや、皮脂の過剰分泌によるベタついたフケも頭皮環境悪化のサインです。
これらは脂漏性皮膚炎などの前兆である可能性があり、放置すると抜け毛の原因となります。頭皮トラブルが続く場合は、皮膚科での診断と治療が必要です。
髪質の変化(細毛化、ハリ・コシの低下)
抜け毛の量自体は変わらなくても、「髪全体のボリュームが減った」「髪にハリやコシがなくなった」「セットがしにくくなった」といった髪質の変化は、AGAの初期症状(軟毛化)である可能性が高いです。
髪の毛が太く成長する前に抜けるようになるため、全体的に薄くなったように感じます。このような自覚症状も、皮膚科を受診する重要な目安の一つです。
皮膚科での抜け毛相談 初診の流れ
抜け毛の悩みで初めて皮膚科を受診する際、どのようなことが行われるのか不安に思うかもしれません。
一般的には、まず詳しい問診で生活背景や症状を把握し、次に医師による頭皮の視診、触診が行われます。流れを理解しておくと、リラックスして診察に臨めるでしょう。
予約から受付までに準備すること
皮膚科、特にAGA治療などを専門的に行っているクリニックでは、予約制を採用しているところが多いです。
事前に電話やウェブサイトで予約を取りましょう。その際、抜け毛の相談であると伝えるとスムーズです。
受診当日は問診票を記入するため、時間に余裕を持って来院します。健康保険証は必ず持参してください。
また、普段使用している育毛剤や内服している薬があれば、その名前がわかるもの(お薬手帳など)を持参すると診察の参考になります。
問診で伝えるべき内容
問診は抜け毛の原因を探る上で非常に重要です。医師から以下のような点について質問されます。正確な診断のために、できるだけ詳しく答えましょう。
- いつから抜け毛が気になり始めたか
- 抜け毛の量や状態の変化(急に増えた、徐々に増えたなど)
- 頭皮のかゆみ、フケ、赤みなどの自覚症状の有無
- 生活習慣(食事、睡眠、ストレス、喫煙・飲酒の習慣)
- 現在治療中の病気や、服用中の薬
- 家族(特に父方・母方の祖父や父)の毛髪の状態(遺伝的要因の確認)
- これまでに行った薄毛対策(市販薬の使用歴など)
視診と触診による頭皮チェック
問診の後は医師が直接、頭皮と毛髪の状態を観察します。視診では、薄毛の進行パターン(M字型、O字型など)、頭皮の色(赤みや炎症の有無)、フケの状態、毛穴の詰まり具合などを確認します。
また、毛髪の太さや密度、硬さなどを触って確かめる触診も行います。
これらの所見から、AGAの進行度分類(ハミルトン・ノーウッド分類など)に当てはめたり、他の皮膚疾患の可能性を探ったりします。
必要に応じて行われる検査
問診と視診・触診だけでAGAの診断がつくケースも多いですが、他の脱毛症との鑑別や、全身状態の確認のために、追加の検査を提案されるときがあります。
例えば、円形脱毛症が疑われる場合や、急激な抜け毛(休止期脱毛症)が起きた場合は、甲状腺機能や貧血の有無などを調べるために血液検査を行うことがあります。
また、頭皮の状態をより詳しく見るために、ダーモスコピー(拡大鏡)検査を行うときもあります。
皮膚科で行う主な検査方法
抜け毛の原因を正確に特定するため、皮膚科ではいくつかの専門的な検査を行います。これらの検査は、AGAの診断を確定したり、他の脱毛症の可能性を排除したりするために役立ちます。
すべての検査が必ず行われるわけではなく、医師が必要と判断した場合に実施されます。
ダーモスコピー(拡大鏡検査)
ダーモスコピーは、特殊な拡大鏡(ダーモスコープ)を使って、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察する検査です。痛みは全くありません。
この検査によって、肉眼では見えにくい毛髪の太さのばらつき(軟毛化の程度)、毛穴の詰まり具合、頭皮の炎症や血管の状態などを確認できます。
AGAでは一つの毛穴から生えている毛の本数が減少し、細い毛が目立つ所見が特徴的です。脂漏性皮膚炎や円形脱毛症の診断にも有用です。
血液検査の目的
抜け毛の原因がAGAや円形脱毛症ではなく、内科的な疾患にある場合もあります。急に抜け毛が増えたときや、倦怠感など他の体調不良を伴う方は、血液検査を行います。
この検査で、貧血(鉄欠乏)、甲状腺機能の異常(亢進症または低下症)、あるいは膠原病などが隠れていないかを調べます。
また、AGA治療薬を開始する前に、肝機能や腎機能など、薬の代謝に関わる臓器の状態をチェックする目的で血液検査を行うケースもあります。
血液検査で確認する主な項目例
| 検査項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 甲状腺ホルモン (TSH, FT3, FT4) | 甲状腺機能亢進症や低下症がないか |
| 鉄 (Fe)・フェリチン | 鉄欠乏性貧血(抜け毛の原因になる)がないか |
| 肝機能 (AST, ALT)・腎機能 (Cre) | AGA治療薬の服用が可能かどうかの判断 |
毛髪検査(引っ張り試験など)
「引っ張り試験(Pull test)」は、医師が患者さんの頭髪の束(数十本程度)を軽く引っ張り、どれくらいの毛が抜けるかを調べる簡易的な検査です。
正常であれば数本程度しか抜けませんが、活動性の高い脱毛症(急性休止期脱毛症や円形脱毛症の活動期など)では、ごそっと抜ける傾向があります。
抜けた毛の毛根の状態を顕微鏡で観察し、成長期毛か休止期毛かを判断する場合もあります。この結果から、脱毛症の種類や活動性を評価します。
皮膚科で期待できる抜け毛治療(AGA中心)
皮膚科での抜け毛治療は、診断結果に基づき医学的根拠のある方法が選択されます。
AGA(男性型脱毛症)と診断された場合、日本皮膚科学会が推奨するガイドラインに沿った内服薬や外用薬による治療が中心となります。治療は継続が重要です。
内服薬による治療(フィナステリド・デュタステリド)
AGA治療の第一選択肢となるのが内服薬です。AGAの原因であるDHT(ジヒドロテストステロン)の生成を阻害する「5α還元酵素阻害薬」を用います。
代表的な薬として「フィナステリド」と「デュタステリド」があります。
これらは、ヘアサイクルの乱れを正常化して抜け毛を減らし、髪の毛の成長期を延長させて毛髪のハリやコシを改善し、薄毛の進行を抑制します。医師の処方が必要な薬剤です。
主なAGA内服治療薬の比較
| 薬剤名 | 作用する酵素の種類 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| フィナステリド | II型5α還元酵素 | AGA治療薬として長く使用実績がある |
| デュタステリド | I型およびII型5α還元酵素 | より広範にDHT生成を阻害するとされる |
外用薬による治療(ミノキシジル)
外用薬(塗り薬)としては、「ミノキシジル」が広く用いられます。ミノキシジルはもともと高血圧の治療薬として開発されましたが、発毛効果が認められて薄毛治療薬として転用されました。
頭皮の血流を改善し、毛母細胞を活性化させることで発毛を促進し、髪の毛の成長期を延長させる作用があります。
内服薬が「抜け毛を防ぐ(守りの治療)」であるのに対し、ミノキシジル外用薬は「発毛を促す(攻めの治療)」と位置づけられ、内服薬と併用するとより効果が期待できます。
治療の継続期間と効果実感の目安
AGA治療は、すぐに効果が出るものではありません。乱れたヘアサイクルが正常に戻り、新しい髪の毛が成長して目に見える変化として現れるまでには時間がかかります。
一般的に、内服薬や外用薬を開始してから、抜け毛の減少や産毛の増加といった初期の変化を感じるまでに最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。
効果を維持するためには治療の継続が大切です。自己判断で中断すると、再びAGAが進行してしまう可能性があります。
治療の副作用と対処法
AGA治療薬は医薬品であるため、副作用のリスクがゼロではありません。内服薬(フィナステリド、デュタステリド)では、まれに性機能の低下(勃起不全、リビドー減退など)や肝機能障害が報告されています。
ミノキシジル外用薬では、使用部位のかゆみやかぶれ、発疹などの皮膚症状が起こる場合があります。
これらの副作用は頻度が高いものではありませんが、万が一、体調に異変を感じた場合はすぐに処方を受けた皮膚科医に相談してください。
医師の管理下で治療を行うことは、こうした副作用への迅速な対応を可能にします。
治療薬の主な副作用(例)
| 治療薬 | 起こり得る主な副作用 |
|---|---|
| 内服薬(フィナステリド等) | 性機能低下(頻度低)、肝機能障害(まれ) |
| 外用薬(ミノキシジル) | 頭皮のかゆみ、かぶれ、発疹、初期脱毛 |
治療と並行したいセルフケア
皮膚科での専門的な治療は抜け毛対策の柱ですが、その効果を最大限に引き出し、頭皮環境を健やかに保つためにはセルフケアも非常に重要です。治療とセルフケアは、車の両輪と考えるべきです。
食生活の見直しと栄養バランス
髪の毛は私たちが食べたものから作られます。「タンパク質(ケラチン)」が主成分であり、その合成を助ける「亜鉛」、頭皮の血行を良くする「ビタミンE」、頭皮環境を整える「ビタミンB群」などが重要です。
特定の食品だけを食べるのではなく、肉や魚、卵や大豆製品、野菜や海藻類などをバランス良く取り入れた食事が基本です。
過度な脂質や糖質の摂取は皮脂分泌を増やし、頭皮環境を悪化させる可能性があるため、控えるよう心がけましょう。
- タンパク質(髪の主成分)
- 亜鉛(タンパク質の合成を助ける)
- ビタミンB群・E群(頭皮環境・血行)
ストレス管理と睡眠の質の向上
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮への血流を悪化させる可能性があります。また、睡眠不足も髪の成長に悪影響を与えます。
髪の毛の成長を促す「成長ホルモン」は、特に深い睡眠中(ノンレム睡眠時)に多く分泌されます。
日中は適度な運動でリフレッシュする、趣味の時間を持つなどしてストレスを発散し、夜は質の高い睡眠を確保するよう努めましょう。毎日7時間程度の睡眠を目安に、規則正しい生活リズムを作る工夫が大切です。
正しいシャンプー方法と頭皮ケア
頭皮を清潔に保つのは基本ですが、洗いすぎは禁物です。シャンプーは1日1回、夜に行うのが理想的です。
洗う際はまずお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うと頭皮を傷つけてしまいます。
すすぎはシャンプー剤が残らないよう、時間をかけて念入りに行いましょう。洗髪後はタオルドライで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで頭皮からしっかりと乾かします。生乾きは雑菌の繁殖につながります。
よくある質問
- Q皮膚科での治療はどれくらい通う必要がありますか?
- A
治療の頻度は症状や治療内容によって異なりますが、AGA治療の場合、一般的には1ヶ月から3ヶ月に1回の通院で経過観察と薬の処方を受けることが多いです。
治療開始直後は薬の副作用の有無を確認するため、通院頻度がやや高くなります。治療が安定すれば、通院間隔が長くなる場合もあります。
医師の指示に従って定期的に通院していきましょう。
- Q治療をやめると元に戻ってしまいますか?
- A
AGA(男性型脱毛症)は進行性の脱毛症であり、現在の治療は主にその進行を抑制し、発毛を促すものです。根本的に体質を「治す」ものではありません。
そのため、内服薬や外用薬の使用を自己判断で中止すると、抑制されていたAGAが再び進行し始め、数ヶ月かけて治療前の状態に戻っていく可能性が高いです。
効果を維持するためには、医師と相談の上、治療を継続するのが原則となります。
- Q治療薬に頼らず生活習慣だけで改善できますか?
- A
バランスの取れた食事や十分な睡眠、ストレス管理などの生活習慣の改善は、頭皮環境を整え、髪の健康を保つ上で非常に重要です。
しかし、すでにAGAが発症・進行している場合、生活習慣の見直しだけで薄毛の進行を止めたり、元の状態に回復させたりするのは困難です。
生活習慣の改善はあくまでも皮膚科での専門的な治療(薬物治療など)の土台であり、治療と並行して行ってその効果を高めるものと考えるのが現実的です。
- Q女性の抜け毛も皮膚科で相談できますか?
- A
もちろんできます。皮膚科は女性の抜け毛(FAGA: 女性男性型脱毛症、びまん性脱毛症、牽引性脱毛症など)の相談も受け付けています。
女性の抜け毛は、ホルモンバランスの変化や貧血、甲状腺疾患など、男性とは異なる原因が隠れているケースも多いため、特に専門的な診断が重要です。
男性用のAGA治療薬が使えない場合もあり、女性に適した治療法(ミノキシジル外用薬や栄養補助など)を提案します。気になる場合はためらわずに受診してください。
参考文献
CASH, Thomas F. Attitudes, behaviors, and expectations of men seeking medical treatment for male pattern hair loss: results of a multinational survey. Current medical research and opinion, 2009, 25.7: 1811-1820.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.
BANKA, Nusrat; BUNAGAN, MJ Kristine; SHAPIRO, Jerry. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 129-140.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
ROSS, Elizabeth K.; SHAPIRO, Jerry. Management of hair loss. Dermatologic clinics, 2005, 23.2: 227-243.
CASH. The psychosocial consequences of androgenetic alopecia: a review of the research literature. British Journal of Dermatology, 1999, 141.3: 398-405.