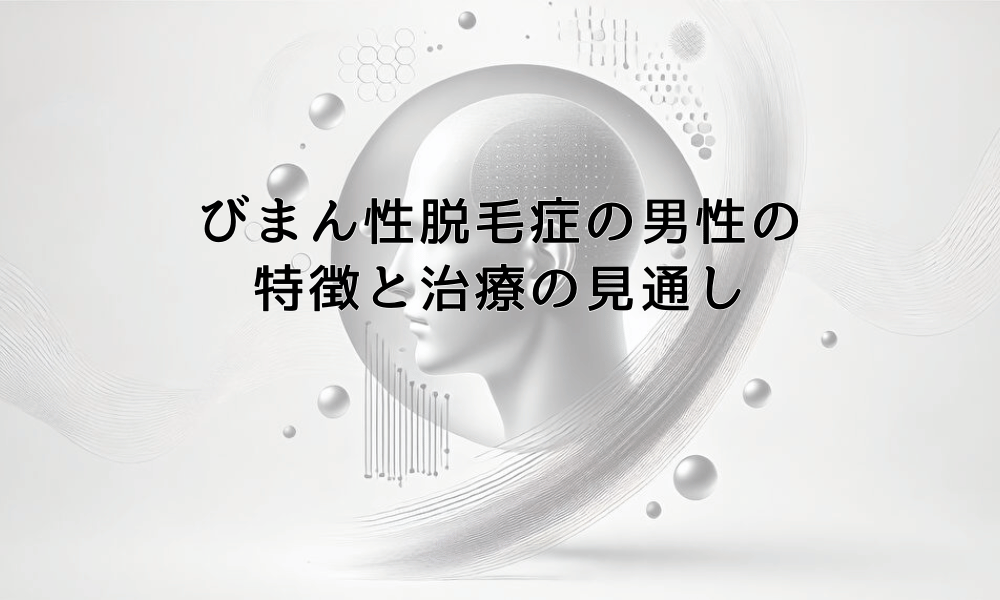「最近、髪のボリュームが減ってきた気がする」「生え際や頭頂部だけでなく、全体的に薄くなってきた」と感じている男性もいらっしゃるのではないでしょうか。
それは男性型脱毛症(AGA)ではなく、びまん性脱毛症かもしれません。女性に多いと思われがちな症状ですが、実は多くの男性も悩んでいます。
この記事では、男性のびまん性脱毛症の特有な特徴、AGAとの見分け方、考えられる原因、そしてクリニックでの治療法と今後の見通しについて詳しく解説します。
男性にも起こるびまん性脱毛症とは?AGAとの違い
薄毛の悩みというと、多くの男性はAGA(男性型脱毛症)を思い浮かべるでしょう。しかし、髪が全体的に薄くなる「びまん性脱毛症」も男性に見られます。
まずは、びまん性脱毛症の基本的な知識と、AGAとの明確な違いを確認しておきましょう。適切な治療法の選択は、症状の正確な把握から始まります。
びまん性脱毛症の基本的な定義
びまん性脱毛症は、特定の部位が後退したり抜け落ちたりするのではなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる状態を指します。
髪の一本一本が細くなったり、ハリやコシが失われたりするため、全体のボリュームダウンを実感するのが特徴です。
地肌が透けて見えるようになり、スタイリングが難しくなったと感じる方も少なくありません。
AGA(男性型脱毛症)との比較
AGAは、男性ホルモンの影響で、主におでこの生え際や頭頂部から薄毛が進行します。一方、びまん性脱毛症は、前述の通り頭部全体に症状が現れます。
原因も異なり、AGAが遺伝や男性ホルモンに起因するのに対し、びまん性脱毛症は生活習慣の乱れやストレスなど、より多様な要因が絡み合って発症します。
AGAとびまん性脱毛症の主な違い
| 項目 | びまん性脱毛症 | AGA(男性型脱毛症) |
|---|---|---|
| 脱毛範囲 | 頭部全体が均一に薄くなる | 生え際や頭頂部から局所的に進行 |
| 主な原因 | 生活習慣、ストレス、栄養不足など | 遺伝、男性ホルモン |
| 進行パターン | ゆっくりと全体の密度が低下 | 特定の型(M字、O字など)で進行 |
なぜ男性がびまん性脱毛症になるのか
男性がびまん性脱毛症を発症する背景には、現代社会特有の要因が深く関わっています。
過度なストレスや不規則な食生活、睡眠不足などが頭皮の血行を悪化させ、髪の成長に必要な栄養素が毛根に行き渡りにくくなります。
これらの要因が複合的に作用し、健康な髪の成長サイクルを乱すことで、びまん性の脱毛を引き起こします。
びまん性脱毛症の男性に見られる主な症状と特徴
男性のびまん性脱毛症の主な特徴は、髪全体のボリュームダウン、髪の分け目や地肌が透けて見える、髪質が細く柔らかくなる、といった点に現れます。
画像検索で見るような典型的なAGAのパターンとは異なる、びまん性脱毛症ならではのサインを見逃さないようにしましょう。
髪全体のボリュームダウン
最も分かりやすい特徴は、髪全体のボリューム低下です。「以前より髪がぺたんとする」「スタイリング剤を使ってもすぐに崩れる」といった感覚は、髪が細く弱くなっているサインかもしれません。
特定の部位だけではなく、頭全体の髪の密度が低下しているように感じます。
地肌の透け感と分け目の広がり
髪の密度が低下すると、光が当たった時に地肌が透けて見えやすくなります。特に、つむじ周りや分け目が以前よりも目立つようになったと感じる方が多いです。
鏡で頭頂部を確認したり、他人から指摘されたりして気づくケースもあります。髪が濡れているときに、特に地肌が目立ちやすくなります。
髪質の変化(細毛・軟毛化)
びまん性脱毛症は抜け毛の増加だけでなく、生えている髪の質にも変化をもたらします。一本一本の髪が細くなり、ハリやコシがなくなって猫っ毛のように柔らかくなる傾向があります。
触った時の感触が以前と違う、髪に力強さが感じられないといった変化は、注意が必要な兆候です。
初期症状のセルフチェック
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| 枕元の抜け毛が増えた | 正常なヘアサイクルを超えた脱毛の可能性 |
| 髪を洗った時の抜け毛が気になる | 排水溝に溜まる髪の量が明らかに増えた場合 |
| 髪型が決まりにくくなった | 髪のハリ・コシ低下やボリュームダウンが原因 |
男性のびまん性脱毛症を引き起こす生活習慣と内的要因
男性のびまん性脱毛症は、栄養バランスの偏った食生活、睡眠不足、過度なストレスなどが主な原因です。
これらの要因が頭皮の血行不良を招き、髪の健やかな成長を妨げます。自分では気づかないうちに、髪の健康を損なう行動を繰り返しているかもしれません。
栄養バランスの偏りと食生活
髪は主にケラチンというタンパク質でできています。そのため、過度なダイエットや偏った食事によるタンパク質不足は、髪の成長を直接的に妨げます。
また、髪の健康維持には亜鉛やビタミン類も重要です。インスタント食品や外食中心の食生活は、これらの栄養素が不足しがちになり、脱毛のリスクを高めます。
髪の成長を支える栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の環境を整え、代謝を促進 | 豚肉、うなぎ、マグロ |
睡眠不足と成長ホルモンの関係
髪は、私たちが眠っている間に分泌される成長ホルモンによって成長が促進されます。特に、午後10時から午前2時は成長ホルモンの分泌が活発になるゴールデンタイムと呼ばれています。
慢性的な睡眠不足や質の悪い睡眠は、この成長ホルモンの分泌を妨げ、髪の健やかな成長を阻害する大きな原因となります。
精神的・身体的ストレスの影響
過度なストレスは自律神経のバランスを乱します。自律神経のうち交感神経が優位になると、血管が収縮し、頭皮への血流が悪化します。
血行不良は髪の毛母細胞に十分な栄養と酸素を届けられなくなり、結果として髪の成長が滞り、抜け毛や薄毛につながります。
仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなど、現代人を取り巻くストレスは深刻な問題です。
AGA(男性型脱毛症)との併発
男性の場合、びまん性脱毛症とAGAが併発しているケースも少なくありません。
生活習慣の乱れなどによって頭皮環境が悪化し、びまん性の脱毛が起きているところにAGAの症状が加わって、薄毛の進行が加速するケースがあります。
この場合、両方の原因に働きかける複合的な治療が必要です。
「まだ大丈夫」が危険信号?進行を加速させる意外な日常習慣
朝食を抜く、熱いシャワーで髪を洗う、長時間同じ姿勢でデスクワークをするといった日常的な習慣が、無意識のうちにびまん性脱毛症の進行を早めている可能性があります。
「自分はまだ若いから」「生活習慣には気を使っているつもり」そう思っている方でも、髪にとっては大きなダメージとなる行動をとっているかもしれません。
朝食抜きと空腹時間の長さ
多忙な朝、朝食を抜いてしまう習慣がある方も見受けられます。
朝食を抜くと、体はエネルギー不足の状態になります。生命維持に直接関係のない髪への栄養供給は後回しにされがちで、毛根が栄養不足に陥りやすくなります。
また、長時間の空腹は血糖値の乱れにもつながり、頭皮環境に悪影響を与える可能性があります。一日の始まりに、髪のための栄養をしっかり補給しましょう。
熱いシャワーと間違った洗髪方法
一日の疲れを癒すバスタイムですが、シャワーの温度が高すぎると頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまい、乾燥やかゆみの原因になります。
頭皮が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱い状態になります。
また、爪を立ててゴシゴシ洗う行為は、頭皮を傷つけ炎症を引き起こす原因です。指の腹で優しくマッサージするように洗うように心がけましょう。
正しいシャンプーの手順
- ぬるま湯で頭皮と髪を十分に予洗いする
- シャンプーを手のひらで泡立ててから髪につける
- 指の腹を使って頭皮をマッサージするように洗う
- すすぎ残しがないよう、時間をかけて丁寧に洗い流す
長時間のデスクワークとスマートフォンの使用
長時間同じ姿勢でパソコンやスマートフォンに向かっていると、首や肩の筋肉が緊張し、血行不良を引き起こします。
頭部は心臓より高い位置にあるため、ただでさえ血流が滞りやすい部位です。首や肩のコリは頭皮への血流をさらに悪化させ、髪の成長を妨げる要因になります。
定期的に休憩を取り、ストレッチなどで体をほぐす習慣を取り入れましょう。
デスクワーク中の簡単ストレッチ
| 部位 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 首 | ゆっくりと首を前後左右に倒す | 痛気持ちいい程度で止める |
| 肩 | 両肩を上げて、ストンと落とす | 数回繰り返す |
| 肩甲骨 | 背中で両手を組み、胸を張る | 肩甲骨を寄せる意識で行う |
専門クリニックで行うびまん性脱毛症の治療法
専門クリニックでは主に内服薬や外用薬を用いた治療、頭皮に直接有効成分を届ける注入治療、そして根本原因に働きかける生活習慣の指導などを組み合わせて、びまん性脱毛症の改善を目指します。
セルフケアだけでは改善が難しいときは、医師による正確な診断のもと、一人ひとりの症状に合わせた治療計画を立てる必要があります。
内服薬による治療
内服薬は体の内側から発毛を促進し、脱毛を抑制する治療の基本です。髪の成長に必要な栄養素を補給するサプリメントや、頭皮の血行を促進する効果のある薬などを使用します。
特に、AGAを併発している場合には、男性ホルモンに作用する治療薬を併用するケースもあります。医師の診断に基づき、適切な薬を処方します。
外用薬(塗り薬)による治療
頭皮に直接塗布するタイプの治療薬です。有効成分が毛根に直接作用し、発毛を促したり、頭皮の血行を改善したりする効果を期待します。
内服薬と併用すると相乗効果が期待できます。市販の育毛剤とは異なり、医療機関で処方される外用薬は、効果が認められた有効成分を高濃度で配合しています。
主な治療薬の種類
| 分類 | 主な作用 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 内服薬 | 血行促進、栄養補給、ホルモン調整 | 毎日決まった時間に服用 |
| 外用薬 | 頭皮の血行促進、毛母細胞の活性化 | 毎日頭皮に直接塗布 |
注入治療(メソセラピーなど)
注入治療は、髪の成長に有効な成分(成長因子、ミノキシジル、ビタミンなど)を、注射器や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する方法です。
有効成分を毛根の深い部分までダイレクトに届けられるため、効果を実感しやすいです。治療時の痛みは少なく、ダウンタイムもほとんどありません。
生活習慣指導と食事カウンセリング
薬物治療と並行して、びまん性脱毛症の根本原因である生活習慣の改善指導も行います。
専門のカウンセラーが、現在の食生活や睡眠、ストレス状況などを詳しくヒアリングし、一人ひとりに合った改善プランを提案します。
治療効果を最大限に高め、再発を防ぐためには、日々の生活の見直しがとても重要です。
治療の見通しと改善までの期間
びまん性脱毛症の治療効果を実感し始めるまでには、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。ヘアサイクルが正常化する過程であり、治療を根気強い継続が改善への鍵となります。
「本当に治るのか」といった不安を抱える方もいますが、適切な治療とセルフケアで改善が見込めます。
効果を実感できるまでの一般的な期間
髪にはヘアサイクル(毛周期)があり、治療を開始してすぐに髪が生え変わるわけではありません。多くの場合、治療効果を実感し始めるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。
初期段階では抜け毛が一時的に増える「初期脱毛」が起こる場合もありますが、これは乱れたヘアサイクルが正常化する過程で見られる好転反応の一つです。
治療期間の目安
| 期間 | 期待される変化 |
|---|---|
| 1〜3ヶ月 | 抜け毛の減少、初期脱毛の可能性 |
| 3〜6ヶ月 | うぶ毛の発生、髪にハリ・コシが出てくる |
| 6ヶ月以降 | 見た目の変化、ボリュームアップを実感 |
※効果には個人差があり、上記の期間はあくまで目安です。
治療効果を高めるためのポイント
治療効果を最大限に引き出すためには、医師の指示通りに薬を継続して使用しましょう。自己判断で中断すると、効果が得られないばかりか、症状が悪化する可能性もあります。
また、処方された薬だけに頼るのではなく、前述した生活習慣の改善にも積極的に取り組むと治療の成功率を高められます。
治療を中断した場合のリスク
治療によって改善した状態を維持するためには、継続的なケアが重要です。
治療を自己判断で中断してしまうと、びまん性脱毛症の原因が取り除かれていない場合、再び薄毛が進行し始める可能性があります。
症状が改善した後も医師と相談しながら、維持療法や予防的なケアに移行していくのが望ましいです。
自宅でできる予防とセルフケア
自宅でできるびまん性脱毛症の予防・改善策として、頭皮の血行を促進するマッサージ、ストレス管理、紫外線対策が有効です。
これらのセルフケアは、クリニックでの治療効果を高める上でも役立ちます。毎日の少しの心がけが頭皮環境を健やかに保ちます。
頭皮マッサージの実践
硬くなった頭皮は血行不良のサインです。頭皮マッサージは血行を促進し、毛根に栄養を届きやすくする効果が期待できます。
シャンプーの際やリラックスタイムなどに、指の腹を使って頭皮全体を優しく動かすようにマッサージしましょう。気持ち良いと感じる程度の力加減で行うのがポイントです。
頭皮マッサージの基本的なやり方
- 両手の指の腹で、こめかみから頭頂部に向かって円を描くようにマッサージする。
- 耳の上から頭頂部に向かっても同様に行う。
- 後頭部の生え際から頭頂部に向かって、指圧するように優しく押す。
ストレス管理とリラクゼーション
ストレスは血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こし、髪に悪影響を与えます。自分なりのストレス解消法を見つけることが重要です。
軽い運動や趣味の時間、湯船にゆっくり浸かるなど、心身をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。意識的に休息を取り、オンとオフのメリハリをつけることが大切です。
紫外線対策の重要性
頭皮は顔の2倍以上の紫外線を浴びていると言われています。紫外線は頭皮を乾燥させ炎症を引き起こすだけでなく、毛母細胞にダメージを与え、抜け毛や薄毛の原因となります。
外出時には帽子をかぶったり、髪用の日焼け止めスプレーを使用したりするなど、頭皮の紫外線対策を忘れずに行いましょう。
シーン別紫外線対策
| シーン | 推奨される対策 |
|---|---|
| 日常の外出 | 帽子、日傘、UVカットスプレー |
| レジャー・スポーツ時 | 通気性の良い帽子、こまめなスプレーの塗り直し |
| 屋内(窓際など) | UVカット機能のあるカーテンやフィルムの活用 |
びまん性脱毛症の男性に関するよくある質問
さいごに、男性のびまん性脱毛症について、患者さんからよくいただくご質問とその回答をまとめました。
- Qびまん性脱毛症は遺伝しますか?
- A
AGA(男性型脱毛症)ほど遺伝的要因は強くないと考えられています。
びまん性脱毛症は、遺伝よりも生活習慣やストレス、栄養状態といった後天的な要因が大きく影響して発症するケースが多いです。
ただし、体質的に頭皮環境が悪化しやすいといった間接的な遺伝要素が関わる可能性は否定できません。
- Q治療を始めたら、すぐに髪は生えてきますか?
- A
残念ながら、すぐに効果が現れるわけではありません。髪の毛には成長期・退行期・休止期というヘアサイクルがあり、治療はこのサイクルを正常に戻すことから始まります。
多くの方が抜け毛の減少や髪質の改善といった変化を感じ始めるまでに、早くとも3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要します。根気強く治療を続ける努力が何よりも重要です。
- Q市販の育毛剤では治りませんか?
- A
市販の育毛剤は主に頭皮環境を整え、今ある髪を健康に保つのを目的とした「医薬部外品」が多いです。
一方で、クリニックで処方する治療薬は、発毛を促進する効果が認められた「医薬品」です。
びまん性脱毛症のように、すでに症状が進行している場合は、医学的根拠に基づいたクリニックでの治療が改善への近道です。
まずは専門医に相談し、ご自身の症状に合った治療法の選択をおすすめします。
- Q治療をやめると、また薄毛に戻ってしまいますか?
- A
びまん性脱毛症の原因となった生活習慣などが改善されていない場合、治療を中断すると症状が再発する可能性があります。
症状が改善した後も良い状態を維持するために、医師と相談の上で治療薬の量を調整したり、生活習慣の改善を継続したりすることが大切です。
自己判断で治療を中断するのは避けてください。
参考文献
LEW, Bark-Lynn; SHIN, Min-Kyung; SIM, Woo-Young. Acute diffuse and total alopecia: a new subtype of alopecia areata with a favorable prognosis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2009, 60.1: 85-93.
FUKUYAMA, Masahiro, et al. Elucidation of demographic, clinical and trichoscopic features for early diagnosis of self‐healing acute diffuse and total alopecia. The Journal of Dermatology, 2020, 47.6: 583-591.
SINCLAIR, Rodney D.; DAWBER, Rodney PR. Androgenetic alopecia in men and women. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 167-178.
STOUGH, Dow, et al. Psychological effect, pathophysiology, and management of androgenetic alopecia in men. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2005. p. 1316-1322.
MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.
ROSS, Elizabeth K.; SHAPIRO, Jerry. Management of hair loss. Dermatologic clinics, 2005, 23.2: 227-243.
BANKA, Nusrat; BUNAGAN, MJ Kristine; SHAPIRO, Jerry. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 129-140.
BERGFELD, Wilma. Diffuse hair loss: its triggers and management. Cleve Clin J Med, 2009, 76.6: 361-370.