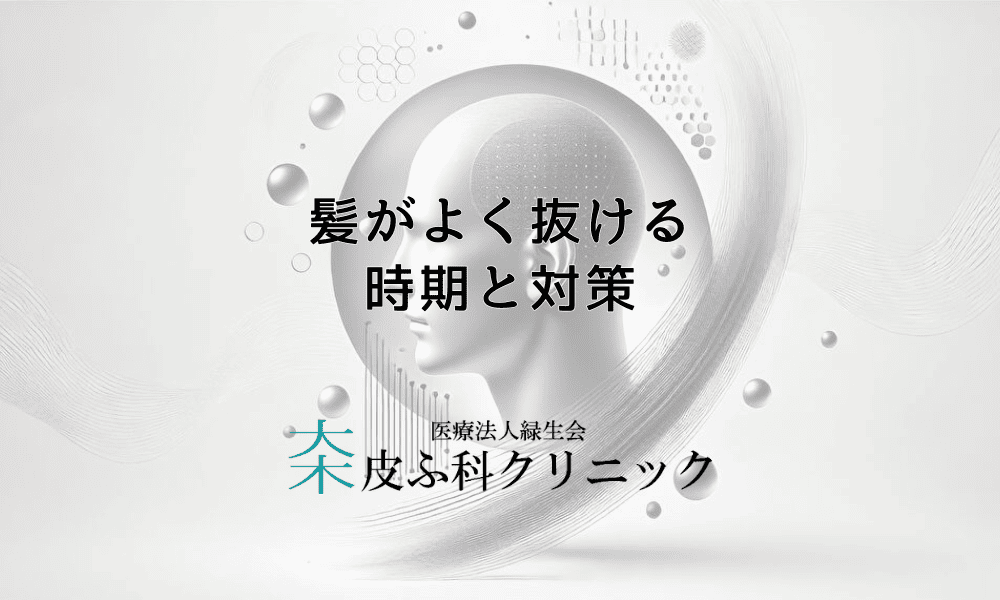髪の毛が多く抜けると感じる時期は、人によって異なるものの、季節や気温・湿度の変化が大きな影響を与えます。
とくに「髪の毛がめっちゃ抜ける」と感じるときは、日常のケアや食生活だけでなく、ストレスやホルモンバランスの乱れなど、複数の要因が絡んでいることも考えられます。
この記事では、髪がよく抜ける時期にどのような特徴があるのか、季節による抜け毛の変化を踏まえて、予防法や日常的に取り組める対策を詳しく解説します。
髪がよく抜ける時期に起こりやすい特徴
季節が移り変わるときなどに髪の毛がよく抜けると感じる人は少なくありません。どのような特徴が重なりやすいのかを知ることは、早めの対処のために重要です。
季節の変わり目に起こる頭皮環境の乱れ
季節が変わると気温や湿度が大きく変化します。頭皮の皮脂分泌量も環境の影響を受けて増減し、乾燥や皮脂過剰などのトラブルが起こりやすくなります。
頭皮環境が乱れると髪の成長期が短くなることがあり、抜け毛が増える原因の1つになります。
ホルモンバランスの変化との関連
人間の身体は季節の変化に合わせてホルモンバランスにも変化が生じます。
特に春や秋は、気温や日照時間の変動が大きいため、自律神経が乱れてホルモンの分泌パターンに影響を与えやすいです。
これが抜け毛を引き起こす一因となり、髪の毛がよく抜けると感じるようになります。
ストレスの増大
年度の切り替わりや職場・学校の環境変化などが重なる春や秋には、ストレスを感じる場面も増えます。
ストレスホルモンが増えるため頭皮の血行が悪くなり、髪の成長を支える毛乳頭や毛包への栄養供給が滞りがちになります。その結果、抜け毛の増加につながるケースが多いです。
生活習慣の乱れ
季節の移り変わりに伴い生活リズムが乱れると、睡眠不足や食生活の偏りが見られる場合があります。
これもまた髪の成長を支える栄養素の不足や、頭皮への負担増加を招きます。
とくに急激なダイエットなどを行うと、髪の材料となるタンパク質やミネラル、ビタミンなどが不足しやすく、抜け毛リスクが高まります。
季節別・頭皮トラブルの主な要因
| 季節 | 気候の特徴 | 主な頭皮トラブル | 抜け毛増加の要因 |
|---|---|---|---|
| 春 | 気温上昇・湿度変化が大きい | 皮脂分泌量の乱れ | ホルモンバランスの変化による抜け毛 |
| 夏 | 高温多湿 | 汗や皮脂の過剰分泌 | 頭皮の湿度過多・紫外線ダメージ |
| 秋 | 気温低下・乾燥が始まる | 頭皮の乾燥・ターンオーバー乱れ | 夏のダメージ蓄積とホルモンバランスの乱れ |
| 冬 | 低温・乾燥 | 頭皮の乾燥・血行不良 | 冷えと乾燥による髪の成長期への悪影響 |
季節による抜け毛のメカニズム
季節に伴う抜け毛の増減は、体内リズムや外的環境など、複数の要素が複雑に絡んでいます。
そのメカニズムを理解すると、なぜ「髪の毛がめっちゃ抜ける」と感じる時期があるのかを把握しやすくなります。
自律神経とホルモンのバランス
自律神経は体温調節や血圧調整など、身体の基礎的な機能を担っています。季節の移り変わりが激しい時期は、自律神経が一時的に乱れやすく、ホルモン分泌にも影響を与えます。
髪の成長に関係の深いホルモンの一例として、男性ホルモンのテストステロンや女性ホルモンのエストロゲンが挙げられます。
バランスが乱れると、髪の成長サイクルに影響が出て抜け毛が増えます。
紫外線や乾燥など外的要因
夏は紫外線の量が増え、頭皮や髪に強いダメージを与えます。紫外線を浴びることで髪のキューティクルが破壊されやすく、枝毛や切れ毛が増えやすいです。
秋に髪の毛がよく抜けると感じる一因として、夏に受けたダメージの蓄積が秋頃に表面化しやすい点が考えられます。
冬は乾燥によって頭皮のバリア機能が低下し、血行不良や皮脂の分泌量低下などが抜け毛を増やす要因になります。
毛周期の変化
髪は成長期・退行期・休止期の3つの段階を経て生え変わります。
季節の変化が毛周期に与える影響は個人差が大きいですが、秋頃は休止期に入る髪の割合が増えるケースが見られます。
これが「秋になると髪が抜けやすい」と言われる理由の1つです。
髪の成長サイクルの概要
| 段階 | 期間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 成長期 | 2年~6年程度 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が長く太く成長する段階 |
| 退行期 | 約2週間 | 毛母細胞の活動が衰え始め、髪の成長が停滞していく段階 |
| 休止期 | 約3ヶ月~4ヶ月 | 成長が止まり、古い髪が抜け落ち、新しい髪の準備が進む |
栄養状態の影響
タンパク質やビタミン、ミネラルなど、髪の成長に必要な栄養素を十分に摂取できないと、季節の変化による負荷がより強く作用してしまいます。
体調を崩しやすい時期にこそ、食事のバランスが崩れると髪がもろくなり、抜けやすくなる場合があります。
髪がよく抜ける時期の対策ポイント
髪の抜け毛が増える時期を事前に把握し、適切な対策を行うことが重要です。
以下の対策を日常生活に取り入れると、抜け毛のリスクを抑えやすくなります。
頭皮マッサージで血行促進
頭皮の血行が悪い状態が続くと、毛乳頭や毛包への栄養供給が滞り、抜け毛につながります。
シャンプー時や入浴後に、指の腹で優しくマッサージすると血流が改善し、頭皮環境を整えるのに役立ちます。
シャンプーや洗髪方法の見直し
シャンプーの選択肢や洗い方も抜け毛対策に欠かせない要素です。
必要以上に強く洗いすぎると頭皮を傷つけたり、皮脂を過剰に取り除いてしまうケースがあります。
逆に洗浄力が弱すぎるものを使うと、汗や皮脂が頭皮に残り、毛穴が詰まる原因になる場合もあります。
シャンプー選びの例
| シャンプータイプ | 特徴 | 適した頭皮・髪質 |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | マイルドな洗浄力で頭皮を優しく洗う | 敏感肌や乾燥しやすい頭皮 |
| ノンシリコン | 髪の軽さを感じやすく、ボリュームアップが期待できる | 皮脂量が多い方やボリュームダウンを感じる方 |
| スカルプ系 | 頭皮ケア成分が含まれ、毛穴汚れをすっきり洗う | 皮脂が過剰な頭皮や抜け毛が気になる方 |
栄養バランスの確保
髪を育てるためには、タンパク質、ビタミンB群、亜鉛、鉄分などが大切です。これらをバランスよく摂取すると、髪の成長を支える土台を整えられます。
外食やコンビニ食が多い方は、あらためて食生活を振り返るとよいでしょう。
生活リズムの安定
睡眠不足や不規則な生活リズムは、ホルモンバランスや自律神経の乱れを加速させます。
決まった時間に就寝・起床することや、適度な運動を取り入れることが抜け毛予防につながります。
生活リズムを整えるための具体的な行動
- 就寝前1時間はスマートフォンを見ない
- 軽いストレッチやヨガなどで身体をほぐす
- 夕食の時間を寝る3時間前までに済ませる
- 定期的にウォーキングや軽いジョギングを行う
季節別に見る抜け毛対策のコツ
季節によって頭皮環境が異なり、必要なケアも変わります。各季節ごとに意識すべき点を押さえておくと、髪の毛がよく抜けるリスクを軽減しやすくなります。
春:環境変化への順応
春は気温上昇や新生活のスタートなど、環境が大きく変わる時期です。
ホルモンバランスの乱れや生活リズムの変化から、ストレスを強く受けやすくなります。
頭皮がベタつきやすくなる半面、花粉やほこりによる刺激も増えるため、洗いすぎや摩擦にも注意が必要です。
春の頭皮ケア対策
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 洗髪後の保湿 | 洗髪後に頭皮用の保湿ローションなどで軽く保湿する |
| 花粉・ほこり対策 | 帽子やスカーフなどで頭皮への花粉やほこりの付着を抑える |
| 心身のストレス管理 | 十分な睡眠と軽い運動でストレスをためにくい習慣を心がける |
夏:紫外線と汗対策
夏は紫外線量が増え、強い日差しが髪や頭皮にダメージを与えます。さらに高温多湿の環境で頭皮が蒸れやすく、雑菌が繁殖しやすくなるため、頭皮トラブルが起きやすいです。
紫外線対策として帽子を着用する、髪の毛専用の日焼け止め商品を使用するなどの工夫が大切です。
秋:夏のダメージの影響からの回復
夏のダメージが蓄積し、秋頃に抜け毛が増えたと感じる人が多いです。
頭皮や髪が乾燥しやすくなる季節でもあるため、保湿ケアを重視するとよいでしょう。
秋は食欲が増進しやすい時期ですが、暴飲暴食は髪に必要な栄養バランスを乱す原因にもなるため注意が必要です。
秋の頭皮ケアと生活習慣
- 髪と頭皮の保湿を意識して、保湿成分入りのシャンプーやトリートメントを利用する
- 夏の紫外線ダメージをリセットするために毛先のトリミングやヘアマスクを取り入れる
- 食欲の秋でも栄養バランスを考慮し、タンパク質とビタミンを意識した食事を心がける
- 適度な運動や半身浴で身体を温め、血行を促進する
冬:乾燥と冷え対策
冬は気温が下がり、空気も乾燥します。頭皮が乾燥すると皮脂分泌が乱れ、フケやかゆみなどのトラブルを招きやすいです。
身体が冷えると血行不良が起こり、髪の成長を阻害します。
暖房の使用でさらに空気が乾燥しやすくなるため、加湿器の利用や保湿ローションの使用などを検討するとよいでしょう。
冬に意識したい頭皮保湿対策
| 方法 | 主な効果 |
|---|---|
| 加湿器を使う | 部屋の湿度を保つことで頭皮の乾燥を防ぐ |
| ぬるま湯で洗髪 | 熱すぎるお湯は頭皮の皮脂を奪いすぎないようにする |
| 保湿ローションやオイル | 頭皮を乾燥から保護し、フケやかゆみを抑える |
抜け毛を予防するための具体的な生活習慣
抜け毛を予防するためには、日々の生活習慣の見直しが大切です。小さな工夫を重ねることで、髪と頭皮の状態を良好に保ちやすくなります。
バランスの良い食事
タンパク質やミネラルが不足すると、髪の成長が阻害されます。肉や魚、大豆製品、野菜や果物などをバランスよく摂取することが欠かせません。
特に亜鉛やビタミンB群は髪の生成をサポートする働きがあるため、牡蠣やレバー、卵などを取り入れると良い結果が期待できます。
髪の成長を助ける栄養素と食品
| 栄養素 | 食品例 | 働き |
|---|---|---|
| タンパク質 | 肉類、魚類、豆類 | 髪の主成分であるケラチンの材料 |
| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、レバー | 毛母細胞の分裂やタンパク質合成を助ける |
| ビタミンB群 | レバー、卵、豚肉、玄米 | 新陳代謝を促進し、髪の生成をサポート |
| 鉄分 | ほうれん草、レバー、赤身肉 | 酸素供給を促進し、血行をサポート |
十分な睡眠
睡眠中に成長ホルモンが分泌され、細胞が修復・再生されます。睡眠不足が続くとホルモン分泌が乱れ、頭皮環境にも悪影響を及ぼします。
就寝時間を一定に保ち、最低でも6時間程度の睡眠を確保するのが理想的です。
ストレスケア
日常的にストレスを感じていると自律神経やホルモンバランスが乱れ、抜け毛につながりやすくなります。
趣味や運動などで気分転換の時間をつくる、気分が落ち込んだら軽い散歩をするなど、自分なりのリラックス方法を見つけると良いです。
適度な運動
ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を習慣化すると、血行が促進されて頭皮への栄養供給が高まります。
また適度な運動はストレスの軽減にも役立ち、髪だけでなく全身の健康維持に役立ちます。
薄毛やAGAが疑われる場合のチェック方法
抜け毛が増えたと感じるときは、単なる季節的な変化だけではなく、AGA(男性型脱毛症)や女性のホルモンバランスによる薄毛などの可能性もあります。
早めに医療機関で相談したりセルフチェックすることが重要です。
AGAの主な特徴
AGAは男性ホルモンであるジヒドロテストステロン(DHT)の影響を受けて発症します。
前頭部から生え際が後退する、頭頂部が薄くなるといった典型的なパターンが多いですが、個人差があります。
AGAと一般的な抜け毛の違い
| 項目 | AGAの特徴 | 一般的な抜け毛 |
|---|---|---|
| 発症部位 | 前頭部や頭頂部など特定部位が中心 | 全体的に髪が抜けることが多い |
| 進行度 | 放置すると徐々に進行して薄毛が目立ちやすくなる | 季節的な要因などにより、ある程度落ち着く場合がある |
| 症状の進み方 | ゆるやかに継続し、薄毛範囲が拡大していく | 一時的に抜け毛量が増えても回復するケースが多い |
女性の薄毛トラブル
女性は妊娠・出産・更年期など、ホルモンバランスが大きく変化するイベントがあり、これが薄毛の原因となる場合もあります。
また、過度なダイエットや偏った栄養摂取は、女性に多いびまん性脱毛(頭髪全体が薄くなるタイプ)を引き起こしやすくなります。
クリニックでの診察の流れ
薄毛や抜け毛の悩みでクリニックを受診した場合、問診や視診、必要に応じて血液検査などが行われます。
症状の原因がホルモンバランスの乱れや栄養不足にあるのか、AGAなのかを見極めてから、内服薬や外用薬などの治療方針が決定されます。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| カウンセリング | 抜け毛や薄毛に関する症状のヒアリング |
| 視診・触診 | 頭皮や髪の状態をチェック |
| 必要に応じた検査 | 血液検査やホルモン値の測定 |
| 治療方針の選定 | 内服薬、外用薬、生活習慣の改善指導など |
抜け毛対策におけるクリニックの役割
抜け毛が一時的なものであれば生活習慣の改善で対処できることも多いですが、AGAや女性特有の薄毛など、医療的ケアが必要なケースもあります。
クリニックの専門的なサポートを活用すると、根本原因に働きかけやすくなります。
専門家による診断の重要性
抜け毛が増えて髪の毛がめっちゃ抜ける状態が続くとき、自分の判断だけでは対処法が限定的になる場合があります。
専門家に相談すると原因に合わせた治療法を提案してもらえるため、治療効果も高まりやすくなります。
クリニックでのケア方法の一例
| ケア方法 | 内容 | 期待できるメリット |
|---|---|---|
| 内服薬(フィナステリドなど) | DHT(ジヒドロテストステロン)の産生を抑制 | AGAなど男性型脱毛症の進行を緩やかにする |
| 外用薬(ミノキシジルなど) | 頭皮に直接塗布し血行を促進 | 髪の成長を促し、抜け毛を減らす |
| メソセラピー | 頭皮に成長因子やビタミンを注入 | 毛包に直接アプローチし、発毛をサポート |
| 生活習慣の指導 | 栄養・睡眠・運動などを総合的に見直す | 抜け毛改善だけでなく健康全般の底上げにつながる |
メリットと注意点
クリニックでの治療は、原因を特定したうえで効果的な治療を受けられる反面、治療費や通院の手間がかかる場合があります。
治療効果を高めるには、専門家の指導だけでなく、患者さん自身が生活習慣改善などを積極的に行う姿勢も重要です。
カウンセリングやアフターケアの充実
治療を開始した直後に劇的な改善が見られるわけではなく、定期的な通院で経過をチェックしながら進めていくことが必要です。
カウンセリングやアフターケアが充実しているクリニックを選ぶと、長期的に取り組みやすくなります。
よくある質問
髪がよく抜ける時期や、季節による抜け毛の変化などを踏まえると、多くの人が抱える疑問や不安があります。ここでは、抜け毛に関してよくある3つの質問を示します。
- Qシャンプーの回数は毎日がいいの?
- A
髪の長さや皮脂分泌量、汗をかく量によって適切な回数は変わります。
皮脂が多い方や汗をかきやすい方は毎日洗うほうが頭皮環境を清潔に保ちやすいです。一方で、乾燥傾向が強い方は1日おきでも十分な場合があります。
ただし、洗わないと頭皮の汚れが蓄積し、抜け毛につながる可能性があるため、頭皮の状態を見ながら判断してください。
- Q抜け毛防止のために髪を短く切ったほうがいいの?
- A
髪を短く切ること自体が直接的に抜け毛を減らすわけではありません。
ただし、髪が長い場合は抜け毛が目立ちやすく、髪の絡まりやシャンプー時のダメージが増えやすくなります。
ショートヘアやミディアムヘアにすると、洗いやすさや乾かしやすさが向上し、頭皮環境を清潔に保ちやすいというメリットがあります。
- Q育毛剤は誰でも使って大丈夫?
- A
市販の育毛剤やスカルプケア商品は、基本的に多くの方が使用できます。
しかし、アレルギー体質や頭皮トラブルがある方は、成分によって刺激を感じる場合もあるため、パッチテストを行うか、医師や薬剤師に相談することが大切です。
持病がある方や妊娠中・授乳中の方は、成分の安全性を確認したうえで使用を検討してください。
参考文献
RANDALL, VALERIE A.; EBLING, F. J. G. Seasonal changes in human hair growth. British Journal of Dermatology, 1991, 124.2: 146-151.
KUNZ, Michael; SEIFERT, Burkhardt; TRÜEB, Ralph M. Seasonality of hair shedding in healthy women complaining of hair loss. Dermatology, 2009, 219.2: 105-110.
COURTOIS, M., et al. Periodicity in the growth and shedding of hair. British Journal of Dermatology, 1996, 134.1: 47-54.
HSIANG, E. Y., et al. Seasonality of hair loss: a time series analysis of Google Trends data 2004–2016. British Journal of Dermatology, 2018, 178.4: 978-979.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
PAUS, Ralf. Therapeutic strategies for treating hair loss. Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies, 2006, 3.1: 101-110.
ROSS, Elizabeth K.; SHAPIRO, Jerry. Management of hair loss. Dermatologic clinics, 2005, 23.2: 227-243.