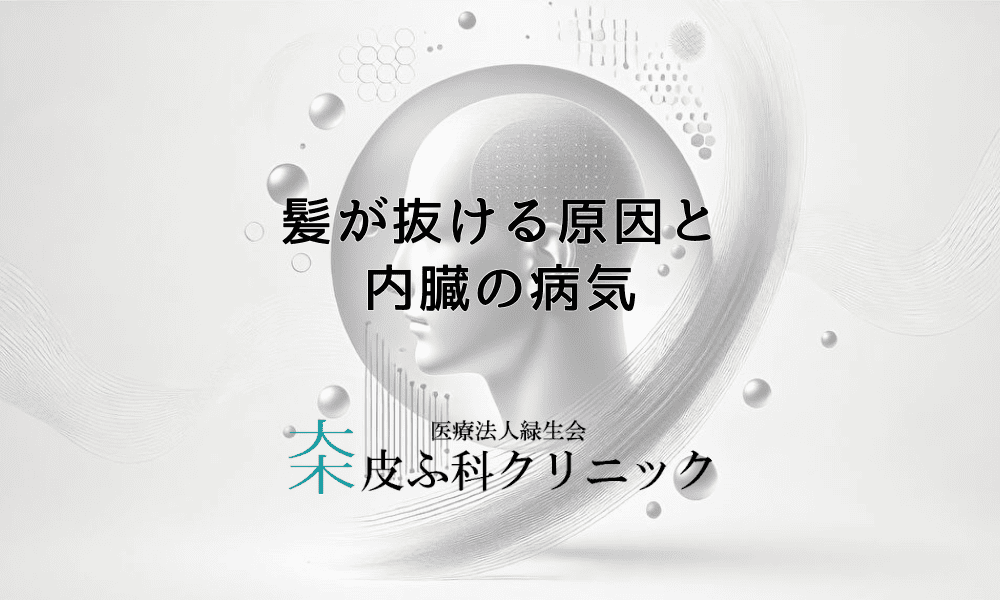髪が抜ける悩みを抱える方が増えていますが、加齢だけではなく、生活習慣やストレス、人によっては内臓の病気などが抜け毛を引き起こす要因として考えられます。
髪は見た目の印象やセルフイメージに深く関わるため、抜け毛が増えると精神的な負担も大きくなりがちです。
この記事では、頭髪が抜けるメカニズムや内臓機能のトラブルと髪の関係、栄養・生活習慣との結びつき、そしてAGA治療・薄毛治療の選択肢にいたるまでを幅広く解説します。
髪が抜けるメカニズムとは
髪の毛は一定の周期で生え替わりますが、そのサイクルが乱れると抜け毛が増加して薄毛のリスクが高まります。
内臓機能との関連を理解するうえでも、まずは髪がどのように成長し、なぜ抜けていくのかを知ることが重要です。
ヘアサイクルの基本
髪の毛は成長期・退行期・休止期を経て抜け落ちます。成長期は髪が伸び続け、退行期は毛根が衰えて短くなり、休止期に入った毛は自然に抜け落ちます。
このサイクルは一般的に数年かけて繰り返され、常に一定の本数が抜けたり生えたりし続けます。
ヘアサイクルの概要
| 段階 | 主な特徴 | 期間 |
|---|---|---|
| 成長期 | 毛母細胞が活発に分裂し髪が伸びる | 2〜6年程度 |
| 退行期 | 毛根が縮小し成長が止まる | 2〜3週間程度 |
| 休止期 | 抜け落ちる準備が整う | 3〜4カ月程度 |
髪は頭皮の毛母細胞によって生成され、そこに栄養や酸素が供給されることでしっかりした毛に育ちます。
血行不良や栄養不足があると、成長期の髪の毛が十分に成長できず、休止期へ移行するスピードが早まり、抜け毛が目立つようになります。
薄毛と抜け毛の違い
抜け毛が多いと、すぐに「薄毛になった」と思い込む方がいますが、実は髪の全体量が減る状態を薄毛と呼び、抜け毛自体はヘアサイクルの一環として日常的に起こります。
髪のボリュームが顕著に減ってきたと感じたら、以下のような要因を疑う必要があります。
- ヘアサイクルが乱れている
- 栄養不足で髪がうまく育たない
- ホルモンバランスが影響している
- 内臓の病気による体調不良が関係している
薄毛は継続的な抜け毛の増加と新たな髪の成長不足が合わさった結果といえます。
短期間で髪が極端に少なくなったと感じたら、単なる加齢の影響だけではない可能性を考慮したほうがよいでしょう。
ホルモンバランスの乱れ
男性の場合、男性ホルモンの働きが髪に大きく影響します。
男性型脱毛症と呼ばれるAGAはジヒドロテストステロン(DHT)という物質の増加によって引き起こされるケースが多く、前頭部や頭頂部の髪が薄くなる特徴があります。
一方、女性でもホルモンバランスの乱れによって抜け毛が増えるケースがあります。妊娠や出産、閉経期などホルモンの変動期になると、一時的に抜け毛が増えやすくなります。
また、過度なダイエットやストレスは女性ホルモンの分泌を乱し、髪の健康に悪影響を及ぼすときがあります。
遺伝的要因とストレス要因
抜け毛や薄毛は遺伝する傾向があります。親族に薄毛の方がいる場合、自身も薄毛になりやすい可能性があります。
ただし、遺伝的素因があっても、必ずしも早期に髪が抜けるわけではありません。生活習慣や栄養バランス、ストレスなどの要因が加わって、抜け毛の進行が促される場合があります。
ストレスは血行不良や自律神経の乱れを引き起こします。慢性的なストレス下では、成長期の髪が休止期に入りやすくなり、抜け毛が増えると報告されています。
過度なストレスを抱え込まないよう、日頃からリラックスできる習慣を取り入れたほうが頭髪の健康にもよい影響を与えます。
内臓の病気と頭髪の関係
髪の成長には栄養素が欠かせませんが、その栄養素を処理・吸収し、全身に届けるのは内臓の働きです。
内臓の病気によっては毛髪に届く栄養が不足したり、体の恒常性が崩れたりして髪が抜ける状態を引き起こすケースがあります。
肝臓の働きと毛髪への影響
肝臓は体内の毒素を分解し、栄養素を代謝する重要な臓器です。
肝臓の機能が低下すると、たんぱく質やビタミン、ミネラルなどの代謝が滞り、頭髪を健やかに保つための栄養が十分に行き渡らなくなります。
- 栄養の利用効率が下がる
- ホルモンバランスが乱れる
- 血液中の老廃物が増える
慢性的な肝臓の病気があると、このような背景によって髪が抜ける原因が強まる場合があります。
また、お酒を飲みすぎると肝臓に負担をかけるため、抜け毛の原因にもなりやすいです。
肝機能低下時に起こりやすい症状
| 症状 | 体への影響 |
|---|---|
| 倦怠感 | 疲労が取れにくい |
| 皮膚のかゆみ | 胆汁酸の増加による肌トラブル |
| 食欲不振 | 栄養摂取量の減少 |
| 抜け毛の増加 | 栄養やホルモンバランスの乱れ |
腎臓機能の低下が引き起こす可能性
腎臓は血液をろ過し、不要な老廃物を体外に排出する役割を担っています。
腎臓の機能が落ちると、体内の老廃物が増加し、全身のめぐりが悪化しやすくなります。血液循環が悪くなれば、頭皮への栄養供給が低下して抜け毛が増えやすいです。
腎臓の病気が続くと、貧血やむくみなども出やすくなり、体力が低下します。日常生活での疲労が回復しにくくなるため、髪の成長にも悪影響が及ぶ可能性があります。
毛髪だけでなく体全体の不調を感じるときは、内科的な検査を受けることを検討する必要があります。
消化器系のトラブルと栄養吸収
胃腸や小腸、大腸などの消化器系にトラブルがあると、食事から摂取した栄養をうまく吸収できません。
栄養不足の状態が長期化すると、髪に必要なタンパク質やミネラルが欠乏し、髪が抜ける量が増えてしまう可能性があります。
消化器系の疾患には胃潰瘍や慢性胃炎、過敏性腸症候群など多岐にわたるものがありますが、いずれのケースでも栄養の吸収効率が悪くなると髪の成長にブレーキがかかりやすくなります。
特にタンパク質が不足すると、髪の主成分であるケラチン合成が円滑に行われなくなり、コシやハリが失われがちです。
消化器系の不調と抜け毛の関連
| 消化器系の不調の例 | 頭髪への影響 |
|---|---|
| 慢性的な下痢 | ミネラル・ビタミンが不足しやすい |
| 胃もたれや食欲不振 | 総カロリーやたんぱく質の摂取不足 |
| 腸内環境の悪化 | 代謝全般の低下 |
| 慢性胃炎・胃潰瘍 | 食事制限による栄養不足 |
甲状腺疾患による代謝変化
甲状腺ホルモンは代謝に深く関わるホルモンです。甲状腺機能が亢進しても低下しても、髪にトラブルが生じる可能性があります。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)の場合は代謝が活発になりすぎて髪が細くなり、抜けやすくなる場合があり、逆に甲状腺機能低下症(橋本病など)では代謝が落ちることで全身のエネルギー不足が生じ、髪の質が悪化して抜け毛が増えるケースがあります。
甲状腺ホルモンの乱れは体重変化や疲労感、動悸や便秘など多岐にわたる症状を伴う場合があります。
抜け毛だけでなく、こうした症状が継続する場合は、甲状腺の検査を視野に入れるとよいでしょう。
栄養バランスと食生活の重要性
髪の健康は内臓の健康と表裏一体です。適切な栄養が摂取できなければ、身体機能だけでなく頭髪にも影響が出ます。
タンパク質不足が招く毛髪トラブル
髪の主成分はケラチンと呼ばれるタンパク質です。肉や魚、大豆製品などからタンパク質をしっかり摂取していないと、髪の土台となるケラチンの生成が滞り、髪が細くなったり抜けやすくなったりします。
極端な炭水化物中心の食生活や無理なダイエットは要注意です。
タンパク質源と含有量
| 食品 | 約100gあたりのタンパク質量 |
|---|---|
| 鶏ささみ | 約23g |
| 木綿豆腐 | 約7g |
| 鮭 | 約22g |
| 納豆 | 約16g |
| 牛モモ肉 | 約21g |
しっかりした筋肉をつけるうえでもタンパク質は重要ですが、頭髪の観点でも大事な栄養素です。
食事で不足していると感じたら、無理のない範囲でプロテイン製品を取り入れる方法もあります。
ビタミン・ミネラルの役割
ビタミンやミネラルも、髪をはじめ全身の健康にとって重要です。
特にビタミンB群や亜鉛、鉄分は頭髪の成長に関与します。
亜鉛はたんぱく質合成の補助を行い、鉄分は酸素を運ぶヘモグロビンの材料になるため、不足すると頭皮や毛根が十分な酸素を得られず抜け毛が増えるかもしれません。
| 栄養素 | 役割 |
|---|---|
| ビタミンB群 | エネルギー代謝や細胞増殖を助ける |
| 亜鉛 | ケラチン合成をサポート |
| 鉄分 | 血液中のヘモグロビンを形成し酸素供給を助ける |
| ビタミンC | コラーゲン合成や鉄分吸収をサポート |
こうした栄養素は野菜や果物、海藻類、魚介類などに多く含まれます。
偏った食事を続けると、髪の成長に必要な栄養が行き届かず、さまざまなトラブルが起こりやすくなります。
食生活と内臓の病気
内臓の病気がある方は、医師の指示に従った食事制限が必要な場合があります。食事制限の内容によっては特定の栄養素が不足しやすくなるため、髪の状態を悪化させるリスクが高まることも考えられます。
たとえば腎臓が悪い場合はタンパク質の摂取量を制限する場合があり、髪にとって大切なケラチン合成がスムーズにいかなくなるケースもあります。
塩分や糖分、脂質の摂りすぎは生活習慣病を引き起こし、結果的に抜け毛の原因につながりやすくなります。
内臓の病気予防だけでなく、髪のためにも栄養バランスの取れた食事を意識したほうがよいでしょう。
内臓と栄養素の関係
| 内臓の病気 | 注意が必要な栄養素 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 腎機能障害 | たんぱく質制限 | ケラチン合成に必要なたんぱく質不足 |
| 肝疾患 | ビタミン・ミネラル代謝の低下 | 抜け毛の増加、髪質の低下 |
| 糖尿病など | 糖質のコントロール | 栄養供給が乱れ、頭皮環境が悪化 |
栄養の偏りを防ぐポイント
栄養の偏りを防ぐには、毎日の食事で多様な食品をバランスよく組み合わせると良いです。外食や加工食品に頼りがちだと塩分や脂質、糖質を過剰に摂取しやすくなります。
自炊が難しい場合でも、コンビニ弁当や惣菜を選ぶ際には野菜が多いメニューやタンパク質がしっかり含まれたメニューを選ぶように意識してみてください。
ストレスと生活習慣が与える影響
現代社会ではストレスによる自律神経の乱れや生活習慣の乱れが、内臓の病気と同様に抜け毛の引き金になりやすいです。
睡眠不足や生活習慣病、喫煙・飲酒なども頭髪に悪影響を及ぼします。
睡眠不足が起こすホルモン乱れ
成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されるため、睡眠不足になると細胞の修復や髪の再生力が損なわれます。
また、十分な休息が取れない状態が続くとストレスホルモンが増加し、自律神経のバランスが乱れ、頭皮の血行不良を引き起こします。
髪の毛に栄養を届けるには、良質な睡眠が必要です。
睡眠と頭髪の関連
- 深い眠りの時間帯に成長ホルモンの分泌が増える
- 自律神経が整いやすくなり血行がスムーズになる
- ホルモンバランスが整うことで髪の成長が促される
- 早寝早起きの習慣はストレス軽減にも役立つ
生活習慣病と頭髪の関係
高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病にかかると、血液循環やホルモン分泌が乱れやすくなります。頭皮の血管にも悪影響が及ぶため、抜け毛が増えるときがあります。
生活習慣病は内臓の病気の一種でもあり、髪にとってはダブルパンチになる可能性が高まります。
喫煙・飲酒と毛髪への悪影響
喫煙は血管を収縮させ、血液中の酸素供給を妨げる原因になります。頭皮への血流が低下すると、髪の毛に十分な栄養や酸素が行き渡りにくくなり、抜け毛が増える可能性が高まります。
飲酒についても、過度な量を摂取すれば肝臓に負担をかけ、栄養代謝を滞らせる要因になります。
飲酒の際は適度な量を心がけ、水分補給をしながら楽しむことが大切です。喫煙をやめるのが難しい場合は、本数を徐々に減らすなどの工夫を考えてみてください。
運動不足と血行不良
適度な運動は血行を促進し、頭皮にも栄養が行き渡りやすい環境を作ります。運動不足に陥ると、全身の代謝が低下しやすく、頭皮環境も悪化しやすくなります。
ウォーキングや軽い筋トレなどを継続すると、体重コントロールにも役立ち、生活習慣病の予防にもつながります。
運動の種類と期待できる効果
| 運動の種類 | 期待できる効果 |
|---|---|
| ウォーキング | 血行促進、ストレス緩和 |
| 軽いジョギング | 心肺機能向上、脂肪燃焼 |
| 筋力トレーニング | 基礎代謝アップ、血糖値コントロール |
| ヨガ・ストレッチ | リラックス効果、自律神経の安定 |
髪の抜け毛を減らすためにできること
髪が抜ける状態を改善するには、内臓や生活習慣、栄養バランスなど複数の要素を総合的に見直す必要があります。
ここでは頭皮環境の整え方や適切なシャンプーの選び方、サプリメントの利用法など、具体的な方法について紹介します。
頭皮環境の整え方
頭皮の清潔さや柔軟性は、髪の健康に直結しています。
皮脂や汚れが溜まりすぎると毛穴が詰まりやすくなり、抜け毛を誘発する可能性があります。一方で過剰な洗浄は頭皮を乾燥させ、かえってフケやかゆみを引き起こす原因になります。
そのため、適度な洗髪と保湿が鍵となります。
| アプローチ | 内容 |
|---|---|
| 適度な洗髪 | 1日1回程度、優しくマッサージをしながら洗う |
| 頭皮マッサージ | 血行を促進し、毛母細胞への栄養供給をスムーズにする |
| 保湿ローションの使用 | 乾燥を防ぎ、頭皮のコンディションを安定させる |
| 紫外線対策 | 帽子や日傘を活用し、頭皮への過度な紫外線を防ぐ |
洗髪とシャンプー選びのコツ
シャンプーは髪だけでなく頭皮に直接触れるものです。刺激の強い成分が含まれたシャンプーは、頭皮のバリア機能を損ない、抜け毛を助長する可能性があります。
アミノ酸系や弱酸性のシャンプーなど、頭皮に優しいものを選ぶと安心です。
洗髪時にはゴシゴシと強く擦らず、指の腹でマッサージをするように洗います。
シャンプーのすすぎ残しがあると、かゆみや炎症を引き起こす恐れがあるため、洗い流しも念入りに行いましょう。
サプリメントや食事の工夫
抜け毛対策にサプリメントを活用する方法もあります。食事だけでは補いきれない栄養素を補充し、髪の土台作りをサポートします。
特に亜鉛やビタミン、ミネラルなどを目的に応じて摂取する方が多いです。
ただしサプリメントはあくまで補助的なものであり、日常の食事バランスが崩れている状態では効果が限定的になります。
| サプリメントの種類 | 働き |
|---|---|
| 亜鉛サプリ | ケラチン合成を手助ける |
| マルチビタミン | 不足しがちな微量栄養素を総合的に補給 |
| フィッシュオイル | 抗炎症作用や血行改善を狙う |
栄養バランスを整える基本は毎日の食事です。まずは三食をしっかり食べ、そのうえで不足を感じる場合にサプリメントを取り入れる方法がおすすめです。
定期的なヘアチェックが大切
抜け毛が気になるときは、早めに頭皮や毛髪の状態をチェックすることで、進行度合いや原因の目安がわかります。
自分で鏡を使って確認するだけではなく、美容院や医療機関で専門的に頭皮チェックを受ければ、適切なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
抜け毛が急増しているのか、髪質が変化しているのか、頭皮に炎症やかゆみがあるのかといった情報を早期に把握することが重要です。
セルフチェックでは判断できない微妙な変化も、専門家の目で確認すれば原因を絞り込む手がかりになります。
内臓の健康を守る方法
内臓が健康であれば、栄養状態やホルモンバランスなどが安定し、髪の健康にもよい影響を期待できます。
ここでは、定期検査や生活習慣の改善、運動やストレスケアなど、内臓の健康を保つうえで大切な方法を取り上げます。
定期検査の必要性
血液検査や尿検査、超音波検査などを受けると、肝臓や腎臓、甲状腺などの状態を客観的に把握しやすくなります。
自覚症状が乏しい初期段階の内臓の病気は見逃しがちですが、検査で早期に発見できれば早めの対処が可能です。
健康チェックにおける代表的な検査
| 検査項目 | 判定できる主な疾患 |
|---|---|
| 血液検査 | 肝機能障害、腎機能低下、甲状腺疾患の有無など |
| 尿検査 | タンパク尿、糖尿、潜血など |
| 超音波検査 | 肝臓・腎臓・甲状腺の形態異常 |
| 心電図 | 不整脈や心臓疾患のリスク確認 |
生活習慣改善と食事管理
内臓の健康を保つには、塩分や脂質、糖分を適度にコントロールしながら多種類の食材をバランスよく摂取すると良いです。
高血圧や脂質異常症、糖尿病などが進行すると、髪だけでなく全身へ影響が及びます。
- 塩分を控えめにしただしやハーブを活用した調理
- 魚や肉、卵、大豆製品などのタンパク質を意識的に摂取
- 食物繊維の多い野菜や海藻、きのこ類を取り入れる
- 甘い飲料やスイーツを控え、水やお茶に置き換える
適度な運動の効果
ウォーキングやジョギング、筋力トレーニングなどの習慣的な運動は、血行促進や体重管理、血糖値コントロールにも役立ちます。
特に血圧やコレステロール値が高い方は、医師と相談しながら運動メニューを決めて取り組むとよいでしょう。
運動が難しい方は、無理のない範囲で散歩やストレッチを取り入れるだけでも違いが出やすいです。
ストレスケア
ストレスはホルモンバランスを乱し、免疫力や内臓機能に悪影響を与えます。
趣味や運動、入浴、瞑想など、自分がリラックスできる方法を見つけて継続すると、ストレスを上手にコントロールできます。
仕事や家事で忙しい方こそ、適度な休息や気分転換を心がけてみましょう。
AGA治療・薄毛治療の選択肢
髪が抜ける悩みがあり、内臓の病気や生活習慣を見直しても改善が難しい場合は、医療機関でのAGA治療や薄毛治療を検討する価値があります。
医療機関での検査内容
抜け毛の原因がAGAなのか、内臓の病気による影響なのかを見極めるために、医療機関では頭皮の状態や血液検査を行うことが多いです。
男性ホルモンの働きを調べる検査や甲状腺機能を確認する検査などを合わせて行い、総合的に判断します。
| 検査名 | 目的 |
|---|---|
| 血液検査 | ホルモンバランスや内臓の状態を把握 |
| 頭皮の視診 | 頭皮トラブルの有無を確認 |
| 顕微鏡検査 | 毛根の状態や毛髪の太さを調べる |
| 問診 | 生活習慣やストレスの度合いを確認 |
内服薬・外用薬の特徴
AGA治療では、男性ホルモンの働きを抑える内服薬や血行を促進する外用薬などを用いる場合があります。
代表的な内服薬にはフィナステリドやデュタステリドがあり、外用薬にはミノキシジルが挙げられます。
これらの治療薬は継続使用が前提となるため、医師と相談しながら長期的なプランを立てる必要があります。
クリニックで行う施術
医療機関によっては頭皮への注入治療や、LEDやレーザーを用いた施術など、さまざまな治療方法を提供しています。
これらの施術は血行促進や頭皮環境の改善を狙いとし、内服薬や外用薬と組み合わせるとより効果を得やすくなる傾向があります。
施術内容や回数は個々の状態によって異なるため、医師やカウンセラーとよく相談して決めるとよいでしょう。
代表的な薄毛治療方法
| 治療法 | 特長 |
|---|---|
| 内服薬治療 | 男性ホルモンの抑制や発毛促進を狙う |
| 外用薬治療 | 頭皮に直接塗布し血行促進を図る |
| 注入治療 | 頭皮に有効成分を注入し発毛を支援 |
| 光・レーザー治療 | 頭皮に対して光やレーザーを照射し血行改善を誘導 |
注意点とカウンセリング
AGA治療は効果が出るまで時間がかかる場合が多く、薬の副作用や費用面も考慮する必要があります。
また、内臓の病気がある場合は使用できない薬もあるため、事前に医師へしっかり相談してください。
治療の進捗を定期的にチェックしながら、途中で疑問が出た場合も早めにクリニックに問い合わせると良いでしょう。
よくある質問
髪が抜ける理由は人それぞれですが、内臓の病気や生活習慣などが絡むケースでは専門的な知識が必要です。ここでは多くの方が気になる疑問を取り上げます。
- QAGAと内臓疾患は関係あるのか
- A
AGAは男性ホルモンの作用によるものが中心ですが、内臓疾患があると栄養の吸収や代謝が悪化し、髪の回復力が落ちる可能性が
あります。AGAそのものの原因が内臓疾患とは限りませんが、内臓が弱っていると治療の効果が出にくいケースは考えられます。
AGA治療をサポートする意味でも健康を整えることが重要です。
- Q健康診断では異常がないのに抜け毛が増える理由は
- A
健康診断の項目では異常値が出ない程度でも、ストレスや栄養不足、軽度のホルモンバランスの乱れが生じている場合があります。
また、病気の初期段階では数値に現れないケースもあるため、抜け毛の増加が気になるなら専門医に相談し、詳細な血液検査やホルモン検査を受けると原因を特定しやすくなります。
- Qサプリメントだけで髪は改善するのか
- A
サプリメントは不足しがちな栄養を補う手段として役立ちますが、それだけで抜け毛や薄毛が劇的に改善するとは限りません。
栄養バランスの良い食生活や適切なヘアケア、生活習慣の見直しと組み合わせると相乗効果を期待できます。
医師や栄養士に相談し、必要性と目標を明確にしたうえで利用するとよいでしょう。
- Qクリニックを受診するタイミング
- A
抜け毛が増えている、髪のボリュームが顕著に減っている、内臓の病気の治療中で髪の状態が気になるなど、少しでも気になるサインがあれば早めに受診を検討してもよいでしょう。
早期発見・早期治療によって進行を遅らせたり、適切なケア方法を見つけたりしやすくなります。
自己判断のみで対策を続けると、原因が見逃されて薄毛が進行してしまうケースもあるため注意が必要です。
参考文献
SPERLING, Leonard C. Hair and systematic disease. Dermatologic clinics, 2001, 19.4: 711-726.
WOLFF, Hans. Diseases of hair. In: Braun-Falco’s Dermatology. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. p. 1029-1059.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
STENN, K. S.; PAUS, Ralf. Controls of hair follicle cycling. Physiological reviews, 2001, 81.1: 449-494.
NANDA, Sonali; DE BEDOUT, Valeria; MITEVA, Mariya. Alopecia as a systemic disease. Clinics in dermatology, 2019, 37.6: 618-628.
LIN, Richard L., et al. Systemic causes of hair loss. Annals of medicine, 2016, 48.6: 393-402.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
SHRESTHA, P.; MATHUR, M. Dermatologic manifestations in chronic kidney disease patients on hemodialysis. Nepal Journal of Dermatology, Venereology & Leprology, 2014, 12.1: 34-40.