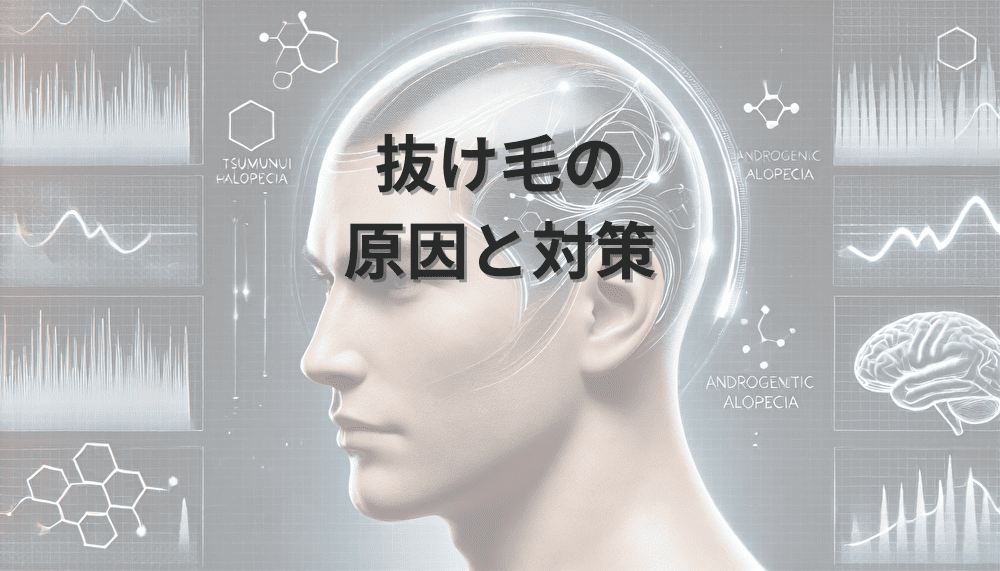髪がよく抜ける状態や、髪が急に抜けるようになった場合、日常生活に支障を感じて不安が募るものです。
家でのケアを何度見直しても改善しないならば、AGAなど病的な要因を考える必要があります。
この記事では髪抜ける原因を医師の視点から解説し、適切な対策や受診の見極めについて詳しく紹介します。
抜け毛の仕組みと髪の成長サイクル
抜け毛は髪の生え変わりにともなう自然な現象ですが、量や頻度が増えすぎると何らかの異変を疑わなくてはなりません。
ここでは髪の成長サイクルや抜け毛の発生メカニズムについて解説し、正常な脱毛と異常な脱毛の境目を整理します。
毛周期と髪の生え変わりの基本
髪は成長期、退行期、休止期という3つの段階を経て新しい髪へと生え変わります。
成長期では髪の毛母細胞が活発に増殖して髪が太く長く伸び、退行期に入ると毛母細胞の活動が低下して髪の成長が止まります。
休止期になると髪は頭皮に留まるだけの状態になり、その後自然に抜け落ちます。
ヘアサイクルの目安
| 期間 | 概要 | 目安となる期間 |
|---|---|---|
| 成長期 | 毛母細胞が活発に働き、髪が伸びる | 2〜7年程 |
| 退行期 | 毛母細胞の活動が低下し、成長が止まる | 約2〜3週間 |
| 休止期 | 髪が抜け落ちるまで頭皮に留まる | 約3〜4か月 |
これが一般的な脱毛の流れであり、健康な状態でも1日におよそ50〜100本程度は抜けるといわれています。
正常な抜け毛と異常な抜け毛の違い
正常な範囲での抜け毛は、先ほど触れたように成長サイクルの最終段階として自然に起こります。
しかし、1日に抜ける本数が極端に多かったり、短く細い髪が大量に抜けたりする場合は注意が必要です。
髪が簡単に抜ける状況が続くと、頭皮環境やホルモンバランスに異常が生じている可能性があります。
異常な抜け毛は単なる生え変わりではなく、何らかの原因による脱毛症のサインかもしれません。
抜け毛の量やタイミングの個人差
髪が急に抜けると感じるタイミングや、本数の多さには個人差があります。髪質や毛髪密度は遺伝的な要素に左右され、さらにホルモン分泌量や日常のストレス状態も影響します。
ある人は季節の変わり目に抜け毛が増えやすく、別の人は病気をきっかけに脱毛を実感しやすいなど、違いはさまざまです。
自分の平常時の髪の状態を知り、異変を早く察知することが大切です。
やむを得ない抜け毛と対策が必要な抜け毛
成長サイクルに基づく正常な抜け毛は体の仕組みとして起こる自然現象です。
一方で、髪抜ける原因がホルモン異常や頭皮トラブルなど病的要素に起因する場合、早めに対処しなければ脱毛が進行してしまう可能性があります。
髪がよく抜ける方やブラッシングのたびに髪がごっそり抜け落ちる方は、一度頭皮環境や生活習慣を振り返り、必要に応じて医療機関を受診することをご検討ください。
髪がよく抜ける時に考えられる状態
髪がよく抜けると感じるとき、その原因はさまざまです。
ホルモンバランスの乱れや過度なヘアケア、ストレスなど、日常生活の中に潜む要因が影響しているかもしれません。
ホルモンバランスの乱れ
男性ホルモンや女性ホルモンのバランスが乱れると、抜け毛が増えやすくなります。たとえば女性の場合、妊娠・出産後のホルモン変動や更年期障害の一環として脱毛を経験する方もいます。
男性では、テストステロンがジヒドロテストステロン(DHT)へ変換されることで起こるAGAが代表的です。
ホルモンバランスの乱れをそのままにすると抜け毛が慢性化しやすいので、早めの対処が必要です。
過度なヘアケアや誤った頭皮ケア
シャンプーのしすぎや強いブラッシングなど、誤ったヘアケアが頭皮にダメージを与えることがあります。
カラーリングやパーマなどの化学処理を頻繁に行うと、頭皮の角質層が傷ついて炎症を起こしやすくなります。
これにより本来健康だった髪が抜けやすくなり、髪がよく抜ける状態につながるケースもあるため、ヘアケアのやり方を再確認するとよいでしょう。
ありがちな間違ったヘアケア
- シャンプー回数の過多や、強く擦り過ぎる洗髪
- 頭皮を引っ張りすぎるヘアスタイルの維持
- 髪や頭皮を長時間濡れたまま放置
- 過度なカラーリングやブリーチ、パーマの繰り返し
- タオルドライ時に強くこすり合わせる
栄養不良やダイエットの影響
極端なダイエットや偏った食生活を続けると、髪の成長に必要なタンパク質、ビタミン、ミネラルが不足しがちです。
とくに亜鉛や鉄分の欠乏は頭皮環境を悪化させ、抜け毛を増やすリスクを高めます。
ダイエットによる体重減少が著しいと、倦怠感などの体調不良に加え、髪が急に抜ける事態も起こりやすいため、栄養バランスには十分配慮してください。
過度なストレスや睡眠不足
長期にわたるストレスは自律神経やホルモンバランスに悪影響を及ぼし、血管が収縮して頭皮への血流量が低下する傾向があります。
その結果、毛母細胞への栄養供給が不十分になり、抜け毛が増えやすくなります。
また、睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減り、髪の成長サイクルにも悪影響を与えます。
髪がよく抜ける要因
| 要因 | 主な例 | 発生しやすい状況 |
|---|---|---|
| ホルモン異常 | AGA、更年期障害、出産後の脱毛 | 加齢、産後、更年期 |
| 頭皮ダメージ | 頻繁なカラーリング、強いブラッシング | 美容室での施術の繰り返し |
| 栄養不足 | 極端なダイエット、偏食 | 食事制限、健康食品に偏り |
| ストレス要因 | 仕事の過度なプレッシャー、睡眠不足 | 長時間労働、心配事が多い環境 |
髪が急に抜ける原因として疑うべきこと
髪が急に抜ける場合、単なる一時的な抜け毛ではなく、特定の病気や疾患が影響している可能性があります。
ここでは突然の脱毛を引き起こす主な要因と、その対処方法を紹介します。
円形脱毛症などの自己免疫疾患
円形脱毛症は、自己免疫機能の異常によって毛母細胞が誤って攻撃されることで起こる脱毛症です。
円形状に髪が抜けるのが特徴で、進行すると頭部全体や全身の体毛に及ぶケースもあります。
発症のメカニズムにはストレスや遺伝的要素も関与すると考えられ、自己判断しづらい特徴があります。早期に皮膚科や専門医の診察を受けることが大切です。
円形脱毛症が疑われる特徴
- 頭部にコイン大の円形状の脱毛斑がある
- 境界が比較的はっきりしている
- 皮膚に目立った炎症がなくツルツルしている
- 爪に凹凸が生じることがある
- 再発を繰り返すケースがある
甲状腺機能異常
甲状腺ホルモンの分泌が過剰または不足すると、代謝や循環に影響が出て、抜け毛の原因になる場合があります。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や甲状腺機能低下症(橋本病)では、髪を含めた全身の症状が出やすく、疲れやすさや体重の急激な増減などが同時に起こることも珍しくありません。
疑いがあるときは血液検査を受けて、内科や内分泌科で診察を受けることを検討しましょう。
急激なダイエットや栄養障害
過剰な食事制限を短期間で行うと、体重は減少しても髪の成長に必要な栄養が著しく不足し、急激に抜け毛が増える場合があります。
リバウンドを繰り返すような不健全なダイエットは、体全体の代謝を混乱させるだけでなく、ホルモンバランスの乱れにもつながりやすく、髪の健康に深刻な影響を与えかねません。
薬剤性脱毛
抗がん剤など特定の薬剤によって、髪の成長を抑制してしまうケースがあります。
抗がん剤の副作用による脱毛は頭部全体に及ぶことが多く、治療終了後に髪が再び生えてくるケースもありますが、個人差が大きいです。
また、高血圧や抗うつ薬などの投薬でも脱毛が起こる可能性があるため、髪が急に抜けると感じたときは担当医へ相談するとよいでしょう。
急な抜け毛を引き起こす病気と特徴
| 疾患名 | 特徴 | 併発症状 |
|---|---|---|
| 円形脱毛症 | 円形状の脱毛斑、自己免疫による毛母細胞の攻撃 | 爪の変形、再発を繰り返す |
| 甲状腺機能異常 | 甲状腺ホルモンの異常分泌に伴う代謝異常 | 体重変化、疲れやすさ |
| 薬剤性脱毛 | 抗がん剤や特定の薬剤使用による毛母細胞抑制 | 薬の副作用に伴う倦怠感など |
| 栄養障害 | 食事制限などで栄養不足が生じる | 倦怠感、肌荒れ、生理不順 |
髪が簡単に抜ける場合に注意したい生活習慣
ちょっとした刺激やブラッシングで髪が簡単に抜ける場合、頭皮環境が悪化していたり、生活習慣に抜け毛を招く要素が潜んでいる可能性があります。
タイトなヘアスタイルの継続
ポニーテールやお団子ヘアのように強く髪を束ねる髪型を長時間続けると、毛根に大きな負担をかけやすくなります。
引っ張りによって頭皮が常に緊張状態となり、血行不良につながるケースも少なくありません。
髪が簡単に抜ける傾向がある方は、できるだけ締め付けないヘアスタイルを選ぶ、もしくは頭皮を休ませる時間を確保すると効果的です。
髪型を選ぶ際に気をつけたいポイント
- 長時間のポニーテールやお団子は控える
- 細いゴムやヘアピンで強く結ばない
- 就寝前は髪を解いて頭皮をリラックスさせる
- ヘアアクセサリーは適度に外して血流を妨げない
長時間の帽子やヘルメットの着用
通気性が悪い帽子やタイトなヘルメットを長時間装着すると、頭皮が蒸れやすくなります。
湿気のこもった頭皮環境は細菌や真菌が繁殖しやすく、フケやかゆみ、炎症などを引き起こして抜け毛の原因につながる場合があります。
帽子やヘルメットを使用する場合は通気性の良い素材を選んだり、適度に外す時間を設けたりするとよいでしょう。
喫煙や過度な飲酒
喫煙は血管を収縮させる要素があるため、頭皮への血流を悪化させる傾向があります。過度な飲酒も肝臓への負担を大きくし、ホルモンバランスを乱すおそれがあります。
これらの習慣がある方は、髪の健康維持の観点からも見直しを考慮してください。
極端な生活リズムの乱れ
夜勤や不規則な労働環境で生活リズムが乱れると、自律神経が不安定になりがちです。
睡眠の質が低下すると頭皮の新陳代謝も滞り、髪の成長サイクルに悪影響を及ぼします。
疲労回復が不十分な日々が続くと、抜け毛の増加を感じやすくなるため、可能な範囲で規則正しいリズムを保つことが望ましいです。
髪が簡単に抜ける人の生活習慣に潜む問題
| 生活習慣 | リスク | 改善策 |
|---|---|---|
| タイトなヘアスタイルの継続 | 毛根への負担増大 | 緩めのヘアスタイルや頭皮マッサージ |
| 長時間の帽子やヘルメットの着用 | 頭皮の蒸れによる炎症 | 通気性の良い素材の帽子、定期的な着脱 |
| 喫煙 | 血管収縮による血流不良 | 禁煙または本数を減らす |
| 過度な飲酒 | 栄養吸収阻害、ホルモンバランス乱れ | 節酒と栄養バランスの改善 |
| 不規則な生活リズム | 自律神経の乱れや睡眠不足 | 睡眠時間の確保、就寝前のリラックス |
抜け毛の原因で多い男性型脱毛症(AGA)の特徴
男性特有の抜け毛の原因として代表的なのがAGA(男性型脱毛症)です。成人男性の薄毛の多くにAGAが関与すると考えられ、進行性である点が大きな特徴といえます。
AGAの仕組み
AGAは男性ホルモンであるテストステロンが、酵素によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換されることで毛母細胞を萎縮させ、抜け毛を引き起こす脱毛症です。
遺伝的要因や加齢によるホルモンバランスの変化が影響し、何も対策を行わないと前頭部や頭頂部を中心に薄毛が広がります。
初期段階で髪が細く短くなる、抜け毛が目立つといったサインを感じることが多いです。
AGAの主な症状
AGAはM字ハゲやO字ハゲと呼ばれるように、前頭部(生え際)や頭頂部(つむじ部分)から髪が薄くなりやすい特徴があります。
進行すると頭皮が広範囲に露出し、髪全体のボリュームも落ちてきます。
また、髪の寿命が短くなっているため、ヘアスタイルが思うように決まらなくなる方も珍しくありません。
AGAを疑う兆候
- 前髪の生え際が後退してきた
- つむじの周りが以前より地肌が見えやすい
- 抜け毛の毛根が細く短い髪が増えてきた
- 父親や祖父が薄毛だった
- シャンプー時の抜け毛が増えてきた
AGAと他の脱毛症との違い
円形脱毛症やびまん性脱毛症とは異なり、AGAは男性ホルモンに関係する特定のパターンをもつ進行性の脱毛症です。
自己免疫異常や病気などによる脱毛とは原因が異なり、毛包のミニチュア化によって徐々に薄毛が進みます。
対策として内服薬や外用薬などを使うことで進行を抑えたり、発毛を促進できる可能性があります。
AGAの特徴と他の脱毛症との比較
| 脱毛症名 | 原因 | 主な脱毛部位 | 進行性 | 代表的な治療法 |
|---|---|---|---|---|
| AGA | 男性ホルモン(DHT)による毛包萎縮 | 前頭部・頭頂部 | あり | 内服薬、外用薬、注入治療など |
| 円形脱毛症 | 自己免疫異常 | 円形状のパッチ状 | 場合による | ステロイド療法、免疫抑制剤 |
| びまん性脱毛症 | ホルモン変動や栄養不足などの複合要因 | 頭部全体 | 場合による | 栄養補給、生活習慣改善 |
| 薬剤性脱毛 | 抗がん剤などによる毛母細胞抑制 | 全体的または特定部位 | 場合による | 投薬中断や終了後の回復 |
AGAは自然に治るのか
AGAは自然に治りにくく、放置すると徐々に進行する傾向があります。生活習慣を整えるだけではホルモンの影響を根本的に抑えることは難しく、充分な改善を実感しにくい場合が多いです。
ただし、医療機関で処方される内服薬や外用薬といった治療法を併用することで、進行を遅らせたり発毛を促したりできる可能性があります。
予防と改善に向けたセルフケア
普段の生活習慣やヘアケアを少し変えるだけでも、抜け毛の進行を抑えたり頭皮環境を整えたりする効果が期待できます。
栄養バランスの見直し
髪の原料となるタンパク質や、頭皮への血行を支える鉄分や亜鉛、ビタミン類を積極的に取り入れることは重要です。
特にレバーや赤身肉、魚介類、ナッツ類、緑黄色野菜などには髪の成長をサポートする栄養素が多く含まれています。
一方で、糖質や脂質の過剰摂取は頭皮の皮脂分泌を増やし、抜け毛につながるリスクを高めるため注意が必要です。
髪の成長をサポートする栄養素
| 栄養素 | 代表的な食材 |
|---|---|
| タンパク質 | 魚、肉、大豆製品など |
| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、ごま |
| 鉄分 | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
| ビタミンB群 | 豚肉、うなぎ、卵、玄米 |
| ビタミンC | 柑橘類、ピーマン、ブロッコリー |
頭皮マッサージや血行促進
頭皮マッサージを行い血行を高めると、毛母細胞へ栄養や酸素が行き渡りやすくなります。
入浴中やシャンプー後に指の腹を使って円を描くように頭皮をほぐすと、リラックス効果も得られます。
爪を立てて強くこする行為は頭皮を傷つけるため控えましょう。
正しいヘアケア方法
適切なシャンプー剤を選び、頭皮に余計な負担をかけない洗い方を意識することが大切です。
シャンプー前には髪をしっかりとブラッシングし、ほこりやスタイリング剤を落としてから洗髪を始めます。
洗浄時はぬるま湯を使い、髪だけでなく頭皮を中心に丁寧に洗ってください。しっかりすすがないとシャンプー剤が頭皮に残ってトラブルを引き起こす恐れがあります。
ストレス管理と睡眠の確保
ストレスや睡眠不足は抜け毛を加速させる要因となりやすいです。適度に休息や運動を取り入れ、趣味やリラクゼーションを通じてストレスを軽減する工夫をしましょう。
就寝前にスマートフォンやパソコンを長時間見ると睡眠の質が落ちやすいため、就寝1時間前は画面を見ない時間を作るなど工夫するとよいです。
自宅で取り入れやすいセルフケアと期待できる効果
| セルフケア | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 栄養バランスの改善 | タンパク質、亜鉛、鉄分の摂取 | 髪の成長促進、頭皮環境の改善 |
| 頭皮マッサージ | 入浴中や洗髪後に指の腹で頭皮をほぐす | 血行促進、リラクゼーション |
| 正しいヘアケア | 適切なシャンプー剤と正しい洗い方 | 頭皮トラブルの軽減、抜け毛抑制 |
| ストレス管理と十分な睡眠 | 適度な運動、画面時間の制限 | ホルモンバランスの安定、育毛効果 |
医療機関で行う治療方法と受診の目安
セルフケアだけでは抜け毛の改善が難しい場合や、抜け毛が急激に進んでいる場合には、医療機関での治療が効果的なケースもあります。
内服薬や外用薬による治療
AGA治療では、医師がフィナステリドやデュタステリドなどの内服薬を処方することがあります。
これらはジヒドロテストステロン(DHT)の生成を抑制して毛母細胞へのダメージを軽減し、抜け毛の進行を食い止める作用が期待できます。
外用薬ではミノキシジルを含むローションなどが代表的で、血流促進による発毛を狙う手法です。
ただし副作用のリスクもあるため、医師と相談しながら正しく使用することが大切です。
メソセラピーや注入治療
頭皮に成長因子やビタミン、ミネラルなどを注入し、毛根を活性化させる治療法があります。
メソセラピーや発毛注射などと呼ばれ、クリニックによって薬剤や手技が異なります。
頭皮の深部に直接成分を届かせることで、内服薬や外用薬では得られにくい局所的な効果を狙うことができます。
注入治療で期待できるメリット
- 必要な栄養素や成長因子を直接毛根に届けられる
- 血行促進をサポートする薬剤の使用
- 全身への薬剤影響が比較的少なく抑えやすい
- 個々の症状や進行度に合わせたカスタマイズが可能
植毛や移植手術
AGAがかなり進行している場合や、他の治療法で満足な結果が得られなかった場合には植毛や移植手術を選択することも視野に入ります。
後頭部や側頭部の髪を移植し、生え際や頭頂部の薄毛部分をカバーする方法です。
外科的手法になるため負担や費用も生じますが、医師と相談しながら自分の希望や体調を踏まえて検討するとよいでしょう。
医療機関での治療方法と特徴
| 治療法 | 主な薬剤・手法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内服薬(AGA治療薬) | フィナステリド、デュタステリド | DHT生成を抑え、抜け毛の進行を遅らせる |
| 外用薬(発毛剤) | ミノキシジル外用薬 | 頭皮の血流を促進し、発毛をサポート |
| メソセラピーや注入治療 | 成長因子・ビタミン・ミネラル注入 | 局所集中ケア、効果が得られやすい場合も |
| 植毛・移植手術 | 自毛移植など | 重度の薄毛に対する外科的アプローチ |
受診の目安とタイミング
抜け毛が増えてきたと感じたら、まずは生活習慣の改善やセルフケアに取り組むことが大切です。それでも変化が乏しかったり、急激に薄毛が進んでいると感じた場合には医療機関を受診してください。
こんな症状があれば医療機関へ
- 数週間で頭皮が見えるほど毛量が減った
- 部分的に大きな脱毛斑ができた
- 頭皮に痛みやかゆみ、強い炎症がある
- かさぶたや大量のフケが発生している
- 円形脱毛症の疑いを繰り返し感じる
特に生え際や頭頂部の地肌が明らかに見え始めたとき、あるいはヘアスタイルで隠すことが難しくなってきたときは、専門的な治療を検討するタイミングです。
髪がよく抜ける、髪が急に抜けるとお悩みの方は、正しい診断と治療を行うために、まずはクリニックに相談してみましょう。
参考文献
PRICE, Vera H. Treatment of hair loss. New England Journal of Medicine, 1999, 341.13: 964-973.
MESSENGER, A. G.; RUNDEGREN, J. Minoxidil: mechanisms of action on hair growth. British journal of dermatology, 2004, 150.2: 186-194.
KAUFMAN, Keith D., et al. Finasteride in the treatment of men with androgenetic alopecia. Journal of the American Academy of Dermatology, 1998, 39.4: 578-589.
MILLAR, Sarah E. Molecular mechanisms regulating hair follicle development. Journal of Investigative Dermatology, 2002, 118.2: 216-225.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.