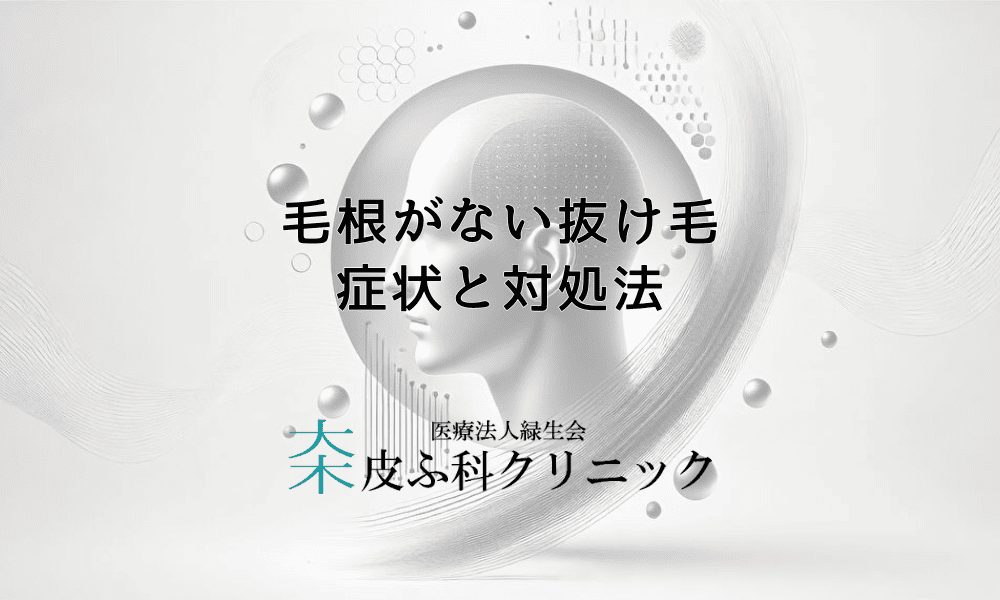髪のボリュームが気になって抜け毛を確認した際、まれに毛根が見当たらないように見えることがあります。
髪の根元の白い部分が全くない、あるいは薄いなど、「抜け毛の毛根がない」と感じる場合、その背景に複数の要因が考えられます。
本記事では、髪と頭皮に関する基礎知識、毛根が見られない抜け毛の状態が示す症状、専門的な検査や治療の流れを解説します。
毛髪の基本的な構造と抜け毛のメカニズム
髪がどのように育ち、抜けるのかを理解すると、抜け毛の毛根がないように感じる理由も分かりやすくなります。
はじめに、髪の構造と、その成長サイクルからみる抜け毛のメカニズムについて述べます。
毛髪を形成する仕組み
髪は、頭皮にある毛包という組織から形成されます。毛包の下部には毛母細胞という細胞群があり、これらが細胞分裂を繰り返して髪が成長します。
毛母細胞は血行や栄養状態、ホルモンバランスなどの影響を受けながら、一定の速度で髪を伸ばします。
毛髪の主成分
毛髪の大部分はケラチンというタンパク質で構成され、髪の太さや強度は遺伝的要因だけでなく、栄養状態や生活習慣によっても変化します。
髪が健やかに伸びるためには、毛母細胞へ十分な酸素と栄養が行き渡ることが重要です。
| 主成分 | 特徴 | 役割 |
|---|---|---|
| ケラチン | タンパク質の一種 | 髪の強度や弾力を保ち、外部環境から髪を保護する |
| メラニン | 髪の色素として存在 | 髪の色を決定し、紫外線など外的刺激から毛母細胞を保護する |
| 脂質 | 髪の表面をコーティングする | 髪内部の水分蒸発を防ぎ、毛髪の保湿と滑らかさを維持する |
毛根と毛包の役割
髪の根元を支える毛根部は、毛包の深部にあたります。一般的には、髪を抜くと毛根の部分が白く膨らんだ形で確認できます。
この白い塊が「毛根鞘」と呼ばれる組織で、毛母細胞とともに髪の成長に深く関係しています。毛根の状態は、髪が抜けたときにどのタイミングの成長サイクルにあったかを判断する材料にもなります。
毛髪の成長サイクルは「成長期→退行期→休止期→脱毛」の流れを繰り返します。正常な抜け毛の場合、毛根がある程度太く、白い塊がはっきりと確認できることが多いです。
抜け毛が生じる流れ
成長期の終盤に近づくと髪の毛母細胞の活性が徐々に落ち、退行期を経て休止期となります。休止期になった髪は毛根が小さくまとまり、頭皮内で押し出される形で抜けていきます。
そのため、通常の抜け毛には毛根部が確認できますが、抜け毛の毛根がないと感じる場合は、毛髪サイクルに異常が生じているか、物理的な切断・ダメージなどが起きている可能性があります。
- 正常な毛髪サイクルは年齢やホルモンなどに左右される
- 毛根部がしっかり残る抜け毛は基本的に自然脱毛の可能性が高い
- 毛根部が確認できない抜け毛は、強い外的力や毛髪サイクルの乱れなどが関わる
抜け毛の毛根がないとはどういう状態か
抜け毛を観察したときに毛根が確認できない場合、それが何らかの病的兆候であるのか、あるいは一時的なものなのかを判断する手がかりになります。
毛根が見えない抜け毛の特徴
毛根がないように見える抜け毛は、髪の先端から根元までを観察しても「白く膨らんだ部分がほとんどない」「毛根が極端に小さい」などの特徴を持ちます。
これは通常の抜け毛とは異なる状態と考えられます。
抜け毛の毛根がないように見える要因
| 要因 | 特徴 |
|---|---|
| 毛髪の途中で切断 | ブラッシングや強い力で引っ張られた結果、毛根付近が切れている可能性 |
| 毛根鞘の変性・損傷 | パーマ液などの強い刺激や炎症が毛根鞘を損なうことで毛根が不明瞭になっている |
| 成長サイクルの異常 | 退行期・休止期が過度に短縮されているため、毛根部の形成が十分でない可能性 |
| 頭皮トラブル | 炎症や皮脂詰まりによる毛包の萎縮が原因で毛根が小型化し、見えにくくなっている |
一時的な抜け毛と継続的な抜け毛
抜け毛の毛根が見えにくい状態が一時的なものであれば、生活環境の変化やストレス、季節的な要因が絡んでいるケースもあります。
しばらくすると自然に落ち着き、正常な抜け毛に戻る方も少なくありません。
しかし、継続的に毛根が不明瞭なまま抜け毛が増えている場合には、頭皮や毛髪の健康に何らかの問題が起きている可能性が高まります。
| 状態 | 原因 |
|---|---|
| 一時的 | 季節の変わり目や強いストレス下に陥っている時期 |
| 継続的 | 長期にわたる薄毛や頭皮トラブル、ホルモンバランスの乱れなど |
見た目と実際の毛根の有無
抜け毛を観察した際に「毛根がない」と思っても、実際には毛根自体が非常に小さいだけで残っているケースもあります。
毛根部は頭皮の内部に深く関わる組織なので、肉眼だけでは正確に判断できない場合が多いです。
- 肉眼での観察は限界がある
- 拡大鏡などで見ると実際には毛根部が残っていることもある
- 早期に専門医に相談して正しく原因を突き止めることが重要
主な原因:炎症や外的要因による毛根トラブル
抜け毛の毛根がないように見える背景には、頭皮の炎症や外的要因が大きく影響している場合があります。
日常生活の中で意外と気付きにくいダメージの積み重ねが、毛髪や頭皮に悪影響を及ぼします。
頭皮の炎症が与える影響
頭皮の炎症は、皮脂の過剰分泌や雑菌の繁殖、過度な紫外線などが原因となって起こります。
炎症が起こると、毛包周辺の環境が悪化し、髪の成長過程が乱れやすくなります。その結果、毛根部がしっかり形成される前に髪が抜け落ちるときがあります。
頭皮の炎症につながりやすい習慣
- 洗髪が十分でない、または洗いすぎで頭皮が乾燥・刺激を受ける
- 枕カバーや帽子を清潔に保っていない
- 硬いブラシで強い力によるブラッシングを行っている
- 合わないヘアケア用品の使用
外部刺激と物理的なダメージ
髪の毛や頭皮は、ブラッシングやドライヤーの熱などの日常的な動作や道具でも大きなダメージを受ける可能性があります。
特に、濡れた髪に強い力を加えると、髪のキューティクルが傷つくだけでなく、毛根部にもダメージが及びやすいです。
| 外部刺激の種類 | ダメージの内容 | 対策 |
|---|---|---|
| ブラッシングやヘアセット | 無理な引っ張りによる切断、毛根への負荷 | 目の粗いコームを使用し、やさしい力でとかす |
| ドライヤーやアイロン | 高温によるキューティクルの損傷、頭皮の乾燥 | 適度な温度に設定し、髪からある程度離して使用する |
| ゴムやヘアアクセ | 特定部分への過度な引っ張り、摩擦 | ゆるめのスタイルを心がけ、長時間同じヘアスタイルを避ける |
パーマやカラーリングのリスク
パーマ液やヘアカラーは、髪に化学的な変化を与えてスタイルや色を変える方法ですが、同時に毛髪や頭皮へ刺激を与えます。
施術後に頭皮が赤く炎症を起こしやすい方や、髪質が急激に悪化する方は、毛根に負担がかかっていることが懸念されます。
美容室での処置だけでなく、ホームカラーでも強い薬剤を使うことで毛根部が傷つきやすくなるため、注意が必要です。
- 頭皮トラブルがあるときはパーマやカラーを一時的に控えたほうが無難
- 美容師と相談しながら薬剤の濃度や放置時間を調整する
- 頭皮保護用のオイルやクリームを活用する
ホルモンバランスと遺伝的要因
抜け毛の毛根がないと感じる背景には、ホルモンバランスや遺伝要因が深く関わるケースも見逃せません。
男女ともにホルモン環境が変化すると、髪の成長サイクルに乱れが生じます。
男性ホルモンとAGAの関係
男性特有の薄毛で知られるAGA(男性型脱毛症)は、男性ホルモンであるテストステロンが毛根付近でジヒドロテストステロン(DHT)に変換される過程で起こる脱毛症状です。
このDHTが毛母細胞の活動を抑制し、成長期を短縮させるため、髪が十分に太く育たずに抜け落ちます。
結果として毛根がしっかりと形成されないまま抜けるときがあり、抜け毛の毛根がないように感じるケースもあります。
AGAの特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発症部位 | 前頭部や頭頂部を中心とした脱毛 |
| 進行パターン | 頭頂部が薄くなるパターン、前髪の生え際が後退するパターン、両者が同時に進行するパターンなど |
| 進行速度 | 個人差が大きいが、放置すると徐々に広範囲に及ぶ |
| 治療・対策 | 内服薬・外用薬、クリニックでの施術など多岐にわたる |
女性ホルモンと脱毛リスク
女性の場合でも、出産や更年期などホルモン変動が大きい時期に抜け毛が増えることがあります。
女性ホルモン(エストロゲン)の減少は、髪の成長を助ける作用が弱まるので、毛髪サイクルが乱れる原因となります。
その結果、抜け毛の毛根が細くなって抜け落ちるため、肉眼では毛根がないように見えやすいです。
- 出産後の脱毛(産後脱毛)は一時的なホルモン変化によることが多い
- 更年期には女性ホルモンだけでなく自律神経の乱れも脱毛に影響する
- 女性の脱毛は男性よりも複合的な要因が多い
遺伝的要素と家族歴の重要性
男性型脱毛症(AGA)は特に遺伝的要因との関連が指摘されていますが、女性でも家族に薄毛や抜け毛の多い人がいると、同じように発症しやすい傾向があります。
遺伝的要素が強い場合、ホルモンの影響や生活習慣の改善だけでは抜け毛が完全に収まらない方が多いため、早期の専門的ケアが重要となります。
- 家族の脱毛傾向は、自分の将来の脱毛リスクを予測する材料になる
- 遺伝といっても遺伝子そのものだけでなく、頭皮環境や生活習慣も似通うことが多い
- 遺伝的リスクを理解した上で適切な予防策や治療法を選ぶことが大切
抜け毛の毛根がない場合に考えられる主な症状
抜け毛の毛根がないように見えるとき、具体的にはどのような脱毛症が考えられるのでしょうか。
ここでは、代表的な脱毛症の症状や特徴を挙げます。自己判断でのケアだけでなく、専門医の診察や検査が必要になるケースも多いです。
円形脱毛症の特徴
円形脱毛症は、突然丸い脱毛斑が出現する自己免疫性の脱毛症です。
ストレスや自己免疫の異常反応によって毛母細胞が攻撃されるため、毛根が正常に機能しなくなり、抜け毛の毛根がないような状態が生じる場合があります。
脱毛斑が1つだけのケースもあれば、複数できる場合や、全頭に及ぶ場合もあります。
| 種類 | 症状 | 傾向 |
|---|---|---|
| 単発型 | 1箇所に円形の脱毛斑ができる | 比較的軽度で、自然に回復する例も多い |
| 多発型 | 複数の脱毛斑が同時または段階的に出現する | 症状が広がりやすく、再発の可能性もある |
| 全頭型 | 頭髪がほぼ全て抜け落ちる | 自己免疫反応が強く、治療期間が長くなる傾向 |
| 汎発型 | 体のあらゆる体毛が脱毛する | まつ毛や眉毛なども抜ける |
休止期脱毛症と慢性的な抜け毛
休止期脱毛症は、毛髪が成長期から休止期に移行する過程が急激に早まることで抜け毛が増える状態を指します。
慢性的な栄養不足や過度なダイエット、ストレスなどが原因で起こる例が多いです。
この場合、毛根が十分に形成されないまま髪が抜け落ちるときがあるため、抜け毛の毛根がないように見えることがあります。
- 休止期脱毛症は一時的に抜け毛が増えるが、原因除去により回復が期待できる
- 常に慢性的なストレスを抱えていると、休止期脱毛が長引く可能性がある
- 栄養管理や生活習慣の見直しが重要
牽引性脱毛症や外傷性脱毛症
ポニーテールや編み込みなど、髪を強く引っ張るヘアスタイルを長期間続けると牽引性脱毛症を起こします。髪が引っ張られることで毛根に負担がかかり、毛包が損傷して毛髪が正常に育たなくなるのです。
結果として毛根が極端に小さくなり、抜け毛の毛根がないように見えるケースがあります。
また、頭皮に外傷を負ったり、やけどなどで毛包が破壊された場合も外傷性脱毛症となり、毛根がほとんど見えない形で髪が抜ける原因となります。
- 強いヘアスタイルでの長時間の引っ張りは避ける
- けがや外傷で頭皮にダメージがある場合、早めの処置が必要
- ダメージ後は毛髪が再生しにくい場合があるため、専門医に相談
専門医が行う検査と診断の流れ
抜け毛の毛根がない状態が継続している、あるいは他にも気になる症状がある場合は、早めに専門医の診察を受けるのが望ましいです。
医療機関では多角的な検査・診断によって、原因を特定し、その人に合った治療を提案します。
視診と問診からわかること
まずは医師が頭皮や毛髪の状態を視診し、患者さんの生活習慣や家族歴などを問診で確認します。
この段階では、脱毛のパターンや頭皮の炎症の有無、使用しているヘアケア用品や食生活などが把握され、症状に応じた詳しい検査を行う必要性の有無が判断されます。
- 視診で頭皮の赤みやフケ・皮脂の状態を確認
- 問診でストレスの度合いや喫煙・飲酒習慣も確認
- AGAや円形脱毛症など、疑われる脱毛症の種類を概略で推定
マイクロスコープや血液検査
頭皮や毛根の状態をより詳しく調べるために、マイクロスコープを使って毛穴周辺や毛根部の拡大映像をチェックする場合があります。
抜け毛の毛根がないように見える原因が、実際には毛根が小さいだけなのか、それとも毛根鞘が損傷しているのかなど、詳細な観察が可能です。
血液検査では、ホルモンバランスや栄養状態、自己免疫の異常の有無などを調べます。これらを総合的に判断して、内服薬や注射、外用薬などの治療方針を決定していきます。
検査で特にチェックされる項目
| 検査種類 | チェック項目 | 目的 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 貧血、甲状腺機能、ホルモン値、免疫機能など | 抜け毛の背景に病的要因がないかを判断 |
| マイクロスコープ | 毛穴の状態、毛根部の形状、頭皮環境の詳細 | 炎症や詰まりの有無、毛包の萎縮などの可視化 |
| 生検(必要な場合) | 組織を一部採取して詳細に検査 | 円形脱毛症など自己免疫疾患の確定診断など、特殊な場合に行う |
他の疾患との鑑別診断
頭皮や髪のトラブルだけが原因とは限らないケースもあります。甲状腺疾患やリウマチなどの自己免疫疾患が絡んでいる可能性も考えられます。
内科的な検査によって他の疾患が疑われる場合には、該当の専門診療科と連携して総合的な治療プランを組み立てるのが基本です。
- 甲状腺機能の低下で代謝が下がると髪が抜けやすくなる
- 免疫疾患が絡む円形脱毛症の場合、自己免疫反応への対策が必要
- 抜け毛以外の体調不良や症状にも注意して総合的に診る
抜け毛の毛根がないケースへの専門的対処法
抜け毛の毛根がないように見える場合、原因によって対処法は異なります。特にAGAや円形脱毛症、生活習慣によるダメージなど、それぞれの症状に合った方法を行わないと効果が得にくいです。
内服薬や外用薬による治療
男性型脱毛症(AGA)が原因で毛根が弱っている場合には、医師が処方する内服薬や外用薬が効果的です。
代表的な治療薬に、AGAを抑制するフィナステリド(プロペシア)やデュタステリド(ザガーロ)、発毛を促進するミノキシジル外用薬などがあります。
これらを使用して頭皮のホルモン環境を整え、毛母細胞の活性をサポートします。
- 内服薬はホルモンバランスに影響するため、医師の指導のもとで服用する
- 女性の場合、妊娠中や授乳中は使用を避けるべき薬もある
- 効果が出るまでに数カ月単位の継続が必要になることが多い
抜け毛治療で使用される薬剤
| 薬剤名 | 主な作用 | 対象 |
|---|---|---|
| フィナステリド | DHT産生酵素の働きを抑制し、男性ホルモンの影響を抑える | 男性型脱毛症(AGA) |
| デュタステリド | 5α-還元酵素を抑え、DHT産生をより幅広く抑制する | 男性型脱毛症(AGA) |
| ミノキシジル外用薬 | 毛細血管拡張作用により血流を促進し、毛母細胞の活動を助ける | AGA、女性の脱毛症 |
頭皮ケアや生活習慣の見直し
専門医の診察により病的要因が見つからなかった場合でも、頭皮ケアや生活習慣の改善は大切です。
頭皮環境が良好になれば、自然と毛根の形成が整いやすくなり、抜け毛の毛根がないように見える状態を改善できる可能性があります。
- 洗髪は1日1回程度、適度な洗浄力のシャンプーを選ぶ
- 頭皮マッサージで血行促進を図り、毛母細胞への栄養供給を助ける
- 十分な睡眠と栄養バランスの整った食事を心がける
クリニックでの施術とフォローアップ
内服薬や外用薬、生活習慣改善だけでは抜け毛が止まらないときや、効果が実感しにくいときには、クリニックで行う施術を提案される場合があります。
例えば、頭皮に育毛成分を直接注入するメソセラピーや、PRP療法、LEDや低出力レーザーを用いた頭皮への刺激など、多様な方法が存在します。
施術後も定期的なフォローアップによって状態を観察し、必要に応じて治療プランの調整が行われます。
| 施術の種類 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| メソセラピー | ビタミンや成長因子などを頭皮に注射し、毛母細胞の活性をサポート | 毛髪の成長促進、抜け毛抑制 |
| PRP療法 | 自己血小板血漿を頭皮に注入して組織修復を促す | 毛母細胞への刺激、炎症軽減 |
| LED・レーザー照射 | 特定波長の光やレーザーを照射して血行促進や細胞活性を狙う | 頭皮環境の改善、抜け毛抑制、発毛促進 |
よくある質問
抜け毛に関する不安は人によってさまざまで、自己流の対処では不十分なこともあります。最後に、外来で多くの方からいただく質問を挙げて解説します。
- Q毛根がないと再び髪が生えない?
- A
実際に毛根そのものが完全に消失している場合は、自然に髪が生えにくくなります。
ただし、多くの場合は「肉眼では見えないほど毛根が小さい」か「毛根鞘が一時的に傷ついている」ケースであり、専門的な治療やケアによって再生の可能性があります。
必要に応じて検査を行い、本当に毛根組織が失われているのかどうかを確認するとよいでしょう。
- Q抜け毛が増えたと感じたら病院へ行くべき?
- A
急激に抜け毛が増えた、あるいは髪の根元を見たときに毛根が見当たらない抜け毛が多い場合は、早めに皮膚科やAGA治療・薄毛治療を扱う医療機関を受診することをおすすめします。
自分で原因を特定するのは難しいため、専門医の客観的な視点と検査が必要です。早期発見と対処が髪の健康に大きく影響します。
- Q自宅でできるセルフケアのポイントは?
- A
日常のヘアケア習慣を改善するだけでも、抜け毛の進行を抑えられる場合があります。
頭皮に優しいシャンプー選び、頭皮の保湿やUVケア、定期的な頭皮マッサージなどが有効です。
ただし、症状が進行している場合はセルフケアだけでは難しいケースがあるため、専門的治療との併用がよい結果につながることも多いです。
参考文献
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.
MOUNSEY, Anne L.; REED, Sean W. Diagnosing and treating hair loss. American family physician, 2009, 80.4: 356-362.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
MUBKI, Thamer, et al. Evaluation and diagnosis of the hair loss patient: part I. History and clinical examination. Journal of the American Academy of Dermatology, 2014, 71.3: 415. e1-415. e15.
SHAPIRO, Jerry; WISEMAN, Marni; LUI, Harvey. Practical management of hair loss. Canadian Family Physician, 2000, 46.7: 1469-1477.
LACARRUBBA, Francesco, et al. Videodermatoscopy enhances diagnostic capability in some forms of hair loss. American journal of clinical dermatology, 2004, 5: 205-208.