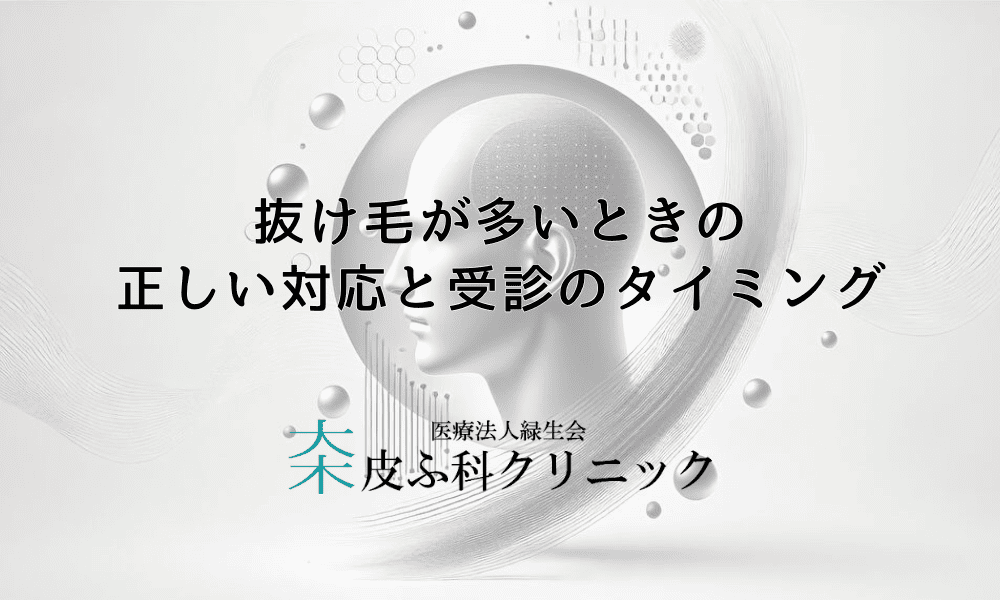抜け毛の量が増えたと感じると、不安や焦りを覚える方が少なくありません。
とくに髪のボリュームが気になりはじめると、日頃の生活習慣やストレス、遺伝要因など、さまざまな原因が頭に浮かぶこともあるでしょう。
この記事では、髪が抜けるメカニズムや日常生活での対策、クリニックへの受診タイミングなどを解説します。
抜け毛の状態を見極めて適切に対応することで、将来的な薄毛やAGA(男性型脱毛症)の進行を予防しやすくなります。
抜け毛が多いと感じる原因
髪の毛は、毛根で生成された後に成長し、やがて自然に抜けていきます。
この繰り返しがヘアサイクルですが、何らかの理由でサイクルが乱れると、抜ける量が増えたように感じることがあります。
遺伝的要因とホルモンバランス
遺伝的な要因に加え、男性ホルモンと深くかかわるメカニズムが抜け毛を増やす一因になります。
男性ホルモンがジヒドロテストステロン(DHT)に変換されて毛根に影響を与えると、髪の成長期が短縮しやすくなります。
女性でもホルモンバランスの乱れが抜け毛の要因となる場合があり、妊娠・出産後や更年期に髪が抜けやすいと感じるときがあります。
以下の点を意識しながら、自身に当てはまる要素がないか振り返ってみましょう。
遺伝とホルモンの影響を考える際のチェック
- 家族や近親者(父母・祖父母)に薄毛や抜け毛の症状がある
- 思春期以降のホルモンの変化で髪質の変化を感じた
- 出産後や更年期に髪のハリやコシが失われた
- 性別に関係なくストレスや生活習慣の乱れでホルモンバランスが崩れやすい
遺伝やホルモンによる抜け毛は、薬や外用剤などを使って早めに対策をはじめると、進行を抑えられる場合が多いです。
ストレスや生活習慣の影響
過度なストレスや乱れた生活習慣も髪の毛に大きな負担を与えます。ストレスホルモンが増加すると血管が収縮し、毛根への栄養供給が減少しやすくなります。
また、睡眠不足や偏った食生活によって頭皮環境が悪化すると、抜け毛が多いと感じるケースが増えることがあります。
ストレスや生活習慣による影響
| 生活習慣・ストレス | 髪への影響 | 改善のヒント |
|---|---|---|
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下 | 就寝時間を一定にし良質な睡眠を確保 |
| 食生活の偏り | 毛髪に必要な栄養不足 | たんぱく質や亜鉛を意識的に摂取 |
| 過度なストレス | 血行不良やホルモンバランス乱れ | リラクゼーションや趣味を取り入れる |
| 喫煙・過度の飲酒 | 血流悪化や栄養阻害 | 禁煙・節酒で頭皮環境を守る |
ストレスを軽減する工夫やバランスのよい食事など、自分でできる対策を続けると抜け毛が増える悪循環に陥るリスクを抑えやすくなります。
外的刺激による負担
毛髪や頭皮は、日々のケアや外部からの刺激によってもダメージを受けます。
高温でのドライヤーの使用や過度なブラッシングは、髪そのものだけでなく頭皮にも負担を与えます。
整髪料の過剰使用や合わないシャンプーを使うと、頭皮が炎症を起こして毛根に悪影響を及ぼすおそれがあります。
外的刺激による抜け毛を予防するためには、洗髪後に優しくタオルドライし、ドライヤーは適度な温度で行う、ブラッシングは濡れている髪を避けて丁寧に行うなど、日々のヘアケアの見直しが大切です。
抜け毛が増える時期と季節性について
抜け毛の量が増えるのは、必ずしも特定の病気だけが原因ではありません。季節の変わり目や体調の変化が大きく関係する場合もあります。
季節の変わり目に抜け毛が増えやすい理由
日本では秋口に抜け毛の増加を感じる方が多いです。夏の強い紫外線や汗などの影響で頭皮がダメージを受け、髪の成長サイクルが乱れやすくなるためと考えられています。
日照時間の変化や気温の低下によって血行が滞りやすくなる点も、一時的な抜け毛の増加につながる要因です。
季節的な頭皮ダメージを減らすためのポイント
- 紫外線対策として帽子や日傘を活用する
- 汗をかいたら早めにシャンプーで汚れを落とす
- 保湿効果のあるヘアケア製品を選ぶ
- 血行を促す頭皮マッサージを取り入れる
秋の抜け毛は一時的な現象の場合が多いですが、長期間抜け毛が多い状態が続くときは他の原因も疑ったほうがいいでしょう。
ホルモンリズムと季節の関係
春から夏にかけて日照時間が長くなると、体内のホルモン分泌や自律神経のバランスが変化します。この変化が抜け毛を増やす要因となる可能性があります。
また、秋から冬にかけては気温が下がり、血管が収縮しやすいため頭皮への栄養供給が減少しやすくなる点にも注意が必要です。
季節変動による抜け毛傾向
| 季節 | 主な気象条件 | 頭皮環境への影響 | 抜け毛の増減傾向 |
|---|---|---|---|
| 春 | 気温上昇 | 皮脂分泌が活発化しやすい | 徐々に抜け毛が増えることがある |
| 夏 | 強い紫外線 | 日焼けによる頭皮ダメージ | 一時的に頭皮環境が悪化しやすい |
| 秋 | 気温低下 | 乾燥や血行不良が起こりやすい | 抜け毛が増えると感じる人が多い |
| 冬 | 低温・乾燥 | 帽子や暖房による蒸れと乾燥 | 頭皮トラブルが出やすく注意が必要 |
こうした季節の特徴を把握しながら、適切な頭皮ケアを心がけると、抜け毛の量を抑えることが期待できます。
一時的な抜け毛と持続的な抜け毛の違い
季節の変わり目などに見られる一時的な抜け毛は、生活習慣や環境を改善すると自然に回復するケースも少なくありません。
一方で、半年以上も抜け毛が多い状態が続く場合は、AGAや女性特有のホルモンバランスの乱れなど、慢性化した原因が潜んでいる可能性があります。
原因を特定せずに放置すると、より深刻な薄毛につながるリスクがあるため、専門医への相談が重要です。
抜け毛の症状とセルフチェック
髪が抜ける量が多いと感じるときは、自分でできるチェック方法を試してみると良いでしょう。
ここでは、抜け毛の状態や頭皮のコンディションを見極めるポイントを紹介します。
髪のボリュームやハリ・コシの変化
鏡を見て髪の根元が立ち上がっているかどうか、ボリュームの低下が気にならないかといった視覚的なチェックは日常的に行いやすい方法です。
触れたときにコシがなくなったり、髪一本一本が細くなったりすると、抜け毛以外のトラブルも起きている可能性があります。
髪の状態を把握するポイント
- 髪が細くなったりコシがなくなったりしていないか
- 頭頂部の地肌が以前より目立っていないか
- 生え際が後退していると感じないか
- 毛先の分裂や切れ毛が増えていないか
これらの兆候が続く場合は、ヘアサイクルの乱れだけでなく、頭皮の栄養不足やホルモンの影響も考えられます。
頭皮の色や感触、フケの有無
頭皮を指で触ったとき、硬さや炎症を感じたり、フケが目立ったりすると頭皮環境が悪化しているサインかもしれません。
本来、健康な頭皮は青白い色で柔らかい状態を保っています。赤みがある、べたついている、逆に乾燥が激しいといった状態が長く続く場合は、抜け毛も増加しやすくなります。
頭皮状態の自己チェックポイント
| チェックポイント | 健康的な頭皮の状態 | 注意が必要な状態 |
|---|---|---|
| 色 | 青白く透明感がある | 赤みや黄色味、炎症がある |
| 触り心地 | 柔らかい | こわばりや痛みを感じる |
| フケの量 | ほとんど目立たない | 大量に出る、または脂っぽい |
| 頭皮の匂い | 無臭か自然な匂い | 皮脂の過剰分泌で強いニオイ |
頭皮の色やフケが気になるときは、シャンプーや頭皮ケアの見直しが大切です。
1日の抜け毛の本数を大まかに把握する
健康な人でも、1日に50~100本程度の髪が抜けます。髪が長い人は髪1本が目立ちやすいので、抜け毛が多いように感じる場合もあります。
大まかな基準として1日100本を超えて抜ける日が続いたり、髪の減りをはっきり感じたりするときは、何らかの原因があるかもしれません。
ただし、数えるのがストレスになったり、髪を過度に引っ張ってしまうと逆に頭皮に負担をかける場合があるため、あくまでも目安として捉えると良いでしょう。
抜け毛を感じたときの生活改善ポイント
抜け毛が増えたと感じるときには、日常生活を振り返り改善できる部分を探してみてください。
ここでは、食事や運動、睡眠といった基礎的な習慣を見直すことで、頭皮環境を良い状態に保つためのアイデアを紹介します。
食事バランスの見直し
髪の主成分であるケラチンを作るには、たんぱく質や亜鉛、ビタミンなどが必要です。
偏った食事が続くと、これらの栄養素が不足して、抜け毛が増える原因となるときがあります。
食生活に取り入れたい食品
- 良質なたんぱく質を含む肉類・魚類・卵
- 亜鉛が豊富な牡蠣やレバー、ナッツ類
- 抗酸化作用のあるビタミンCを含む野菜や果物
- 鉄分やミネラルを含む海藻類
無理なダイエットや偏食を避け、バランスの良い食事を心がけると、健康な髪の育成につながります。
適度な運動と血行促進
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、血行を促し頭皮への栄養供給を助けます。
激しい運動ではなく、続けやすい運動を日常生活に取り入れるのがポイントです。
運動習慣と頭皮への影響
| 運動習慣 | 頭皮・毛髪へのメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| ウォーキング | 血行促進、ストレス軽減 | 歩きすぎによる疲労に注意 |
| 軽い筋トレ | 全身の代謝向上、成長ホルモンの安定 | 正しいフォームで無理なく続ける |
| ヨガ・ストレッチ | 自律神経の調整、頭皮の緊張緩和 | 呼吸法を意識しリラックスを心がける |
| ジョギング | 有酸素運動による血行改善 | オーバーワークに注意 |
運動後は汗や皮脂が溜まりやすいため、適切な頭皮ケアを忘れないようにしてください。
質の良い睡眠を確保する
睡眠中には髪の成長に関わるホルモンが分泌されるため、質の良い睡眠は髪や頭皮の健康に直結します。寝不足が続くとストレスが高まり、自律神経が乱れるため抜け毛が進行しやすくなります。
寝室の照明や室温を整え、就寝前にスマホやPCの画面を見る時間を減らすといった工夫をすると、深い睡眠を得られる可能性が高まります。
こうした地道な習慣の積み重ねが、頭皮の状態を良い方向に導きやすくなります。
AGA(男性型脱毛症)とは
抜け毛が多いと感じる原因として代表的なものに、AGA(男性型脱毛症)があります。
男性に多い印象ですが、女性の場合も似た仕組みで抜け毛が進行するケースがあります。
AGAの原因とメカニズム
AGAは男性ホルモンが酵素の働きによってDHT(ジヒドロテストステロン)へ変換されることにより、毛根が刺激を受けて髪の成長期が短縮する現象です。
前頭部や頭頂部を中心に髪が薄くなるパターンが多く、放置すると徐々に進行していく可能性があります。
AGAを疑うときのサイン
- 生え際が後退している
- 頭頂部の髪が密度低下で透けて見える
- 髪全体はある程度残っているが、頭頂部のみ顕著に薄い
- 抜け毛の本数や髪質の低下をはっきりと感じる
遺伝による体質も関係しやすいですが、ストレスや食生活などの生活習慣も影響を及ぼすことがあります。
男性だけじゃない女性の脱毛症
女性ホルモンの減少やバランスの乱れによって、女性も脱毛症に悩むケースがあります。
女性の場合は男性と比べて全体的に髪が薄くなる特徴があり、生え際よりも分け目などからボリュームダウンが進む方が多いです。
出産後や更年期など、ホルモンバランスが大きく変動する時期に抜け毛が増える例も珍しくありません。
男性型脱毛症と女性型脱毛症の特徴
| 項目 | 男性型脱毛症 | 女性型脱毛症 |
|---|---|---|
| 主な症状 | 前頭部~頭頂部の後退 | 分け目や頭頂部からのボリューム減 |
| 原因となるホルモン | DHT(ジヒドロテストステロン) | エストロゲン減少、DHTなど |
| 進行パターン | パターン型の進行 | 全体的に薄くなる傾向 |
| 受診のきっかけ | 生え際の後退、頭頂部の薄毛 | 頭皮が見えやすくなる、髪のハリ不足 |
女性は髪が命といわれるように、心理的ダメージも大きいものです。早い段階から頭皮ケアやホルモンバランスの管理を意識すると、抜け毛の進行を抑えられます。
AGAの進行度合いと見極め方
AGAは段階的に進行するため、進行度合いに応じた対策を行うのが望ましいです。
生え際や頭頂部の薄毛範囲が広がっている場合は、中期~後期に差し掛かっている可能性があります。
抜け毛が増えている段階で受診し、医師の診断を受けると自分の状態を客観的に把握できるでしょう。
クリニックを受診するタイミングと検査方法
抜け毛が気になりはじめたら、いつどのようにクリニックを受診すればいいのかを知るのも大切です。
ここでは、受診の目安や検査でわかることについて紹介します。
受診の目安となるサイン
日常的なケアを行っても抜け毛が多い状態が変わらない、または悪化する場合は、クリニックへ相談するタイミングといえます。
具体的には以下のようなサインがあるとき、専門医の診断を受けると原因を特定しやすくなります。
早めの受診を考えたいサイン
- 半年以上、抜け毛が増加傾向にある
- 髪のボリュームが明らかに減少して地肌が透けて見える
- かゆみやフケ、頭皮の痛みなどトラブルが続いている
- 家族に薄毛や脱毛症の既往があり、自分も遺伝の可能性を感じる
これらに当てはまる方は、自己判断だけで対処を続けるよりも、医療機関で検査を受けるのが望ましいです。
クリニックで行われる検査内容
病院やクリニックでは、頭皮や毛髪の状態を詳しく調べるための検査を行います。
どのような検査が実施されるか知っておくと、不安を和らげやすいです。
一般的な検査の内容と目的
| 検査名 | 概要 | 得られる情報 |
|---|---|---|
| 視診 | 医師が頭皮や髪を目視で確認 | 脱毛部位の範囲や頭皮の炎症の有無など |
| マイクロスコープ | 拡大鏡を使って頭皮や毛穴を観察 | 毛穴の詰まり、炎症、発毛状態をチェック |
| 血液検査 | ホルモン値や栄養状態を確認 | AGAや貧血などの要因を把握 |
| 画像撮影 | 頭髪の部位ごとの写真を撮影 | 治療前後の比較や進行度の記録 |
こうした検査結果を踏まえ、適切な治療や生活改善のアドバイスを受けます。
受診前に準備したいこと
抜け毛の状態や生活習慣の変化、使用中のヘアケア製品などを事前にメモしておくと、受診時に医師へスムーズに情報を伝えられます。
また、家系的に薄毛の人が多い、最近強いストレスを感じたなどの情報も診断に役立ちます。
頭皮や髪のことで相談したい内容を事前に整理しておくと、限られた診療時間を有効に使えるでしょう。
抜け毛予防や治療の選択肢について
抜け毛が多いと感じるときの治療には、薬剤やヘアケア商品だけでなく、生活習慣の改善や機器を使った施術など、多様な方法があります。
ここでは、クリニックなどで行われる代表的な方法と、自宅での対策を解説します。
内服薬や外用薬による治療
AGAの治療には、男性ホルモンの働きを抑制する内服薬や、毛根を刺激して発毛を促す外用薬がよく用いられます。
主なものとして、フィナステリドやデュタステリドなどの内服薬と、ミノキシジルの外用薬があります。
いずれも継続的な使用が大切で、効果が出るまでに数か月かかる場合があります。
治療薬選択に関わるチェックポイント
- 過去に薬剤でアレルギーや副作用を経験したことはないか
- 妊娠中や授乳中で注意が必要な薬剤がないか
- 他の持病があり、別の薬を内服していないか
- 効果が出るまでの期間とコストを理解しているか
医師の指示に従いながら、定期的に効果や副作用の有無を確認すると安心です。
機器を使った頭皮ケアや施術
医療機関では、頭皮に成長因子を注入する方法やLEDライトを照射して血行を促進する施術なども行われるケースがあります。
こうした施術は治療薬だけでは十分に効果を感じにくい人や、より積極的に発毛を目指したい人に選択肢として挙げられます。
代表的な施術内容と特徴
| 施術名 | 主な効果 | 通院頻度 |
|---|---|---|
| メソセラピー | 成長因子や栄養成分を頭皮に直接注入 | 月に1~2回程度 |
| LED治療 | 頭皮に安全な光を照射し血行を促す | 週1回程度 |
| HARG治療 | 専用のカクテル剤を注入し発毛を促進 | 医療機関によって異なる |
| 低出力レーザー治療 | 低出力レーザーで頭皮を刺激して育毛 | 週1回~数回程度 |
施術の頻度や費用は施術内容によって変わり、複合的な治療が行われる場合もあります。
自宅でできるケアの継続
治療を受けていても、自宅でのケアを怠ると効果を十分に得られない可能性があります。
頭皮マッサージや栄養バランスの良い食事、適度な運動など、クリニックでの治療と併せて実践すると、より良い結果に近づきやすいです。
シャンプーや育毛剤を適切に使い、頭皮環境を整える工夫も忘れずに行いましょう。
よくある質問
抜け毛に関する不安を抱える方から寄せられる質問と、その回答例を紹介します。症状や原因は個々人で異なるため、あくまでも参考とし、気になる点があれば専門医に相談してください。
- Q抜け毛が多いと感じるときに市販の育毛剤だけで対策しても大丈夫?
- A
市販の育毛剤には、頭皮環境を整える成分や保湿成分が配合されており、一定の効果が期待できます。
特に初期の抜け毛や頭皮の乾燥・かゆみなどの軽度なトラブルであれば、使用を続けると改善につながる場合もあります。
ただし、AGAのようにホルモンの影響が大きい場合は、市販の育毛剤だけでは進行を抑えきれないケースがあるのも事実です。
効果を感じにくい場合や症状が進んでいると感じるときは、医療機関の受診を検討することがおすすめです。
- Q抜け毛が多い原因がわからない場合、どの診療科を受診すればいい?
- A
髪のトラブルは皮膚科が対応することが多いですが、専門外来として「発毛外来」や「脱毛症外来」を設置しているクリニックも存在します。
男性型脱毛症の場合はAGA治療を専門とする施設での受診がスムーズです。
また、女性の場合は女性の脱毛症に詳しい医師が在籍しているクリニックを選ぶと、ホルモンバランスの検査なども含め総合的に診断してもらいやすくなります。
- Q親からの遺伝が心配だけど、予防する方法はある?
- A
AGAを含む抜け毛の傾向には遺伝の要素があると考えられています。しかし、遺伝だけで必ず発症するわけではなく、食生活やストレス管理などの要因も大きく関係します。
予防としては、規則正しい生活習慣や適度な運動、頭皮ケアを徹底するなど、頭皮環境を良い状態に保つ努力が重要です。
家族に薄毛の人が多い場合は、気になる兆候が出た段階で早めにクリニックを受診すると、より適切なアドバイスを受けやすいです。
- Qクリニックの治療費はどのくらいかかる?
- A
処方薬や施術内容によって費用は大きく変動します。保険適用外の自由診療が中心となることが多いため、費用も比較的高額になりがちです。
内服薬だけで月々数千円~数万円、注入系の治療や特殊な施術を組み合わせるとさらに上乗せされるケースがあります。
事前にクリニックへ問い合わせ、治療方針や費用について十分に納得してから開始すると良いでしょう。
参考文献
MARTINEZ-VELASCO, Maria Abril; VAZQUEZ-HERRERA, Norma Elizabeth; TOSTI, Antonella. How to Evaluate Treatment Response in Hair Diseases. Hair and Scalp Treatments: A Practical Guide, 2020, 291-322.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
SPRINGER, Karyn; BROWN, Matthew; STULBERG, Daniel L. Common hair loss disorders. American family physician, 2003, 68.1: 93-102.
PRICE, Vera H. Treatment of hair loss. New England Journal of Medicine, 1999, 341.13: 964-973.
PAUS, Ralf; COTSARELIS, George. The biology of hair follicles. New England journal of medicine, 1999, 341.7: 491-497.
LIN, Richard L., et al. Systemic causes of hair loss. Annals of medicine, 2016, 48.6: 393-402.
MOUNSEY, Anne L.; REED, Sean W. Diagnosing and treating hair loss. American family physician, 2009, 80.4: 356-362.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.