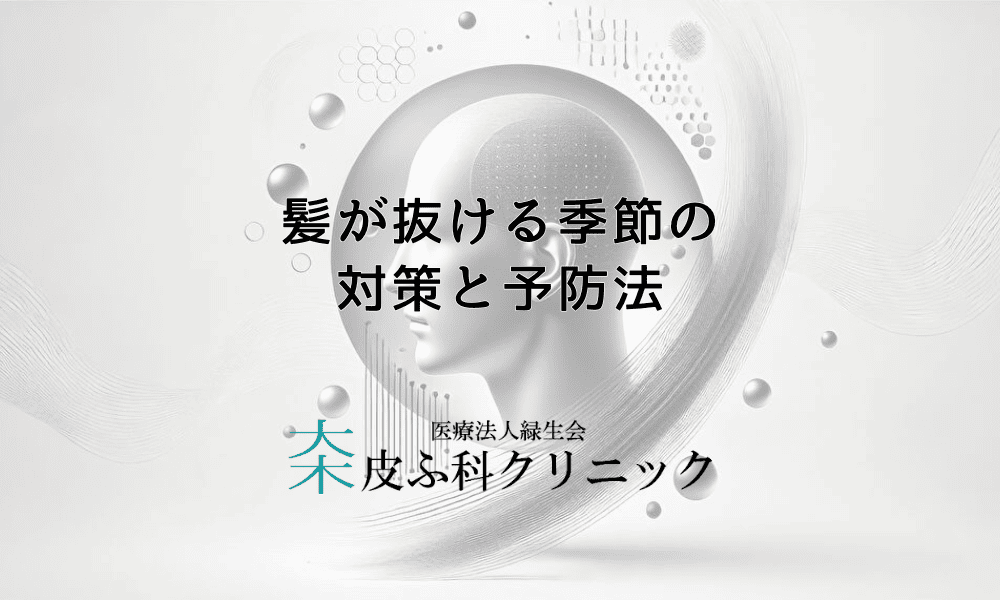健康状態や生活習慣だけでなく、季節や時期によって髪の抜けやすさが変わる場合があります。
とくに春から夏、秋にかけては気候の変化が激しく、頭皮や毛髪に影響を及ぼします。抜け毛が増えると「もしかして薄毛が進行しているのか」と不安になる方もいるでしょう。
この記事では、髪が抜けやすい季節や時期ごとのヘアケア方法、日常生活での注意点や病院受診の目安などを詳しく解説します。
髪が抜けやすい時期と季節の関係
髪が抜けるタイミングには個人差がありますが、多くの方が感じる時期としては季節の変わり目が挙げられます。
気温や湿度の変化だけでなく、紫外線や生活習慣の乱れなども抜け毛につながる可能性があります。
ヘアサイクルの基礎
髪は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しながら生え替わります。
成長期は髪がしっかりと伸びる期間で、退行期は成長が止まり、休止期では毛根が休んで脱毛が起こる準備をします。そして最終的に抜け落ちることで、新しい髪が生える土台になります。
| サイクル名 | 主な期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 成長期 | 2〜6年 | 髪が太く長く育つ |
| 退行期 | 約2〜3週間 | 毛根が縮小し始める |
| 休止期 | 約3〜4か月 | 次の髪が成長する準備を行う |
髪は一定の周期を経て自然と抜け落ちるため、全く抜け毛がない状態はむしろ不自然です。ただし、何らかの要因によってヘアサイクルが乱れると、抜け毛が増えやすくなります。
季節変化と抜け毛のメカニズム
春から夏にかけては日差しが強くなり、頭皮が紫外線の影響を受けやすくなります。強い紫外線は頭皮の角質を傷つけ、炎症を起こす引き金になりかねません。
また、夏場は汗や皮脂の分泌が増え、頭皮環境が乱れやすい状態が続きます。こうした状態が秋にかけて持ち越されると、抜け毛が増える原因につながります。
一方、冬は乾燥が進みやすくなるため、頭皮の皮脂バランスが乱れて抜け毛が増えるケースもあります。
季節ごとのケアを怠ると、本来は正常範囲で収まる抜け毛が増加する恐れがあります。
男性と女性での違い
男性はAGA(男性型脱毛症)の影響を受けやすく、ヘアサイクル自体が乱れてしまう傾向があります。季節の要因に加え、男性ホルモンの変化や遺伝的な要素が重なって抜け毛が加速するケースがあります。
女性の場合は、出産や更年期、ダイエットによる栄養不足などが重なると、季節要因以上に抜け毛が増える場合があります。
女性ホルモンが乱れたときやストレスが強いときは、髪のハリやコシまで影響が出やすいので注意が必要です。
AGA(男性型脱毛症)の発症リスク
AGAは男性ホルモン(DHT)の影響で起こる症状で、前頭部や頭頂部を中心に髪が薄くなる特徴があります。
季節によってAGAの症状が急激に進むわけではありませんが、もともと抜け毛が多い時期に重なると、症状の進行が目立ちやすくなります。
頭皮のかゆみや炎症などが強い場合は、単なる季節的な抜け毛ではなくAGAや他の頭皮トラブルを併発している可能性もあります。
自己判断だけで判断せず、必要に応じて医療機関への相談も検討してみてください。
季節による頭皮トラブル
| 時期 | トラブル例 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 春〜夏 | 炎症、汗疹 | 紫外線、発汗、皮脂過剰 |
| 秋 | 抜け毛増加 | 夏のダメージ蓄積、湿度変化 |
| 冬 | 乾燥、フケ | 低湿度、過度な暖房 |
春のヘアケアと注意点
春先は気温が上がり始めるため、頭皮の皮脂分泌が増える傾向があります。
また、寒暖差が激しく、体調を崩しやすい時期でもあるので、髪の栄養不足や頭皮環境の乱れに注意が必要です。
乾燥と皮脂バランス
春は花粉や黄砂などで頭皮が刺激を受けやすく、皮脂分泌も活発になりやすいです。過剰に分泌された皮脂が毛穴を詰まらせると、抜け毛や頭皮のニオイの原因になる場合があります。
一方で、急激に空気が乾燥する日もあるため、頭皮や髪は乾燥と皮脂過多を同時に抱えがちです。洗浄力の強すぎるシャンプーの使用やゴシゴシ洗いは避けて、頭皮に負担をかけないようにしましょう。
洗髪時に気をつけるポイント
- ぬるま湯(38℃前後)で頭皮を予洗いする
- シャンプーは適量で、泡立ててから頭皮を丁寧に洗う
- 爪を立てず、指の腹でやさしくマッサージする
- すすぎ残しがないように時間をかけてしっかり洗い流す
頭皮の皮脂バランスを整えるために、洗浄力のやさしいシャンプーを選び、髪と頭皮をケアしていきましょう。
食事とサプリメントのポイント
抜け毛対策において、食事は大きな役割を果たします。
髪の主成分であるタンパク質、頭皮の健康を支えるビタミン類や亜鉛などをしっかりと摂取すると、ヘアサイクルが整いやすくなります。
忙しい生活の中で栄養が偏る場合は、サプリメントを取り入れる方法もあります。ただし、サプリメントだけに頼らず、バランスのよい食事を基本に考えてください。
栄養素と髪への働き
| 栄養素 | 代表的な食材 | 髪への働き |
|---|---|---|
| タンパク質 | 魚、肉、豆製品、卵 | 髪の主成分を形成 |
| ビタミンB群 | レバー、豚肉、納豆 | 頭皮の代謝促進 |
| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、かぼちゃの種 | 毛母細胞の生成サポート |
| ビタミンC | 柑橘類、パプリカ、キウイ | コラーゲン生成に関与 |
スタイリング時の注意
春は気温差が激しく、朝晩の冷え込みと日中の暖かさで汗をかきやすい場合があります。
ワックスやスプレーなどスタイリング剤を多用すると、頭皮に付着して毛穴詰まりを招くことがあります。外出後は早めにシャンプーを行い、整髪料や汗をしっかり落とすようにしましょう。
特に花粉が多い時期は、帽子を被るなどして頭皮を花粉から守るのも良い方法です。
ただし、帽子の締め付けや蒸れがかえって頭皮環境を悪化させる場合もあるので、通気性の良いものを選んでください。
ストレス対策で健やかな頭皮へ
春は新年度や新生活が始まる時期で、精神的なプレッシャーも増えがちです。
ストレスが増えると自律神経が乱れ、頭皮への血流が低下して抜け毛が増える可能性があります。適度な休息や軽い運動などでストレスを解消し、頭皮の血行を促進することも大切です。
ストレスが強いとホルモンバランスも崩れやすいため、できるだけ心身をリラックスできる時間を確保してみてください。
夏の髪が抜けやすい原因とケア方法
夏場は紫外線が強く、頭皮がダメージを受けやすい時期です。汗や皮脂の分泌量が増える一方で、エアコンの風による乾燥も気になります。
これらの要因が重なると抜け毛が増加しやすくなるため、日頃から適切な対策を講じることが大切です。
紫外線対策が鍵
夏の紫外線は頭皮や髪に大きな負担をかけます。紫外線を大量に浴びると、頭皮のコラーゲンが減少し、毛根が弱ってしまう場合があります。
屋外の活動が多い方は、日傘や帽子の活用、UVカット機能のあるヘアケア商品の使用などで頭皮を保護しましょう。
また、夏の海やプールで髪が濡れたまま強い日差しに当たると、水分が蒸発する際に髪の内部もダメージを受けます。
プール後や海水浴後はできるだけ早めにシャワーで塩分や塩素を落とし、頭皮ケアにも気を配ってください。
UV対策ヘアケア剤の選び方
- SPFやPA値が表記されている商品を選ぶ
- スプレータイプは髪全体にむらなく噴霧しやすい
- ベタつきの少ない軽いテクスチャーを選ぶ
- 海やプール後は速やかに洗い流す
汗と皮脂のコントロール
夏は大量に汗をかきやすいため、毛穴周辺に皮脂や汚れが溜まりやすくなります。その結果、毛根が炎症を起こし、抜け毛が増える可能性があります。
頭皮のベタつきが気になる方は、夏専用のクールシャンプーや頭皮ケア剤を活用すると良いでしょう。
ただし、洗浄力が強すぎる製品を使うと必要な皮脂まで洗い流し、頭皮が乾燥して逆に皮脂を過剰に分泌する恐れもあります。
洗髪回数を増やす場合は、頭皮にやさしいタイプのシャンプーを選ぶよう意識してください。
エアコンによる乾燥トラブル
夏は暑さを逃れるためにエアコンを使う機会が増えますが、長時間エアコンの風を浴びると髪と頭皮が乾燥します。
乾燥が進むとフケやかゆみなどの頭皮トラブルが起きやすく、それが悪化すると抜け毛の原因にもなります。
適度な室温設定や加湿器の利用など、室内環境にも注意を払って髪と頭皮の乾燥を防ぐことが大事です。就寝時にはエアコンのタイマー機能を活用するなど、過度な冷房を避ける工夫も取り入れてみてください。
夏に意識したい生活習慣と頭皮の状態
| 生活習慣 | 頭皮への影響 | 改善策 |
|---|---|---|
| エアコンの長時間使用 | 頭皮の乾燥 | 加湿器、適度な温度設定 |
| 汗をかいたまま放置 | 毛穴詰まり、炎症 | 早めの洗髪、クールダウン |
| 強い日差しを長時間浴びる | 頭皮のコラーゲン減少 | 帽子や日傘の使用、UVケア |
水分補給と塩分バランス
暑い時期は体内の水分量が減りやすく、血行不良や頭皮トラブルのもとになります。
水分をこまめに摂取し、汗で失われた塩分のバランスも整えると、頭皮への栄養供給がスムーズに行われやすくなります。アルコールやカフェインは利尿作用があるため、摂りすぎに注意してください。
夏場は熱中症対策も重要ですが、頭皮や髪のためにも体全体の水分・塩分バランスをコントロールし、健やかな頭皮環境を保ちましょう。
秋に増える抜け毛の理由とケアポイント
多くの方が「秋になると髪が抜ける量が増えた」と感じる傾向があります。
夏に受けた紫外線ダメージや頭皮のベタつき、日照時間の減少によるホルモンバランスの乱れなど、複合的な要因が影響するためです。
夏のダメージが髪に影響
夏場の強い日差しや高温多湿の環境は、想像以上に頭皮や髪に負担をかけています。そのダメージが徐々に現れ始めるのが秋です。
毛根が夏の間にダメージを受けていると、秋に入って抜け毛の量が増える傾向にあります。
また、夏に乱れた生活リズムや食生活が秋になるまで持ち越されると、頭皮の血行不良や栄養不足が目立ちやすくなります。
秋に向けて生活習慣を見直し、髪が抜けやすい時期を乗り越えていきましょう。
秋に取り入れると良い行動
- 就寝時間を一定に保ち、十分な睡眠を確保する
- 紫外線の弱まる秋でも帽子やスカーフで頭皮を守る
- 夏バテを引きずらないよう、栄養バランスの良い食事を心がける
- 適度な運動で血行促進を図る
保湿重視のヘアケア
秋になると空気が一気に乾燥しやすくなります。乾燥した頭皮はフケやかゆみを引き起こしやすくなり、それが進むと抜け毛増加につながりかねません。
秋のケアは保湿を意識し、頭皮専用のローションやオイルなどで潤いを与えることも検討してみてください。
洗浄力が控えめで保湿成分を含むシャンプーを選び、髪を洗ったあとは適切なトリートメントやヘアオイルでダメージを補修しながら水分を閉じ込める工夫をしましょう。
食事と睡眠で体の内側からケア
夏から秋への気温変化に体がうまく対応できないと、自律神経が乱れて髪と頭皮に影響が出やすくなります。
規則正しい食事と十分な睡眠を心がけ、内側からのコンディション調整を忘れないようにしましょう。
タンパク質やビタミン、ミネラルを含む食品をバランス良く摂り、寝不足を避けると髪の成長に必要なホルモンの分泌も促進されやすくなります。
秋のヘアケアに活用できるアイテム
| アイテム | 特徴 | 使用のポイント |
|---|---|---|
| 保湿系シャンプー | アミノ酸系成分配合が多い | 頭皮の潤いを守りながら洗う |
| スカルプローション | 頭皮の血行促進や保湿効果 | 洗髪後に頭皮へ塗布すると効果的 |
| ヘアオイル | キューティクルの保護 | タオルドライ後、毛先を中心になじませる |
秋の抜け毛が気になる場合の受診のタイミング
秋に抜け毛が増えるのはある程度自然な現象ですが、明らかに髪のボリュームが減ったり、頭皮に異常を感じたりする場合は早めの受診も検討してください。AGAや頭皮の炎症が隠れている可能性もあります。
特に前頭部や頭頂部に抜け毛が集中している場合や、かゆみや赤みがある場合は放置せずに医療機関へ相談すると原因を早期に特定できます。
冬の頭皮トラブルを防ぐケア方法
冬は気温と湿度が下がり、頭皮が乾燥しやすくなります。暖房の風も頭皮や髪の水分を奪いやすく、フケやかゆみなどのトラブルが多く見られます。
乾燥から頭皮を守る
冷たい外気と室内の暖房が繰り返される冬は、頭皮の乾燥が進みやすい季節です。頭皮が乾燥すると角質が剥がれ、フケや炎症の原因になる場合もあります。
潤いを保つためには、洗浄力の強すぎないシャンプーを選ぶことや、入浴後に頭皮用の保湿剤を使うなどのケアが必要です。
特に乾燥性のフケが多い方は、保湿成分配合のシャンプーや頭皮用エッセンスを試してみてください。頭皮のターンオーバーを整えると、抜け毛が増えにくい環境を作れます。
冬の乾燥対策に役立つ行動
- 室内が乾燥しすぎないように加湿器を活用する
- こまめに水分を摂り、体内から潤いを保つ
- お湯の温度は高すぎないように注意する(40℃前後を目安)
- ドライヤーは頭皮よりも髪中心に当て、オーバードライに注意
静電気によるダメージ
冬は空気が乾燥しているため静電気が起きやすく、髪のキューティクルが傷つく要因になります。
キューティクルのダメージは髪の乾燥や枝毛、切れ毛を招き、見た目のボリュームダウンにつながることもあります。
静電気を防ぐには、保湿力の高いシャンプーやトリートメントを使用し、髪をしっかり保湿する工夫が重要です。
ナイロン素材の帽子やマフラーで静電気が起きやすい方は、綿やウールなど、通気性のある素材を選ぶのもおすすめです。
血行促進で頭皮を暖める
寒い季節は血管が収縮しやすいため、頭皮への血流が滞りがちです。
頭皮マッサージや入浴で体を温め、頭皮の血行を促進する工夫をすると、毛根へ栄養が届きやすくなります。血流が良くなるとヘアサイクルが安定し、抜け毛が減りやすくなる効果が期待できます。
また、適度な運動やストレッチなどで体全体の血行を促進することも大切です。運動はストレス解消にもつながるので、冬場でも積極的に体を動かしてみてください。
血行促進のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入浴 | 38〜40℃のお湯にゆっくり浸かる |
| マッサージ | シャンプー時や入浴後に指の腹で頭皮をやさしく圧迫 |
| 運動 | ウォーキングや軽いストレッチを習慣化 |
| 生活習慣 | 暖房による冷えすぎを防ぎ、体温を保つ |
冬の抜け毛が長引くときの対処
冬の抜け毛が急増し、その状態が長く続く場合は、頭皮の極端な乾燥やホルモンバランスの乱れが原因になっている可能性があります。
AGA治療や薄毛対策を専門とするクリニックでは、頭皮の状態をチェックし、必要に応じて適切な治療を行います。
セルフケアだけでは改善を感じにくい場合や、頭皮にかゆみや湿疹がある場合は、なるべく早めに受診して専門家に相談すると安心です。
季節を通じた抜け毛予防のポイント
髪が抜けやすい季節や時期は人によって異なりますが、基本的には季節ごとの特性に合わせたケアが肝心です。
一年を通して継続的に頭皮環境を整えることが、抜け毛だけでなく、髪のハリ・コシを保つ近道にもなります。
日常的なヘアケアの見直し
季節に合ったシャンプーやトリートメント選びが大切です。
夏のベタつきや冬の乾燥など、その時々で抱える頭皮や髪の悩みは変わるので、同じ製品を使い続けるよりも季節に応じて切り替える柔軟さを持つと良いです。
また、ブラッシング方法やドライヤーの使い方など、毎日のヘアケアを見直すだけでも抜け毛の増加を防ぎやすくなります。
通年で意識したいヘアケア
- シャンプー前の予洗いとしっかりしたすすぎ
- タオルドライで髪をこすらず、押さえるように水分を取る
- ドライヤーは髪から20cmほど離して、根元から毛先へ当てる
- ブラシは髪質や頭皮に合ったものを選ぶ
食事と生活習慣の一貫性
髪や頭皮の健康は体の内部環境とも深く関係します。バランスの良い食事と充分な睡眠は、どの季節でも髪の栄養補給とヘアサイクルの安定に直結します。
慢性的な睡眠不足や過度なダイエットなどが続くと、一時的に抜け毛が増えるばかりか、長期的な薄毛リスクを高めるケースもあります。
定期的な運動やストレスケアも意識し、頭皮だけでなく身体全体の健康を維持すると良いでしょう。
気になるときは専門医の診断も
髪が抜けやすい季節に対してセルフケアを行っても改善が見られない場合や、抜け毛の量が極端に多いと感じるときは、専門医への相談を検討してください。
早期の段階でAGAや薄毛の兆候を把握できれば、治療の選択肢も広がりやすくなります。
髪や頭皮の状態を自分で判断するのは難しい部分もあるため、気になる症状があれば遠慮なく医師や専門スタッフに相談しましょう。
病院やクリニックで相談するメリット
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 原因特定 | 頭皮や髪の状態を医師が診断し、正確に原因を把握できる |
| 早期治療 | AGAなどの脱毛症の場合、早めの治療で進行を抑えられる |
| ライフスタイル指導 | 栄養指導やヘアケアのアドバイスが受けられる |
| 安心感 | 自己判断の不安を解消し、専門家のフォローを受けられる |
年間を通して意識したいヘアサイクルの理解
髪は数年かけて生え変わるため、1か月や2か月で劇的に改善するわけではありません。
季節や時期の変化による抜け毛は、あくまでもヘアサイクルの一端です。定期的に自身のヘアサイクルを観察し、時期によってケアを工夫することが大切です。
抜け毛が気になる時期だけ対策を強化するのではなく、通年でのケアを大事にしながら、必要に応じて追加のケアや受診を行うと長期的な髪の健康を保ちやすくなります。
AGA治療・薄毛治療を考える際のポイント
髪が抜ける季節や時期が続くと、薄毛の進行が気になり始める方も多いでしょう。
特に男性はAGA、女性は女性型脱毛症(FAGA)の影響を受ける場合があります。ここでは実際に治療を検討する際のポイントを整理してみます。
AGA・FAGAのチェック
AGAやFAGAはホルモンバランスや遺伝要素が絡むため、市販の育毛剤だけでは根本的な解決に至らない場合があります。
以下のような兆候が見られる場合は、早めに専門の医療機関で検査を受けると安心です。
AGA・FAGAを疑う兆候
- 前髪や生え際、頭頂部の髪が薄くなってきた
- 全体的にボリュームダウンを感じる
- 髪のコシやハリが急激に弱まった
- 毛が細く柔らかくなってきた
治療法とクリニックの選び方
AGA治療では内服薬(フィナステリドやデュタステリド)や外用薬(ミノキシジル)などを使うことが多いです。医療機関によっては注入治療やレーザー治療などの独自の施術を組み合わせて行う場合もあります。
治療効果や副作用のリスク、費用などをしっかり確認し、自分の症状や生活スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
専門クリニックであれば、発毛効果やアフターケアについて詳しく説明を受けられるので、安心して治療を進められるでしょう。
代表的なAGA・薄毛治療の種類と特徴
| 治療法 | 主な特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 内服薬 | ホルモンへのアプローチ | 副作用リスクを把握する必要あり |
| 外用薬 | 血行促進や成長因子活性化 | 毎日の継続が必要 |
| 注入治療 | 直接頭皮に有効成分を注入 | 費用が高額になる場合あり |
| レーザー治療 | 血行促進や毛母細胞活性化 | 定期的な通院が必要 |
継続と経過観察が鍵
AGAやFAGAの治療は、効果が現れるまでに数か月以上かかる場合が多いです。ヘアサイクルの長さを考慮すると、継続的に治療を行いながら定期的に経過観察をする必要があります。
途中でやめてしまうとせっかくの効果が失われやすいため、医師と相談しながら治療プランを立てましょう。
また、季節による抜け毛の増減に一喜一憂せず、長期的な視点で改善を目指すのも大切です。
クリニック受診までに心がけたいこと
クリニックを受診する前に、ヘアケアや生活習慣の改善を試すのも無駄ではありません。適切なシャンプー選びや栄養バランスの見直し、ストレス管理などを行うと、治療の効果を高める土台が作れます。
また、頭皮や髪の状態を記録しておくと、受診時に医師へ具体的な情報を伝えやすくなり、スムーズに診断や治療方針を決めやすくなります。
よくある質問
髪が抜ける季節や時期の対策、ヘアケアの方法などについて、患者さんから寄せられる質問とその回答を紹介します。
- Q季節の変わり目に抜け毛が増えたら、すぐに病院へ行くべきですか?
- A
季節の変わり目に一時的に抜け毛が増えるのは多くの方に見られる現象です。
生活習慣の見直しやヘアケアを工夫しても明らかに改善が見られない場合や、頭皮トラブルが起きている場合には早めに医療機関を受診することをおすすめします。
抜け毛の原因を正確に把握するためには専門医の診断が有効です。
- QAGA治療薬を飲み始めたら、すぐに抜け毛が減りますか?
- A
AGA治療薬を飲み始めてすぐに抜け毛が減るわけではありません。効果を感じるまでには数か月かかるケースが多いです。
ヘアサイクルの期間を考慮しながら、焦らずに継続することが大切です。途中でやめると効果が半減しやすいので、医師の指示に従って治療を続けてください。
- Q女性でも季節的に抜け毛が増えることはありますか?
- A
女性でも季節の変わり目には抜け毛が増えることがあります。ホルモンバランスの乱れやストレス、生活習慣の変化などが重なると、抜け毛や髪質の低下が顕著になる場合もあります。
女性特有の薄毛(FAGA)が心配な方は、一度クリニックで相談してみると良いでしょう。
- Qどの季節がいちばん髪が抜けやすいですか?
- A
人によって差がありますが、一般的には夏から秋にかけて抜け毛が増えやすいと感じる方が多いです。夏の紫外線ダメージや汗、皮脂の影響が秋に表面化し、抜け毛が目立つようになります。
一方、冬の乾燥や春の花粉など、他の季節にも髪のトラブルは起こりやすいので、1年を通じたケアが大切です。
参考文献
HSIANG, E. Y., et al. Seasonality of hair loss: a time series analysis of Google Trends data 2004–2016. British Journal of Dermatology, 2018, 178.4: 978-979.
KUNZ, Michael; SEIFERT, Burkhardt; TRÜEB, Ralph M. Seasonality of hair shedding in healthy women complaining of hair loss. Dermatology, 2009, 219.2: 105-110.
BUONTEMPO, Michael G., et al. Seasonal trends in hair loss: A big data analysis of Google search patterns and their association with seasonal factors. Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, 2023, 37.12.
RANDALL, VALERIE A.; EBLING, F. J. G. Seasonal changes in human hair growth. British Journal of Dermatology, 1991, 124.2: 146-151.
HAMAD, Fatema AK. Seasonal hair loss. Medical Journal of Babylon, 2018.
COURTOIS, M., et al. Periodicity in the growth and shedding of hair. British Journal of Dermatology, 1996, 134.1: 47-54.
RANDALL, Valerie Anne. Androgens and hair growth. Dermatologic therapy, 2008, 21.5: 314-328.
MALKUD, Shashikant. Telogen effluvium: a review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 2015, 9.9: WE01.