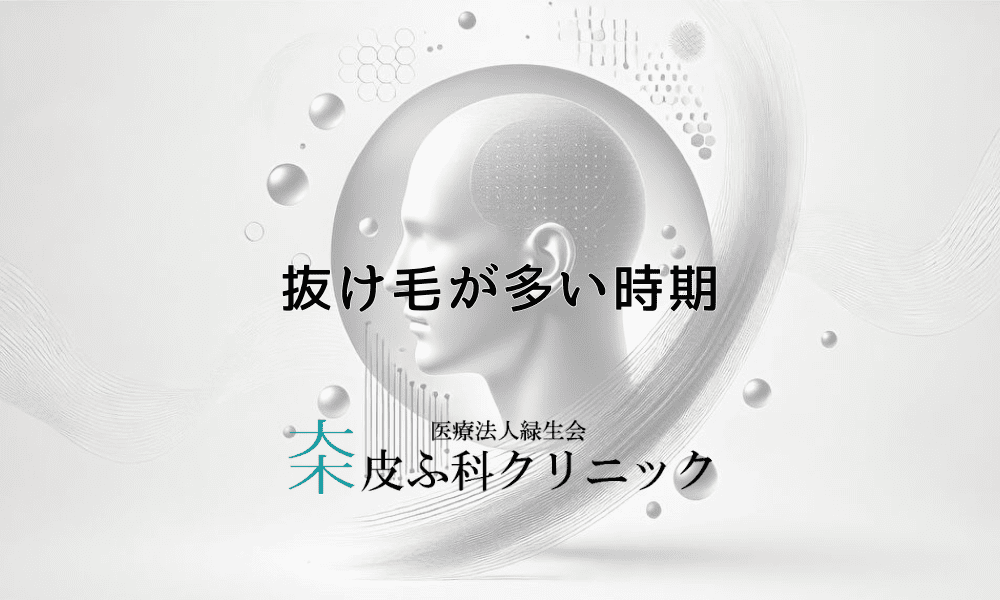抜け毛には毛周期という自然なサイクルがありますが、季節によって変動があるのか、特に抜け毛が多い時期はいつなのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、抜け毛と季節の関係、特に秋に抜け毛が増えやすいと言われる理由を詳しく解説します。
さらに、ご自身でできる日常的な対策から、季節性の抜け毛とAGA(男性型脱毛症)との違い、専門的な治療が必要なケースの見極め方まで幅広い情報をまとめます。
抜け毛は季節によって変動するのか
髪の毛が抜けること自体は誰にでもある自然な現象ですが、その量が時期によって変動するように感じる方もいます。
抜け毛の周期と季節の関係
髪の毛には一本一本に寿命があり、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。これを毛周期(ヘアサイクル)と呼びます。
通常、ほとんどの髪の毛(約85〜90%)は成長期にあり、数年間伸び続けます。その後、退行期に入り毛根が縮小し、最終的に休止期を迎えて自然に抜け落ちます。
そして、同じ毛穴からはまた新しい髪の毛が生え始めます。このサイクルは常に一定ではなく、体調やホルモンバランス、そして環境要因によって影響を受ける場合があります。
季節の変化もその環境要因の一つとして、抜け毛の量に影響を与える可能性が考えられています。
多くの人が抜け毛を実感しやすい時期
一般的に、抜け毛が多い時期として多くの人が実感しやすいのは「秋」と言われています。夏に受けたダメージの影響や、体の変化などが複合的に関わっていると考えられます。
また、春先に抜け毛の増加を感じるという声も聞かれます。このように、特定の季節に抜け毛の変化を感じる方は少なくありません。ただし、その程度や時期には個人差があります。
抜け毛量の目安
| 季節 | 抜け毛の傾向(一般的な目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 春 | やや増加傾向 | 環境変化、花粉などの影響も考えられる |
| 夏 | やや減少傾向 | 紫外線ダメージは蓄積されやすい |
| 秋 | 増加傾向 | 夏のダメージ、気候変動などの影響 |
| 冬 | やや減少〜横ばい | 乾燥による頭皮トラブルに注意 |
個人差はある?季節変動を感じない人も
季節による抜け毛の変動は、全ての人に当てはまるわけではありません。抜け毛の量を日々細かく数えている人は稀であり、多少の増減に気づかないケースも多いでしょう。
また、生活環境や体質、遺伝的な要因や基礎疾患の有無などによっても抜け毛のパターンは異なります。そのため、季節による抜け毛の変化をほとんど感じない人もいます。
大切なのは、平均的な傾向に一喜一憂するのではなく、ご自身の普段の抜け毛の状態を把握しておくことです。
なぜ特定の季節に抜け毛が増えると感じるのか
特定の季節、特に秋に抜け毛が増加すると言われる背景には、いくつかの要因が考えられます。これらの要因が複合的に絡み合い、抜け毛の変動につながると推測されています。
夏のダメージの蓄積と秋への影響
夏の間、私たちは強い紫外線にさらされます。紫外線は髪の毛そのものだけでなく、頭皮にもダメージを与えます。
頭皮が日焼けすると炎症を起こしたり、乾燥しやすくなったりして、毛根の働きが弱まるときがあります。また、夏は汗や皮脂の分泌が増え、毛穴が詰まりやすくなるため頭皮環境の悪化につながります。
これらの夏に受けたダメージがすぐには現れず、少し遅れて秋頃に抜け毛の増加として現れる可能性があります。
気候変動と頭皮環境の変化
秋は夏から冬へと移り変わる季節であり、気温や湿度が大きく変動します。急な気温の低下は血行不良を招きやすく、頭皮への栄養供給が滞る原因となりえます。
また、空気が乾燥し始めると頭皮も乾燥してフケやかゆみといったトラブルを引き起こし、これも抜け毛につながる可能性があります。
気候の変化に体が適応しようとする過程で、一時的に頭皮環境が不安定になることが考えられます。
ホルモンバランスの季節変動説
人間の体内のホルモンバランスは、日照時間の影響を受けることが知られています。例えば、睡眠に関わるメラトニンや精神安定作用のあるセロトニンなどは、日照時間の変化によって分泌量が変動します。
これらのホルモンが直接的に毛周期にどの程度影響を与えるかは明確には解明されていませんが、間接的に体調や自律神経のバランスに影響し、結果として抜け毛の増減に関与している可能性も指摘されています。
動物の換毛期の名残という説
犬や猫などの動物には、季節の変わり目に毛が生え変わる「換毛期」があります。これは、気候の変化に適応するために毛の量を調整する自然な現象です。
人間にも大昔の動物としての機能の名残として、わずかに換毛期のような性質が残っており、それが秋の抜け毛増加の一因となっているのではないか、といった説もあります。
科学的根拠はまだ十分ではありませんが、一つの可能性として考えられています。
特に抜け毛が多いとされる季節とその理由
一般的に抜け毛が増えやすいとされるのは秋ですが、他の季節にも注意すべき点があります。季節ごとの抜け毛の傾向と、その背景にある理由について見ていきましょう。
秋(9月〜11月頃)がピークと言われる理由
多くの人が抜け毛の増加を実感しやすいのが秋です。
これには前述の通り、夏の間に受けた紫外線ダメージの蓄積、汗や皮脂による毛穴詰まりの影響が時間差で現れること、気温や湿度の急激な変化による頭皮環境の悪化、血行不良などが複合的に関わっていると考えられます。
また、動物の換毛期の名残やホルモンバランスの変動説も、秋に抜け毛が増える理由として挙げられます。一年の中で抜け毛が最も気になる時期と言えるかもしれません。
秋に抜け毛が増える要因
| 要因 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 夏のダメージ蓄積 | 紫外線による頭皮・毛髪ダメージ、皮脂詰まりなど |
| 気候の急激な変化 | 気温低下による血行不良、乾燥による頭皮トラブル |
| ホルモンバランス等の変動説 | 日照時間変化に伴う体内リズムの変化の可能性 |
春(3月〜5月頃)にも注意が必要?
秋ほどではありませんが、春先に抜け毛が増えると感じる人もいます。
これは、冬の寒さによる血行不良や乾燥の影響が残っていることに加え、新生活や環境の変化に伴うストレス、花粉などのアレルギー物質による頭皮への刺激などが原因として考えられます。
特に、生活環境が大きく変わる方は知らず知らずのうちにストレスを溜め込み、それが抜け毛に影響している可能性もあります。
夏と冬の抜け毛の傾向
夏は一般的に髪の成長が活発になり、抜け毛は比較的少ない傾向にあると言われます。
しかし、強い紫外線対策を怠ると頭皮や髪に大きなダメージを与え、秋の抜け毛増加につながるため油断はできません。また、汗や皮脂対策も重要です。
一方、冬は寒さによる血行不良や、暖房による空気の乾燥が頭皮環境を悪化させる可能性があります。
頭皮が乾燥するとフケやかゆみが出やすくなり、これも抜け毛の原因となりえますので、適切な保湿ケアが大切になる季節です。
季節性の抜け毛とAGA(男性型脱毛症)の違い
抜け毛が増えたと感じると、「もしかしてAGA(男性型脱毛症)では?」と心配になる方もいるかもしれません。
しかし、季節性の抜け毛とAGAは異なるものです。その違いを理解して適切な対応をとることが重要です。
抜け毛の量だけで判断しない
季節性の抜け毛は、一時的に抜け毛の本数が増える場合がありますが、毛周期全体が乱れているわけではありません。通常、秋に増えたとしても、しばらくすると元の状態に戻る方が多いです。
一方、AGAは進行性の脱毛症であり、特定のパターンで薄毛が徐々に進行していくのが特徴です。単純に「抜け毛が多い」という量だけで判断せず、抜け毛の質や薄毛の進行パターンに注目する必要があります。
AGAの特徴的な症状とは
AGAには、季節性の抜け毛とは異なるいくつかの特徴的な症状が見られます。
- 生え際の後退(M字型)
- 頭頂部の薄毛(O字型)
- 軟毛化(髪の毛が細く、短くなる)
これらの症状が見られる場合、季節性の抜け毛だけでなくAGAの可能性も考える必要があります。
AGAは男性ホルモンや遺伝が関与しており、毛周期の成長期が短縮されることで髪の毛が十分に育つ前に抜け落ちてしまう状態です。
AGAの主な症状
- 生え際の後退
- 頭頂部の薄毛
- 髪の毛の軟毛化
季節変動とAGAが併発する可能性
注意したいのは、季節性の抜け毛とAGAが同時に起こる可能性があることです。
もともとAGAが緩やかに進行している人が、秋になって季節性の要因が加わることで、抜け毛が急激に増えたように感じるときがあります。
そのため、「秋だから抜け毛が多いのだろう」と自己判断してしまうと、AGAの発見や治療開始が遅れてしまうリスクがあります。
季節性抜け毛とAGAの簡単な比較
| 項目 | 季節性の抜け毛(一時的) | AGA(男性型脱毛症) |
|---|---|---|
| 主な原因 | 季節変化、環境要因、一時的な体調変化 | 男性ホルモン、遺伝 |
| 進行 | 一時的、回復傾向あり | 進行性 |
| 薄毛の部位 | 全体的に増える傾向 | 生え際、頭頂部など特定のパターンで進行 |
| 毛質 | 通常の太さの毛が抜ける | 細く短い毛(軟毛化)が増え、抜け毛にも見られる |
不安な場合は専門医へ相談を
抜け毛の増加が一時的なものなのか、それともAGAのような治療が必要な脱毛症なのかを自分で正確に判断するのは難しい場合があります。
「抜け毛が異常に多い気がする」「以前より明らかに髪が細くなった」「特定の部位の薄毛が気になる」といった不安がある場合は、自己判断せずに早めに皮膚科やAGA専門クリニックを受診することをおすすめします。
季節の変わり目に行うべき抜け毛対策(セルフケア)
抜け毛が多い時期と感じた場合でも、日々のセルフケアを見直すと頭皮環境を健やかに保てて、抜け毛の予防や改善につなげることが期待できます。
バランスの取れた食事と栄養摂取
髪の毛は主にタンパク質(ケラチン)でできています。そのため、良質なタンパク質の摂取は非常に重要です。
また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、頭皮環境を整えるビタミンB群も積極的に摂取したい栄養素です。
髪の成長に役立つ主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンを作る | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝促進、皮脂バランス調整 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、緑黄色野菜 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、アボカド、うなぎ、植物油 |
| ビタミンC | コラーゲン生成補助、抗酸化作用 | 果物(キウイ、イチゴ)、野菜(パプリカ、ブロッコリー) |
正しいシャンプー方法と頭皮ケア
毎日のシャンプーは、頭皮の汚れや余分な皮脂を落として清潔に保つために重要ですが、間違った方法で行うと逆に頭皮を傷つけてしまう可能性があります。
まず、シャンプー前にブラッシングで髪のもつれをほどき、ホコリなどを浮かせることから始めましょう。次に、ぬるま湯で髪と頭皮を十分に予洗いします。
シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは避けましょう。すすぎは泡が残らないように、時間をかけて丁寧に行います。
シャンプー後は、ドライヤーで髪だけでなく頭皮もしっかり乾かす工程が大切です。濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなります。
正しいシャンプーの手順概要
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| ブラッシング | 髪のもつれを解き、ホコリを浮かせる |
| 予洗い | ぬるま湯で髪と頭皮を十分に濡らし、汚れをある程度落とす |
| シャンプー | 手で泡立て、指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗う |
| すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧に洗い流す |
| 乾燥 | タオルドライ後、ドライヤーで頭皮からしっかり乾かす(温風冷風を使い分ける) |
質の高い睡眠とストレス管理
睡眠不足や質の低い睡眠は髪の成長に必要な成長ホルモンの分泌を妨げ、自律神経のバランスを乱して血行不良を招くなど、抜け毛の原因となります。
毎日決まった時間に寝起きして、規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は避け、リラックスできる環境を整えるのも大切です。
睡眠の質を高める
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 就寝前の習慣 | ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、軽いストレッチをする |
| 寝室環境 | 寝具を快適なものにする、部屋を暗く静かにする |
| 生活リズム | 決まった時間に寝起きする、日中に適度な運動をする |
ストレス軽減
また、過度なストレスも自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行を悪化させます。自分に合ったストレス解消法を見つけ、溜め込まないようにする工夫も重要です。
- 趣味を楽しむ時間を作る
- 軽い運動や散歩をする
- 友人や家族と話す
- 瞑想や深呼吸を行う
紫外線対策の重要性
紫外線は髪の毛のキューティクルを傷つけ、パサつきや切れ毛の原因となるだけでなく、頭皮にもダメージを与えて炎症や乾燥を引き起こします。
特に紫外線の強い季節や時間帯に外出する際は、帽子や日傘を使用する、髪用のUVカットスプレーを利用するなどして、紫外線から髪と頭皮を守ることを意識しましょう。
これは夏だけでなく、日差しが強い日には年間を通して心がけたい対策です。
生活習慣の見直しによる抜け毛予防
日々のセルフケアに加えて、生活習慣全体の見直しも抜け毛の予防や頭皮環境の改善につながります。健康的な生活は、健やかな髪を育む土台となります。
喫煙や過度な飲酒の影響
喫煙は血管を収縮させ、血行を悪化させます。頭皮の毛細血管も例外ではなく、血流が悪くなると髪の毛の成長に必要な栄養素や酸素が毛根に届きにくくなり、抜け毛の原因となります。
また、タバコに含まれる有害物質は、髪の毛を作り出す毛母細胞の働きを妨げる可能性も指摘されています。
過度な飲酒も、アルコールを分解する過程で髪の毛の成長に必要な栄養素が大量に消費されたり、睡眠の質を低下させたりするため、間接的に抜け毛に影響を与える可能性があります。適量を心がけると良いです。
喫煙・飲酒と抜け毛の関係
| 習慣 | 髪への主な悪影響 |
|---|---|
| 喫煙 | 血管収縮による血行不良、毛母細胞への悪影響、栄養素供給の阻害 |
| 過度な飲酒 | 栄養素(亜鉛、ビタミン)の消費、肝臓への負担、睡眠の質の低下による成長ホルモン分泌抑制 |
適度な運動習慣を取り入れる
適度な運動は全身の血行を促進し、頭皮への血流改善にもつながります。血行が良くなると毛根に栄養が行き渡りやすくなり、髪の健やかな成長をサポートできます。
また、運動はストレス解消にも効果的です。ウォーキングやジョギング、ヨガなどの自分が続けやすい運動を生活に取り入れてみましょう。
ただし、激しすぎる運動は活性酸素を増やして逆効果になる可能性もあるため、無理のない範囲で行うことが重要です。
帽子や日傘による物理的な保護
紫外線対策として帽子や日傘が有効ですが、これらは紫外線だけでなく、外部からの物理的な刺激や冬場の寒さ、乾燥した空気などからも頭皮を守る役割を果たします。
特に頭頂部や生え際など、髪の毛が薄くなっている部分は直接的なダメージを受けやすいため、意識的に保護するのが望ましいです。
ただし、帽子を長時間かぶり続けると蒸れて頭皮環境が悪化するケースもあるため、通気性の良い素材を選んだり、こまめに脱いで換気したりする工夫も必要です。
生活習慣で見直したいポイント
| 項目 | 見直しの方向性 |
|---|---|
| 食事 | バランスの取れた栄養摂取、特にタンパク質、ビタミン、ミネラルを意識する |
| 睡眠 | 規則正しい時間に十分な睡眠をとる、睡眠の質を高める工夫をする |
| 運動 | 適度な運動習慣を取り入れ、血行促進とストレス解消を図る |
| 嗜好品 | 禁煙または節煙を心がける、飲酒は適量にとどめる |
| ストレス | 自分に合ったストレス解消法を見つけ、溜め込まないようにする |
| 外部刺激 | 紫外線、寒さ、乾燥などから帽子や日傘で頭皮を保護する(蒸れに注意) |
抜け毛が多い時期に関するよくある質問
抜け毛や薄毛に関する悩みは、なかなか人には相談しにくいものです。ここでは、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q抜け毛は何本くらいまでなら正常範囲ですか?
- A
健康な人でも、1日に50本から100本程度の髪の毛は自然に抜け落ちています。これは毛周期による正常な現象です。
シャンプー時やブラッシング時に一時的にまとまって抜けるため多く感じるときもありますが、1日の合計本数がこの範囲内であれば、過度に心配する必要はないでしょう。
ただし、急激に抜け毛が増えたと感じるときや、以前よりも明らかに本数が多い状態が続く場合は注意が必要です。
季節によって多少の変動はありますが、明らかに150本、200本と多い状態が続く場合は、何らかの原因が隠れている可能性があります。
- Q食事で特に意識すべき栄養素は何ですか?
- A
髪の健やかな成長のためにはバランスの取れた食事が基本ですが、特に意識したい栄養素がいくつかあります。
まず、髪の主成分であるタンパク質は必須です。肉や魚、卵や大豆製品などから良質なタンパク質を摂取しましょう。
次に、タンパク質を髪の毛(ケラチン)に合成する際に重要な役割を果たす亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉など)も大切です。
さらに、頭皮の血行を促進するビタミンE(ナッツ類、アボカドなど)や、頭皮環境を整えるビタミンB群(豚肉、レバー、青魚など)、抗酸化作用があり頭皮の健康を保つビタミンC(果物、野菜)なども積極的に摂りたい栄養素です。
- Qセルフケアで改善しない場合はどうすれば良いですか?
- A
バランスの取れた食事や正しいヘアケア、十分な睡眠やストレス管理などのセルフケアを続けても抜け毛の改善が見られない方や、薄毛が進行しているように感じる方は、自己判断を続けずに専門医に相談すると良いでしょう。
特に、AGA(男性型脱毛症)やFAGA(女性男性型脱毛症)、円形脱毛症など、治療が必要な脱毛症が原因である可能性も考えられます。
早期に適切な診断を受けて原因に合った治療を開始することが、症状の進行を食い止め、改善につながる鍵となります。
- Qクリニックではどのような検査や治療を行いますか?
- A
薄毛治療を行うクリニックでは、問診や視診はもちろん、マイクロスコープで毛穴や毛根の状態を拡大して観察したり、血液検査でホルモンバランスや栄養状態を確認したりする場合もあります。
治療法は、診断結果や患者さんの希望に応じて選択されます。
AGAやFAGAの場合、内服薬(フィナステリド、デュタステリド、ミノキシジルなど)や外用薬(ミノキシジル)による治療が中心です。これらは、抜け毛の原因に直接働きかけたり、発毛を促進したりする効果が期待できます。
その他、頭皮に直接有効成分を注入する治療(メソセラピーなど)や、LED照射による治療、自毛植毛などの様々な選択肢があります。
どの治療法が適しているかは個々の症状や状態によって異なりますので、専門医とよく相談して納得のいく治療法を選択することが大切です。
参考文献
RANDALL, VALERIE A.; EBLING, F. J. G. Seasonal changes in human hair growth. British Journal of Dermatology, 1991, 124.2: 146-151.
KUNZ, Michael; SEIFERT, Burkhardt; TRÜEB, Ralph M. Seasonality of hair shedding in healthy women complaining of hair loss. Dermatology, 2009, 219.2: 105-110.
COURTOIS, M., et al. Periodicity in the growth and shedding of hair. British Journal of Dermatology, 1996, 134.1: 47-54.
HSIANG, E. Y., et al. Seasonality of hair loss: a time series analysis of Google Trends data 2004–2016. British Journal of Dermatology, 2018, 178.4: 978-979.
RANDALL, Valerie Anne. Hormonal regulation of hair follicles exhibits a biological paradox. In: Seminars in Cell & Developmental Biology. Academic Press, 2007. p. 274-285.
WILLIAMS, Lana J.; WHITE, Christine D.; LONGSTAFFE, Fred J. Improving stable isotopic interpretations made from human hair through reduction of growth cycle error. American Journal of Physical Anthropology, 2011, 145.1: 125-136.
BLACK, D., et al. Seasonal variability in the biophysical properties of stratum corneum from different anatomical sites. Skin research and Technology, 2000, 6.2: 70-76.
RANDALL, Valerie Anne. Androgens and hair growth. Dermatologic therapy, 2008, 21.5: 314-328.