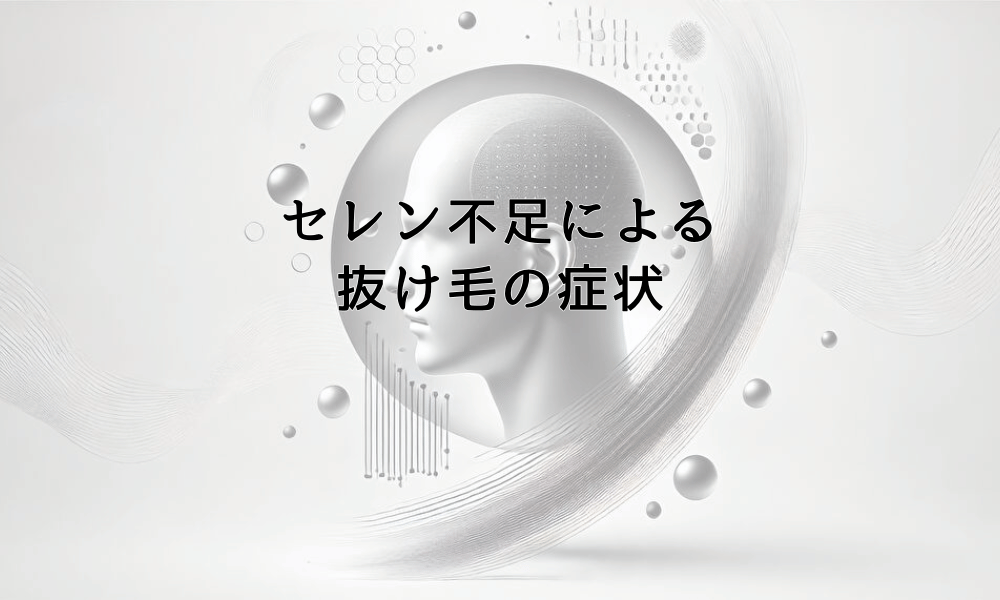抜け毛が増えた、髪が細くなったと感じている方が増えている印象です。その原因は、必須ミネラルの一つである「セレン」の不足かもしれません。
セレンは強力な抗酸化作用を持ち、頭皮の健康を守り、毛髪の成長を支える重要な栄養素です。
しかし、食生活の乱れや特定の生活習慣によって、知らず知らずのうちに不足してしまうケースがあります。
この記事では、セレンが髪に与える影響から、不足すると現れる抜け毛のサイン、そして健やかな髪を取り戻すための効果的な栄養摂取法までを詳しく解説します。
そもそもセレンとは?髪の健康にどう関わるのか
セレンという栄養素の名前を初めて聞く方もいるかもしれません。セレンは私たちの身体の機能を正常に保つために必要な「必須ミネラル」の一種です。
強力な抗酸化作用で頭皮と毛髪をダメージから守り、ヘアサイクルを正常に保つ働きがあります。体重あたりに含まれる量はごくわずかですが、その影響力は決して小さくありません。
ミネラルの一種としてのセレンの役割
セレンは、体内で作られる特殊なたんぱく質(セレノプロテイン)の構成成分となります。このセレノプロテインは、身体のさまざまな機能を調節する上で大切な働きをします。
特に、活性酸素から細胞を守る抗酸化作用の中心的な役割を担う酵素の働きを助けることが知られています。
髪の毛を作り出す毛母細胞も、他の細胞と同じく活性酸素によるダメージを受けるため、セレンによる保護機能は毛髪の健康維持に直接つながります。
セレンが関わる体内の主要な働き
| 主な働き | 身体への影響 | 毛髪への関連性 |
|---|---|---|
| 抗酸化作用 | 細胞の酸化ストレスを軽減し、老化を防ぐ | 毛母細胞を保護し、健康な髪の育成を支える |
| 甲状腺機能の調節 | 甲状腺ホルモンの活性化を助ける | 毛髪の成長サイクル(ヘアサイクル)を正常に保つ |
| 免疫機能の維持 | 身体の防御システムを正常に保つ | 頭皮の炎症を防ぎ、健康な頭皮環境を維持する |
抗酸化作用と頭皮の健康維持
私たちは呼吸をするだけで体内に活性酸素を取り込んでいます。これに加え、紫外線やストレス、不規則な生活なども活性酸素を増やす原因となります。
増えすぎた活性酸素は細胞を傷つけ、老化を早める「酸化ストレス」という状態を引き起こします。
頭皮の細胞がこの酸化ストレスにさらされると、血行が悪化したり毛母細胞の働きが低下したりして、健康な髪が育ちにくくなります。
セレンは活性酸素を除去する酵素「グルタチオンペルオキシダーゼ」の主要な構成成分であり、頭皮を酸化ストレスから守って、抜け毛や薄毛の予防に貢献します。
甲状腺ホルモンとの関係と毛髪サイクル
セレンは、甲状腺ホルモンの代謝にも深く関わっています。甲状腺ホルモンは身体の新陳代謝を活発にする働きがあり、髪の毛が生まれ変わるサイクル、いわゆる「ヘアサイクル」を正常に保つためにも重要です。
セレンが不足すると甲状腺ホルモンの働きが鈍くなり、ヘアサイクルの「成長期」が短くなって、「休止期」にとどまる毛髪の割合が増える場合があります。
その結果、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまい、全体的に髪が薄くなったと感じる原因の一つになります。
セレン不足が引き起こす抜け毛のサイン
セレン不足は、すぐにはっきりとした症状として現れにくいため、気づかないうちの進行する可能性があります。
髪質の悪化(パサつき・細毛)、抜け毛の増加、フケやかゆみといった頭皮環境の悪化サインを見逃さずに、早めに対応していきましょう。
髪質の変化(パサつき・細毛)
セレンは健康な髪のキューティクルを維持するためにも役立ちます。不足すると、髪の表面が乱れてツヤがなくなり、パサついた印象になります。
また、毛母細胞の働きが弱まるために新しく生えてくる髪が十分に成長できず、以前よりも細くコシのない髪質に変化する場合があります。
「最近、髪のまとまりが悪くなった」「一本一本が弱々しくなった」と感じる場合は、セレン不足のサインかもしれません。
髪質の変化チェックポイント
| チェック項目 | 以前の状態 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 髪のツヤ | 自然な光沢があった | パサつきが目立ち、ツヤがない |
| 髪の太さ | しっかりとした太さがあった | 細く、切れやすくなった |
| 髪のハリ・コシ | 根元から立ち上がりがあった | 全体的にボリュームダウンした |
抜け毛の増加とヘアサイクルの乱れ
セレン不足による甲状腺機能の低下は、ヘアサイクルに直接影響を及ぼします。通常、髪の毛は2年から6年程度の成長期を経て、自然に抜け落ちます。
しかし、ヘアサイクルが乱れると成長期が短縮され、まだ成長途中であるはずの細く短い毛が抜けるようになります。
シャンプーやブラッシングの際に、明らかに抜け毛が増えたと感じたり、枕に付着する毛の量が気になったりした場合は注意が必要です。
頭皮環境の悪化(フケ・かゆみ)
セレンの持つ抗酸化作用は、頭皮の健康状態を保つ上でも重要です。
セレンが不足し、頭皮が酸化ストレスにさらされると、皮膚のバリア機能が低下します。その結果、外部からの刺激に弱くなり、乾燥しやすくなって、フケやかゆみといった頭皮トラブルを引き起こすケースがあります。
頭皮環境の悪化は、健康な髪が育つ土台を損なうことになり、間接的に抜け毛を助長する原因となります。
あなたは大丈夫?セレン不足になりやすい生活習慣
セレンは多くの食品に含まれているため、通常の食生活を送っていれば極端に不足することは稀です。
しかし、加工食品の多用といった偏った食生活、過度なダイエット、消化器系の疾患などが原因でセレン不足が起こりやすくなるのも事実です。
この機会に、ご自身の生活を振り返ってみましょう。
偏った食生活と加工食品の多用
セレンは魚介類や肉類、卵や穀物などに豊富に含まれています。
しかし、ファストフードやインスタント食品、スナック菓子といった加工度の高い食品ばかりを食べていると、これらの栄養素を十分に摂取できません。
特に、野菜中心の食生活や、特定の食品を避けるような極端な食事制限をしている場合、セレンの摂取量が不足する可能性があります。
土壌のセレン含有量が少ない地域での生活
植物に含まれるセレンの量は、その植物が育った土壌のセレン濃度に大きく影響されます。日本は全般的に土壌のセレン含有量がそれほど高くない地域とされています。
そのため、国内産の野菜や穀物だけに頼るのではなく、魚介類や肉類など、多様な食品からセレンを摂取する意識が大切です。
海外でも、特定の地域ではセレン欠乏が社会的な問題となっている場所もあります。
消化器系の疾患や加齢による吸収率の低下
栄養素は食事から摂取するだけでなく、体内で適切に消化・吸収されて初めて利用されます。
クローン病や潰瘍性大腸炎といった消化器系の疾患を抱えている方は栄養素の吸収がうまくいかず、セレン不足に陥るときがあります。
また、加齢に伴い消化機能が全般的に低下している状態も、栄養素の吸収率を下げ、結果的に体内でのセレン不足を招く一因となります。
セレン不足を招く要因
| カテゴリ | 具体的な内容 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 食生活 | 加工食品中心、外食が多い、極端な食事制限 | 多様な食材を取り入れたバランスの良い食事 |
| 身体の状態 | 消化器系の疾患、加齢による消化機能の低下 | かかりつけ医への相談、消化に良い調理法の工夫 |
| 生活環境 | 土壌のセレンが少ない地域、不規則な生活 | 魚介類や肉類を意識的に摂取する |
過度なダイエットによる栄養不足
体重を減らすことだけを目的とした無理なダイエットは、身体に必要な栄養素の全体的な欠乏を招きます。
食事量を極端に減らすとセレンだけでなく、たんぱく質や亜鉛、ビタミン類といった、髪の健康に欠かせない他の栄養素も同時に不足してしまいます。
その結果、髪が栄養失調状態となり、抜け毛が一気に進行する危険性があります。健康的なダイエットは、栄養バランスを保ちながら行うのが基本です。
抜け毛改善を目指すセレンの効果的な摂取法
抜け毛改善のためには、セレンを豊富に含む魚介類や肉類などを日々の食事に取り入れるのが基本です。
ビタミンEやCと一緒に摂取すると吸収率が高まりますが、サプリメントなどによる過剰摂取は健康被害のリスクがあるため注意が必要です。
セレンを豊富に含む食品一覧
セレンは、私たちの身近にある多くの食品に含まれています。特に、魚介類や肉類、卵や穀類に豊富です。
- 魚介類(マグロ、カツオ、イワシなど)
- 肉類(豚レバー、鶏肉、牛肉など)
- 卵類
- 穀類(玄米、全粒粉パンなど)
- ナッツ類(ブラジルナッツ、カシューナッツなど)
日々の食事にこれらの食品をバランス良く取り入れるように心がけましょう。
食品別セレン含有量の目安(可食部100gあたり)
| 食品カテゴリ | 食品名 | セレン含有量(μg) |
|---|---|---|
| 魚介類 | クロマグロ(赤身) | 約110 |
| 魚介類 | カツオ(春獲り) | 約99 |
| 肉類 | 豚レバー | 約75 |
| 卵類 | 鶏卵(全卵) | 約25 |
| 穀類 | 玄米 | 約23 |
※文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より引用。含有量は目安です。
吸収率を高める食べ合わせの工夫
セレンは、他の栄養素と一緒に摂取すると、体内での吸収率や利用効率が高まることが知られています。
特に、ビタミンEやビタミンCといった抗酸化作用を持つビタミンと一緒に摂るのがおすすめです。
これらのビタミンは、セレンと協力して活性酸素から細胞を守る働きを強化します。
セレンと相性の良い栄養素
| 栄養素 | 相乗効果 | 多く含まれる食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンE | 互いの抗酸化作用を高め合う | アーモンド、植物油、アボカド |
| ビタミンC | セレンの働きを助け、抗酸化力をサポート | ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ |
| たんぱく質 | セレンはたんぱく質と結合して体内に貯蔵される | 肉、魚、大豆製品、卵 |
例えば、カツオのたたきに香味野菜(ビタミンC)を添えたり、玄米ご飯(セレン)と納豆(たんぱく質)、アボカド(ビタミンE)を組み合わせたりするなどの工夫が効果的です。
1日の推奨摂取量と過剰摂取のリスク
セレンは身体に必要ですが、摂りすぎは禁物です。厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」では、成人男女の推奨量が設定されています。
また、通常の食事で過剰摂取になることはほとんどありませんが、サプリメントなどを利用する際には上限量(耐容上限量)を超えないように注意が必要です。
- 成人男性の推奨量 30μg/日
- 成人女性の推奨量 25μg/日
- 耐容上限量(男女共通) 450μg/日(成人)
セレンを過剰に摂取すると、脱毛や爪の変形、胃腸障害や神経系の異常などの健康被害(セレノーシス)を引き起こす可能性があります。
特にブラジルナッツはセレンの含有量が非常に高いため、食べる量には注意しましょう。
食事だけで改善は難しい?サプリメント活用の注意点
食事での改善が難しい場合、サプリメントの活用も有効な手段ですが、自己判断での使用は避けるべきです。
セレン単体だけでなく他の栄養素とのバランスを考え、過剰摂取のリスクを避けるためにも、まずは医療機関で相談すると良いでしょう。
サプリメントを選ぶ際の基準
市場には多くのセレンサプリメントが出回っていますが、選ぶ際にはいくつかのポイントを確認しましょう。
まず、含有量が明確に表示されているか、そして過剰摂取にならない量であるかを確認します。
また、セレン酵母など、吸収されやすい形で配合されている製品を選ぶのも良いでしょう。不要な添加物が少なく、信頼できるメーカーの製品を選ぶ意識も大切です。
医療機関で相談する重要性
抜け毛の原因はセレン不足だけとは限りません。自己判断でサプリメントを摂取する前に、まずは医療機関で専門家の診断を受けることを推奨します。
血液検査を行えば、体内のセレン濃度や他の栄養素の状態を客観的に把握できます。その上で、医師や管理栄養士が本当に必要な栄養素や適切な摂取量を判断し、アドバイスを行います。
専門家の判断によって、無駄なサプリメント摂取や過剰摂取のリスクを避けられます。
他の栄養素とのバランスを考える
髪の健康は、セレンという一つの栄養素だけで成り立つものではありません。
髪の主成分であるたんぱく質(ケラチン)、その合成を助ける亜鉛、頭皮の血行を促進するビタミンEなど、多くの栄養素が互いに連携しあって機能しています。
セレンだけを大量に摂取しても、他の栄養素が不足していれば十分な効果は期待できません。
特定の成分に特化したサプリメントよりも、髪に必要な栄養素をバランス良く配合した製品を選ぶか、食事全体のバランスの見直しが根本的な解決につながります。
AGA治療とセレン摂取の相乗効果
抜け毛や薄毛の原因が、男性ホルモンの影響によるAGA(男性型脱毛症)である場合、栄養改善だけでは進行を止めるのは困難です。
その場合は、クリニックでの専門的な治療とセレンをはじめとする栄養摂取を組み合わせると、より改善効果が期待できます。
クリニックでの診断の重要性
「自分の薄毛は栄養不足が原因なのか、それともAGAなのか」を自己判断するのは非常に難しいです。
クリニックでは専門の医師が問診や視診、マイクロスコープによる頭皮チェックなどを行い、薄毛の原因を正確に診断します。
原因の特定が適切な対策への第一歩です。もしAGAと診断された場合は、医学的根拠に基づいた治療法を提案します。
治療薬と栄養指導の組み合わせ
AGA治療では、主に脱毛を抑制する内服薬や、発毛を促進する外用薬を使用します。これらの治療によってヘアサイクルを正常化させ、髪が育つ土台を整えます。
その上で、セレンを含む栄養指導を行うと、新しく生えてくる髪をより強く、健康に育てられます。
治療薬が「髪の成長を邪魔する要因を取り除く」働きをし、栄養が「髪が成長するための材料を供給する」働きをするとイメージすると分かりやすいでしょう。
AGA治療と栄養改善の役割分担
| アプローチ | 主な役割 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| AGA治療(医療) | 脱毛の進行を抑制し、発毛を促す | 内服薬(フィナステリド等)、外用薬(ミノキシジル等) |
| 栄養改善(食事) | 健康な髪を育てるための材料を供給する | セレン、亜鉛、たんぱく質等のバランスの取れた食事 |
身体の内外から行う薄毛対策
薄毛治療は、薬を飲むだけで終わりではありません。クリニックでは治療と並行して、一人ひとりの生活スタイルに合わせた食事や生活習慣のアドバイスを丁寧に行います。
身体の外側からの働きかけ(治療薬)と、内側からの働きかけ(栄養・生活習慣)を同時に行うことで、総合的な薄毛対策を実現します。
髪の悩みを一人で抱え込まず、いちど専門家に相談してみましょう。
セレンと抜け毛に関するよくある質問
さいごに、患者さんからよく寄せられるセレンと抜け毛に関する質問とその回答をまとめました。
- Qセレンを摂り始めてから効果が出るまでどのくらいかかりますか?
- A
髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、栄養状態が改善されてからその効果が目に見える形で現れるまでには、少なくとも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。
ヘアサイクル全体が改善し、髪質の変化を実感するには、継続的な摂取が大切になります。焦らず、じっくりと体質改善に取り組む姿勢が重要です。
- Qセレンの過剰摂取で副作用はありますか?
- A
通常の食事で問題になるケースは稀ですが、サプリメントの不適切な使用により耐容上限量(成人で450μg/日)を超えた摂取が続くと、脱毛、爪の変形や脆弱化、疲労感や胃腸障害、神経系の症状などの中毒症状(セレノーシス)が現れる可能性があります。
サプリメントを利用する場合は必ず含有量を確認し、上限を超えないように注意してください。
- Q子どもや女性でもセレン不足による抜け毛は起こりますか?
- A
子どもや女性でも起こり得ます。セレンは性別や年齢に関わらず、すべての人にとって必要な栄養素です。
特に、成長期の子供の偏食や、女性の過度なダイエットはセレン不足を招きやすく、それが抜け毛や髪のトラブルにつながる可能性があります。
女性の場合は、甲状腺機能の変調が抜け毛の原因となるケースも多く、セレン不足がその一因となることも考えられます。
- Q他のミネラル(亜鉛など)との関係は?
- A
髪の健康には、セレンだけでなく亜鉛も非常に重要なミネラルです。亜鉛は、髪の主成分であるケラチンたんぱく質の合成に不可欠です。
セレンと亜鉛は、ともに抗酸化作用や免疫機能の維持に関わるなど、協力して働く場面も多くあります。
どちらか一方だけを摂取するのではなく、両方をバランス良く摂取する意識が、健やかな髪を育むためには大切です。
多くの食品には両方のミネラルが含まれているため、バランスの取れた食事を心がけましょう。
参考文献
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
WATTS, David L. The nutritional relationships of selenium. Journal of Orthomolecular Medicine, 1994, 9: 111-111.
ALDOSARY, Barrak M., et al. Case series of selenium toxicity from a nutritional supplement. Clinical Toxicology, 2012, 50.1: 57-64.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
KANEKURA, T., et al. Selenium deficiency: report of a case. Clinical and experimental dermatology, 2005, 30.4: 346-348.
HWANG, Seon Wook, et al. Changes in murine hair with dietary selenium excess or deficiency. Experimental dermatology, 2011, 20.4: 367-369.