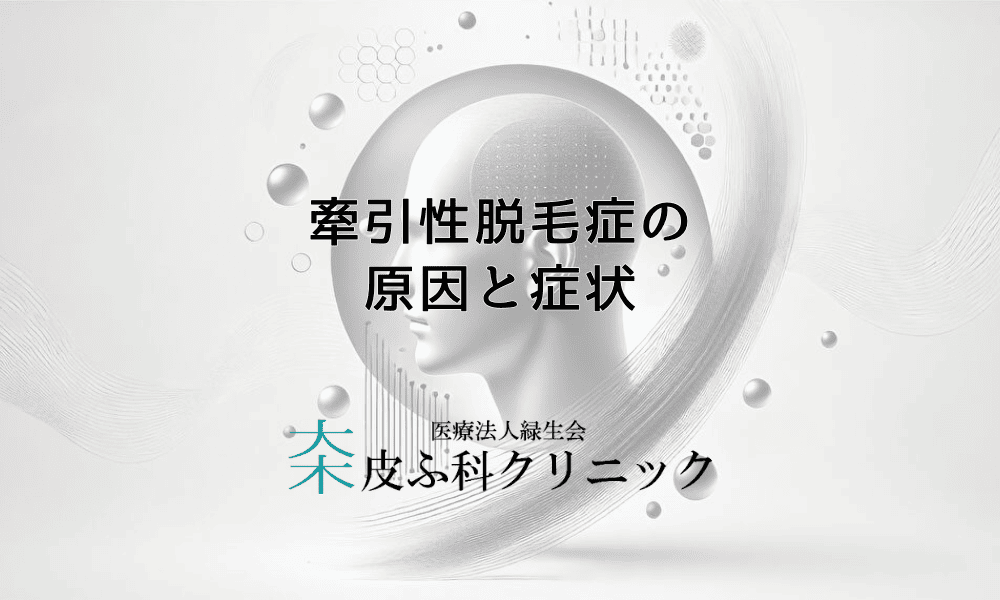髪を強く結んだり、ヘアアレンジのくり返しによって髪の生え際が薄くなる現象は、牽引性の脱毛症が疑われます。
普段の何気ないヘアスタイルや頭皮への刺激が原因となり、徐々に髪が抜けてしまうケースがあるため注意が必要です。
初期の段階で適切に対処すれば、より大がかりな薄毛治療につながる前に改善が見込めます。
牽引性の脱毛症とは?
牽引性脱毛症は、髪の一部分に常に強い力がかかる状態が続いたときに起こる脱毛症として知られています。
髪を長時間結んだり、エクステンションをつけたりする習慣がある方は要注意です。髪の付け根が引っ張られることで毛母細胞に負担がかかり、脱毛が起こりやすくなります。
牽引性脱毛症の定義
髪を強く引っ張る習慣が続くことで、頭皮の特定の部位に負荷がかかり、毛根がダメージを受けて髪が抜けやすくなる状態を指します。
とくにポニーテールなどで髪をまとめる機会が多い方に起こりやすいといわれます。
頭皮には血行や栄養状態に関わる要素が多く存在しますが、牽引による直接的なストレスは毛根に物理的なダメージを与えます。
その結果、頭頂部や生え際、こめかみ付近など、髪を結んだときに負荷が集中しやすい場所で症状が進行する傾向が強いです。
症状と初期サイン
初期症状としては「生え際が目立つようになった」「髪を結ぶ部分の毛が細くなった」「頭皮が赤みを帯びている」といった変化が見られます。
普段からヘアアレンジをするときに頭皮の違和感を覚えたり、結んだ部分の抜け毛が増えたりすると牽引性の脱毛症を疑う必要があります。
- 髪が細くなってきた
- 頭皮がかゆい、痛い
- ヘアゴムを外したあとに部分的な脱毛が目立つ
- 分け目が広がってきたように感じる
髪を結ぶ頻度が多いときほど進行が早くなるケースも見られますので、早期の段階で対策を行うことが大切です。
頭皮への負荷
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪を強く引っ張る髪型 | ポニーテール、きつい三つ編み、アップヘアなど |
| 頭皮のケア不足 | 過度なスタイリング剤の使用、シャンプー不足 |
| 毛根環境の悪化 | 頭皮の血行不良、毛母細胞のダメージ |
| 長時間の圧迫 | ヘアアクセサリーの締めつけ、エクステの装着 |
発症のメカニズム
髪の付け根を引っ張り続けると、毛根部にある毛母細胞が炎症を起こしやすくなります。炎症が起こると髪の成長サイクルが乱れ、休止期が延長されるなどの影響を受けて髪が抜けやすくなります。
さらに、頭皮の血行不良も併発しやすいので、毛根に必要な栄養素が届きにくくなって脱毛に拍車がかかるケースもあります。
AGAとの関連
牽引性の脱毛症とAGA(男性型脱毛症)は原因が異なりますが、頭皮へのダメージが蓄積するとAGAの進行を促進してしまう可能性もあります。
女性の場合も女性型脱毛症(FAGA)との合併がみられるケースがあり、ヘアサイクルが乱れた部位は他の要因による脱毛も起こりやすいです。
そのため、早期に気づいて対処するとAGAやFAGAの予防にもつながります。
牽引性脱毛症を引き起こす原因
繰り返し髪を結ぶスタイルだけが原因と思われがちですが、さまざまな要素が関係しています。日々の生活習慣やヘアケアの仕方によって、症状をより深刻にしてしまう場合もあります。
ヘアスタイルの影響
ポニーテールやお団子などで髪をしっかり結ぶと、毛根部分に大きな負担がかかります。長時間同じヘアスタイルを続けると、頭皮の特定のエリアに負荷が集中し、抜け毛が増える原因になります。
また、髪を結ぶ位置が常に同じだと、同じ部分ばかりが引っ張られるので、脱毛の偏りが顕著になります。
髪を結びすぎることによる影響
- 頭皮の血流が滞る
- 毛母細胞が引っ張られ炎症を起こしやすい
- 同じ部分の抜け毛が増える
- 生え際や頭頂部の髪が細くなりやすい
結ぶ強さを調整する、定期的に髪をほどくなど、日常生活のなかで負担を軽減する工夫が必要です。
ヘアアクセサリーの使用
ヘアゴムやピン、バレッタなどをきつく使い続けると、毛の立ち上がり部分が圧迫されます。ゴムのくい込みや金具による刺激が頭皮のトラブルを引き起こすリスクもあります。
特に髪を結ぶ箇所が細いヘアゴムだと、局所的に強い力がかかるため注意が必要です。
アクセサリー選びの目安
| アクセサリー種類 | 注意点 | 推奨される素材・形状 |
|---|---|---|
| ヘアゴム | 細くて締め付けが強いものは避けたい | 柔らかく伸縮性のある太めゴム |
| バレッタ | 金具が鋭利だと髪や頭皮に負荷をかけやすい | プラスチックや樹脂製で広い面積を持つ |
| カチューシャ | 長時間使用で生え際に負担をかける | 締め付けが緩めの素材 |
| エクステンション | 接着部が強く引っ張る仕組みだと危険 | 頭皮に負担が少ない装着方法 |
頭皮への負担が増す生活習慣
牽引による物理的ストレスに加え、栄養バランスの偏りや睡眠不足などの習慣があると、髪の回復力が落ちてしまいます。
自律神経が乱れることで血行不良になり、毛根への栄養供給が滞るため抜け毛が増えるリスクが高まります。
遺伝やホルモンバランスとの関係
牽引性による脱毛は外部からの圧力が主な原因ですが、もともと髪が抜けやすい体質の方やホルモンバランスの乱れがある方は、症状が出やすくなると知られています。
特に女性は妊娠・出産や更年期などでホルモン変動が大きいため、ヘアスタイルへの負荷が重なると脱毛が進行しやすくなるケースがあります。
初期段階でのセルフケアと予防策
早い段階で気づいて対策を取れば、進行を抑えたり症状を軽減したりできる可能性があります。髪のケアや頭皮環境を整える方法を取り入れ、牽引によるダメージを和らげる工夫を行いましょう。
髪型の見直し
髪を結ばないスタイルや、ヘアバンドや緩めのゴムを使用して頭皮への引っ張りを減らすだけでも効果があります。
同じ場所を強く引っ張り続ける状態を避けることが重要です。髪をどうしても結ぶ必要があるときは、結び目をその日によって変える、少し下の位置で緩めにまとめるなどの工夫を加えましょう。
髪型を変えたほうがよい理由
- 頭皮にかかる力を分散できる
- 同じ毛根への負荷を減らす
- 頭皮の血流改善をサポートする
- すでに痛んだ毛根の回復を促しやすくする
正しいヘアケアと頭皮マッサージ
強い洗浄力のシャンプーで髪を洗うと、頭皮が乾燥して炎症を起こしやすくなります。頭皮の潤いを保つシャンプーを選び、指の腹で優しくマッサージしながら洗うと良い切です。
マッサージによって血行がよくなり、毛根がダメージから回復しやすくなる可能性が期待できます。
ストレス管理と睡眠の確保
精神的ストレスや慢性的な睡眠不足は、頭皮や髪の細胞の再生に大きな影響を及ぼします。
自律神経が乱れると血管の収縮や拡張のバランスが崩れ、頭皮に十分な栄養を届けにくくなるため、抜け毛が増えやすくなります。
就寝前のスマートフォン使用を控える、軽い運動や深呼吸を取り入れるなど、ストレスを軽減する工夫を心がけてください。
ストレス緩和に役立つポイント
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 有酸素運動 | ウォーキングやジョギングなどでリフレッシュ |
| 深呼吸・瞑想 | 呼吸を整え、自律神経のバランスを整える |
| 趣味の時間 | 好きなことに没頭し、緊張を和らげる |
| 規則正しい生活 | 就寝時間を一定にして睡眠リズムを整える |
栄養バランスの見直し
髪や頭皮を支えるタンパク質やビタミン、ミネラルが不足すると、抜け毛が増えるリスクが高まります。
偏った食生活は頭皮環境を悪化させる要因になるので、日々の食事で栄養バランスを整えることを意識するとよいでしょう。鉄分や亜鉛なども髪の生成に深く関わります。
- タンパク質(肉、魚、大豆製品など)
- ビタミン群(野菜、果物、卵など)
- ミネラル類(海藻、ナッツ類など)
- 鉄分(赤身肉、レバー、ほうれん草など)
早期発見のポイントとセルフチェック方法
牽引性による脱毛は、気づかずに放置すると症状が進みやすい傾向にあります。定期的に髪の状態をチェックし、少しでも異常を感じたら原因を振り返ることが大切です。
鏡での観察
生え際や頭頂部、こめかみ部分を中心に、髪の密度や太さに変化がないかを観察します。特に、髪を結んだあとにゴムを外したとき、生え際が広がっているように感じる場合は注意が必要です。
髪型を変えてみても抜け毛の量が変わらないときは、より深刻なダメージが進行している可能性があります。
自宅で行う簡易チェック
- 生え際の後退が気になる
- 頭皮に赤みや痛みがある
- 以前より髪が細くなったと感じる
- 同じヘアスタイルを毎日している
- ゴムを外した後に髪が大量に抜ける
上記に心当たりのある方は、早めに対策を行うと良いでしょう。
美容師や家族に見てもらう
他人の視点で見ると、髪の薄さや分け目の変化を客観的に把握しやすくなります。
美容院でカラーリングやカットをするときに相談すれば、プロの視点で毛根の状態や頭皮環境をチェックしてもらえます。また、家族に頭頂部や普段は見えにくい箇所を定期的に見てもらうのも有効です。
チェック頻度の目安
| 時期 | チェック内容 |
|---|---|
| 月に1回~2回程度 | 生え際やつむじの密度、髪の細さに変化がないか |
| 季節の変わり目 | 抜け毛が増えやすい時期なので全体的な量を確認 |
| 美容院へ行くタイミング | 美容師に頭皮環境を見てもらう |
| 家族に依頼 | 見えにくい後頭部や頭頂部を客観的に評価 |
ヘアログやアプリの活用
髪の状態を記録するためのスマートフォンアプリを使い、定期的に写真を撮っておく方法があります。撮影した写真を時系列で比較すると、わずかな変化にも気づきやすくなります。
変化が緩やかであっても、早めに行動すれば深刻な薄毛になる前に対策を打ちやすくなります。
自己判断による放置のリスク
牽引による脱毛は、たとえ軽度でも放置すると回復までに時間がかかりやすい特徴があります。
「まだ大丈夫」と思い込みがちな方ほど、気づいたときには脱毛範囲が拡大しているケースが見受けられます。早めにチェックしておくことが重要です。
クリニックで行う治療方法とその効果
セルフケアで改善しきれない場合は、クリニックでの治療を検討することが有益です。頭皮の状態に合わせた治療法を組み合わせると、脱毛症状を緩和し、発毛を促すことが期待できます。
内服薬や外用薬の処方
頭皮の炎症を抑えたり、毛根を活性化したりするための薬剤を使用する治療法があります。
男性型や女性型の脱毛と併発している可能性がある場合には、ホルモンバランスに働きかける薬の処方を行うケースもあります。
医師の判断に基づいて使用量や使用期間を決めるため、安心して治療に取り組めます。
| 薬剤の種類 | 主な効果 |
|---|---|
| 炎症を抑える薬 | 頭皮の炎症を鎮めて毛母細胞の負担を軽減 |
| 血行促進を促す外用薬 | 毛根への栄養供給を高め、発毛をサポート |
| ホルモンバランス調整薬 | 男性ホルモンや女性ホルモンの乱れによる脱毛抑制 |
| ビタミン剤など | 不足しがちな栄養を補給して髪を強くする |
頭皮ケアの施術
スカルプケアやメソセラピーなど、頭皮に直接働きかける施術によって血流を高め、毛根に働きかける方法があります。
頭皮の汚れや余分な皮脂を取り除き、頭皮環境を整えたうえで薬剤を浸透させることで、より改善効果を得られると考えられます。
- スカルプクレンジングで毛穴づまりを解消
- マッサージや鍼治療で血流をスムーズにする
- 薬剤や成長因子を注入して毛母細胞を刺激する
生活習慣やヘアスタイルの指導
物理的ストレスを減らすために、髪を結ぶ頻度やヘアアクセサリーの選び方を見直す指導を行うクリニックもあります。
医師や看護師が頭皮状態を定期的にチェックし、状況に応じてアドバイスをしてくれるため、自己流のケアでは不十分な場合でも専門的なサポートを受けられます。
クリニック受診のメリット
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 専門的な診断 | 牽引性だけでなく、AGAや他の要因も総合的に判断 |
| オーダーメイド治療 | 患者の頭皮環境や生活スタイルに合わせた多角的なアプローチ |
| 定期的な経過観察 | 自宅では気づきにくい変化も早めにキャッチし、治療方針を調整できる |
| 医師や看護師の指導 | ヘアスタイルや日常習慣の改善点を具体的に提案 |
治療期間と費用の目安
治療期間は数か月から半年以上かかるケースが多いです。完全に発毛が確認できるまでには個人差があり、生活習慣や年齢、脱毛の進行度などによっても変動します。
費用は保険適用の有無や施術内容によって異なるため、カウンセリング時にしっかり確認すると良いでしょう。
牽引による脱毛と他の脱毛症との違い
髪の結び方が関係している牽引性の脱毛症と、男性ホルモンなどの内的要因による脱毛症とは区別が必要です。
原因を誤って捉えると、適切な治療タイミングを逃してしまうリスクがあります。
男性型脱毛症(AGA)との違い
AGAは男性ホルモンの影響で頭頂部や前頭部の髪が薄くなる脱毛症です。
一方で牽引性による脱毛は、髪を引っ張る外的要因が強く、男女問わず起こりうる点に特徴があります。
AGAと併発するケースもあるため、専門医の診察で正確に区別する必要があります。
円形脱毛症との違い
円形脱毛症は自己免疫反応によって突然円形や楕円形に髪が抜け落ちる脱毛症です。
牽引性の脱毛症は、比較的広範囲に生え際が後退したり、特定の結び目付近が薄くなったりするのが特徴で、円形脱毛症のようにはっきり円形に抜けることはあまりありません。
脱毛症の特徴比較
| 脱毛症の種類 | 主な特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 牽引性の脱毛症 | 髪を引っ張る髪型などの外的な負荷で生え際や頭頂部が薄くなる | 物理的ストレス、頭皮への圧力 |
| AGA(男性型脱毛症) | 前頭部や頭頂部から徐々に薄くなる | 男性ホルモン、遺伝的要因 |
| 円形脱毛症 | 円形や楕円形で突然脱毛する | 自己免疫反応、ストレス |
| FAGA(女性型脱毛症) | 頭頂部や分け目を中心に髪が細くなり、ボリュームが減っていく | ホルモンバランス、加齢、遺伝 |
拡散型脱毛症との違い
拡散型脱毛症は、髪が全体的に薄くなるタイプで、頭髪全体のボリュームが少しずつ減っていくのが特徴です。
牽引性の場合は明らかな物理的な刺激に起因し、特定の部位に症状が集中することが多い点が異なります。
拡散型は栄養不足やホルモン変調が影響している方が多く、牽引とは直接関係しない場合がほとんどです。
正確な診断の重要性
自分の脱毛症状がどのタイプに当てはまるかを正確に把握すると、効果的な治療計画を立てやすいです。
誤ったケアを続けると症状が悪化するリスクがあるため、専門医の診察を受けることが早い回復への近道といえます。
脱毛症が進行したと感じた場合の対処法
牽引による脱毛が進み、髪のボリュームが大幅に減ってしまったと感じるなら、早めに専門的なケアを検討したほうがよいでしょう。
セルフケアだけでは対処しきれない場合も多いため、クリニックへの受診を含めた複数の対策を考える必要があります。
専門医への相談
脱毛の原因が明らかになっていない場合や、セルフケアを続けても改善の兆しが見られない場合には、まずは専門医に相談するのが確実です。
血液検査や頭皮の状態チェックなどを行い、複数の要因が絡んでいるかどうかを判断します。必要に応じて内服薬や外用薬、施術などの提案を受けられるため、症状の緩和や回復が期待できます。
相談時に伝えるとよい情報
- 髪を結ぶ頻度や時間
- 使用しているヘアアクセサリーの種類
- 抜け毛に気づいた時期と脱毛範囲の変化
- 食生活や睡眠リズムなどの生活習慣
- ストレスの有無や体調の変化
ウィッグや増毛技術の活用
脱毛部位が目立って気になる場合は、一時的にウィッグや増毛技術を利用する方法もあります。見た目を気にせず日常生活を送れるため、精神的ストレスを軽減できる利点があります。
ただし、ウィッグを長時間装着すると頭皮に汗や皮脂がたまりやすいので、定期的なケアを欠かさないようにしましょう。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| ウィッグ | 手軽に装着でき、全体的なボリュームをカバーできる | 長時間使用で蒸れやすい、定期的なお手入れが必要 |
| 増毛技術 | 部分的に髪を増やせるため、自然な仕上がりを目指しやすい | 費用がかかる場合が多い、定期的なメンテナンスが必要 |
ストレスケアと頭皮ケアの継続
一度脱毛が進行すると、髪が回復するまでには時間を要します。治療と併行してストレスケアや頭皮マッサージ、栄養バランスの改善といったセルフケアを継続することで、より早い回復を目指せます。
焦らず、長期的な視点で取り組む意識を持つとよいでしょう。
モチベーションを保つ工夫
脱毛治療は比較的長期にわたるケースが多く、目に見える変化が出るまでに時間がかかる場合があります。
定期的に写真を撮って経過を比較する、担当医や看護師と相談して治療メニューを調整するなど、途中であきらめずに取り組める工夫が役立ちます。
よくある質問
牽引による脱毛症に関して、多くの方から寄せられる疑問とその回答を整理しました。日常のヘアケアやクリニックでの治療について、不安や気になる点がある場合の参考にしてください。
- Q牽引性の脱毛症は放置しても自然に治りますか?
- A
軽度であれば、髪を結ばないスタイルに変えるなどして頭皮への負担を減らすと自然に回復するケースもあります。
しかし、中程度から重度にかけて進行している場合は、毛根が弱っている状態が続くため回復までに時間がかかります。
放置すると回復が遅れる可能性があるため、早めにセルフケアや専門医の診察を検討すると良いでしょう。
- Q髪を結ぶ頻度を減らせば完治するのでしょうか?
- A
頭皮や毛根への負担が減るため回復の助けになります。とはいえ、すでに毛根が深刻なダメージを受けていると、完治までには栄養補給や血行促進など、ほかのケアも必要になる場合があります。
定期的に頭皮の状態をチェックしながら適切なケアを組み合わせることが大切です。
- Q男性でも牽引性の脱毛症は起こりますか?
- A
男性もヘアスタイルやヘアアクセサリーなどで髪を強く結ぶ機会があれば起こり得ます。
また、趣味や仕事でウィッグを使用するケースもあり、頭皮が締め付けられる状況が続くと牽引による脱毛が発生します。男女問わず注意が必要です。
- Q牽引とAGAの見分け方がわかりません
- A
自分で見分けるのは難しい場合が多いです。結ぶ位置や生え際など特定の部分の脱毛が顕著で、ヘアスタイル変更や頭皮ケアで改善する場合は牽引の可能性が高いです。
ただしAGAや他の要因が絡むこともあるので、専門医に相談するのが確実です。
参考文献
AKINGBOLA, Christiana Oyinlola; VYAS, Jui. Traction alopecia: A neglected entity in 2017. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2017, 83: 644.
BILLERO, Victoria; MITEVA, Mariya. Traction alopecia: the root of the problem. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2018, 149-159.
SHARQUIE, Khalifa E., et al. Traction alopecia: clinical and cultural patterns. Indian Journal of Dermatology, 2021, 66.4: 445.
UZUNCAKMAK, Tugba Kevser, et al. Trichotillomania and Traction Alopecia. In: Hair and Scalp Disorders. IntechOpen, 2017.
KHUMALO, Nonhlanhla P., et al. Determinants of marginal traction alopecia in African girls and women. Journal of the American Academy of Dermatology, 2008, 59.3: 432-438.
SAMRAO, Aman, et al. The “Fringe Sign”-A useful clinical finding in traction alopecia of the marginal hair line. Dermatology Online Journal, 2011, 17.11.
FCDERM, PHD. Traction Alopecia. Alopecia, 2018, 135.
KARLS, Raimonds. Traction Alopecia. In: Hair Disorders. CRC Press, 2021. p. 62-67.