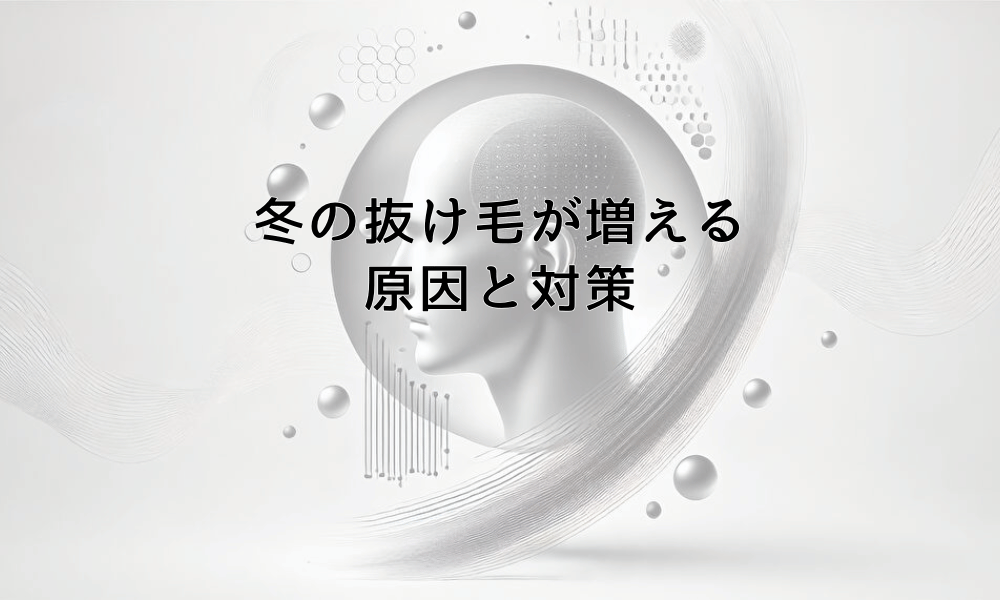診察をしていると「冬になると、シャワーの排水溝や枕に付く髪の毛が増える気がする」とおっしゃる方がいます。
季節の変わり目、特に冬は空気が乾燥し、寒さで体の調子も変化しやすい時期です。
この季節的な要因が頭皮環境や髪の健康に影響を与え、抜け毛の増加に繋がる場合があります。
冬に抜け毛が増えるのは本当か?季節性の脱毛の事実
冬に抜け毛が増えるという感覚は、気のせいではありません。
多くの人が経験するこの現象には、髪の毛の生まれ変わりの周期と季節的な要因が深く関係しています。まずは、髪と季節の基本的な関係を理解しましょう。
髪の毛のヘアサイクル(毛周期)とは
髪の毛は、1本1本が独立した寿命を持ち、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。これをヘアサイクル(毛周期)と呼びます。
健康な頭皮では、ほとんどの髪(約85~90%)が成長期にあり、数年かけて太く長く成長します。
その後、退行期を経て休止期に入ると髪の成長は完全に止まり、やがて自然に抜け落ちて新しい髪に生え変わります。
ヘアサイクルの各期間
| 期間 | 割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 成長期 | 約85~90% | 2~6年かけて髪が活発に成長する。 |
| 退行期 | 約1% | 約2週間で毛根が小さくなり、成長が止まる。 |
| 休止期 | 約10~15% | 約3ヶ月間、毛根に留まった後、自然に脱毛する。 |
季節の変わり目と抜け毛の関係性
ヘアサイクルは一定のリズムを保っていますが、ホルモンバランスの変化や体調、そして季節的な要因によって影響を受けます。
特に、夏の間に浴びた紫外線のダメージや、夏バテによる栄養不足の影響が秋口に現れ、抜け毛が増えることはよく知られています。
冬の抜け毛も、この秋からの流れを引き継ぎつつ、冬特有の環境要因が加わるために起こると考えられます。
冬と秋の抜け毛の違い
秋の抜け毛が夏のダメージの蓄積を主な原因とするのに対し、冬の抜け毛は「乾燥」と「血行不良」という、現在進行形の環境要因が大きく影響します。
秋の抜け毛が一時的なものであれば心配は少ないですが、冬になっても抜け毛が減らない、あるいは増えていると感じるときは冬特有の原因に対する対策が必要です。
季節ごとの抜け毛の主な要因
| 季節 | 主な要因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 秋 | 夏の紫外線ダメージ、夏バテ | 休止期の髪が一斉に抜けやすい。 |
| 冬 | 乾燥、血行不良 | 頭皮環境が悪化し、ヘアサイクルが乱れやすい。 |
冬の抜け毛を引き起こす原因
冬という季節が、どのようにして髪の健康に影響を与えるのでしょうか。ここでは、冬の抜け毛に繋がる4つの主な原因を掘り下げて解説します。
乾燥による頭皮環境の悪化
冬は空気が非常に乾燥します。肌がカサカサするのと同じように、頭皮も水分を奪われて乾燥します。
乾燥した頭皮はバリア機能が低下し、フケやかゆみを引き起こしやすくなります。
この頭皮環境の悪化は、健康な髪が育つ土台を揺るがし、ヘアサイクルを乱して抜け毛を増やす原因となります。
頭皮の乾燥が進んだサイン
| サイン | 状態 | 対策 |
|---|---|---|
| 細かいフケ | 頭皮の角質が剥がれ落ちている。 | 保湿シャンプーの使用、洗いすぎない。 |
| かゆみ | 外部刺激に敏感になっている。 | 爪を立てずに指の腹で優しく洗う。 |
| つっぱり感 | 頭皮の水分が不足している。 | 頭皮用ローションで保湿する。 |
寒さによる血行不良
気温が下がると、私たちの体は体温を逃がさないように血管を収縮させます。この体の反応により、特に体の末端である頭皮の血行が悪くなりがちです。
髪の毛の成長に必要な栄養素は、血液によって毛根へ運ばれます。そのため、血行不良に陥ると髪に十分な栄養が届かなくなり、髪が細くなったり、成長期が短くなって抜けやすくなったりします。
暖房による影響と対策
寒い室内で快適に過ごすための暖房器具も、使い方によっては抜け毛の原因になります。
エアコンやストーブの温風は、室内の空気をさらに乾燥させます。特に、温風が直接頭皮に当たると、乾燥を著しく進行させてしまいます。
加湿器を併用したり、暖房の設定温度を少し下げたりする工夫が大切です。
冬の運動不足がもたらす影響
寒さから外出が億劫になり活動量が減る冬は、運動不足に陥りやすい季節です。
運動不足は全身の血行を滞らせるだけでなく、ストレスの発散機会を減らすことにも繋がります。
適度な運動は血行を促進し、ストレスを軽減する効果があるため、髪の健康を維持するためにも重要です。
見過ごしがちな冬の生活習慣と髪への影響
乾燥や血行不良といった一般的な原因のほかにも、冬特有の何気ない生活習慣が、知らず知らずのうちに頭皮に負担をかけているケースがあります。
ここでは、多くの人が見過ごしがちなポイントに焦点を当てます。
熱いお風呂やシャワーの落とし穴
寒い日に熱いお風呂やシャワーを浴びるのは気持ちが良いものですが、髪にとっては注意が必要です。
42度を超えるような熱いお湯は、頭皮を守るために必要な皮脂まで洗い流してしまいます。皮脂が過剰に奪われると頭皮のバリア機能が低下し、乾燥をさらに悪化させる原因となります。
シャワーの温度は38度から40度程度のぬるま湯に設定するのがおすすめです。
帽子の着用と頭皮の蒸れ
冬の防寒対策として帽子をかぶる習慣は、頭部を寒さから守り血行不良を防ぐ上で有効です。
しかし、暖かい室内に入っても帽子をかぶったままでいると、頭皮が蒸れてしまいます。蒸れた環境は雑菌が繁殖しやすく、かゆみや炎症、ニオイの原因になるときがあります。
屋外では着用し、室内ではこまめに脱いで頭皮を快適な状態に保つ工夫が大切です。
年末年始の食生活の乱れ
忘年会やクリスマス、お正月などのイベントが続く年末年始は、食生活が乱れやすい時期です。
アルコールの過剰摂取や、脂っこい食事、糖分の多い料理に偏ると皮脂の分泌が過剰になったり、髪の成長に必要なビタミンやミネラルが不足したりします。
この時期の不摂生が、後々の頭皮環境の悪化や抜け毛に繋がると覚えておきましょう。
冬の「なんとなく不調」と髪の関係
冬は日照時間が短くなるため、気分が落ち込んだり、やる気が出なかったりする「冬季うつ」のような症状を感じる人もいます。
この背景には、日光を浴びると生成されるセロトニンという神経伝達物質の減少が関係していると言われます。
セロトニンの減少は自律神経のバランスを乱し、この乱れが血行不良や皮脂の過剰分泌などを引き起こし、間接的に髪の健康に影響を与える可能性があります。
冬の不調が髪に与える影響
| 冬の不調 | 体への影響 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 日照不足 | セロトニン減少、自律神経の乱れ | 血行不良、皮脂バランスの乱れ |
| 生活リズムの乱れ | ホルモンバランスの変動 | ヘアサイクルの乱れ |
冬の頭皮環境を整えるヘアケア方法
冬の厳しい環境から髪と頭皮を守るためには、毎日のヘアケアの見直しが重要です。
ここでは、保湿と血行促進を意識した具体的なケア方法を紹介します。
保湿を重視したシャンプーの選び方
洗浄力が強すぎるシャンプーは、乾燥した頭皮に必要な潤いまで奪ってしまいます。
冬の間はアミノ酸系などのマイルドな洗浄成分で、保湿成分が配合されたシャンプーを選ぶと良いでしょう。
自分の頭皮の状態に合わせて、適切な製品を見つけることが大切です。
シャンプー選びで注目したい保湿成分
| 成分の種類 | 代表的な成分名 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| アミノ酸類 | グリシン、アルギニン | 髪と頭皮に潤いを与える。 |
| 植物由来エキス | アロエベラエキス、カミツレ花エキス | 保湿、抗炎症作用。 |
| 高保湿成分 | ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド | 高い保水力で乾燥を防ぐ。 |
正しい髪の洗い方と乾かし方
シャンプーの方法一つで、頭皮への負担は大きく変わります。ゴシゴシと強くこするのではなく、指の腹を使ってマッサージするように優しく洗いましょう。
また、濡れた髪はダメージを受けやすいため、シャンプー後はすぐに乾かすことが重要です。
タオルで優しく水分を拭き取った後、ドライヤーを頭皮から20cmほど離して、根本から乾かしていくのがポイントです。
正しい髪の洗い方の手順
- シャンプー前にブラッシングで汚れを浮かす
- ぬるま湯で頭皮と髪を十分に予洗いする
- シャンプーを手のひらで泡立ててから髪につける
- 指の腹で頭皮をマッサージするように洗う
- すすぎ残しがないように、時間をかけて丁寧に洗い流す
頭皮マッサージの具体的な方法
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐして血行を促進するのに効果的です。シャンプー中や、お風呂上がりの体が温まっている時に行うのがおすすめです。
指の腹を頭皮に密着させ、頭皮全体をゆっくりと動かすようなイメージで行いましょう。
気持ち良いと感じる程度の力加減で、毎日数分でも続ける習慣が大切です。
トリートメントと頭皮用美容液の活用
シャンプー後のトリートメントは、髪の水分や油分を補い、乾燥や静電気から守る役割を果たします。
さらに、頭皮の乾燥が特に気になる場合は、頭皮専用のローションや美容液(スキャルプエッセンス)を取り入れるのも良い方法です。
保湿成分や血行促進成分が含まれた製品を選び、マッサージしながらなじませると、より効果が期待できます。
抜け毛対策に繋がる冬の食生活
健康な髪を育てるためには外側からのケアだけでなく、内側からの栄養補給も重要です。バランスの取れた食事は、強い髪を作るための基本となります。
髪の主成分となるタンパク質の摂取
髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質が不足すると、髪が細くなったり、ハリやコシがなくなったりします。
肉や魚、卵や大豆製品など、タンパク質を豊富に含む食品を毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。
亜鉛やビタミンの役割と多く含む食品
タンパク質を髪の毛の成分であるケラチンに再合成する際には、亜鉛が必要です。また、ビタミン類は頭皮の健康を保ち、血行を促進する働きがあります。
これらの栄養素が不足しないように、様々な食材からの摂取を心がけましょう。
髪の健康を支える栄養素と食品例
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す。 | 豚肉、うなぎ、マグロ、納豆 |
| ビタミンE | 血行を促進する。 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |
体を温める食材のすすめ
冬の寒さによる血行不良を改善するためには、体を内側から温める食材を積極的に摂るのも有効です。
根菜類や香味野菜には、体を温める作用を持つものが多くあります。温かいスープや鍋物にして食べると、効率よく体を温められます。
血行促進で髪に栄養を届ける生活習慣
食事やヘアケアに加えて、日々の生活習慣を見直すことも、冬の抜け毛対策には大切です。
ここでは、血行を促進し、髪に栄養を届けるための3つの習慣を紹介します。
自宅でできる簡単なストレッチ
長時間同じ姿勢でいるときが多い方は、首や肩の筋肉が凝り固まり、頭部への血流が悪くなりがちです。
仕事の合間や寝る前などに、簡単なストレッチを取り入れましょう。首をゆっくり回したり、肩を上げ下げしたりするだけでも血行改善に繋がります。
入浴によるリラックスと血行改善
シャワーだけで済ませず、湯船にゆっくり浸かるのも血行促進に効果的です。
38~40度のぬるめのお湯に15分程度浸かると、副交感神経が優位になりリラックスできる上、全身の血行が良くなります。
このリラックス効果は、ストレスによる抜け毛の予防にも繋がります。
質の良い睡眠を確保する工夫
髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に最も多く分泌されます。特に、眠り始めの深いノンレム睡眠時に分泌が活発になります。
睡眠不足や質の悪い睡眠は、ホルモンバランスの乱れや血行不良を招き、髪の成長を妨げます。
毎日決まった時間に就寝・起床し、寝る前はスマートフォンなどの強い光を避けるなど、睡眠環境を整える工夫が重要です。
睡眠の質を高めるための工夫
- 就寝1~2時間前に入浴を済ませる
- 寝室を快適な温度・湿度に保つ
- カフェインやアルコールの摂取を控える
- リラックスできる音楽を聴く、アロマを焚く
セルフケアで改善しない場合の選択肢
ここまで紹介したセルフケアを続けても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が進行しているように感じる場合は、専門クリニックへの相談を検討しましょう。
季節性の抜け毛だと思っていたものが、実はAGA(男性型脱毛症)の初期症状である可能性もあります。
抜け毛とAGA(男性型脱毛症)の関係
AGAは男性ホルモンの影響でヘアサイクルが乱れ、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまう進行性の脱毛症です。
季節性の抜け毛は一時的なものですが、AGAは放置すると薄毛が徐々に進行していきます。
生え際の後退や頭頂部の薄毛など、特定のパターンで薄毛が進行している場合は、AGAを疑う必要があります。
専門クリニックで相談するメリット
専門のクリニックでは、医師が頭皮の状態をマイクロスコープで詳しく診察し、抜け毛の原因を正確に診断します。
自己判断で市販の育毛剤を使い続けるよりも、原因に合った適切な治療を早期に始めるほうが、薄毛の進行を食い止める上で最も効果的です。
髪の悩みはデリケートな問題ですので、専門家に相談できる安心感も大きなメリットです。
クリニックでの主な治療法
AGA治療は内服薬や外用薬を中心に行うのが一般的です。患者さんの症状や進行度、生活スタイルに合わせて、適した治療法を提案します。
治療は継続が重要であり、医師と相談しながら進めていきます。
主なAGA治療法の比較
| 治療法 | 特徴 | 主な作用 |
|---|---|---|
| 内服薬 | AGAの進行を抑制する。 | 5αリダクターゼの働きを阻害する。 |
| 外用薬 | 頭皮に直接塗布して発毛を促す。 | 毛母細胞を活性化させ、血行を促進する。 |
| 注入治療 | 有効成分を頭皮に直接注入する。 | より直接的に発毛をサポートする。 |
冬の抜け毛に関するよくある質問(Q&A)
さいごに、冬の抜け毛に関して患者さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。
- Q冬の抜け毛はどのくらいで治まりますか?
- A
冬特有の乾燥や血行不良が原因である場合、春になり気候が温暖で穏やかになれば、自然と抜け毛が落ち着くケースが多いです。通常、1~2ヶ月程度で改善が見られます。
しかし、3ヶ月以上経っても抜け毛が多い状態が続く場合は、季節性以外の原因も考えられるため、一度専門医に相談することをおすすめします。
- Q加湿器を使えば頭皮の乾燥は防げますか?
- A
加湿器の使用は室内の湿度を保ち、頭皮の乾燥を防ぐ上で非常に有効です。湿度の目安は50~60%程度が理想的です。
ただし、加湿器だけに頼るのではなく、保湿成分の入ったシャンプーを使ったり、頭皮用ローションで直接保湿したりするなど、複数の対策を組み合わせるとより効果的です。
- Qマフラーやニット帽は抜け毛の原因になりますか?
- A
直接的な原因にはなりにくいですが、注意は必要です。マフラーの静電気が髪にダメージを与えたり、ニット帽による蒸れが頭皮環境を悪化させたりする可能性はあります。
静電気防止スプレーを使ったり、室内では帽子を脱いだりするなどの工夫をしましょう。
素材も、化学繊維よりはウールやコットンなどの天然素材のほうが、静電気が起きにくく通気性も良い傾向にあります。
- Q冬だけ育毛剤を使うのは効果がありますか?
- A
冬の期間だけ育毛剤を使用するのも、頭皮環境を整えるという点では一定の効果が期待できます。
特に、保湿成分や血行促進成分が含まれた育毛剤は、冬の乾燥や血行不良対策として有効です。
ただし、AGAが原因の薄毛の場合、育毛剤の使用を止めると再び進行する可能性があるため、根本的な改善を目指すのであれば、継続的な治療が必要です。
参考文献
RANDALL, VALERIE A.; EBLING, F. J. G. Seasonal changes in human hair growth. British Journal of Dermatology, 1991, 124.2: 146-151.
HSIANG, E. Y., et al. Seasonality of hair loss: a time series analysis of Google Trends data 2004–2016. British Journal of Dermatology, 2018, 178.4: 978-979.
COURTOIS, M., et al. Periodicity in the growth and shedding of hair. British Journal of Dermatology, 1996, 134.1: 47-54.
RANDALL, Valerie Anne. Hormonal regulation of hair follicles exhibits a biological paradox. In: Seminars in Cell & Developmental Biology. Academic Press, 2007. p. 274-285.
RANDALL, Valerie Anne. Androgens and hair growth. Dermatologic therapy, 2008, 21.5: 314-328.
JOHNSON, E. Environmental influences on the hair follicle. In: Hair Research: Status and Future Aspects; Proceedings of the First International Congress on Hair Research, Hamburg, March 13th–16, 1979. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1981. p. 183-194.
HARRISON, S.; SINCLAIR, R. Telogen effluvium. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 389-395.
LIYANAGE, Deepa; SINCLAIR, Rodney. Telogen effluvium. Cosmetics, 2016, 3.2: 13.